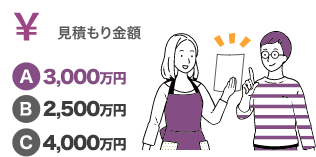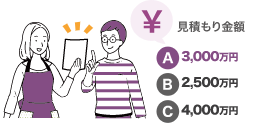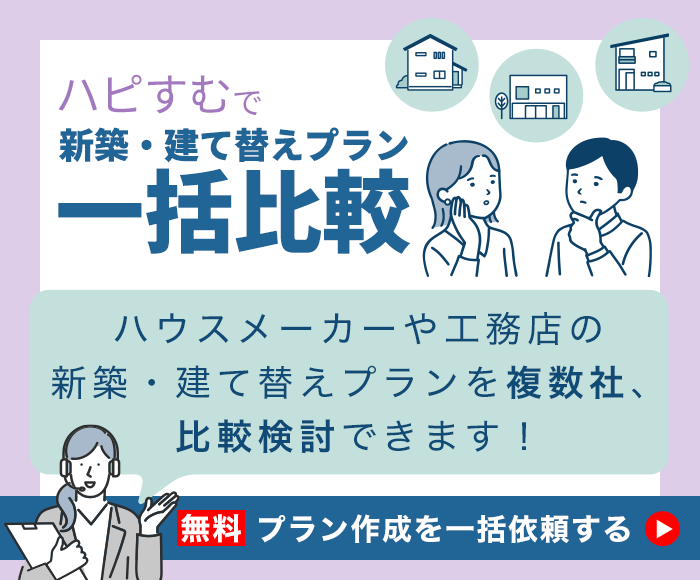2023年11月28日更新
購入する土地において重視したい条件の優先順位はどう決める?
目次
購入する土地において重視したい条件の優先順位の決め方

注文住宅を購入する際の土地探しにおいて、価格や広さ、立地などの様々な条件の中からどのように優先順位に決めるとよいのか、実際に土地を購入した人に行った調査などを参考に解説します。
実際に土地を購入した人の優先順位一位は予算と利便性
実際に土地を購入して注文住宅を建てた人が最も優先したのは「予算」と「利便性」であるという結果がでています。
予算を優先した人の理由は、土地探しの段階で予算を明確にしていたためという意見や、建物本体にかける費用や、老後資金、教育費など土地以外の支出を考えてという意見がありました。
利便性を重視した人は、通勤や通学、買い物などの便利さを第一に考えたケースや、高齢になった時のことを考えてという意見が出ています。自動車の運転免許の有無も土地選びに関係するようです。
理想の暮らしに必要な条件をリストアップし優先順位を決める
全ての希望を満たす土地を探すのは大変ですが、土地探しに迷った際は優先順位を決めることで頭の整理を行うことができます。自分の理想の暮らしのために必要な条件をリストアップしておきましょう。
リストアップした中から優先順位を決め、何に重きを置くかによって、土地と建物の予算配分が変わることもあります。どうしても譲れない条件と諦めてもよいことを整理しておくことが大切です。
家族で優先順位を決める
土地を選ぶ際には、家族全員で優先順位を話し合うようにしましょう。人それぞれに優先順位は異なるはずなので、自分も含めた家族全員の希望を明確にした上で優先順位を決めることが重要です。
例えば、夫婦どちらかの実家の近くに住みたい場合や、職場から近い場所を優先する場合、子どもの学区を優先する場合などが考えられます。また、親の介護などの問題もあるかもしれません。
ライフプランから優先順位を決める
住宅ローンは何十年もの長い期間支払い続けるケースが多いため、現時点において支払いが可能な場合でも、実際にローンの返済を行ううちに月々の生活が大変になるケースも少なくはありません。
教育費や老後の資金なども踏まえたライフプランを練り、資金計画を立てることが必要となります。住宅ローンを払い始める年齢も重要なポイントです。定年退職などで収入が減少した後のことも考えておきましょう。
また、子どもの校区を配慮するのは中学生ぐらいまでのことですので、校区を優先するかどうかについては慎重に考えましょう。子どもが成人して独立する場合や、親と同居する可能性なども視野に入れる必要があります。
購入する土地において重視したい条件ごとの優先順位
購入する土地において重視したい条件を絞ることができた場合、さらにそれぞれの条件ごとに優先順位を考え、妥協できる点とできない点を明確にしておくとよいでしょう。
土地面積の広さにおける優先順位
土地の面積が広いと土地の価格も高額になります。土地に費用をかけすぎると、家本体に使える費用が少なくなり、希望していたような家が建てられないという可能性もあるので、注意しましょう。
ただし、駐車スペースや庭、家族の個室など、必要なものが配置できていないような面積では困るため、土地面積と予算の配分については十分に考えることをお勧めします。
土地周辺の交通状況における優先順位
主要道路の交通量を確認するには、朝夕の通勤時間帯に勤務先までの経路をたどり、道路の渋滞状況や交通機関の混み具合などを確認しておくとよいでしょう。通勤時間にどれくらいかかるのかを知っておくことは重要です。
学校に通う子どもがいる場合には、通学路の確認をすることを忘れてはいけません。通学路の交通量や、危険な場所がないかなどが重要なポイントです。
都心においては特に交通の利便性を重視する傾向にあります。一方、地方においては通勤に時間がかかっても、自然環境や子育て環境を重視する傾向があり、都心と地方とでは優先順位が異なります。
最寄り駅から土地までの距離における優先順位
最寄り駅から土地までの距離が近いと利便性がよいというメリットがありますが、土地の値段が高く、広い土地が取れないという点がデメリットです。広さと利便性のどちらを優先するかを選択しておきましょう。
また、駅から近い土地は騒がしい傾向にあるため、静かな環境を求めるならば、最寄り駅からの距離が遠い土地を選ぶという選択肢もあります。
土地の法的規則による優先順位
土地には様々な法的規制があり、購入すれば所有者が何をしてもよいという訳ではありません。建ぺい率や容積率、高さ制限など、土地の法的規則は家づくりに大きな影響を及ぼします。
家を建てることができる広さは、敷地面積に対する建ぺい率と容積率で決まります。建ぺい率は敷地に対する建築面積の割合で、容積率は敷地面積に対して延べ床面積が占める割合です。
建ぺい率と容積率を超えた建物を建設することはできません。高さに関しては、地域ごとに近隣の建物の日照を妨げないための制限があります。また、前面にある道路の幅によっても建物の高さに制限があるので注意が必要です。
同様に、各自治体には必ず「都市計画図」があり将来の地域開発の展望が予測でき、参考になります。役所で購入できますがインターネットでも閲覧できます。
土地を購入した後に、法による制限によって自分が建てたい建物を建てることができないなどということがないように、土地にどのような法的規則があるのか事前に調べておくようにしましょう。
購入する土地を実際に見る際に重視すべき条件の優先順位
購入を希望する土地を実際に見る際のポイントについて紹介します。それぞれの条件の中で重視すべき点について詳しく解説します。
土地の形状や地盤
希望する建築物を建てることができるかどうかに関わるため、土地の形状や地盤は大変重要です。形状や地盤の状態によって価格が大きく変わるという点も注意すべきポイントとなります。
土地の形状について重視すべきポイント
土地の形状は大きく分けて「整形地」と「非整形地」の2種類に分かれます。これらの土地にはそれぞれ特徴があり購入価格にも関わるため、それぞれの土地について理解し、必要な用途に応じて選択することが必要です。
整形地は長方形や正方形などのようにある程度形が整っている土地のことです。住宅を建てる上では、敷地全体を有効活用でき、建築物を建てやすいという特徴があり、非整形地と比べて高額になる傾向にあります。
非整形地は形が整っておらず三角形や傾斜がある土地のことを言います。整形地と比べて土地の価格が安いことが多く、税率も低いという特徴がありますが、建築物を建てるのに適していない場合も多く、注意が必要です。
非整形地の形状は実に様々で、工夫次第で整形地と変わらない活用方法を取ることができます。例えば、角が出ている非整形地の場合、出ている部分を庭などにすることで有効活用が可能です。
整形地にしないと建築物を建てることができない場合には、整形地にするために多額の費用がかかることもあります。また、非整形地を整形地にするために近隣の土地を購入しなければいけないケースも考えられます。
非整形地を安く手に入れても、整形地にするための費用が必要となったり、建てたいと思っていた家を建てることができない場合もあるため、事前にハウスメーカーや工務店に相談することをおすすめします。
地盤について重視すべきポイント
地震の多い日本においては、土地選びをする際に地盤の固さが重要なポイントとなります。地盤が脆いと、地震の際に地盤沈下や土砂崩れ、液状化現象などが起こる可能性があり大変危険です。
地盤が脆い土地を購入した場合には、建物を建てる前に地盤改良の必要が生じ、工事にかかる費用が変わってきます。土地の広さなどにもよりますが、地盤改良には約100万円程度の費用が必要です。
地盤調査は土地を購入してからしか行うことができないため、購入前には他の方法で判断する必要があります。役所が作成したハザードマップや古い資料などを調べることで、ある程度は、地盤の固さを判断することが可能です。
ハザードマップには、地震が起きた時に液状化する恐れのある箇所などが記されています。また、古い地図などを見て、昔は田んぼや沼だった土地の場合には、地盤が緩いことを予想することができます。
大都市に多く見られる埋立地はもとは海や湖、沼だった場所に土を入れて人工的に作られているため、地盤沈下や液状化の恐れがあります。
特に注意したいのは戦後の混乱期にゴミや産廃物を無届で廃棄され、盛土で隠しただけといった悪質な埋立地もあり、役所も把握していないケースもあります。
都心部から近く魅力的な立地であったとしても、慎重に考慮するようにしましょう。
一度家を建てたら長くその土地で生活することになるため、地盤沈下などのトラブルが起こると長期間にわたって悩まされ続けることになります。地盤のことは土地選びにおいて優先すべき重要なポイントです。
周辺環境や治安状況
購入したいと思う土地が見つかった場合には、周辺環境や治安状態を事前にチェックしておくとよいでしょう。人通りが少なく見通しが悪い場所がないか、周辺の店舗の営業時間や利用者の雰囲気などがポイントとなります。
周辺環境を調べるには昼間と夜に歩いてチェックするのがおすすめです。また、地域のコミュニティについても調べておく必要があります。近隣に住んでいる人の口コミも参考にするようにしましょう。
地域の治安状態については、警視庁や自治体が用意している犯罪情報マップや交通事故発生マップなどでも確認が可能です。また、学校や図書館などの近隣地域であれば、治安状態がよいことが多いと予想できます。
土地の日当たり
太陽の光を室内に取り込むことによって、空間が明るくなり、洗濯物の乾きが早くなるなどのメリットがあります。土地を購入するにあたって、日当たりを重視する人は多いのではないでしょうか。
日当たりのよい土地を購入する上で重要になるのは方角です。南向きの土地は一般的に日当たりがよいとされていますが、季節によって日当たりの条件は異なり、冬場は太陽の入射角度が低く光が差し込みにくくなります。
また、南向きの家でも、周辺の建物の影になり日が入らない場合があります。周囲に高層建築物がないかどうか、隣接する住宅に隠れて日陰にならないかなどを確認するようにしましょう。
日当たりを優先するのならば、異なる季節や時間帯における日当たりの状態を確認しておくとよいでしょう。
隣の土地との境界線
土地を購入する際には、隣人とのトラブルを避けるためにも、契約を結ぶ前に境界をはっきりと把握しておくことが大切です。不動産売買時には、売主は買主に対し境界点および境界線を明示する必要があるとされています。
境界は隣地との境界点に設置されている「境界標」で表されますが、土に埋もれてしまったりブロック塀の下敷きになるなどして確認できない場合もあるため、境界標が境界点全てに設置されているか確認するようにしましょう。
境界標は隣地の了解を得ずに勝手に設置することはできません。原則として、資格を有する土地家屋調査士や測量士が測量を行った測量図に基づき、隣地との立会い、承諾を得て初めて設置が可能です。
雨天時の水の流れ
雨天時の水の流れを確認しておくことも重要となります。特に周りよりも低い土地の場合には注意が必要です。隣地の雨水が敷地内に放流されて水が溜まっていないかどうかを確認しておくようにしましょう。
土地の下見は晴れた日だけでなく、雨の日にも行うことをおすすめします。水はけがよいかどうかを確認することもできるからです。庭の水はけは建物本体にも影響を及ぼすため、重視すべきポイントとなります。
仲介を依頼する業者選びで迷ったら重視したい優先順位
相続や知人から土地を紹介してもらう場合を除いて、土地は仲介業者を通して購入するのが一般的です。仲介業者選びに際して重視すべき条件について紹介します。
仲介業者の営業スタイル
仲介業者の営業スタイルによって土地の販売方法や取り扱う商品などが異なります。仲介業者の営業スタイルを把握しておくことは、自分に合った業者探しの参考となります。
地域密着型の仲介業者の場合、土地の売主や地域についての情報が多く、値段交渉の余地や、掘り出し物の情報を得ることができるというメリットがあります。一方、大手仲介業者の場合、取扱数が多く、スタッフの対応も早いのがメリットです。
また、仲介手数料の額は上限だけに決まりがあるので、業者によって異なることがあります。仲介手数料は売買価格が400万円以上の場合、土地の売買価格の3%+6万円が上限です。
仲介業者が売主、買主双方の代理を行う時には、仲介業者は売主と買主の双方から手数料を得ることができます。このような取引は両手取引と言われ、買主が支払う仲介手数料が割引されることもあります。
両手取引は仲介業者が2倍の手数料を得ることができるため、売主に値下げをさせてでも取引を成立しようとする業者も存在します。米国では両手取引は法的に規制されており、健全な不動産流通を妨害するとの考えもあります。
仲介業者の営業成績
土地の購入は高額な取引となるため、安心して任せることができる仲介業者かどうかを見極める必要があります。仲介業者の取扱高や仲介件数などの営業実績は不動産の専門誌などで確認することができます。
取扱い高が多い企業が必ずしも自分にとってよい企業だとは限りません。個人向けの取り扱いが多い業者と、企業向けの取り扱いが多い業者があるので、その仲介業者の強みを確認しておくとよいでしょう。
仲介業者の行政処分歴
仲介業者の信頼性を確認する方法の一つとして、行政処分歴を調べるという方法があります。宅地取引業法に違反があった場合には、国土交通大臣や都道府県知事などの行政から処分が下されます。
仲介業者の行政処分歴は行政機関の名簿で確認できます。国土交通省や地方整備局管轄の国土交通大臣免許を所有する業者と、都道府県管轄の業者があり、いずれも国土交通省のホームページから問い合わせが可能です。
悪徳な仲介業者を見極めるためには、行政処分歴の確認は有効な方法と考えられます。
仲介業者の資産状況
仲介業者の資産状況が気になる場合には、会社四季報などで財務情報や資本移動などの情報を調べることができます。ただし、資産状況がよい業者が必ずしも自分にとってよい業者だとは限りません。
小さな業者でも親身になってよりよい取引を努めている業者はたくさんあります。倒産の心配がある業者の場合には資産状況の確認も必要ですが、業者を選ぶ際の優先順位として重視するかは個人の考え方によって異なります。
土地の購入希望が重なった際に優先順位が高くなる人の特徴

人気がある土地の場合には、同時に複数の購入申し込みが重なるケースもあります。そのような時に、優先順位が高くなる人にはいくつかの特徴があります。優先順位が高くなる人の特徴についてまとめました。
住宅ローン審査が下りる確実性が高い人
一般的には土地の購入希望者が重なった場合、買付証明書の提出が早い方を優先するとされていますが、住宅ローンを利用する場合にはローンの審査が下りる確実性が高い人が優先される傾向にあります。
買付証明書で購入の申し込みを行ったとしても、ローンの審査が下りなければ契約することはできません。金融機関から承認が得られなければ売買契約は白紙となってしまいます。
リスクを回避するために、勤務先や年収、自己資金額などの様々な条件を照らし合わせてより確実性が高い人を優先するケースも少なくはありません。
新居を購入する人
住宅を買い替える場合には、今まで住んでいた家の売却が済むまでは住宅ローンが思うように借りることができない場合もあります。このようなケースでは、競合相手がいれば不利になることもあり注意が必要です。
新居を購入する場合には、今まで住んでいた住宅について心配する必要がないため、買い替えのケースと比べると優先順位が高くなると考えられます。
値引き交渉をしない人
売り出されている金額に対して、この値段ならば購入するというような値引き交渉をする人も見受けられますが、説明するまでもなく、値引き交渉をしない人の方が有利です。
すぐに契約できる人
高額な土地を購入する際にはローンを利用するのが一般的ですが、中には現金で購入するケースもあります。このような場合には、ローンの審査を待つ必要がなく、すぐに契約を結ぶことが可能です。
すぐに契約できる人の優先順位は非常に高いと考えられます。
建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?
こここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。
正確な建て替え金額を知るためには、建て替え前に「見積もり査定」を受ける必要があります。
そのとき大事なのが、複数社に査定依頼して必ず「比較検討」をするということ!
「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」
「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」
そんな方は、簡単に無料で一括査定が可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。
一生のうちに建て替えをする機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!
一括見積もりをする