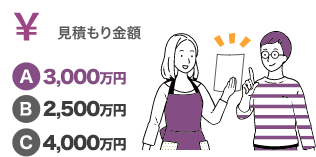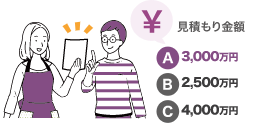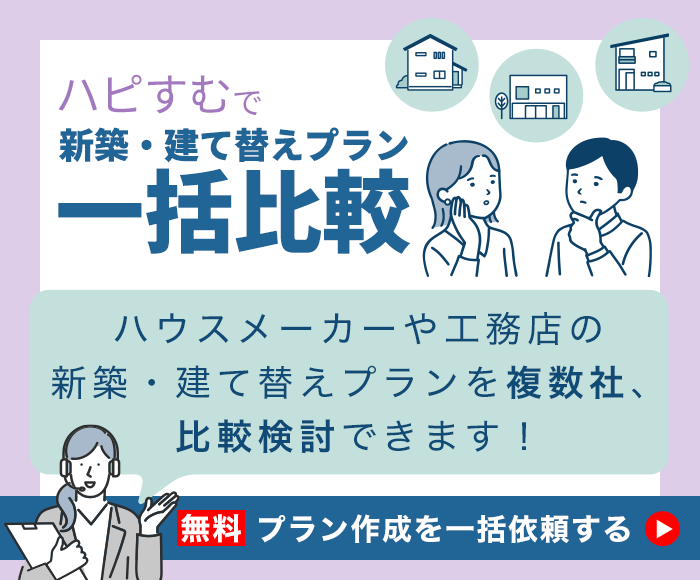2023年12月14日更新
建て替えで組んだ住宅ローンの控除について解説します
目次
建て替えで住宅ローン控除を受ける条件とは

住宅ローン控除とは、正確には「住宅借入金等特別控除」と言い、制度を利用するためにはさまざまな条件を守る必要があります。
住宅ローン控除を利用するためには、どのような条件である必要があるのか、基本的な条件を見てみましょう。
住宅の床面積
住宅ローン控除の適用を受けるためには、対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であることが求められます。
マンションの場合は専有部分の床面積、一戸建て住宅の場合は各階の床面積を合計したもので計算します。
住宅ローンの返済期間
住宅ローン控除の適用条件には、ローンの返済期間も含まれており、10年以上返済が続くローンを組んでいる必要があります。
もし、住宅ローンの返済期間が9年の場合は、住宅ローン控除を利用することができませんので注意しておきましょう。
対象物件での居住
住宅ローン控除を受けるためには、自らが居住している住居であること、住民票を移していることが条件です。
控除を受ける年の合計所得金額
年間の所得も住宅ローン控除の条件とされており、各種控除を引いた所得が年間3,000万円以下であることが対象です。
長期譲渡所得の課税の特例などの適用がない
住宅ローン控除では、所得税の控除を二重で受けることができないため、長期譲渡所得の特例といった他の軽減税率と同時に利用することができません。
12月31日までに住宅を取得している
住宅ローン控除は、12月31日に住宅を取得していれば翌年から制度を利用することができます。
つまり、平成30年12月31日までに居住を開始していれば、平成30年分の確定申告分から対象になり、平成31年1月1日から居住を開始すると、平成31年分の確定申告の対象となるのです。
対象物件での居住状態
居住状態も条件に含まれており、建て替え後6カ月以内に新居に住み始めること、さらに、上の項目でもあるように、12月31日まで住みつづけていることも必要です。
この居住状態の判断は住民票を移してからの期間で判断されますので、住んでいても住民票を移していないと、住宅ローン控除の対象とはなりません。
建て替えで受ける住宅ローン控除は年度によって違うの?
住宅ローン控除を利用した場合、控除額は年度によってどれくらい変わるのでしょうか?
住宅ローン控除の控除額は景気などを勘案して定期的に変更されており、平成26年3月までは控除率が1%、最大控除額は10年間で合計200万円まででした。
2014年4月から2021年12月までの期間に住宅ローン控除を利用した場合については、控除率が1%、最大控除額は10年間で400万円に引き上げられています。
ただ、住宅ローン控除は所得税の支払い額から直接控除される制度のため、所得税額より控除額が大きいと所得税額を超えた部分は控除しきれません。
この場合は住民税の一部を余剰分で控除することができ、2014年3月までは所得税の課税総所得金額の5%、上限9.75万円まで、平成26年4月から2021年12月までは7%、上限13.65万円まで控除できます。
建て替えの住宅ローン控除はどう手続きすればいいの?
住宅ローン控除の手続きは、どのように行えば良いのでしょうか?
住宅ローン控除を利用するためには、適用が受けられる年に確定申告を行う必要があります。
翌年以降については、給与所得者は年末調整で対応できるため、確定申告は不要です。
ただ、自営業者、個人事業主などの毎年確定申告が必要な方については、継続して確定申告を行わなければなりません。
住宅ローン控除に必要な書類
確定申告書
確定申告を行うためには、まず必要事項を記入するための確定申告書を入手する必要があります。
入手方法は税務署の窓口、または国税庁のホームページでデータをダウンロードしてプリントアウトしてください。
確定申告書については、収入形態によって形式が違い、給与所得者は確定申告書Aを用います。
どの確定申告書を使えば良いのかわからない時には、税務署の窓口または確定申告相談の窓口で確認すると良いでしょう。
住宅借入金等特別控除の計算明細書
住宅ローン減税の申請に必要なのが、こちらの住宅借入金等特別控除の計算明細書です。
確定申告書と同じく、税務署の窓口または国税庁のホームページから入手することができます。
住民票
本人確認書類が必要ですので、役所でマイナンバー付き住民票を入手し、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明書も用意しておいてください。
マイナンバーカードを既にお持ちの方については、こちらで代用可能です。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
住宅ローンでいくら借り入れているかを証明する書類です。
住宅ローン契約を結んだ金融機関から郵送されますので、受け取ったら大事に保管しておきましょう。
フラット35を利用している場合については、住宅金融支援機構から送られてきます。
土地・家屋の登記簿謄本(登記事項証明書)
住宅の登記状況を証明する書類です。
法務局の窓口で申請を行えば入手できます。
売買契約書または工事請負契約書のコピー
新築なら不動産売買契約書、建て替えの場合は工事請負契約書が工事を依頼した業者から届きます。
こちらも住宅ローン減税の申請に必要ですので、受け取ったら大事に保管しておいてください。
給与収入があれば源泉徴収票
会社勤めの方など、源泉徴収票が発行されているという方は、こちらも確定申告の際に合わせて提出します。
会社から年末から年始にかけて送られてきますので、確定申告まで大事に保管しておきましょう。
建て替えで受けている住宅ローン控除が途中で適用されなくなる場合があるの?

住宅ローン控除は10年にわたって受け続けることができますが、何らかの理由で控除が中断されてしまうことがあります。
住宅ローン控除が中断される条件について見てみましょう。
合計所得金額が3,000万円を超えた
住宅ローン控除は、合計所得金額が3,000万円以下であることが条件のひとつに設定されています。
そのため、10年の間に所得が増え、3,000万円を超えてしまった場合には住宅ローン控除がその年から中断されてしまうのです。
ただし、一度中断されたとしても、合計所得金額が3,000万円以下になれば、再度住宅ローン控除を受けることができます。
この場合は10年間の控除期間が残っていることが条件ですので、最初に申請してから10年を超えていた場合には再度控除を受けることはできません。
繰り上げ返済をして返済期間が10年未満になった
住宅ローン控除では、ローン返済期間が10年を超えている必要があります。
もし、繰り上げ返済を行って、ローンの返済期間が10年以下になってしまった場合には、住宅ローン控除を受けることができなくなってしまうのです。
繰り上げ返済を行うと利息を減らすことができるのでお得ではありますが、減らせる利息と住宅ローン控除で受けられる減税分を比較し、どちらがお得か判断してから繰り上げ返済を行うようにしましょう。
転勤などにより居住者がいなくなる
住宅ローン控除は、控除を受ける年の12月31日に居住している必要があるため、転勤などで12月31日に住んでいない状態になった場合、控除を受けることができません。
ただし、国内に単身赴任し、家族が家に住んでいる状態なら継続して控除を受けることができます。
また、転勤が終わり、また自宅に戻った場合については、控除期間が残っていれば住宅ローン控除の再開が可能です。
対象物件を賃貸にして賃借人を入居させた
住宅ローン控除は控除を受ける対象者が住んでいることが条件です。
そのため、対象物件を賃貸にし、他人を居住させた場合は住宅ローン控除の対象とはならなくなってしまいます。
この条件は家賃を受け取っているかどうかは関係ありませんので、何らかの理由で友人や親族に家を無償で貸し出したとしても住宅ローン控除を受けることができません。
認定住宅の認定が取り消された
長期優良住宅に認定された住居は、さまざまな税制上の優遇を受けることができますが、長期優良住宅の認定を維持するためには、維持保全状況の記録を作成して保管しておく必要があります。
もし、記録の作成を怠ると、長期優良住宅の認定が取り消されてしまい、各種控除等が受けられなくなってしまうのです。
この優遇の除外は、長期優良住宅であることが条件ではない控除についても行われるため、住宅ローン控除まで中断されてしまいます。
建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?
ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。
実際に建て替えをするべきなのか、リフォームをするべきなのかを検討するためには、プロに現状を相談し、「プランと費用を見比べる」必要があります。
そのときに大事なのが、複数社に見積もりを依頼し、「比較検討」をするということ!
この記事で大体の予想がついた方は次のステップへ行きましょう!
「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」
「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」
そんな方は、簡単に無料で一括査定が可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。
一生のうちに建て替えをする機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!
この記事の監修者プロフィール

タクトホームコンサルティングサービス
亀田融一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。
一括見積もりをする