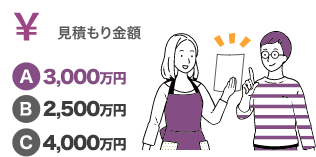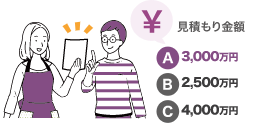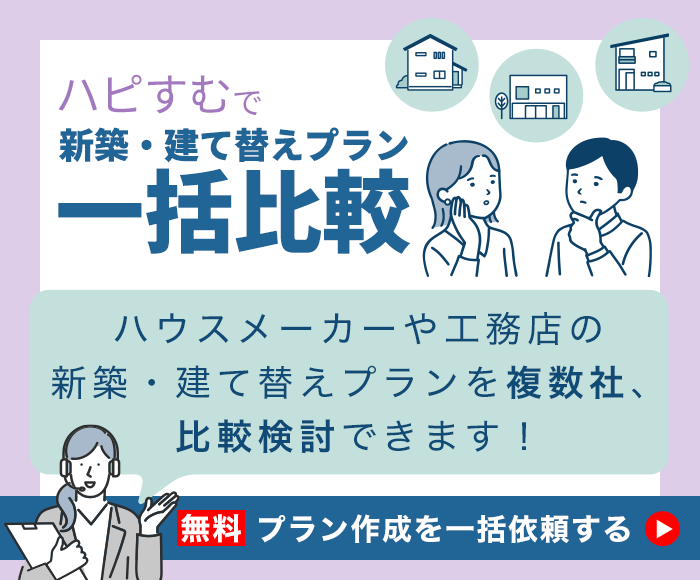2023年12月19日更新
中古住宅の建て替え費用や手順などを詳しく解説
目次
- 1 中古住宅を建て替えるかリフォームするかの判断基準について
- 2 建て替えで業者選びの前にすること
- 3 中古住宅の建て替えやリフォームのメリット・デメリット
- 4 「建て替えvsリフォーム」どちらが得?
- 5 建て替えたいのは規格住宅か注文住宅か
- 6 建て替え費用を抑えるコツ
- 7 建て替えの見積もり相場はどのくらい?
- 8 家を建て替える場合の中古住宅の解体費用について
- 9 家を建て替える場合の中古住宅の解体費用を抑える方法
- 10 住宅を建て替える場合の流れや手順について
- 11 建て替えについての注意点や期間について
- 12 中古住宅を建て替える場合に気をつけたいこと
- 13 木造住宅の建て替えの際申請できる補助金とは
- 14 建て替えとリフォームの税金の違いは?
- 15 建て替えを依頼する際の住宅会社の選び方
中古住宅を建て替えるかリフォームするかの判断基準について

住宅の築年数が経過し、老朽化が気になってきた場合、より快適な住まいにするためには家を建て替えるのかリフォームするのかを、どのような基準で判断すればいいのでしょうか。
中古住宅を建て替えるかリフォームするかを判断する際に、考えるべきことの詳細をご紹介します。
リフォームの定義
リフォームと聞くと風呂やトイレ、外壁、屋根など部分的なものを想像しやすいのですが、「全面リフォーム」となると、建て替えと何が違うのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
全面リフォームも部分的なリフォームも、改修範囲は異なるものの既存の建物の基礎部分を残した状態で、設備や内装などを新しいものと取り替えて作り直します。
近年よく耳にするリノベーションもリフォームの一種と捉えられていたり、一緒の意味で使われている場面があります。
しかし、厳密に言えば「リノベーション」は、既存のものを新しくして原状回復を図ることが目的の「リフォーム」とは少し異なり、デザインや機能を追求して新しい価値を生み出す場合に用いられる言葉です。
建て替えの定義
建物の基礎部分を残して行われるリフォームとは異なり、建て替えは基礎部分もすべて解体して撤去した後に、基礎から新しく建物を建て直すことを指します。
ただ、地域の条例や建築基準法など、関連する建築関係の法の制約を受ける場合があるので注意が必要です。
住み続ける年数を考える
まず、これから先どれくらいその家に住み続けるのかを考えましょう。
築年数が古い住宅の場合、年齢が若かったり親子2代に渡って住む予定があるなど、住み続ける年数が長くなることが予想されるならば、建て替えを行った方がいい場合があります。
逆に築年数がまだ築10年以内だったり数年住んでから違う場所へ引っ越す予定であれば、大がかりな建て替えではなく、劣化や不具合が生じている部分だけリフォームするという選択肢があるでしょう。
将来のライフスタイルの変化を考える
近年、高齢になっても不自由なく快適に過ごせるようにバリアフリー仕様にリフォームするケースが増えています。
リフォームで将来必要になる設備や仕様にしておけば、建て替えのように大規模な工事や高額な費用をかけずとも、長くに渡って快適に住み続けられる住まいを手に入れることができるでしょう。
一方建て替えでは、家族が増えたり二世帯住宅にしたいなどの家族構成の変化に対応することができます。
家族が増えると部屋数を増やしたり、家を二世帯仕様にしてキッチンやお風呂などを2つに増やしたいなどのニーズが高まるため、リフォームよりも建て替えを選ぶケースが多い傾向にあります。
ライフスタイルの変化による住宅建て替えのタイミング

建物自体に特段の問題は発生していなくても、ライフスタイルの変化に伴い住宅の建て替えを余儀なくされるケースがあります。
いったいどのようなライフスタイルの変化が生じれば、住宅建て替えのタイミングになるのでしょうか。それぞれの事情をみていきましょう。
親と同居することになったタイミング
自宅の建て替えを検討するタイミングのひとつが、親と同居することになった場合です。
結婚後別々に暮らしていた親と同居をするようになる理由はいろいろあります。
その一例を挙げてみましょう。
- 父が亡くなり、母が一人暮らしになったため
- 母が亡くなったので、父の身の回りの世話をするため
- 共働きをするので、まだ幼い子どもの面倒をみてもらうため
- 自営業で、近い将来跡を継ぐことになるため
こうした理由で同居が必要になることが考えられるでしょう。
しかし、配偶者の両親と同居するのは一般的に難しいことが多いとも言われています。
そのため選択されることが多いのが完全別世帯型の二世帯住宅への建て替えです。
完全別居型の二世帯住宅は、共同住宅や長屋と同等の仕様が求められるために、工事費は通常の住宅よりも高額になります。
そのため子世帯の年収がまだ低い段階では、工事請負代金に見合うだけの住宅ローンの融資をしてもらうことは難しいと考えられます。
そのようなケースに向いている住宅ローンが、親子ペアローンです。
似た商品に親子リレーローンがありますが、こちらは先に親が単独で返済をしていき、高齢になったところで子が返済をしていくという仕組みです。
しかし、親子ペアローンは、親と子が同時に返済をしていくもので、実質的に2本の住宅ローンが同時に実施される仕組みになっています。
まだ親に十分な収入があるのであれば、子どもと合算をすることで、大きな額の融資を受けることが可能になります。
また、親子それぞれが団体信用生命保険に加入できるので、親に万が一の事態が発生しても、親が返済している住宅ローンを肩代わりする必要はありません。
親子がそれぞれ住宅ローンを利用している形になっているので、住宅ローン控除も持ち分に応じて親子それぞれに適用されるというメリットもあります。
親の介護が必要になったタイミング
既に両親と同居している場合においても、建て替えが必要になるタイミングがあります。
親が病などで倒れて歩行が困難なった場合には、介護が必要になります。幸い軽症だった場合でも、当面のリハビリが必要になることもあるでしょう。
介護やリハビリが必要な状況になれば、既存の部屋の配置では対応できない状況も発生します。
トイレや浴室の近くに親の寝室を配置することや車いすでの移動が可能なようにするなどの工事は、リフォームだけでは対応しきれないケースも考えられます。
そのため、このように親の介護が必要になったときも住宅の建て替えを検討するタイミングだと言えるのです。
ただし住宅のバリアフリー化は、資金の負担を増加させるばかりではありません。
積極的なバリアフリー化を行うことでフラット35Sの基準に適合すれば、10年間金利を引き下げてもらうことができます。
子どもの成長に伴い部屋数を増やすことになったタイミング
子どもが成長するとともにプライバシーに対する配慮が必要になってきます。
このため、兄弟同室だった部屋を増やすことも検討しなくてはいけません。
しかし状況によっては、単に一部屋を増築するだけでは根本的な問題を解決できないこともあります。
その場合は、全面的な建て替えを検討することもあるでしょう。
通常は住宅ローンを借りて建て替えをすることになりますが、その際に考慮すべき問題は、将来の教育資金の確保です。
子どもが大学に進学した場合の入学金や授業料を捻出できるようにローンの返済をしなくてはいけません。
住宅ローン返済期間中のキャッシュフロー表を作成するなどして、将来を見据えたうえで、住宅ローンの返済額を決める必要があります。
子供が独立したタイミング
子どもが結婚をして別世帯をもつと、急に家の中が広々と感じられるようになります。
さらに足腰が弱ってくると、2階への上り下りが苦痛になり、1階だけを生活エリアにしたいという思いが出てくるケースもあるでしょう。
このような場合は「減築」という方法があります。減築というのは、文字どおり建物の一部を解体して、延べ床面積を減らす方法です。
いらなくなった子供部屋を解体したり、2階を全て解体して平屋にしたりなど、いろいろな減築方法が考えられます。
減築は単に解体するだけではなく、その後の補修もセットになります。
2階を解体したのであれば、その撤去後に屋根を構築します。
1階の部屋を減築したのであれば、その撤去後に外壁を築き上げます。
こうして不要な部屋を減らすことで快適な生活を過ごせるようになるという方法もあるのです。
中古住宅の寿命を考える
今住んでいる家の築年数が古い場合、もしリフォームを選んだとしても家の寿命がすぐにおとずれて、数年後に建て替えが必要になる可能性があります。
リフォームから数年で建て替えをするのであれば最低限の修理・修繕などで留めておくという判断もできるため、この先家の寿命がどの程度残っているのかを判断した上で、リフォームか建て替えかを選ぶといいでしょう。
では、構造別の家屋の耐用年数は具体的にどれくらいなのでしょうか。構造別の耐用年数を見ていきましょう。
- 木造:約22年
- 軽量鉄骨造:約19〜27年
- 鉄筋コンクリート造:約47年
上記の耐用年数はあくまで目安であり、家の環境や修繕が行われた頻度などによっても耐用年数は大きく変わります。
上記では木造は約22年とされていますが、実際は築30年以上経過しても問題なく住める家はたくさんあります。
そのため、築年数だけでリフォームか建て替えを選ぶ前に一度住宅診断を受けておくといいでしょう。
設備機器や資材の老朽化
水回りや浴室などの水回り設備は、毎日利用する箇所であるがゆえに劣化が気になりやすい箇所です。
使用頻度などによっても異なりますが、浴室の寿命は約10年〜約15年、キッチン設備の寿命は約20年と言われています。この年数を過ぎるとさまざまな不具合が出てくる可能性が高くなるでしょう。
木造住宅の場合は、築30年を超えると建て替えや住み替えを検討する人が増えると言われています。これは、30年を過ぎると設備機器だけではなく、屋根や外壁材などの資材等も老朽化が進み、複数の箇所で不具合が出てくるためだと考えられます。
このように、設備機器や資材の老朽化が進んだタイミングで建て替えを検討する人も多いのです。
ローンの支払いが終わった後に建て替えるという選択肢も
リフォームや建て替えを検討している人の中には、まだ住宅のローンが残っている人も少なくありません。
ローンが残っていても借り換えなどのダブルローンを組むことで建て替えは可能ですが、ローンの金額がその分増えるため返済が困難になる恐れがあるでしょう。
もし家の不具合が初期の段階であるならば最低限の修理・修繕をして、ローンを支払い終えた後に建て替えをするという方法もあります。
1981年以前に建てられた住宅は建て替えた方がいい
1981年6月以前に建てられた住宅の場合、「旧耐震基準」で建てられた可能性が高いでしょう。
旧耐震基準の建物は震度6強以上の地震があった場合、倒壊の危険が高いと言われています。
一方、1981年以降に建てられた家は「新耐震基準」となるのですが、「新耐震基準」では震度6〜7の地震が発生しても倒壊や崩壊しないことを基準としています。
地震が多い日本ではいつ大規模な地震が発生するかわからないため、1981年以前に建てられた中古住宅の場合は、人命を優先するためにも建て替えることを検討しましょう。
消費税の引き上げや金利の変動による住宅建て替えのタイミング

消費税の増税が2019年の10月に予定されています。これにより消費税は8%から10%に引き上げられます。
こうした増税を控えた時期というのも住宅建て替えのタイミングになることがあります。
また金利の動向も建て替えのタイミングとは無縁ではありません。
さまざまな経済動向が住宅の建て替えのタイミングにどう影響するのかみていきましょう。
消費税の引き上げに合わせた住宅建て替えの為の資金計画
消費税の引き上げの日がゆるぎないものになれば、建て替えの決断を急ぐ必要も出てくるでしょう。
引き上げ率2%ということは、たとえば建築工事費が3千万円なら、60万円も支払額に差が生じてきます。
この差額によって資金計画が大きく変わってくることもありますから、建て替えを消費税引き上げの前にするのか、後でもいいのかの決断は非常に重要だと言えるでしょう。
例えば増税後の対策として、すまい給付金の増額や次世代住宅ポイントの付与、住宅ローン減税の3年間延長、贈与税非課税枠の拡大など、様々な公的措置が予定されているため、条件次第では増税後に建て替えた方が有利になります。
増税前後で資金計画がどう変わるのかを十分に検討する必要があります。
マイナス金利政策により低金利なタイミングで建て替えローンを組む
国のマイナス金利政策により、現在住宅ローンは低金利で推移しています。
この状況に乗じて建て替えローンを利用することによって住宅を建て替えるタイミングとすることがあります。
建て替えローンというのは、現在住んでいる住宅がローンの返済中である場合、建て替え費用に加えてローンの残債相当額を融資してくれるものです。
これを利用することで、現在の住宅ローンを一括返済して、建て替えを実現することができます。
もし現在の住宅ローンが高金利の時代に借りたものであれば、建て替えローンを利用することで、一気に金利の支払いが軽減することになります。
つまり低金利の今だからこそ、建て替えローンを利用して建て替えを実施することで費用を抑えることができると言えるのです。
木造住宅を建て替えるまでの寿命を伸ばせるのか?
家を建て替えたいと思っていても、資金面や生活面などからすぐに建て替えることが難しいこともあるでしょう。では、木造住宅を建て替えるまでの寿命を伸ばすことは可能なのでしょうか。
一般的に木造住宅の寿命は約30年と言われています。しかし、最近では資材や技術が向上し、現在では木造住宅の寿命は約80〜100年と言われるほどになってきました。
そうは言っても、すでに老朽化が進んでいる住宅の場合は、ここまで長く住み続けることは難しいでしょう。
建物の寿命を延ばすためには、プロに点検を依頼し、特に劣化が進んでいる箇所はメンテナンスやリフォームする必要があります。部分リフォームであれば費用を抑えながら住宅の寿命もある程度は延ばすことができるでしょう。
建て替えで業者選びの前にすること

家屋の建て替えは、今後の住まいの快適性を大きく左右するため、後悔しない住宅づくりをする必要があります。
建て替えの業者を選ぶ前にいくつかの項目を決めておくことで、業者選びや計画などをスムーズに進めることができます。
では、具体的にどのような内容なのか詳細を見ていきましょう。
建て替えの目的を明確にする
建て替え業者を選ぶ前にまずは建て替えの目的を明確にします。
住宅の老朽化やライフスタイルの変化、家族構成の変化など建て替える理由は様々ですが、建て替えをする目的を明確にしないと業者に建て替えプランを提案される際、決断に迷ったり、必要のない工事まで行ってしまい、後悔する可能性があるからです。
目的を明確にしておけば、業者とのやりとりもスムーズにでき、建て替えに最適なプランを提案してもらいやすくなります。
建て替え費用の予算を決めておく
次に重要なのが建て替えの予算です。
建て替えの際には様々な設備やプラン、デザインなどがあるので「少しでもいい家を」と思って何でも選んでいると、予算をオーバーしやすくなります。
少しのオーバーならなんとかなると思い設備などを選んでいると、結果的には少しの差が積み重なって予算を大幅にオーバーする可能性も高くなるでしょう。
建て替え費用にかける予算を決めておくことで、予算内でできることをある程度絞れるため、設備や仕様などが選びやすくなるでしょう。
どのような家にしたいか家族で決めておく
新しい住宅を建築するということは、今後家族がその家を拠点として生活するということです。
そのため、できるだけ家族の意見を汲んだ家にすることが理想です。
しかし、現実には家族全員の意見を100%取り入れた家を作るのは難しいでしょう。
その場合、譲れることと譲れないことを家族で決めて、優先順位をつけてから業者と交渉すると、家族の意見もまとまりやすくなり、決断もしやすくなります。
中古住宅の建て替えやリフォームのメリット・デメリット
次に、中古住宅を建て替えた場合とリフォームした場合のメリット・デメリットを見ていきましょう。
中古住宅を建て替える場合のメリット
中古住宅を建て替える場合の主なメリットは以下の通りです。
- 今住んでいる家を取り壊して新しい家を建てるため、築年数がリセットできる
- 間取りや設備など自由に選ぶことができる
- 地盤改良や構造の強化を含めた、大掛かりな地震対策ができる
- 比較的簡単に多額のローンを組むことができる
建て替えの最大のメリットは、何と言っても新しい家を建て直せることでしょう。
築年数がリセットされるため、今後長く住み続けることができます。
間取りや設備なども自由に選べるため、前の家と違った間取りやデザインを選ぶことも可能です。
また、リフォームではなかなか難しい、家の構造強化ができるため地震に強い家になるでしょう。
中古住宅を建て替える場合のデメリット
中古住宅を建て替える場合の主なデメリットは以下の通りです。
- 家を取り壊し解体、撤去する費用がかかる
- 既存の家を撤去した際、地盤に問題があれば地盤工事が必要になる
- 家を新築するため建設費が高額になる
- 工期が長くなりやすい
- 固定資産税、不動産取得税など税金がかかる
- 仮住まいをしなければならないため賃貸の家賃が必要になる
- 引っ越しを2回しなければならない
- 思い出のある家がなくなってしまう
中古住宅を建て替えることで新しい家を手に入れることができますが、同時に思い出がつまって愛着がある家を解体しなければなりません。
また新しい家を建設する費用の他にも解体・撤去・地盤調査にかかる高額な費用が必要になるため、余裕をもった資金計画が必要となります。
中古住宅をリフォームする場合のメリット
中古住宅をリフォームする場合の主なメリットは以下の通りです。
- 大規模なリフォームでなければ住みながら工事できる
- 引っ越しをしなくてもいい
- 建て替えより費用を抑えることができる
- 予算に合わせて工事内容を選ぶことができる
- 内装や設備などを新築同様にすることも可能
- 建て替えより税金がかからない
- 自治体の補助金が利用できる場合がある
- 住んでいる家を残しておくことができる
- 施工期間が建て替えより短い
中古住宅をリフォームする場合の最大のメリットは、既存の家を取り壊さず新築同様にできることでしょう。
既存のものを最大限に利用することで、建て替えよりも費用が抑えられます。
また各自治体によってはリフォームに対する補助金制度もあるため、それらを利用するとさらに負担が軽減されるでしょう。
中古住宅をリフォームする場合のデメリット
中古住宅をリフォームする場合の主なデメリットは以下の通りです。
- 大規模な間取り変更ができない可能性がある
- 構造強化をしたい場合、大規模な工事が必要となるため費用が高額になる
- 構造上の劣化が見られた場合、建て替えを行った方がいいケースがある
- 1981年以前に建てられた場合、耐震性に問題がある
- リフォーム時にシロアリ被害などが見つかった場合駆除や予防の費用がかかる可能性がある
中古住宅をリフォームする場合のデメリットは、建て替えではないため、リフォーム後数年経過したら再度リフォームが必要になる可能性があることでしょう。
築年数が古くなればなるほど劣化部分が増えていくため、修理修繕などは避けて通れない道です。
また、実際に床を剥がして床下を見てみると、シロアリ被害が発生していたというケースも少なくありません。
その場合、シロアリ駆除や防蟻処理を行わなければならず別途費用がかかってしまうでしょう。
「建て替えvsリフォーム」どちらが得?
建て替えとリフォームの違いについてご説明してきましたが、では実際にどちらの方がお得なのでしょうか。
費用の比較
建て替えでは、家を建て替えるだけの費用だけではなく、既存の建物の解体費や処分費、建て替え中の仮住まい、引越し費用なども必要になります。
近年は建築基準法が改正されたことで施工工事費用が上昇傾向にあります。
また、建て替えを選ぶことで固定資産税や都市計画税など各種税金がかかるようになることも覚えておきましょう。
一方で、全面リフォームを選んだ場合なら、費用は一般的に建て替えの約7割から約8割程ですむことがほとんどです。
リフォーム内容や建て替えの内容によって費用は大きく異なってくるので、具体的に費用を提示することは容易ではありません。
しかし、解体費用などを含めた建て替え費用に関しては約3000万円程は見込んでおきたいところです。
全面リフォームならば約2000万円程を想定しておくと良いでしょう。
キッチンのリフォーム

キッチンのリフォームは、約50万円〜約150万円が相場の価格帯です。
キッチンは、選ぶスタイルや選ぶグレードによって価格が大きく異なります。
壁付けのキッチンから対面のペニンシュラキッチンに変更するなど、位置の変更を伴う場合は、内装工事に加えて給排水配管工事・ガス配管工事・換気ダクト配管工事費などがともなうため、工事費用が高くなります。
また、扉の面材やキッチンカウンターの素材によっても金額は増減します。
風呂場・浴室のリフォーム

浴室のリフォームは、約50万円〜約150万円が相場の価格帯です。
今の浴室が在来工法の浴室か、ユニットバスかによっても金額は異なります。
ユニットバスからユニットバスへの交換工事のほうが、費用も工期も抑えられるます。
浴室の扉を交換する場合は、洗面所との間の壁の解体も必要になることが多いでしょう。
洗面所のリフォーム

洗面所のリフォームは、約20万円〜約90万円が相場の価格帯です。
洗面台の大きさや収納棚、オプションの有無によっても金額は異なります。
クロスや床材の張り替えを同時に行うこともあります。
トイレのリフォーム

トイレのリフォームは、約20万円〜約50万円が相場の価格帯です。
和式のトイレから洋式トイレへの交換や、トイレの位置を変更する工事、広さを広くする工事などでは50万円以上かかることもあります。
場合によっては、汲み取り式のトイレから浄化槽へと変更することもあり、その場合は浄化槽の設置費用が約60万円〜約80万円程度かかると考えておきましょう。
地域によっては、補助金を受給できる場合も多いので、その場合は大幅に低く抑えることができます。
リビングのリフォーム

リビングのリフォームは、約10万円〜約200万円と、相場の価格帯の幅が大きいという特徴があります。
リビングでは、クロスやフローリングの張り替え、間取りの変更など、どのような工事をするかによって金額は大きく異なります。
床暖房の設置や、壁の撤去・新しい建具の設置など大規模なリフォームになると金額は高くなるでしょう。
外壁のリフォーム

外壁のリフォーム工事は、約100万円〜約280万円が相場の価格帯です。
外壁のリフォームは、住宅の坪数や選ぶ塗料によっても金額は異なります。
雨風や紫外線から住宅の構造体を守るために、定期的に塗り替える工事を行う方も多く見られます。
塗り替え以外にも、耐久性を高めるために外壁の重ね張りや張り替えを行うこともあります。
屋根のリフォーム

屋根のリフォーム工事は、約50万円〜約170万円が相場の価格帯です。
雨樋の交換工事などや外壁のリフォーム工事と同時に行うと足場代が節約できます。
塗り替えだけにとどまらず、屋根材そのものの葺き替えや重ね葺きまで数種類のリフォーム方法があります。
フルリフォーム
フルリフォームは、住宅の坪数と、リフォーム範囲によって金額が大きく異なりますが、約700万円〜約2,500万円が費用相場です。
主に柱や土台などの主要構造部だけを残して、サッシ・外壁・屋根、それに内部全体まで解体し改装するフルリフォーム。
内部空間だけを対象に、間仕切り壁なども取り払って改装するものの、サッシ・外壁などには手をつけない内部リフォームなど。
フルリフォームにもいくつかのパターンがあります。
築20年目程度までの住宅では内部だけのリフォーム、築25年程度を超える住宅では、内外部ともにフルリフォームすることが多いでしょう。
建て替えたいのは規格住宅か注文住宅か
建て替える際に規格住宅か注文住宅かどちらかを選ぶことになります。
規格住宅と注文住宅のメリット・デメリットをそれぞれ見ていきましょう。
規格住宅のメリット・デメリット
規格住宅の主なメリットとデメリットは以下の通りです。
【規格住宅のメリット】
- 価格が決まっていることが多く予算が立てやすい
- デザインや仕様が決まっているためイメージしやすい
- 注文住宅より割安なことがある
- 時代にあった間取りや設備になっている
【規格住宅のデメリット】
- 間取りが変更できない
- 広さや仕様が決まっている
- シンプルな仕様が多い
- 土地と合わないケースがある
注文住宅のメリット・デメリット
注文住宅の主なメリットとデメリットは以下の通りです。
【注文住宅のメリット】
- 自分が希望する間取りにできる
- 設備などが自由に選べる
【注文住宅のデメリット】
- 価格が高額になりやすい
- 間取りや設備などを一から決める必要がある
規格住宅と注文住宅どちらを選ぶか
規格住宅と注文住宅どちらもメリットとデメリットがありますので、一概にどちらがいいのか断言することはできません。予算や新しい住宅に求めることなどが合致した方が最適な住宅と言えるでしょう。
規格住宅の方が割安で最新の設備が整っていることが多いため、間取りや仕様が希望通りで土地に合えば規格住宅がおすすめです。
一方で、凝ったデザインや間取りにしたい場合や、規格住宅に希望の仕様がない場合は注文住宅の方を選んだ方がいいでしょう。
建て替え費用を抑えるコツ

リフォームと建て替えについて述べてきましたが、ここでは建て替えを選んだ際にその費用を抑えるコツをご紹介します。
できるだけ安く建て替えをしたいとお考えの方は、費用を抑えるコツを知っておくと満足度の高い建て替えを実現できるでしょう。
木造住宅にする
日本では昔から木造住宅が多いのですが、最近では鉄筋コンクリート構造や鉄骨構造の住宅も増えてきています。
どのような構造でもメリットとデメリットはありますが、木造住宅には費用を抑えられるというメリットがあります。
材料費も比較的安く済みますし、防錆、耐火処理も不要で、建物が軽いので基礎工事の費用も抑えられます。
鉄筋コンクリートや鉄骨の住宅に比べて耐震や耐火などに不安が残るという人もいるかもしれませんが、近年の木造住宅は技術が向上したこともあり、あまり心配しなくてもよいでしょう。
一言で木造住宅といっても伝統的な在来工法と2×4工法とがあり、それぞれの工法にメリットとデメリットがあります。そのため、建て替えの際には専門業者に希望を伝えた上でアドバイスを仰ぐなどしてよく検討しましょう。
昔から日本人に馴染みのある木造住宅は木の温もりを感じられ、精神的にもリラックスできる効果があると言われています。
費用を抑える目的以外にも木造住宅にするメリットはたくさんあるのです。
屋根・床・壁などのグレードを落としてみる
家を建て替えるにあたって理想に合うようなデザインや素材を選びたいと思っている方もい多いでしょう。
しかし、あまりにも理想を追い求めすぎると、思っていたよりも費用が高くなってしまう場合もあります。
理想に近いもので、グレードを落とした素材を使った屋根や床、壁などにすると費用を抑えられます。
見積もりの際にはどのグレードの素材が使われているかを確認するようにしましょう。
また、気候や手入れのしやすさを考慮した素材を選ぶことで、長期間使用することができるので、将来的なメンテナンスコストがかからず、結果的に費用を抑えることに繋がります。
建築費以外の神事や仮住まいを工夫する
解体整地後の地鎮祭や建築途中での上棟式なども簡素に済ませましょう。
工事中の仮住まいにかかる費用は、約6ヵ月分の家賃と敷金礼金にかかる費用が必要です約100万円程度必要でしょうが、マンスリーマンションや公団なども検討すべきでしょう。
自治体によっては格安の仮住まい住宅の特別枠がありお得です。
建て替えの資金援助なら贈与税が非課税対象になる
建て替えを決めた際、ローンを利用するのではなく身内から資金援助をしてもらうという方もいるでしょう。
このようなケースであれば通常は贈与税の対象となりますが、期間限定措置として2019年2月現在では「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」が適用されます。
ただ、贈与者の範囲や贈与を受ける人の年齢、所得、建て替えを終えて居住する時期などに条件があります。
贈与者は実の父母と祖父母に限られ、受贈者は20歳以上でその年の所得が2000万円以下であること、翌年の3月15日までに居住することなどが条件としてありますが、詳しくは税理士等に問い合わせてみましょう。
建て替えの見積もり相場はどのくらい?

建て替えの見積もりを取っても、一般の人にとって、見積もりの金額が安いかどうかは判断しにくいものです。
さらに、見積もりの金額は、依頼した業者によって数百万円以上の差が出ることもあります。
見積もりを取った時、予想外の金額を提示されて慌てないように、約30〜40坪の平均的な戸建住宅を例に、建て替え費用の相場を知っておきましょう。
建て替えの見積もり相場
建て替えの見積もりは、約30坪~40坪程度の戸建住宅の場合、約2500〜3600万円が相場です。
なお、解体する建物と新しく建てる建物の規模や、使用する構造材、設備のグレード、施工エリア等によって見積もりの金額は変動します。
建て替えの見積もり詳細と相場
建て替え費用は、主に以下の内訳になっています。
- 建物の解体費用:約100〜250万円
- 設備代:約300〜500万円
- 建築費用:約1900〜2500万円
- その他諸費用:約200〜300万円
※「その他諸費用」には、住宅ローン手数料、仮住まい費用、税金等が含まれます
建て替えの見積もりを見る時は費用の詳細も確認する
建て替えの見積もりを取ったら、建築費用だけでなく、解体費用や諸費用といった詳細の金額まで記載されていることを確認しましょう。
まれに、建て替えの「建築費用だけ」の見積もりを作る住宅会社もいますが、見積もりが安いと錯覚して契約すると、後から他の費用も必要なことに気づいて予算オーバーするかもしれません。
あるいは、「一式」とだけ書かれていて、どの費用にいくらかかるかわからない、不親切な見積もりを作る悪質な業者も存在します。
解体費用や設備代などの詳細も含めて、合計金額の見積もりを作ってくれるような、良心的な住宅会社を見つけましょう。
建て替え費用の見積もりを取る時に注意すべきこと
建て替えは、依頼主の希望次第で見積もりもプランの内容も全く異なります。
希望の予算に最も近い見積もりを作ってもらい、納得した状態で工事に進むためにも、以下の点に注意しておきましょう。
相見積もりを取って建て替え費用やプランを比較する
建て替えを行う住宅会社を選ぶ時は、複数の会社で相見積もりを取って、金額や打ち合わせの雰囲気等を比較することが大切です。
また、相見積もりを取ることは、プランニングのダブルチェックにも効果的です。
例えば、建て替え後に導入したいキッチンが、A社では安く仕入れられても、B社は価格が割高になっているケースもあります。
建て替えの相見積もりは全社に「同じ条件」で依頼すること
建て替えの相見積もりは、全ての業者に同じ条件で依頼することが重要です。
もし異なる条件で複数社に相見積もりを依頼しても、金額は当然バラバラになり、プランニングの内容も比較できなくなってしまいます。
見積もり金額はプランニング次第でアップすることもある
建て替え後の家に満足するためには、初回の見積もりだけで契約に進んでしまわず、納得行くまで見積もりを作り直してもらうことが大切です。
しかし、プランニングを進めるうちに、設備の仕様変更や間取り変更などでコストがかさみ、プランが最終決定する頃には、見積もり金額が大幅にアップしている可能性もあります。
その他、プランの変更に伴って仮住まいの期間が長くなったり、入居後に買う家具が増えたりして予算をオーバーする恐れもあるため、当初の見積もり金額よりも多めに資金を準備しておくと良いでしょう。
リフォーム会社紹介サービスの「ハピすむ」は、 お住まいの地域や建て替え・リフォームのニーズを詳しく聞いた上で、 適切で優良な会社を最大3社紹介してくれます。
複数の大手リフォーム会社が加盟しており、 高額のリフォームを検討している方も安心してご利用いただけます。
建て替えで必要な工事費用以外の費用
建て替えでは、ご紹介した費用の他にもさまざまな費用が必要になります。
具体的にどのような費用なのか見ていきましょう。
仮住まいと引っ越しにかかる費用
建て替え時には今まで居住していた家を撤去しなければならないため、賃貸などに仮住まいをすることになります。
解体工事から新居へ入居するまでの期間は一般的に約6ヵ月程度であるため、仮住まいにかかる費用は、約6ヵ月分の家賃と敷金礼金にかかる費用でしょう。
また、建て替えの際には仮住まいへの引っ越しと新居への引っ越しが必要になるため、合計2回の引っ越し費用が必要です。
もし、荷物が多い場合はトランクルームなどを借りて新居完成まで荷物を預けておくと、引っ越し時の荷物が少なくなり引っ越し費用が抑えられる可能性があるでしょう。
しかし、その分トランクルームのレンタル費用がかかります。
一般的に借家は短期契約を嫌いますので、マンスリーマンションや公団なども検討すべきでしょう。
自治体によっては格安の仮住まい住宅の特別枠がありお得です。
ローンや登記の手続き費用と近隣への挨拶品などの費用
住宅ローンの手続きや、解体・建築時に必要な登記の際にも手数料がかかります。
一般的に手数料は現金で支払わなければならないため、あらかじめ現金を用意しておきましょうしょう。
また、上記の手数料以外にも、近所への挨拶の品や上棟式などの費用がかかります。
これらの諸経費や仮住まいの費用だけでも現金で約200万円程度が必要になるでしょう。
そのため、現金を手元に残しておく必要があります。
家を建て替える場合の中古住宅の解体費用について
家を建て替える場合、必ず中古住宅の解体工事を行います。
解体工事にかかる費用は家の構造や立地などの条件によって異なります。
では、具体的に解体費用の相場はどれくらいなのか見ていきましょう。
中古住宅の解体費用は立地や条件により大きく変動する
家の解体工事費用は、立地や条件、地域によって大きく変動します。
例えば、接する道が狭く、解体する家で重機やトラックの利用ができない場合、人力で家を解体したり廃材を運び出すなど、手作業で行う項目が多くなります。
そのため、一般的な解体費用よりも割高になる可能性があるでしょう。
また、住宅街で近隣の家との距離が近い場合、防音や埃・ゴミなどの対策を強化しなければならないため、防音対策をするための養生が必要です。
その分、かかる費用も高くなるでしょう。
その他にも家が一般的な住宅よりも大きかったり、駐車場や倉庫などがある場合はそれらも解体する必要があるため、解体費用がより高くなる傾向にあります。
解体工事を依頼する際には、解体しなければならないものをリストアップし立地などを伝えた上で見積もりをもらうようにしましょう。
中古住宅の構造ごとの解体費用相場
中古住宅を解体する場合、家の構造によって費用相場が変わります。構造別の解体費用の相場は以下の通りです。
【中古住宅の構造別解体費用相場】
木造の場合(30坪〜39坪あたり)
- 解体工事:約75万円〜約120万円
- 付帯工事:約10万円〜約100万円
※付帯工事…設備撤去費、残置物処分費、養生費、諸経費など
鉄骨造りの場合
- 解体工事:約90万円〜約160万円
- 付帯工事:約10万円〜約100万円
鉄筋コンクリートの場合
- 解体工事:約120万円〜約200万円
- 付帯工事:約10万円~約100万円
解体費用の相場は立地や条件によって異なるとご説明しましたが、同じ30坪でも重機が使用できる場合とできない場合とでは金額が大きく変わります。
また鉄骨造や鉄筋コンクリートの方が木造より耐久性や耐火性に優れ頑丈なため、解体するときの手間や人手、工期などがより必要になります。そのため、解体費用も木造より高額になる可能性が高いでしょう。
地中埋設物があると解体に追加費用がかかる
地中埋設物とは、家を建てる際に出たコンクリート・ゴミ・瓦などの廃材を業者が回収せずに地中に埋めたものや、井戸、大きな石などのことです。
中には浄化槽が埋められたままのケースがあり、その場合浄化槽を掘り起して取り除く作業が必要です。
地中埋設物を撤去せずにそのままにしておくと、新しい家を作る際に地盤が弱くなる可能性があります。
そのため、地中埋設物を見つけたら解体業者に撤去を依頼するのが一般的です。
また、地中埋設物は、住宅を壊して撤去した後に地面を掘り起さないと確認できないため、見積もり時には把握できません。
見積もり時に地埋設物が予想できていなかった場合、追加費用として請求される可能性があるでしょう。
地中埋設物の撤去費用の相場は数万円〜数十万円ほどです。
また、建物にアスベストが使用されていた場合も追加費用がかかることがあります。
アスベストは健康に被害を与えるため、法律で決められた方法に基づいて撤去することが義務づけられています。
しかし、解体業者の中には地中埋設物やアスベストを利用して高額な費用を請求し、トラブルに発展するケースがあります。
もし追加料金を請求された場合、どのような埋設物の撤去なのか、撤去する費用はいくらなのかを請求書に細かく記載してもらいましょう。
家を建て替える場合の中古住宅の解体費用を抑える方法
家を建て替える場合、解体費用や建築費用など高額な費用がかかります。
少しでも解体費用を抑えるためにはどのような方法があるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
自治体の補助制度を利用する
家屋を解体する際には自治体の補助制度を利用できることがあります。
全ての自治体ではありませんが、一部の自治体では解体補助金制度が設けられています。
補助金制度があるかどうか、自分が住む市町村に問い合わせを行い、確認しておくと良いでしょう。
尚、空き家を解体する場合には、自治体ごとに補助金や助成金を支給してくれる制度があります。
では、どのような住宅が対象となるのか見ていきましょう。
【空き家解体補助金制度の対象住宅例】
- 個人が所有している建築物である
- 1年以上居住しておらず、居住実績がない
- 一戸建て住宅または併用住宅
- 公共事業で移転等の保証対象ではない
- 抵当権が設定されていない
- 放置することで衛生上害を及ぼす可能性がある住宅
- 放置することで倒壊の危険性がある住宅
- 市内の解体業者が工事を行う
- 解体工事着手前に申請していること
- 新耐震基準に適合していない住宅
- 自治体の空き家バンクに登録されている住宅
- 住民税を滞納していないこと
対象住宅は各自治体によって詳細が異なることがあるため、解体補助金制度を利用したい場合は役場に問い合わせて確認しましょう。
建物滅失登記手続きを自分で行う
「建物滅失登記」とは、解体して建物が無くなったことを法務局の登記簿に登記することです。
この手続きを行わないと、固定資産税を支払い続けなければならなかったり建て替えができないなどのデメリットが生じます。
また、建物滅失登記は申請義務があるため、手続きを行わないと10万円以下の罰金が発生する場合があります。
「登記」というと書類作成や手続きが難しいと感じて専門家に依頼する人も多いのですが、この場合、約4〜5万円を目安に依頼料金がかかります。
しかし、建物滅失登記の手続きは意外と簡単にできるため、自分で行えば費用を抑えることができるのです。
建物滅失登記の手続き方法は以下の通りです。
【建物滅失登記の手続き方法】
〈必要なもの〉
- 建物滅失登記申請書(法務局のホームページからダウンロード可)
- 取り壊し証明書(解体業者から取り寄せる)
- 解体した建物の位置が掲載された地図
- 解体業者の登記事項証明書
- 解体業者の印鑑証明書(解体業者から取り寄せる)
〈建物滅失登記の期日〉
- 建物の解体工事後1カ月以内
〈手続き場所〉
- 建物がある場所を管轄する法務局または郵送
解体をハウスメーカーではなく解体業者に直接依頼する
建て替えを決めた場合、ハウスメーカーに解体も含めて依頼するケースがあるのですが、実際の解体は解体業者が行うことが多いため、仲介のための手数料が必要になります。
中間マージンの割合は解体費用の約10%が目安になるため、解体費用が高額であれば手数料も高額になるでしょう。
このような手数料は解体業者に自分で直接依頼することで抑えることができるため、解体工事を行う場合はできるだけ自分で解体業者を探して依頼するようにしましょう。
住宅を建て替える場合の流れや手順について

住宅の建て替えには、決まった手順や流れ、申請のタイミングがあります。
ハウスメーカーや工務店から建て替えの流れや申請書の手続き等の説明がありますが、事前に知っておき、建て替えをスムーズにすすめましょう。
【1】建て替えを依頼するハウスメーカー・工務店を選ぶ
住宅の建て替えをしようと思ったら、まず施工を依頼する建築会社を選ばなくてはなりません。
住宅を建築する会社は、ハウスメーカーや工務店などさまざまです。
それぞれ住宅のスタイルや構造・施工・デザインなどに色々な特徴があります。
ハウスメーカーの展示場や工務店の見学会、家族・友人の紹介などから、候補となる会社を複数選び、数社に間取りを作成してもらって見積もりを依頼しましょう。
【2】1社に絞り契約・設計のプランを決める
数社の建築会社から間取りと見積もりが提出されたら、それを検討し、建て替えを依頼する会社を1社に絞りましょう。
建て替えを依頼する会社が決まったら、その会社と「工事請負契約書」を交わします。
工事請負契約書には、住宅の設計図・仕様・金額・工期等が添付・明記されています。
工事請負契約書は法的拘束力のある契約書です。
契約までに、間取り・見積もりを十分検討し、不安な点・不明な点がないようによく理解してから契約するようにしましょう。
契約後は、図面・仕様などの詳細な打合わせが行われ、最終の施工図面が決定されます。
【3】住宅ローンを申請する
住宅を建て替えする際、ほとんどの人が住宅ローンを借りて住宅資金を準備します。
「工事請負契約書」を交わす前に、数社の金融機関を検討して、住宅ローンの審査が通ることを確認する必要があります。
「工事請負契約書」を交わした後に金融機関に正式な住宅ローンの申請を行うのですが、あらかじめ住宅ローンの実行はいつになるのか、ローンの支払いがいつからはじまるのか、つなぎ融資はいくらぐらいになるかを確認しておきましょう。
建築会社への支払いは、住宅完成時に全額支払うという形式ではありません。
工事請負契約書に明記されていますが、「契約時」「着工時」「上棟時」「中間金」「竣工時」など数回に分けて支払うことになっています。
住宅ローンが実行されるのは、住宅が完成し、表示登記・抵当権設定が完了してからになります。
そのため、住宅ローンが実行される前の支払いは、金融機関から資金を借りて支払うことになります。
これがつなぎ融資です。
【4】 解体業者を探す
住宅を建て替えるには、まず旧住宅を解体しなくてはなりません。
解体工事は、住宅を建築する会社に依頼する方法もありますが、別途解体業者を探し、直接依頼することも可能です。
直接、解体業者に依頼すると手数料がかからず、建築会社を通して依頼するよりリーズナブルに解体工事が行えるでしょう。
解体業者を探す時は、まず見積もりを取ることから始めます。
解体業者の見積もりは、解体する住宅、残すもの(ブロックや物置・植木など)・道路の状況(解体重機を設置できるかなど)を確認します。
見積もりは数社に依頼して比較、検討しましょう。
解体工事を依頼する時には、見積もりを見ながら工事範囲についての確認も忘れずに行いましょう。
【5】仮住まい先を探す
住宅の建て替え工事中は、アパートや実家などに仮住まいをしなければなりません。
工事中の仮住まいは、今までと通勤・通学・部屋の広さなどの生活環境があまり変わらず、費用を抑えられる場所がベストです。
しかし、短期間で希望の仮住まいを見つけることは難しいでしょう。
住宅の建て替え計画をはじめたら、早いタイミングで仮住まいを探しましょう。
建て替え中の仮住まいの選び方
仮住まいは、生活環境・家族の人数・荷物の量・費用などを考慮して選びます。
生活環境は、通勤や通学、買い物する場所が変わらない場所で探すと良いでしょう。仮住まいの広さは、家族の人数と荷物の量を考えて検討しましょう。
賃貸物件は2月から3月にかけて年度末の繁忙期になります。人気のある賃貸は早くから埋まってしまいます。そのため、この時期は仮住まいする物件がなかなか見つからないケースや賃貸費用が割高になるケースがあります。
また、仮住まいは短期賃貸となるため、長期で借りてくれる人がいるとなかなか貸してもらえません。仮住まいをするなら、賃貸需要が落ち着く5月頃から借りると探しやすく、短期でも貸してもらえるケースが多くなります。
ペットも一緒に仮住まいできる物件は、探すのが難しい傾向にあります。ペットだけ実家や兄弟の家に預かってもらう、早くからペット可の物件をさがす、ペットホテルを検討するなど早くからペットの仮住まいも考えておくと良いでしょう。
賃貸アパート・戸建て賃貸住宅の費用
賃貸アパートや戸建て賃貸住宅を借りる場合の費用目安を見てみましょう。賃貸期間は半年、諸経費を含めた金額を予定しておきましょう。
賃貸アパート 6ヶ月間借りる場合
| 家賃 | 6万円/月 | 60,000×6ヶ月 | 360,000- |
| 共益費 | 3千円/月 | 3,000×6ヶ月 | 18,000- |
| 敷金 | 家賃2ヶ月分 | 60,000×2ヶ月 | 120,000- |
| 礼金 | 家賃1ヶ月分 | 60,000×1ヶ月 | 60,000- |
| 合計 | 558,000- |
その他、駐車場代費用や荷物を預けるコンテナ費用、退去をする時に清掃などの費用が別途かかるケースがあります。事前に不動産屋に確認しておきましょう。
マンスリーマンションの費用
工事期間が短い場合は、マンスリーマンションを検討してみるのも良いでしょう。マンスリーマンションを3ヶ月借りる場合の費用目安を見てみましょう。
マンスリーマンション2DKタイプ 3ヶ月間借りる場合
| 賃料(光熱費含む) | 5千円円/日 | 150,000-/月 | 450,000- |
| 契約事務手数料 | 20,000- | ||
| 退去時清掃料 | 30,000- | ||
| 合計 | 500,000- |
マンスリーマンションの場合、部屋のタイプにより1日の賃料が大きく変わり、狭い部屋程安くなる傾向にあります。工事期間が短い場合は、マンスリーマンションは安く借りることができるので検討してみると良いでしょう。
駐車場や荷物を預ける倉庫が必要な場合は、別途その金額も検討しておきましょう。
引越しの時期と費用
仮住まいへの引越しや新築住宅への引越しは、できれば2.3月の繁忙期は避けた方が良いでしょう。費用が高くなるだけでなく、日曜日や大安など早くから埋まってしまい、なかなか希望日に引越しすることができません。
引越しは、2.3月を避けて引越し会社の繁忙期が終わってからにすると費用も安くすることができます。
【6】解体する家を片づける
仮住まいを探しながら、仮住まいに引っ越しする準備をします。
その際、引越しの準備をするだけでなく、解体する家の片付けをしましょう。
解体する家の片付けで大事なポイントは、新居で使用しない物を処分することです。
不要な物をできる限り処分できれば、仮住まいへの引越し荷物が減り、引越しの費用も抑えることができます。
また、新築の家への引越し・片付けも楽になります。
そのために、不用品の処分は計画的に行っておくことが大切です。
自治体の不燃物の処理日や処理先などを事前に調べ、積極的に処分しましょう。
【7】近隣に挨拶をする
仮住まいに引越しする前に、近隣に挨拶に行きましょう。
解体工事中や建設中は、音やほこりが出ます。また、工事車両の出入りもあります。
工事が始まる前に挨拶を済ませておくことが、工事中の近隣トラブルを防ぐことにつながるでしょう。
【8】仮住まいに引越す
仮住まいが決まり、解体工事開始日が決まったら、仮住まいに引越しします。
引越しは、解体工事がはじまる2〜3日前にはすべて完了できるように行いましょう。
引越し作業は、1日で終わらないこともあります。しかし引越し作業中に照明・コンセントなどの電気や掃除で使用する水道が必要になることもあるでしょう。
解体前の電気の外部線取外しや水道を止める工事などの日程も考慮して、引越しから解体まで少し余裕を見ておきましょう。
【9】家の解体工事の着工・完了
引越しが終わり、電気やインターネット・電話などの外部配線などの取外しが終了すると、解体ができるようになります。
住宅の解体工事は、40坪程の木造2階建て住宅で約10日から約2週間かかります。
今の解体工事は、法律で分別解体・処分が義務付けられており、解体では、解体物の処分にあわせて分別解体されます。
【10】地盤調査と地盤改良を行う
解体工事が終了したら、地盤調査を行います。
地盤調査は、土地の地盤の強さを調べる調査です。
調査結果と土の種類・土地の履歴などを基に、地盤の専門家や建築士が地盤改良の有無・地盤改良の方法を検討します。
地盤調査は必ず行いますが、地盤改良は調査結果により、行う住宅と行わない住宅があります。
工事日数は、工事の種類にもよりますが、約3~6日が目安です。
【11】地鎮祭を行う
住宅工事の着工前には「地鎮祭」を行います。
地鎮祭は、家を建てる土地の神様に家を新築することを報告し、土地を清め、工事の無事と完成を祈る祭事です。
時間は1時間前後かかります。
特に宗教の定めがない場合は、神道の神式で行うことがほとんどです。
建築会社が神社を紹介してくださる場合もありますが、地域の神社にお願いすることもできます。
【12】新築工事の着工・完了
地鎮祭が終わったら、いよいよ新築工事の着工です。
着工する前に「建築確認申請書」を所定の機関に提出して建築許可を得ます。
この手続きは、建築会社や設計事務所が行います。
他にも都市計画法や消防法の届出などがある場合、新築工事を着工するまでに必要な申請は、建築会社が行うことがほとんどです。
許可がおりたら住宅の基礎工事がはじまり、その後、上棟・木工事完了・内装工事と進み、住宅が完成します。
【13】新築物件の引き渡し
住宅が竣工したら、次は引渡しとなります。新築住宅は、引渡しまで建築会社の管理下にあり、住宅の鍵は工事用の鍵を使用しています。
また、竣工から引き渡しまでの間に工事の内容を確認し、住宅ローン実行の手続きを行います。
引渡しの日には工事費用の決済を行い、最終金を支払います。
新しい家の本鍵を受け取り、引き渡しとなります。
建物の表示登記と所有権の保存登記を行う
所有者や土地・建物の現状を登記記録に残します。
家の所有権を主張するための登記となるため、不動産登記は司法書士などの専門家に任せると安心です。
住宅ローンの実行と残金の清算
ローン申請を行った金融機関に返済を開始し、その他にかかった費用や残金の清算をします。
上記が全て完了したら入居開始となります。
中古住宅を建て替える手順は一般的にこのような流れとなるため、あらかじめどのタイミングで現金が必要なのかなどを確認し、余裕を持った計画を立てていきましょう。
建て替えについての注意点や期間について

次は、建て替えする際の注意点や期間についてご紹介します。
建て替えはどれくらい期間がかかるのか?
建て替えの場合、既存の家を撤去してから新しい住宅を建築するため、更地に新築住宅を建築する期間より長くなります。建て替えにかかる期間の目安の内訳は以下の通りです。
- ウスメーカー選び:約1カ月間
- ウスメーカー決定、間取りや建設方法の決定、申請手続き:約3カ月間
- 既存の家の解体撤去工事、新しい家の建築、鍵の引き渡し:約5カ月間
上記の期間はあくまで目安ですが、建て替えの計画段階から鍵の引き渡しまでを見てみると建て替えにかかる期間は約1年近くになります。
住宅建築時の天候不良やトラブルなくスムーズに進めば1年かからないケースもあります。
建て替えも地盤調査が必要
先程「基礎づくり」でも少し述べましたが、建て替える際には必ず地盤調査が必要です。
今まで家が建っていた場所で異常はなかったから地盤調査は要らないと思うかもしれませんが、今住んでいる家屋が新築されたときに地盤調査が行われておらず、もともと軟弱な地盤の上に家屋が建てられていた可能性もあります。
また、「瑕疵担保履行法」で必要な保険や供託では、基礎設計を行う上で地盤調査は必須になっています。
地盤調査を行い地盤が軟弱だと判断された場合は、地盤改良工事をする必要が出てくるでしょう。
改良工事をするかどうかは、地盤の状態や基礎の種類などを考慮した上で判断されます。
地盤調査や地盤改良工事は、家の取り壊し費用とは別にかかるため、建て替えを希望する場合は地盤調査にかかる費用も準備しておきましょう。
地盤調査と地盤改良工事費用相場
新しい家を建てるために地盤調査は必ず行わなければなりません。
地盤調査には主に「スウェーデン式サウンディング試験」「表面波探査法」「ボーリング調査」の3種類があります。
それぞれの費用相場は以下の通りです。
- スウェーデン式サウンディング試験:約3万円
- 表面波探査:約7万円
- ボーリング調査:約9万円〜
一般的に住宅に地盤調査では、スウェーデン式サウンディング試験と表面波探査が選ばれます。
また、地盤調査で地盤に問題があった場合、地盤改良工事をしなければ家を建てることはできません。
地盤改良工事には「柱状改良工法」「表層改良工法」「鋼管杭工法」があります。
それぞれの費用相場は以下の通りです。
- 柱状改良工法:約120万円〜約150万円/30坪あたり
- 表層改良工法:約90万円/30坪あたり
- 鋼管杭工法:約150万円〜約210万円/30坪あたり
中古住宅を建て替える場合に気をつけたいこと
中古住宅を建て替える際、建て替えができなかったり決められた条件の中で建築しなければならない場合があります。
では、中古住宅を建て替える場合に気をつけなければならないこととはどのようなことなのか詳細をご紹介します。
再建築不可物件について
再建築不可物件とは、接道義務を果たしていない土地のことです。
尚、既存不適格物件の場合は、建て替え後の住宅を現行の法規に適合させれば建て替えは可能です。
既存不適格物件と接道義務を果たしていない土地とは以下のような物件・土地となります。
【既存不適格物件】
- 日照が確保できず日照権の基準をクリアできていない
- 耐震基準が古く耐震強度が不足している
- 容積比率がオーバーしている
既存不適格物件とは住宅を建築した後に法改定があり、現行の法律では不適格となった物件のことですが、既存の住宅が現在建っていることに問題はありません。
しかし、建て替えとなると現在の建築基準法などに適合した住宅にしなければならないため、新築を建てる際には制約が出てしまう可能性があります。
【接道義務を果たしていない土地】
建築基準法で定められている「接道義務」とは、幅4m以上の道路に敷地が2m以上接地しなければならない規定のことです。
土地に接地している道路が建築基準法で認められていない場合や、土地に接している道が2m以下の場合は接道義務を果たしていないということになります。
接道義務は防災上の観点から定められた法律で、消防車などが侵入できる公園や広い敷地に隣接している場合、家の再建築が認められるケースもありますが、原則として建て替えできない可能性が高いでしょう。
セットバックが必要な中古住宅を建て替え
「二項道路」とよばれる幅員4m未満の道路に接した物件の場合、建て替え時にセットバックさせる必要があります。
二項道路に接した土地の場合、建て替えの際には道路の中心から2m以上後退させて建築しなければなりません。
セットバックは建物だけではなく、外構の門や塀なども対象になるため、敷地や住宅が狭くなるでしょう。
土地が借地だった場合
住宅を建てる場合、土地が必要です。通常、自分が所有している土地に住宅を建てる、又は親などの親族の土地(いずれ相続する予定)に子が住宅を建てるのがよくあるケースです。
しかし、住宅の建て替えが簡単にできないのが、借地の住宅に住んでいる場合です。この場合は、土地の所有権は地主にあり、今の住宅は地主の承諾を経て、住んでいることになります。
住宅が老朽化し、建て替えをしたいとなった場合、住宅の建て替えには地主の承諾が必要です。法律的には、借地契約書に増改築を制限する記載がなければ、建て替えできるとされています。
しかし、建物の構造や形状などは借地契約書に記載されている建物を建てなければなりません。もちろん、増改築を制限する記載があれば、住宅の建て替えはできません。
借地契約書の増改築の制限以外に地主の承諾が得られないケースがあります。はっきりと理由が語られない場合が多いのですが、家賃滞納や近隣トラブル・地主の相続などにより家の建て替えを断られるケースもあります。
また、住宅の建て替えができることになった場合、住宅ローンのことも確認が必要です。住宅ローンは通常土地と住宅に抵当権を設定して(土地と住宅を担保とする)借りることができます。
住宅を建て替える時に住宅ローン等を借りる場合、金融機関に担保を提示しなければなりません。地主は、自分の土地を他人の住宅ローンの担保とする住宅ローンを承諾することはまずありません。
借地の場合、地主の建築許可と住宅ローンの有無により、再建築ができないケースが多いのが現状です。
住宅ローン等を借りたい場合は、借地でも融資してもらえるか、銀行に確認しておかなければなりません。
木造住宅の建て替えの際申請できる補助金とは
木造住宅の建て替えを行う際、条件を満たせば利用できる補助金制度もあります。
建て替えを検討している場合は、一度お住まいの地域で利用できる制度がないか探してみると良いでしょう。
補助金の申請は、工事の着工前に行うことが条件となっているものがほとんどであるため、補助金の利用を考えているのであれば、工事が始まる前に忘れずに申請しておきましょう。
申請できる補助金の例
2021年2月時点で、木造住宅の建て替えの際に利用できる補助金制度の具体的例をご紹介します。
しかし、建て替えで利用できる補助金制度の有無は地域によって異なり、また、制度の内容や条件等も地域によって大きく異なります。実際に利用を検討する時には、お住まいの自治体に事前にご確認ください。
取り壊しの補助金
木造住宅の建て替えの際に、家を取り壊すための解体費についての補助を受けられる制度を用意している地方自治体があります。建物自体の解体費用や、古いブロック塀の解体費用などが補助の対象です。
新築時の補助金
建て替えの際に、太陽光発電設備やエコキュート等の省エネ設備を導入した場合に補助金が受けられる制度を用意している地方自治体もあります。
新築の補助金
建て替え新築時に、ZEH(ゼッチ)と呼ばれるエネルギー収支がゼロになるよう設計された住宅を建てる場合などには、国の補助金制度が利用できます。
また、生け垣の設置や壁面・屋上緑化などを行った場合に補助が受けられる制度を用意している地方自治体もあります。
建て替えとリフォームの税金の違いは?

建て替え、リフォーム、フルリフォームでは、税金面でさまざまな相違点があります。
住宅の建築工事や住宅の取得に関わる、印紙税、登録免許税、不動産取得税についてここでは詳しく紹介します。
※2022年10月時点での情報です。
印紙税
住宅を建て替えるときにもリフォームするときにも、建築業者と「工事請負契約」を結びます。
その際には印紙を購入し、印紙税を納める必要があります。
一部リフォームなどに多い価格帯の100万円超え〜1,000万円以下では400円〜10,000円です。
建築工事請負契約の場合、軽減措置により半額になることが多いです。
フルリフォームや建て替えによくある価格帯の、契約金額が1,000万円超え〜5,000万円以下までであれば、20,000円の印紙税がかかります。
こちらも、建築工事請負契約の場合、軽減措置により半額になることが多いです。
登録免許税
建て替えでは、新築住宅の登録免許税がかかりますが、リフォームでは原則かかりません。
ただし、リフォームであってもローンのため抵当権設定を行う場合などは、かかってきます。
登録免許税は、不動産登記にあたって登記を行う者が、国に納める税金です。
原則として、登録免許税額は、不動産の固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。
固定資産税評価額とは、固定資産税の基準になる価格のことです。
自治体が算出し、3年に1度見直されます。
土地の場合は、毎年1月1日時点の地価公示価格の約70%、建物の場合は、再建築価格の約50〜70%か新築住宅にかかった費用の約50〜60%が主な目安となります。
新築住宅を取得した場合の、住宅の所有権保存登記の税率は、0.4%となります。
不動産取得税
建て替えでは、新築住宅の不動産取得税がかかります。
リフォームでは、かからない場合がほとんどです。
ただし、建築確認申請をともなう規模のリフォームなどの場合、家屋の価値が高まったと見なされた場合は、かかってきます。
不動産取得税とは、住宅や土地など不動産を取得した場合に納める税金です。
固定資産税とは違い、取得時の一度だけ支払います。
不動産取得税は、建物の固定資産税評価額に4%を掛けて算出されます。
ただし、住宅の場合は軽減税率が適用されることもあり、その場合は3%となります。
固定資産税
建て替えでもリフォームでも、固定資産税は毎年納める必要があります。
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や家屋の状態によってかかる税金です。
リフォームでも「建築確認申請」をともなう工事をした場合は、固定資産税は上がります。
確認申請を出す必要があるのは、住宅の柱や壁、屋根、梁、階段など主要構造部をリフォームした場合や、増築する場合です。
建て替えを依頼する際の住宅会社の選び方
建て替えを成功させるためには最適な住宅会社を選ぶ必要があります。
優良な住宅会社を見つけるためには、建て替えの実績や施工例などが参考になるでしょう。
それぞれの住宅会社のホームページなどでは、施工例や実績などが掲載されているため、簡単に情報を得ることができます。
次に、アフターフォローなどがしっかりしている会社を選ぶことも重要です。
施工後何かトラブルがあったときに無料で対処するなどのサービスがあれば、安心して建て替えを依頼することができます。
また、住宅会社から最適なプランをもらうためには、間取りや設備などのイメージと予算をあらかじめ決めておくことも大切になります。
そうすることで希望するイメージや予算にあった内容のプランを提出してもらうことができ、正確な見積もりを出してもらうこともできるでしょう。
また、プランや見積もりはできるだけ1社のみではなく、複数の住宅会社からもらうようにしましょう。
1社のみのプランや見積もりの場合、その内容や金額が良いのかどうかが比較できず判断がつきにくくなるためです。
インターネットや口コミなどで良さそうな住宅会社を何社か見つけたら、それぞれ同じ条件で見積もりやプランの提出を依頼し、見積もり結果や対応などを比較しながら建て替え依頼をする住宅会社を決めましょう。
耐震性や省エネ性などの対応があるか比較する
近年耐震性や省エネ性に優れた住宅や、シックハウス症候群対策などが施された住宅が人気です。
特に日本は地震大国と言われているため耐震性は欠かせません。そのため、同じ金額であればこれらが備わった住宅の方が選ばれやすくなります。
しかし、機能や性能が良くなるほど金額も上がります。最終的には予算に近いかどうかや、対応が良いかどうかなども判断材料にして選ぶとよいでしょう。
外壁や屋根などのメンテナンスを比較する
建て替えた住宅には長い間住み続けていくため、メンテナンスを行う頻度なども重要なポイントとなります。
外壁や屋根、配管などは定期的にメンテナンスをしていかないと家の耐用年数に関わる劣化が発生しやすくなります。
外壁や屋根は初期費用が安くても、メンテナンス頻度が高い仕様だった場合、メンテナンス費用がその分必要になるため、長い目で見ると割高になる可能性があります。
建て替え後の対応が充実しているのか確認する
住宅は一度買えば終わり、ではありません。その後住み続けるためには定期的な点検や手入れが不可欠です。
建て替えの業者を選ぶ際は、建て替え後の対応が充実している会社を選ぶようにすることもポイントです。
もし建て替え後に外壁が剥がれてきたなどのトラブルが発生した場合、無料で修理が受けられるなどの保証がないと、後々トラブルの原因となる可能性もあります。
そのため、保証期間が長かったり瑕疵に関して無料で修理が受けられるなどの対応がある業者を選ぶようにしましょう。
建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?
ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。
実際に建て替えをするべきなのか、リフォームをするべきなのかを検討するためには、プロに現状を相談し、「プランと費用を見比べる」必要があります。
そのときに大事なのが、複数社に見積もりを依頼し、「比較検討」をするということ!
この記事で大体の予想がついた方は次のステップへ行きましょう!
「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」
「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」
そんな方は、簡単に無料で一括査定が可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。
一生のうちに建て替えをする機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!
この記事の監修者プロフィール

タクトホームコンサルティングサービス
亀田融一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。
一括見積もりをする