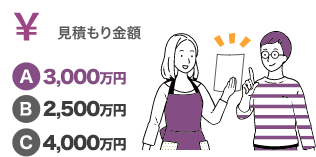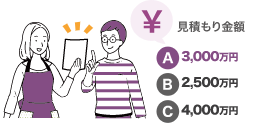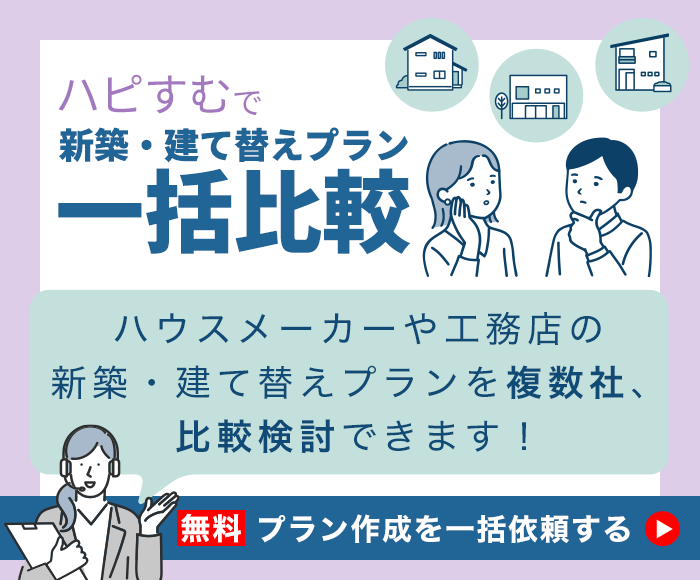2023年12月12日更新
ローコスト住宅で長期優良住宅は建てられる!メリットや注意点について
ローコスト住宅とは何かについて
 4
4
住宅を検討している時、住宅のチラシやインターネットでみかける「ローコスト住宅」とは、どのような住宅なのでしょうか?
一般的なローコスト住宅の内容や平均的な建築工事費用、メリット・デメリットを見てみましょう。
ローコスト住宅とは
ローコスト住宅とは、住宅の建築工事費用を極力抑えて建てられた住宅をいいます。
住宅を建てる時にかかる費用は、3種類あり、一つは、住宅そのものの建築工事費用。もう一つは、解体や地盤調査など住宅そのものの工事費用以外の費用。
それと、諸経費といわれる税金や登記などの住宅を取得するためにかかる費用です。
ローコスト住宅は、「住宅にかかる建築工事費用」がローコストで建てられる住宅です。
ローコスト住宅は、間取りやデザイン・使用する材料にルールや標準仕様設定することにより、その範囲内で建てる住宅は「住宅にかかる建築工事費用」が非常にリーズナブルに建てられる住宅になっています。
建てたい希望の住宅がローコスト住宅で建てられるなら、とてもお得な住宅となります。
ローコスト住宅の平均的な坪単価について
一般的なローコスト住宅の坪単価は、30万~50万円といわれています。
これは、「住宅の建築工事費用」の部分です。
大手ハウスメーカーの坪単価は、60万円~80万円といわれていますので、ローコスト住宅の坪単価は非常に魅力的な坪単価です。
同じ面積40坪の住宅を比較してみます。
- 大手ハウスメーカー
坪70万円、面積40坪 2,800万円 - ローコスト住宅
坪40万円、面積40坪 1,600万円
大手ハウスメーカーとローコスト住宅の建築工事費用の差は、1,200万円となります。
ローコスト住宅のメリットとデメリット
ローコスト住宅のメリットは、坪単価が低く、リーズナブルに住宅を建てられることにあります。
住宅を建てる時、ほとんどの人が住宅ローンを借りて、建築費用を用意します。
住宅ローンには、借入期間中に滞りなく返済ができるように収入制限が設けられています。
そのため、ある程度の自己資金と年収が必要になります。
ローコスト住宅はリーズナブルなので、自己資金があまりない、年収が高くない人でも住宅を建てることが可能になります。
いっぽうでローコスト住宅のデメリットは、住宅会社が決めている標準仕様以外の設備や材料を使用すると割高になることです。
また、部屋数や窓の数にも制限があるので、追加でつけるオプションも割高となっています。
そのため、標準以外の設備や仕様・オプションを多くつけると、結果的に大手ハウスメーカーの坪単価より高くなってしまうケースがあります。
また、ローコスト住宅は、設備のグレードや気密・断熱性能が低い場合があるといわれています。
標準仕様を確かめて、グレードや性能を確認しておくと良いでしょう。
ローコスト住宅で長期優良住宅の認定が受けられるのか
ローコスト住宅を検討している時に不安に感じるのが、設備の性能(エコ性能)や断熱や気密・耐震性能です。
ローコスト住宅は品質が低いといわれているからです。
住宅性能が高い「長期優良住宅」は、住宅の性能を確かめながら、設計し建てられる住宅です。
ローコスト住宅でも長期優良住宅にすることはできるのか、長期優良住宅の概要やメリット・デメリットを見てみましょう。
ローコスト住宅も長期優良住宅にすることはできる
ローコスト住宅を長期優良住宅の仕様で建てるにはどうしたらいいのでしょうか。
まずは、打合わせをしている建築会社に長期優良住宅の仕様と施工及び完成・引き渡し後の維持管理対応ができるか、確認してみましょう。
会社の対応は3つにわかれます。
一つは、標準仕様が長期優良住宅となっている場合、問題なくできるという対応。
もう一つは、対応はできますが、長期優良住宅にするための追加費用がかかるという対応。
もう一つは、長期優良住宅は対応していないというものです。
これは、住宅会社の方針やシステムによるものなので、長期優良住宅を希望する場合には対応している会社にお願いしましょう。
その際、費用が別途かかるかどうかを確かめておきましょう。
長期優良住宅とは
長期優良住宅は、長く安心して、快適に暮らせる住宅として、一定の基準をクリアし、所定機関から「長期優良住宅認定制度」の認定を受けている住宅をいいます。
主な認定基準には、バリアフリー性・可変性・耐震性・省エネルギー性・居住環境・維持保全計画があります。
住宅を着工する前に、所定機関に認定を受ける申請書類と図面を申請し、認定を受けます。
長期優良住宅のメリットとは
長期優良住宅のメリットは、性能の高い住宅を建てることができること。
バリアフリー・耐震性能・温熱環境(夏涼しく、冬暖かい)・省エネルギー性が高い住宅となります。
性能が高い住宅として認定されることで、税制の優遇や所得税控除・税制控除や優遇金利を受けることができます。
長期優良住宅の税制優遇や控除など(2019年2月調査)
| 一般住宅 | 長期優良住宅 | ||
|---|---|---|---|
| ① 住宅ローン控除 | 住宅ローンの残高に対して、所得控除が受けられる制度 |
|
|
| ② 不動産取得税 | 住宅を取得した時に1度だけ支払う税金の控除額が増える |
|
|
| ③ 登録免許税 | 所有権の保存登記・移転登記の登録免許税の減税※2 |
|
|
| ④ 固定資産税 | 固定資産税の減税※3 |
|
|
| ⑤ 地震保険 | 耐震等級による割引 | 保険会社により耐震等級数により割引があります | |
| ⑥ 住宅ローン金利 |
|
|
- ※1 不動産取得税の税率は、本則4%。2021年3月31日までに住宅を取得した場合は3%。
- ※2 所有権保存登記の税率は、本則0.4%。所有権移転登記の税率は本則2.0%。
2020年3月31日までに住宅を取得した場合、所有権保存登記税率は0.15%・所有権移転登記税率は0.3%。 - ※3 固定資産税の減額の適用は、2020年3月31日までに取得した住宅に適用されます。
長期優良住宅のデメリットとは
長期優良住宅のデメリットは、費用がかかることと、工事期間が長くなることです。
長期優良住宅でかかる費用は、3つあります。
一つは、長期優良住宅は住宅の性能がアップするため、建築工事費用がその分高くなること。
長期優良住宅の認定を受けるための申請費用と申請書類作成費用が別途かかること。
長期優良住宅の税制優遇やローン減税などのメリットを受けるには、認定機関による認定を受けなければならないので、長期優良住宅の認定は必須事項です。
また、完成・引渡し後には、建築会社による定期的な維持管理が定められています。
別途、費用がかかるケースがあります。
工事期間は、長期優良住宅の認定申請に一定期間がかかる(2週間から1ヶ月)ことと、認定許可がおりる前に工事を着工することができないため、長くなります。
ローコスト住宅の注意点について
ローコスト住宅で長期優良住宅を建築したい時には、費用面で注意したい点があります。
ローコスト住宅でも長期優良住宅を建築することは可能ですが、費用と特徴を知っておきましょう。
ローコスト住宅で長期優良住宅にしたいなら予算は上がる
ローコスト住宅の場合、住宅の建築工事費用を安くするために、長期優良住宅の仕様は標準仕様となっていないことがほとんどです。
ローコスト住宅を建てる会社によっては、長期優良住宅の対応がない会社もあります。
ローコスト住宅を長期優良住宅の基準に対応するためには、費用がかかります。
また、設計技術・施工技術も必要になります。
また、長期間にわたり住宅を管理していく人材や部署が必要になります。
ローコスト住宅を建てる会社で長期優良住宅を建てる場合は、事前に対応ができるかどうか、また、長期優良住宅にする予算はどのぐらいかかるのか、確認しておきましょう。
さまざまなポイントでコストがかかる
長期優良住宅を建てる際にかかるコストには、主に2つのポイントがあります。
一つは、住宅を建てる際にかかる性能アップに対する建築工事費用と「長期優良住宅の認定」を取得するための申請費用です。
住宅の見積もりを依頼する時に、「長期優良住宅仕様にしたいこと」と「申請にかかる費用」を見積もりしてもらいましょう。
もう一つは、長期優良住宅で義務付けられている10年ごとの点検と維持管理費用にかかるコストです。
この点検と維持管理は、住宅会社によるものです。
会社により費用は様々です。
点検に費用はかかるのか、不具合があった場合の費用はどうなるのか、確認しておきましょう。
リフォーム業者に依頼する際の最適な選び方について

長期優良住宅で家を建てると、色々な税制優遇やローン減税・金利優遇がありますが、リフォームでも「長期優良リフォーム」という補助金制度があります。(年度により補助金制度が変わります)
耐久性が高く、地震に強く、省エネ性能が高い、維持管理がしやすい住宅にリフォームする場合、工事費用の一部に対して国から補助金が出る制度です。最大300万円の補助金が出ます。
大きなリフォームをする際には、このような補助金制度を使って、高い性能の住宅にリフォームしながら、資金を補助してもらえると助かります。
リフォーム業者を選ぶ時には、補助金制度の知識がある業者やリフォームの実績が豊富で、アフターサービスや保証が手厚い業者を選びましょう。
リフォーム業者に依頼する時には、性能の高いリフォームにしたいことや補助金制度を使いたいことを伝えましょう。
また、予算やリフォームの希望を家族で話し合いを事前にしておきましょう。
建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?
ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。
注文住宅の設計プランや費用は、施工店によって大きく異なることがあります。
そのときに大事なのが、複数社に見積もりを依頼し、「比較検討」をするということ!
実際に注文住宅を建てるには時間がかかるので、この記事で大体の予想がついた方は早めに次のステップへ進みましょう!
「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」
「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」
そんな方は、簡単に無料で一括査定が可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。
一生のうちに注文住宅を建てる機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!
この記事の監修者プロフィール

タクトホームコンサルティングサービス
亀田融一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。
一括見積もりをする