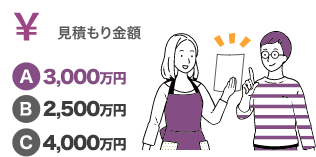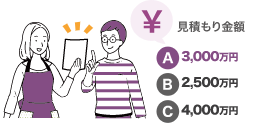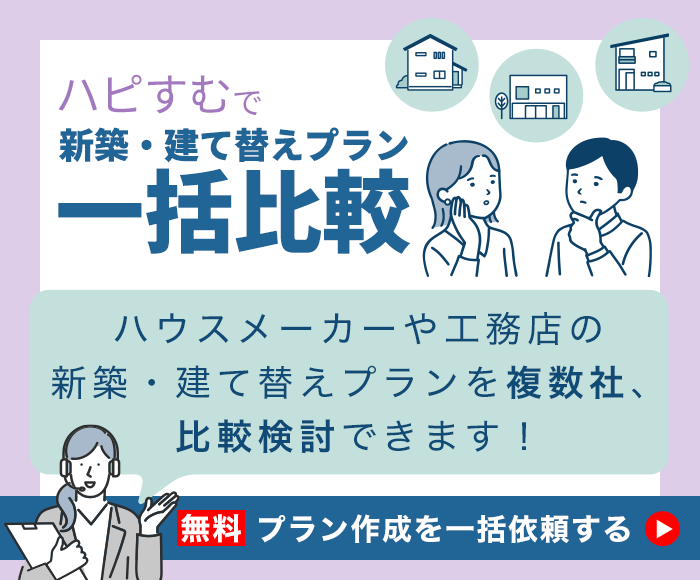2023年12月18日更新
ローコスト住宅のランニングコストは高い?ありがちな後悔や失敗について
目次
- 1 いくらぐらいからローコスト住宅になるのか
- 2 なぜローコスト住宅は安いのか?低価格のからくり
- 3 ローコスト住宅・注文住宅・建売住宅の違い
- 4 ローコスト住宅!そのメリット・デメリット
- 5 ローコスト住宅の建築費用を抑えるコツ
- 6 ローコスト住宅のオプションに含まれるものとは?
- 7 ローコスト住宅のオプションの注意点
- 8 ローコスト住宅はランニングコストが高いのか
- 9 ローコスト住宅と普通の注文住宅ではメンテナンス費用は違うのか?
- 10 ローコスト住宅の築年数とメンテナンス費用の関係とは
- 11 ローコスト住宅のメンテナンス費用をおさえるにはどうしたらいいのか
- 12 ローコスト住宅のトラブルを回避する方法
- 13 ローコスト住宅にありがちな失敗や後悔について
- 14 コストを抑えられる間取りのポイント
- 15 ローコスト住宅の寿命はどれくらいか
- 16 ローコスト住宅の依頼先はどこが良いか
いくらぐらいからローコスト住宅になるのか

住宅は大きな買い物ですから、希望する家を予算内で実現したいものです。
土地の値段を安くすることは難しいですが、家の値段は工夫次第で安くできます。
できるだけ価格をおさえて家を建てたい場合に、ローコスト住宅が検討されます。
ローコスト住宅はどのようなものなのでしょうか。
また、実際にいくらからなら建てることができるのかを解説します。
ローコスト住宅とは
ローコスト住宅とは、コストをおさえて建てる住宅のことです。
たとえば洋服でもオーダーメイドでは高くなりますが、同じ材料を使って大量かつシンプルに作ったものは安く売られています。
同じようにデザインや仕様をそろえて大量に材料を調達することで、住宅の価格をおさえて提供するのが一般的なローコスト住宅です。
材料費以外に、建築費用をおさえる設計上の工夫をおこないます。
ローコスト住宅の坪単価について
ローコスト住宅は、実際にどの程度の坪単価で建てることが可能なのでしょうか。
坪単価とは、標準的な建築費用を延べ床面積で割ったものです。
つまり1坪(約3.3平方メートル)あたり、いくらくらいで住宅を建てられるのかの目安になります。
住宅を建てる業者は標準的な仕様の坪単価を表示していますので、比較検討できるようになっています。
ローコスト住宅を提供するメーカーや工務店の坪単価は、30~50万円が一般的です。
ローコストを売りとしていない一般的なハウスメーカーの坪単価は60~80万円になります。
ただし、ローコスト住宅を販売するメーカーごとに坪単価の算出方法が異なることがあるため注意が必要です。
表示されている坪単価が安いというだけで決めることなく、標準とする建築費用に含まれていないオプション工事を確認するほか、床面積に含まれている範囲を確認して比較します。
建築費用を確実に比較するためには、オプションや床面積の出し方などの条件をそろえる必要があります。
ローコスト住宅の予算とは?
ローコスト住宅の坪単価がわかれば、次にローコスト住宅を建てる場合の実際の予算を確認してみましょう。
住宅の価格を抑える場合、面積が大きく影響します。
広くなれば広くなるほど、建築費が高くなることは想像できるでしょう。
つまり、広さをおさえることが住宅の価格をおさえるひとつのポイントです。
ローコスト住宅では、延べ床面積を20~30坪程度にすることが多くなります。
たとえば坪単価30万円で30坪の家を建てる場合、建築費用は約900万円。
坪単価50万円で30坪の家を建てる場合で、約1,500万円程度の家を建てることが可能になります。
ローコスト住宅では、多くが「1,000万円代の家を建てる」と広告しています。
つまり、一般的に建築費用が1000万円代の予算であれば、ローコスト住宅を検討することになります。
1,000万円で家を建てることは可能?
1,000万円で家を建てることは可能です。
先ほど確認したように、坪単価30万円で30坪の家なら約900万円、坪単価50万円で20坪の家であれば約1,000万円の家が実現することになります。
ただし、坪単価はあくまでも目安ですので、ローコスト住宅を選んだはずなのに高くなってしまったということや、後悔することがないようにこれから照会する注意点に気をつけてすすめてください。
なぜローコスト住宅は安いのか?低価格のからくり
ところでなぜローコスト住宅は安いのでしょうか。
ローコストということは質が落ちるのではないのかと心配する声も聞こえてくるのですが、実はそうではないのがローコスト住宅です。
それではローコスト住宅がなぜ低価格を実現できるのか、その理由について説明します。
資材や設備費のコストダウン
低価格での住宅建設を実現するために、ローコストハウスメーカーは住宅を建てるための資材の徹底的なコストダウンを追求しています。
資材の質を落とすのではなく、資材や設備の種類などを限定して一括で大量発注をしています。
そうすることで、建築資材や設備のコストダウンが可能になるのです。
設備のスペックのグレードダウン
建築費用の低価格を実現するために、標準設備のスペックを下げられているケースもあります。
高級素材・高性能となれば、その設備のコストが上がるのは当たり前です。
しかし設備のスペックを下げれば、住宅の建築費用を低く抑えることができます。
もしも標準設備で満足ができないのならば、グレードアップができるようなオプションを用意していますので、さまざまなニーズを持った発注者に満足してもらえるよう配慮されています。
間取り・デザインがシンプル
ローコスト住宅の基本は、間取り・デザインともにシンプルなことです。
シンプルな造りにすることで、間取りやデザインの規格化がしやすくなり、コストを抑えられるのです。
確かにローコスト住宅ではない注文住宅ならば、家族の暮らし方に合わせた間取りやデザインを自由に設計して、それを取り入れることができるでしょう。
しかしそのように個々の要望に応じてデザインをして建設すれば、間取りが複雑になり、建築に必要なパーツも増えることになります。
また凝った装飾を施せば、予算にしわ寄せが出てきてしまいます。
ローコスト住宅ではそうした個人の細かな要望は応えられないかもしれませんが、人が住むという基本に重点を置き、装飾性などを排除したからこそ、低予算で住宅を建てることができるのです。
人件費の削減
住宅建築で最もコストがかさむもの一つが人件費です。
その人件費を削減する方法として、資材を事前にプレカットしておき、建築現場ではすぐに資材の組み立てに取り掛かるようにすることで、工期を少しでも短くするようにします。
工期が短くなれば、その分、人件費も削減することができます。
広告宣伝費の削減
ローコストハウスメーカーが低価格を実現できる手段の更なる方法のひとつが、宣伝費用の削減です。
新聞や雑誌、テレビなどマスコミで流される宣伝費用は膨大です。この費用を各店舗で請け負っていたら大きな負担となります。
そこでフランチャイズチェーン化されたローコストハウスメーカーは、本部が一括で宣伝費用を取り仕切ることで、実際に営業をする支部は宣伝費用を削減できます。
広告宣伝費用に限らず、資材の一括購入や資材のプレカットなどを通して、住宅建築に関わる無駄を少しでも省くことで、ローコストハウスメーカーは低価格を実現しているのです。
ローコスト住宅・注文住宅・建売住宅の違い
新築住宅を検討するにあたりローコスト住宅、注文住宅、建売住宅の3つにはどのような違いがあるのか紹介しています。
ローコスト住宅
ローコスト住宅とはとにかくコストを重視して販売されている住宅のことを指します。
材料の大量仕入れや広告費の削減、向上である程度組み立てるなどにより費用を抑えています。コストは安く抑えていますが、間取りや設備が似通っている住宅です。
注文住宅
注文住宅は自由度が非常に高く、間取りや外観、設備など施主の希望に沿って作る家のことを言います。そのため、設計費、材料費などの費用は高くなってしまいますが、家族の好みを反映することができる住宅です。
建売住宅
建売住宅とは、土地と建物とが一緒に販売されている住宅のことです。一般的に注文住宅に比べて安く、ローコスト住宅に比べると高めです。
基本的にハウスメーカーの規格で建てられているので自由度は低いですが、既に住宅が完成しているので打ち合わせなどの手間を省くことができます。
ローコスト住宅!そのメリット・デメリット
ローコスト住宅は相場より安価に家を建てることができますが、どのようなメリット・デメリットが考えられるのでしょうか?
ローコスト住宅のメリット
ローコスト住宅のメリットとしては次のような点が挙げられます。
価格が安い
ローコスト住宅の最大のメリットは、なんといっても価格が安い点でしょう。
大手ハウスメーカーが坪あたり約60万円~80万円であることを考えると、坪あたり約30万円~40万円という安さは画期的です。
30坪の家を想定した場合、大手ハウスメーカーだと1千8百万円になるのに対して、ローコスト住宅は1千万円前後で建設可能です。
この価格だと、住宅ローンの限度額が低い価格帯の若い世帯の人でも購入が可能になります。そのため住宅ローンの返済額もあまり負担にならず、余力を子どもの教育費に回すことなどができます。
工期が短い
ローコスト住宅では、人件費を抑えるために、工期も短縮されています。概ね3カ月くらいで完成するため、仮住まいの家賃も節約できます。
品質が安定している
ローコスト住宅は、基本的に同一の設備機器を使用しているために、たとえ経験の浅い職人であっても、当該工事に関しては経験値が上がっています。
このため比較的安定した仕上がりを期待することができます。
選択を迷う必要がない
ローコスト住宅は、使用する製品がほぼ決まっているので、建築主の選択の余地はほとんどありません。
そのため思い悩むタイプの人であっても、悩む必要がない点がメリットだといえます。
ローコスト住宅のデメリット
それでは反対に、ローコスト住宅のデメリットはどんな点なのでしょうか。
耐久性・耐震性などが心配
耐震性については、確認検査機関の中間検査で構造合板や建築金物の位置が適切に施工されているかをチェックしているので、必要以上に心配する必要はありません。
しかし耐久性に関しては、外壁や屋根の使用材料に価格の安いものを使用していることから、経年劣化が早まることが想定できます。
このため早い段階でのメンテナンスが必要になります。
素材・設備のグレードが低い
ローコスト住宅は、一般的に屋根や外壁材、フローリングやクロス・クッションフロアなどの内装材、お風呂やキッチン・洗面・トイレなどの設備のグレードが低いといわれています。
ローコスト住宅の会社では、ローコストを実現するために、法律上や安全性の面で必要な最低限の設備を標準仕様として用意しています。
標準仕様以外のグレードアップや追加する設備(浴室乾燥機や食器洗い機など)はオプション仕様となります。あくまでもローコストを実現するために、必要最低限のものを標準仕様としているのです。
工事の質が良くない
ローコスト住宅を建てる際に現場の人件費を抑えるため、下請け会社に工事を全てまかせる、または契約社員や外注社員に現場監督をまかせる会社があります。
そのため、現場監督があまり現場に来ないことや、現場の管理が十分にできていない場合があり、工事の質は良くないといわれます。
また、工事日程を短期間にすることでコスト管理をしている会社もあり、厳しい工期のために、工事の質が下がっているケースもあります。
住宅性能が劣っている
住宅の性能には、暑さ、寒さをコントロールする断熱性やすき間面積の指標となる気密性、住宅にかかるエネルギーを省力化する省エネルギー性など様々な性能があります。
ローコスト住宅では、これら住宅性能が劣っているといわれています。
住宅性能の質は、使用する素材や材料・設備の種類と施工技術の高さにより、性能の良し悪しが決まります。
最近では、住宅の性能を表す数値指標として「住宅性能表示」や「省エネルギー法などの法律により定められている仕様や数値」があります。
使用する材料・素材・設備の種類や施工方法の確認も重要です。
ランニングコストがかかる
ローコスト住宅の断熱材は、グラスウールが用いられています。グラスウール自体は主流の断熱材なので性能的には問題ありません。
ただしグラスウールの断熱性能は、充填方法や壁の取り付けが正常に施工されて初めて効果が発揮できるものです。このため施工不良があると断熱性能が劣った住宅になります。
またローコスト住宅は標準的な断熱工事しか行わないので、近年の高気密・高断熱化を図った住宅に比べて断熱性能が大きく劣り、光熱費が高くついてしまいます。
通年していくとその差は相当の金額になりますから、ローコスト住宅はランニングコストがかかるということを認識をしておく必要があります。
デザイン・間取りが決まっている
ローコスト住宅では、間取り、デザインがシンプルです。
同じ床面積の住宅でも、住宅の形状や階数によって、工事金額は変わり、シンプルなデザインほど安い傾向にあります。
住宅の形状でいえば、正方形に近い四角い住宅が最も安く、凸凹が多い形状の住宅は割高です。間取りでは、小さな部屋が数多くある場合、窓やドア・壁などが増えるため割高になります。
また、平屋建てより総2階の住宅の方が坪単価は安く、ローコスト住宅は、その坪数により部屋数が決まっています。
デザイン・間取りがシンプルなローコスト住宅は、デザインよりコストを重視するという人向きです。
外観に高級感がない
ローコスト住宅は、価格高騰につながるデザイン要素は極力排除しています。
また、外壁のサイディングも安い価格帯のものを使用しています。そのため、外観の高級感は期待できません。
オプションを選ぶと高くなる
ローコスト住宅を建てている会社では、ローコストで建てる住宅の屋根や外壁・内装材の仕様・キッチンやお風呂などの設備を「標準仕様」として決めています。
標準仕様を決めることで、ローコスト住宅では同じ材料・設備を多く使用することとなり、その商品を大量に仕入れます。結果、通常より安く仕入れることが可能となり、ローコスト住宅が実現できるというわけです。
しかし、「標準仕様」以外の素材や設備を使えないわけではありません。標準仕様以外のオプション品を選ぶこともできます。
しかしオプション品は、割安で仕入れられている標準仕様と比較すると、割高になってしまいます。
アフターサービス・保証が不十分
ローコスト住宅では人件費を削減しているため、アフターサービスや保証が不十分な傾向があります。このため、どこまで保証してくれるのかなど細部にわたって確認をしておく必要があります。
ローコスト住宅の平屋は可能?
平屋には1階の部分しかないので、一般的な2階建て住宅と比べてコストが抑えられると思う方も多いかもしれません。
しかしながら、平屋住宅は意外とコストがかかりがちです。そのことをきちんと理解していないと、2階建て住宅以上に建築費用が高くなることも。
平屋住宅が2階建て住宅よりも建築費用が高くなる理由として、屋根と基礎工事が挙げられます。
平屋が2階建て住宅と同じ床面積を確保しようとすると、単純に屋根と基礎の施工面積が2倍程度になってしまいます。これが坪単価が高くなる要因となってしまうのですね。
しかしながら、平屋住宅でもやり方次第で建築費用を抑えることは可能です。
平屋の建築費用を高くしてしまうポイントの1つに、敷地面積が挙げられます。2階建てと同じくらいの居住スペースを平屋で確保しようとすると、どうしても広い敷地面積が必要になってしまいます。
しかし間取りやプラン次第では、必要な敷地面積を抑えることができます。敷地面積が狭くなるとそれだけ必要な屋根や基礎の面積も減らせるので、それが建築費用削減につながるのです。
また住宅会社によっても、建築費用にバラツキがでてきます。平屋の建築実績が少ないと資材も割高になりやすく、プランや間取りにも制限があることが多いようです。
建築価格を抑えるためには、住宅会社選びも重要なポイントになってくるでしょう。
平屋をローコストで建てる際は、間取りや住宅会社をしっかり吟味して選ぶようにしてみてください。
ローコスト住宅の建築費用を抑えるコツ
ローコスト住宅は規格住宅ばかりでなく、自分でプランが決められる自由設計の住宅もあります。
この場合、どうやって建築費用を抑えればいいのでしょうか。
外観は正方形に近い総2階建てにする
同じ面積の建物の場合、正方形が最も周長が短くなります。
このため正方形に近い外観にすると、外壁の面積が小さくなり、基礎の長さも短くなるので、工事費が節約できます。
また屋根の面積も、総2階にすることで面積を最小に抑えることができます。
屋根の形をシンプルにする
日本家屋の屋根の形状は寄棟や入母屋など多彩にあります。
これらの屋根形状の中で最も安価に施工できるのが、切妻屋根と片流れ屋根です。
しかし片流れ屋根は一方の壁が高く立ち上がり外壁面積が増加するので、ローコストにするためには、切妻屋根が最も適しています。
間取りはシンプルに
間取りをシンプルにすることで、内装下地や壁クロスを節約することができます。
廊下や階段も極力部屋に取り込んだ方が、壁や建具を減らせるので、建設コストを下げることができます。
水回りを1ヶ所に集める
台所、洗面所、浴室、便所、洗濯機置き場などの水回りは、極力集中して配置した方が、給排水管の節約になります。
空調機器は量販店で購入する
エアコンを住宅施工会社に依頼すると、隠蔽配管になり見た目が美しく仕上がります。しかし、エアコン機器の製品代は、住宅施工会社の経費が上乗せされているため、高くついているのです。
エアコンは電気の量販店で自分で選んで購入し、電気店に取り付けてもらう方が費用的には安くなります。
減税制度や補助金を利用する
返済期間が10年以上の住宅ローンを借りた場合、確定申告をすることで、10年間住宅ローン控除を受けることができます。
また消費税率引上げによる住宅取得者の負担を軽減するために「すまい給付金制度」があります。
住宅ローン減税は、納税した額から控除する仕組みであるため、収入が低い人は効果が小さくなります。
しかし、すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対する制度であることから、低所得者に厚く給付される仕組みになっています。
ローコスト住宅のオプションに含まれるものとは?

一般的にローコスト住宅は、最低限の設備を備えた住宅であるケースが多いです。
しかし、耐震性や断熱性、設備などをアップグレードしたい場合は「オプション」として追加費用を支払うことでアップグレードさせることができます。
では、ローコスト住宅でできるオプションには具体的にどのようなものがあるのか見ていきましょう。
耐震性をアップさせるオプション
ローコスト住宅が比較的安価な家だからと言って、耐震性に問題があるわけではありません。
建築基準法では、最低でも震度6弱〜7の地震が発生しても倒壊しない程度の耐震性を維持するように定められており、もちろんローコスト住宅もこの基準を満たしています。
しかし、地震大国の日本では耐震性は命に関わることでもあるため、耐震性をアップさせたいと希望する人が増えており、追加費用を払ってでも充実させるケースが多いようです。
耐震性をアップさせるオプションには、耐震パネル・ダンパー・耐震金具の設置などがあり、これらは構造部分に直接設置します。
断熱性をアップさせるオプション
室内の快適性を上げるために、断熱性をアップさせるという選択肢があります。
外気の影響を受けにくくなるため、冬や夏などにエアコンなどの空調効率が良くなり、結果的に光熱費も削減できる可能性があります。
ローコスト住宅で断熱性をアップさせるオプションには、外断熱や遮熱シートなどを施工する方法があります。
その他には、窓のサッシのグレードをアップして複合窓にすることもあります。
設備のグレードをアップさせるオプション
一生のうちに家を建てる機会は何度もないため、お風呂やキッチンにもこだわった設備を設置したい人は多いのではないでしょうか。
特に、水回りはこだわりたいという人が多いようです。
ローコスト住宅の設備は基本的にベーシックなものが多く、機能や仕様などをプラスしたい場合は、オプションとして追加費用を支払うことになるでしょう。
大手ハウスメーカーの場合は、標準装備でもグレードの高い設備であるケースが多いため、いくつかのローコスト住宅と見比べてみてグレードアップの必要があるかどうかを検討するとよいでしょう。
その他に、ローコスト住宅では網戸や照明などの生活に必要なものが標準仕様ではなく後から自分で設置する必要があるケースもあります。
生活に必要な設備が標準仕様に含まれているのかどうかの確認も必要です。
内外装のグレードをアップさせるオプション
ローコスト住宅では、内装や外装も最低限なものにしていることが多いようです。
ただし、最低限と言ってもすぐに雨漏りするようなことはありません。
外装のオプションでは、より耐久性の高いガルバリウムを外壁に導入したり、屋根用遮熱塗料の塗布で耐久性や断熱性を上げることが可能です。
一方、内装のオプションでは、床や建具に無垢材を使用したり壁に漆喰などを選べたりすることもあり、こだわりの空間にしたい場合によく選ばれる傾向にあります。
ローコスト住宅のオプションの注意点

ローコスト住宅は安く家を買うことができるというメリットがありますが、注意しなければならない点もいくつかあります。
ローコスト住宅のオプションの注意点についてご紹介します。
オプションを徐々に付けることで価格を上げようとする営業手法に注意
広告で見るローコスト住宅の費用を見ると、とても安く表示されているため「こんなに安いなら相談してみよう」と思う人も少なくないのではないでしょうか。
実は、ここに大きなカラクリが隠されています。
まず、広告などで表示されている費用には、住宅を建てる上で必要な経費が含まれていないケースがあります。
まずは、一般的なローコスト住宅の標準仕様に含まれるものを見ていきましょう。
- 住宅本体の材料費、工事費
- 外構工事費
- 付帯工事費(給排水工事、現場管理費、設計費など)
- その他工事費(照明やアンテナなどの電気工事、カーテンなどの内装工事)
- 諸経費(登記費用、火災保険など)
- 消費税
多くのローコスト住宅では上記の費用が含まれていますが、一部のメーカーでは水道・ガス・電気の引き込み費用や浄化槽設置費、確認申請費、調査費など住宅本体の費用以外の付帯工事費および経費などが含まれていない可能性があります。
そのため、いざ見積もりをしてみると2倍以上の金額になったというケースも少なくないようです。
このように、ローコスト住宅の場合、広告などでは最低限の費用を表示し、実際に見積もりを依頼すると、あれもこれもとオプションが必要になるケースが多いため、どこまでの費用が含まれるのか必ず確認するようにしましょう。
絶対に必要な設備をオプションとしているメーカーに注意
先程の項目と少し似ている部分がありますが、ローコスト住宅のハウスメーカーの中には、標準仕様の中に、絶対に必要な設備をオプションとしているケースがあります。
例えば、照明・テレビのアンテナ・網戸など生活に必要なものであってもオプションになってしまうことがあります。
生活に必要な設備をオプションとしているメーカーの場合、全てを揃えると決して贅沢をしていなくても最終的な価格が高くなってしまうため、メーカー選びの際にどこまでが標準仕様なのか必ず確認するようにしましょう。
ローコストメーカーのオプション費用は割高である場合が多い
ローコスト住宅のオプション費用は、一般的な注文住宅のオプション費用よりも割高である可能性が高いと言えます。
ローコスト住宅メーカーのオプション費用は以下の通りです。
- キッチンカウンター追加費用:約22万円
- 二階トイレ追加費用:約26万円
- 二階洗面化粧台追加費用:約15万円
- ロフト追加費用:約19万円
ローコスト住宅では二階にトイレがないなど最低限の設備しかないため、不足分を追加するためにはオプションを選ばなければなりません。
しかし、そのオプション費用が割高なため、満足な住宅に仕上げるのに100万円以上の費用がかかる可能性もあります。
費用を少しでも抑えたい気持ちは誰しもありますが、ローコスト住宅を建てる際はよく費用の内訳を確認して、総合的に判断するようにしましょう。
ローコスト住宅はランニングコストが高いのか

ローコスト住宅に限らず、新築の戸建てやマンションに入居すると、月々の光熱費がどれくらいかかるか気になるところではないでしょうか。
住居を維持するためには、月々の維持費とは別に10年目くらいに大規模なメンテナンスも発生します。
ローコスト住宅はどのくらいのランニングコストがかかるのでしょうか?
ローコスト住宅はイニシャルコストが安い
建築契約をして入居するまでにかかる費用を「初期費用(イニシャルコスト)」いい、ローコスト住宅でよく言われる3つのコストのうちのひとつです。
その他のコストには入居後の維持費としてのランニングコスト、外壁塗り替えや給湯器交換などの大型メンテナンス費のライフサイクルコストがあります。
ローコスト住宅の初期費用(イニシャルコスト)が低く抑えられている理由のひとつに、建物の形が正方形や長方形のシンプルな形で設計され、間取りのパターンが決められていることにあります。
注文主は建築会社が提示したプランから選ぶことでコストダウンにつながっています。
また、室内の壁を多用せず広い空間作りをしたり、設備も標準グレードを低めに設定されたりしていることも建築費用を抑える要因となっています。
ローコスト住宅を建築する会社は、材料費や人件費、広告宣伝費を抑えるなどさまざまなコストカットによって低価格住宅の建築を可能にしています。
建て方が雑だとランニングコストは高くなる
ローコスト住宅の欠点の一つに、気密性や断熱性が低いことがあります。
断熱材に低いグレードの物を使用すると遮熱性が得られず、熱効率が悪くなり、ランニングコストに影響してしまうのです。
断熱材は安価な繊維毛断熱材のグラスウールを使う事が多いのですが、気密性が低いと壁の内部で結露が起き、グラスウールが結露を吸い込んで湿ってしまい、カビが発生する原因になったり、断熱効果を失う事にもなります。
ローコスト住宅を建築する会社、業者が職人の手間賃を安く値切ったり、現場監督の管理不足による職人任せにしてしまった現場では雑な工事をされることがありますが、施行主にはなかなか発見できることではありません。
雑な工事の影響は入居後の不具合となってから露見するので、それまでは判らないまま、住み続けてしまうことになります。
ローコスト住宅=雑とは限らない
しかし、ローコスト住宅が安かろう悪かろうと単純に結論付けることはできません。
建築会社は、自社の評判を落とすような粗悪品を建築する意図は当然持っていません。
コストをおさえても快適な生活が送れる家を提供することが社会に貢献するという気持ちを持っているからです。
後々クレームになるような症状が出るほとんどの原因は、職人の技術力の差で生まれるものが多いです。
特に大工の腕の良しあしが住まいの出来に大きな影響を与えます。
腕の良い大工さんなら建付けの狂いはあまり出ませんが、経験が足りない大工さんだと粗が目立ちます。
また、職人に支払う工賃を不当に値切っていたり、短い工期を強いていたりすると、職人のモチベーションもあがらず、作業レベルも高まりません。
その様な現場は入居後に色々トラブルに見舞わる可能性が出てきます。
ローコスト住宅の耐震性や断熱性は?

ローコスト住宅は資材の大量購入によるスケールメリットや経費の削減によって建築価格の引き下げを行っていますが、構造部分もある程度簡素化することで費用を抑えています。
そのため、上の項目でもご紹介したように、断熱材が使用されていなかったり、量が少なく十分な量が設置されていなかったりといったこともあるのです。
また、耐震性についても、建築基準法における最低限の耐震性を設計上確保するに留まっていることが多いため、建築後に調査を行ってみると実際には耐震性が不足していたという事例もあります。
もちろん、大半の事例では耐震性の問題が見つかったということはないのですが、通常の住宅に比べ設計面で数値的にぎりぎりの部分まで資材の量を抑えている傾向が多いため、ある程度注意しておく必要があるでしょう。
もし、建築後に断熱性や耐震性の問題が見つかった場合、どちらも大がかりなリフォームを行わなければ改善することができません。
リフォーム費用を含めると通常の住宅商品を選んだ場合や、注文住宅を建てた場合と費用が変わらないといったことも考えられます。
そのため、設計上の耐震性や断熱性については、実際に施工を開始する前の、プランの打ち合わせや詳細設計を行う段階で十分に確認しておきましょう。
費用が追加でかかってしまいますが、不安な場合は外部の住宅コンサルタントに依頼し、図面や材料から十分な断熱性や耐震性が確保されているかを確認してもらうのもおすすめです。
ローコスト住宅は換気性能にも注意が必要
忘れられがちですが、快適な住宅を作るためには換気性能にも注意を払う必要があります。
住宅の状態を維持するためには、換気を行って室内の湿気を排出することが重要ですが、ローコスト住宅ではこの排気設備にシンプルな換気扇を用いることが多いのです。
このタイプの換気設備はローコストで換気性能が高く、ランニングコストも抑えられるのですが、室内の空気をそのまま排出する構造のため、冷暖房の効率が下がってしまいます。
多少コストは上がりますが、ローコスト住宅でも熱交換を行うことで冷暖房効率を下げずに換気を行うことができる換気設備に変更が可能な場合もあります。
換気設備の変更はコストがかかりますが、光熱費を抑えることができるため、ランニングコストを引き下げることができ、将来的な出費も抑えることができます。
可能なら建築段階で変更しておくと良いでしょう。
ローコスト住宅と普通の注文住宅ではメンテナンス費用は違うのか?

ローコスト住宅は建築費用が普通の注文住宅に比べて割安に設定されているため、建材や設備を安価で質の低いものを利用していると思われがちです。
しかし、ローコスト住宅といっても基本的に建材や設備の質そのものは低くありません。
ローコスト住宅では、注文住宅でも使われている建材や設備を一括で大量購入することで仕入れ費用を抑え、低価格化を実現しているのです。
つまり、ローコスト住宅だからと言ってメンテナンスのタイミングが注文住宅より早くなったり、メンテナンスにかかる費用が高くなったりしてしまうとは一概には言えないでしょう。
メンテナンス費用については、場合によりますが、ローコスト住宅の方が普通の注文住宅に比べて安価になる事例もあります。
これは、ローコスト住宅は建坪を減らすことで建築費を抑えていることが理由です。
屋根や外壁など、作業面積が広ければ広いほどコストがかかるメンテナンスの費用を建坪の少なさによって抑えることができるのです。
ローコスト住宅は安価なため、どうしてもメンテナンスの負担が大きいように思われがちですが、基本的に通常の建売、注文住宅などと同じまたはやや安価なメンテナンス費用で収まる傾向があります。
ローコスト住宅の築年数とメンテナンス費用の関係とは
メンテナンスでは、住宅の築年数によってどの部位のメンテナンスを行うかが重要です。
これは、建材や設備に設定されている耐用年数がそれぞれの部位ごとによって違うことが理由で、耐用年数が過ぎる前にメンテナンスを行うことで、他の部位に老朽化の影響を抑えることができます。
特に屋外と面している部分や水回りに関する部分については、老朽化によって防水性が低下してしまうと、構造部材部分に雨水や水漏れが発生する可能性が高まります。
そのため、メンテナンスが遅れてしまった場合、水漏れによって発生した腐食の修繕費用も必要となり、メンテナンスにかかる手間もコストも増大してしまうでしょう。
メンテナンスを行う時期は、水回り設備は築10年ごろ、内装は築15年ごろ、屋根や外壁などの外装部分については築20年頃が目安です。
費用については、ローコスト住宅では決められたグレードの資材や設備が用いられていることが多いため、同じグレードのものを利用すれば費用を抑えることができます。
ただし、上位グレードの資材や設備はそれだけ耐用年数が長く、老朽化しにくいものが多いため、長期的なメンテナンスコストの低下を考えるなら、現在使用中の建材や設備より上位のものを使うのも良いでしょう。
住宅のメンテナンスの基本は、老朽化や劣化、故障などを早期に発見し、早期に対策を行うことです。
上でも述べている通り、発見が遅れてしまうと、メンテナンスしなければならない範囲が広がり、コストがそれだけ増大してしまいます。
築年数を重ねたローコスト住宅では、定期的に点検を行い、老朽化などの問題が起こっていないか確認するようにしましょう。
ローコスト住宅のメンテナンス費用をおさえるにはどうしたらいいのか
ローコスト住宅に限らず、住まいの状態を維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせませんが、メンテナンスにかかる費用を抑えるためにはどのような方法をとれば良いのでしょうか?
普段から掃除と点検を行う
住宅に限らず、設備や建材などは汚れがついたままだと劣化や故障が発生しやすくなるため、定期的な掃除を行うことが重要です。
故障や劣化を抑えることができれば、メンテナンスの回数も抑えることができるため、将来的にかかるメンテナンス費用も抑えることができます。
また、掃除を行う際には同時に設備や建材の状態を確認しておくことで、劣化や故障などの問題を早期に発見することができ、問題の拡大を防ぐことができるでしょう。
事前にメンテナンスを計画する
設備や建材部分の故障や劣化によってトラブルが発生してからメンテナンスを行うという場合も多いのですが、この対応方法では問題のある箇所以外にも被害が拡大することが多く、コストが増してしまう可能性があります。
住宅外装や水回りなど、本格的な劣化や故障が発生すると被害が拡大しやすい部位については、築年数を元にトラブルが発生する前の段階でメンテナンスを計画しておくと良いでしょう。
トラブル発生前にメンテナンスを行うことで、該当部位だけのメンテナンスに絞ることができ、メンテナンス費用の増大を防ぐことができます。
専門家に相談する
使用する建材や設備、メンテナンスの方法など、家の手入れについてわからないことがあったら、ハウスメーカーやリフォーム業者などの専門家に相談するようにしましょう。
専門家に相談することで、予算の範囲内で最善のメンテナンス方法を採れる可能性が高まります。
メンテナンスの記録を残す
住宅建材や設備にはそれぞれ耐用年数が設定されているため、メンテナンスや点検を行った場合には必ず記録を残しておきましょう。
記録を残しておくことで、メンテナンスのスケジュールが立てやすくなり、重大なトラブルが発生する前にメンテナンスを実施できます。
建築時に設備や建材のグレードを上げておく
ローコスト住宅では、建築費用を抑えるために一定グレードの建材や設備が用いられています。
これらのグレードは、建築時に変更することができるので、耐用年数が長い建材や設備にあらかじめ交換しておくことで、メンテナンスを行うまでの期間を延ばすことができるでしょう。
ローコスト住宅のトラブルを回避する方法

低価格を実現するためにいろいろな試みが行われているローコスト住宅ですが、そのために問題が起きることもあるようです。
そこでローコスト住宅のよくある問題を避けるための方法をご紹介します。
ローコスト住宅に合う土地を用意する
土地を購入してから住宅を建てる際には、土地選びの段階からローコスト住宅を建てることを念頭に土地を検討しましょう。
ローコスト住宅を建てるのに向いている土地のポイントは3つあります。
1つは、土地の形状がシンプルであること。土地の形状は、できれば整形地で道路や隣地との土地の高さに差がない土地を選びましょう。
ローコストで建てられる住宅の形状は、正方形に近い形です。土地の形状が三角形や台形をした不整形な土地では住宅も凸凹した形状になり、土地にも無駄なスペースができてしまいます。
また、道路や隣地との高低差があると、基礎や外構工事などの費用が通常より多くかかります。高低差がなければ必要のない工事ですので、土地を見にいったときに確認しておきましょう。
もう1つは、土地に対する法規制があまりない土地を選びましょう。家を建てる時、工事費用がかかる法規制があります。
防火対策をしなければならない防火・準防火地域や市への届出が必要な市街化調整杭域・風致地区・地区計画地域などは、別途費用がかかりますので確認しておきましょう。
加えて、小さな分譲地では、上下水道やガスの引込みができているかも確認しましょう。
特にもともと一つの土地を2つに分けた分譲地は注意が必要です。片方の土地は引込みされていないというケースがあるからです。
上下水道・ガスの引込みには費用がかかります。購入前には概算でもよいので費用を確認しておきましょう。
見積内容を把握する
ローコスト住宅の見積もりは、必ず複数社で見積もりをとりましょう。住宅の建築工事金額には定価がありません。
1社だけの見積もり書では、その金額が妥当なのか、相場よりお得なのかわかりません。複数社に見積もりを依頼して、相場を知り、比較しながら検討しましょう。
また、見積もりを依頼する時には、同じ間取り・床面積・仕様・設備で見積もりを依頼して、同条件のもとで比較・検討するようにしましょう。
見積もり内容を把握するために、見積もりの説明は打合わせをしながら、家族みんなで聞くことをおすすめします。
わからないことは質問して、不明な点がないようにするのが後悔なくローコスト住宅を建てるときのポイントです。
オプション価格の確認
ローコスト住宅の特徴は、シンプルな間取りに、意匠的にも余計なものを排除した住宅です。
ですが、それでは物足りないと感じられる方もいるでしょう。
そうした個々の要望を受け入れるために、ローコストハウスメーカーではオプションを用意しています。
キッチンやバスルームなどの設備のグレードアップや、耐震性や断熱性を標準仕様よりも高い仕様への変更、または内装でも壁や壁紙の素材をより贅沢なものへと変更するなどです。
そうしたオプションを付け加えれば、より自分の理想とする家に近づくことができますが、仕方がないことですが建築費用に反映されます。
そこでオプションをつける場合にはそれがどれほどの価格なのかを細かくチェックする必要があるでしょう。
ローコスト住宅を建てたはずなのに、最終的な価格は低価格ではなくお得感がなかったというのでは残念です。
見積もり内容を確認する
これはローコスト住宅に限らず、注文住宅を建てる際にも必ずすべきことですが、見積内容はしっかりとチェックしましょう。
業者によっては見積もり段階では細かな工事費を省いていたりすることも考えられます。
最低でも2、3社の見積もりは揃え、工事項目なども含めた最終的な見積もりで業者間の比較をするようにしましょう。
コストダウンは割り切って検討、でも無理な計画はしない
ローコスト住宅ではさまざまな部分にかかるコストをカットすることによって相場より安い建築費用を実現しています。
そのため、製品によっては建築後に不便さを感じてしまうこともあるのです。
例えば、建築費用を削減するために断熱材の量が少なく作られており、夏は暑く冬は寒い住宅になってしまうこともありますし、形状をシンプルにするために収納スペースの数が少ないといったことも考えられます。
収納スペースの数や位置については、設計図面を確認すれば十分把握することができますが、断熱材の量については図面からの確認が難しいため、実際にハウスメーカーに問い合わせる必要があるでしょう。
また、同様に壁の防音性についても事前の確認を行っておくことをおすすめします。
家族だけで暮らすとは言え、生活リズムの違いなどによって生活音が問題になることもあるなど、壁の防音性が低すぎると生活に影響を与えてしまうかもしれません。
間仕切り壁が石膏ボードだけで作られている場合など、使用する石膏ボードによってはほぼ音が筒抜けとなってしまうこともあるため、壁の防音性についても事前に確認が必要です。
建築後の保証体制についても確認しておく
新築住宅の場合、建築後に施工不良が発生した場合や、予期しない故障などが起こった場合には建築会社の規定に沿って対処が行われます。
通常の住宅商品の場合、大手メーカーなどでは約10年間の保証が用意されていることが多いのですが、保証による修繕費用を考慮して価格設定を行う必要があるため、ローコスト住宅では保証がやや薄い場合もあるのです。
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法が施行され、構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分の瑕疵については、全ての住宅に対して10年間の瑕疵担保責任が義務付けされる様になりました。
しかし、その他の部分の保証については住宅会社により異なります。
例えば、保証期間が大手メーカーの通常製品に比べて短い約5年に設定されていたり、保証範囲が施工不良や初期不良といった、法律上対処しなければならない最低限の部分に制限されていたりすることもあります。
このような場合、通常の住宅商品なら無償で修繕が行えるにもかかわらず、ローコスト住宅では自分で費用を支払って修繕しなければならないという事態が起こるでしょう。
せっかくローコスト住宅を選んで費用を抑えられたと思っても、修繕費用が高額になると建築費用のメリットが大幅に失われてしまいます。
もちろん、ローコスト住宅を販売している業者の中でも、通常住宅と遜色ない保証体制を敷いている場合もあるので、建築後の対応が心配という方は、こういった保証体制にも力を入れている会社を選ぶと良いでしょう。
信頼できるハウスメーカー・工務店を選ぶ
せっかくのマイホームを建てるのですから、信頼のできるハウスメーカーや工務店を選ぶことも大切です。
広告に踊らされるのでなくご自身の目で展示場などに行き、品質やデザインを確認したり業者の実績などを調べることも業者を選ぶ材料になるでしょう。
また営業マンや担当者と直接会って話し、こちらの要望に耳を傾け、それに対して専門的な知識も交えながらわかりやすく説明をしてくれるような業者なら、後々まで信頼できる業者と言えます。
またどの業者にも特色があり、それと自分の要望と合うかどうかも業者選びのポイントになります。
納得ができて信頼のできるハウスメーカーや工務店を選ぶのが、後悔しない業者選びの方法です。
ローコスト住宅にありがちな失敗や後悔について
ローコスト住宅には注文住宅の様な自由度はありません。
規格化された商品プランを組み合わせて家を建てることでローコストを実現しているので、細かい施主のこだわりを叶える選択肢がないことがほとんどです。
希望する設備を依頼するのも一つ一つ相談をしなければならず、自由に選択できない欠点が入居後の後悔につながることもあります。
ローコスト住宅の建築費は1,500万円未満が多く、土地の購入費用を含めると総額3,000万円から4,000万円台を買われる方が多いのも特徴です。
地方の工務店によってはローコスト住宅に特化して、土地代を除き1.000万以下でも小家族なら十分住みよい規格住宅も提供されています。
地場信用金庫などとの連携で、若年層向けの商品開発も進んでいます。
その反面、土地購入を含む融資限度額の壁や、建築仕様の選択肢の少なさゆえに夢を希望通りに実現できないことが根深い後悔として残るケースもあるようです。
実際、購入者は30代から40代が多くいることは統計で出ています。
住宅ローンの融資限度額も関係し、選択肢の少なさゆえに夢を希望通りに実現できないことが根深い後悔として残るケースもあるようです。
ローコスト住宅で後悔しないための注意点
ローコスト住宅で建てる際には、よく確認しておきたい注意点があります。それは価格やオプションの確認、間取りやデザインの確認、材質の確認、アフター保証の確認の4つです。
価格&オプション料金を確認する
ローコスト住宅の見積もりが出てきたら、見積もりの内容を確認しましょう。一般的に住宅の見積もりは主に4つの項目にわかれています。
・住宅の見積もり 一般的な項目と内容の例
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 建物本体価格 | 標準仕様の坪単価で計算される価格 | 坪単価×坪数 |
| オプション価格 | 間取りや設備などの変更で追加になる価格 | 各々の価格の合算 |
| 付帯工事価格 | 屋外給排水設備工事や足場・アンテナ工事解体費など、 住宅を建てるためにかかる費用。住宅の建築地などの状況により金額が異なる費用 |
各会社により、付帯工事の内容が違うため要確認 |
| 諸経費 | 消費税・登記費用・建築確認申請費用など |
住宅を建てる時は、これら4つの項目の費用が必ずかかります。
住宅会社によっては、建物本体のみの価格を表示して、坪単価を安く見せる工夫をしていることがあります。
どこまでが標準仕様・設備なのか、間取りや設備などのオプション金額はいくらになるのか、その他付帯工事の金額も確認することが大切です。
間取り・デザインについて
ローコスト住宅では、ローコストを実現させるために、色々な工夫をしています。
その中に、間取りやデザインについて細かい決まりのある規格住宅があります。規格住宅の場合、間取りもデザインも住宅会社の方が用意しています。
自分の好みとは関係なく、規格通りに建てなければなりませんが、坪単価は非常にローコストです。
ただし、ローコスト住宅の中には、ある程度の間取り変更に対応している注文型のローコスト住宅もあります。
規格型よりもルールが少ないため、坪単価は高めですが、完全注文住宅に近い住宅が建てられます。
ローコスト住宅を検討する際は、規格型なのか注文型のローコスト住宅なのか、どちらが自分たちに合うのかよく検討しましょう。
納得のいく材質を使っているか?
ローコスト住宅では、標準仕様の材料や設備が決まっていますが、標準仕様のものがすべてではありません。
住宅は一度建てると、簡単に建て替えなどできませんし、リフォームするにもある程度費用がかかります。
標準仕様の材料や設備が納得いかない場合は、価格は上がりますが、オプションにしてでも代えてもらうように相談しましょう。
アフター保証はあるか?
家を建てること際に一緒に考えておきたいのが、「アフター保証」です。アフター保証は家が完成した後、不具合が生じた時にとても重要となります。
不具合が起きた箇所や症状・原因により保証内容が違いますが、住宅会社では独自の「保障約款」があり、工事請負契約時に契約書に添付することになっています。工事契約をする前に保証約款を確認しておきましょう。
2000年4月に施行された「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」において、新築住宅では、屋根・柱・基礎などの住宅の基本的構造や雨漏りなどにかかわる部分について、最低10年間の保証を行うよう定めています。
そのため、ローコスト住宅に限らず、どのハウスメーカーや工務店で家を建てた場合でも、最低10年間は無償で保証を受けることが可能となりました。
近年はアフター保証の面で差別化を図るため、品確法の規定とは別に、長期間の定期点検やメンテナンスを行っているハウスメーカーや工務店もあります。
3カ月点検ではサッシや建具の調整など、1~2年点検や5年点検では基礎・外壁の吹き付け・防水シートの点検、玄関ドア・サッシ・室内建具の点検、給排水の点検など。
10年以降の点検では基礎コンクリート・外壁・屋根・ベランダの点検など、長期間、定期的に点検やメンテナンスを行っているところもあります。
また、住宅設備関連や内装などについては、標準的な保証期間は2年間となっているため、不具合箇所については、建ててから2年以内に確認しておくようにしてください。
ただし、使用したことによって発生した不具合については、有償での修理などとなるので注意しましょう。
ローコスト住宅の問題点とは

ローコスト住宅は低価格で新築のマイホームを手に入れられるとあって、特に若い世代から注目を集めています。
ローコスト住宅とはローコストハウスメーカーや、施工費用を安く抑えた工務店によって建てられる物件で、1,000万円台でも新築の家が建てられることがあります。
しかしローコストだからこそ何か問題があるのではと疑うのは、ごく一般的なことでしょう。
そこで、ローコスト住宅を建てるときの注意点とは何か、順を追って見ていきましょう。
設備のグレードを下げすぎた
設備のグレードを下げると、住宅の建設費用を手っ取り早く下げることができます。
だからと言って、どんどん下げてしまうとあとで後悔することがあります。
設備は、目に見えるものでキッチンやバストイレなどの水回りの機器などのほか、換気や給湯設備、コンセント、照明器具なども考えられます。
たとえば、毎朝同じ時間帯にトイレを使う家族がいるのに、コストカットをしようとトイレを1つにしてしまったため朝はトイレの取り合いが起きてしまう。
コンセントの数を減らしたために必要な場所にコンセントがなく、通路に長々と電気コードが出てしまう。
キッチンのコストを抑えたために収納が足りなくなり、物があふれてしまうなど。
これらの結果が後悔となり、日々の生活にストレスを抱えることになります。
あとから追加などの工事をしようとすると建築時に組み込むより費用がかかってしまうことにも注意が必要です。
ほかにも、断熱性能のグレードを下げすぎたために、結露によって建物の構造体に早く傷みがでてしまい、結果的に高くついてしまうことも考えられます。
耐震性能や遮音性能も下げすぎることがないようにしたいポイントです。
やみくもに設備のグレードを落として安くすることばかりに目を向けるのではなく、必要なものと不要なものをよく話し合い整理することが大切になります。
その価格表示にからくりあり⁈
ローコストハウスメーカーが低価格を実現できる理由は、無駄なコストを徹底的に削減した努力の結果だと言えます。
広告費用を抑えたり、資材を一括購入するなどして資材の単価を下げるなどすることで低価格を実現しています。
誤解があっていけないのは、資材の質が良くないから低コストというのではなく、無駄な支出を抑えたから実現している価格だということです。
ただカタログなどに表示されている坪単価に関しては、実際に住宅を建築するためのコストよりも低く表示されていて、その価格はより一層安く見えることがあります。
なぜそうしたことができるのかというと、坪単価の価格の算出方法に法的な決まりはなく、各業者の判断によって算出していいことになっているからです。
そのため少しでもお客様にお得に見せるために、坪単価の価格には必要かどうかわからない配管工事や電気や水道の引き込み工事費用、浄化槽の設置工事などは含まれていないことが多く、坪単価も安くなります。
また設備費用も含まれている場合と含まれていない場合があり、実際の建設費用は最初の坪単価から比べると大きく隔たりがあることもあるのです。
そのため坪単価を鵜呑みにしないというのが、ローコスト住宅に限らず住宅価格をチェックするときに気をつけたいことです。
標準設備+オプションで高い物件になる?
標準設備に含まれるものだけでローコスト住宅を建てられればいいのですが、実際にはプラスアルファの設備投資を希望される受注者も多いようです。
ローコスト住宅は規格住宅のため、標準設備内ですべての設計がおさまれば低価格の家が建てられます。
しかし標準設備以外のものを注文した場合、オプション価格が追加されるため、想定していたよりも総費用は高くついたというのはよく聞かれる話です。
短い工期には要注意⁈
ローコスト住宅の建設にかかる工期は約4カ月が目安です。これでも十分に短い工期ですが、さらに短い工期を謳っているハウスメーカーも少なくありません。
工期が4ヶ月よりも短いとなると、手抜き工事などの住宅のクオリティへの悪影響が考えられますので、短すぎる工期が提示された時には注意が必要です。
希望の間取りにできない
家の形状は基本的に正方形か長方形に限られるので、部屋の間取りもいくつかあるパターンから選ぶことになります。
プランニングされた間取りの長所は、材料に無駄が出ないことです。
一定の決まった長さで統一することで、無駄を無くしています。
プランが規格化されることによって設計の打ち合わせも少なくて済むので、設計費用のコストをカットできます。
ローコスト住宅は今までに規格化量産化されたプランを組み合わせた商品であることをまずは理解しておきましょう。
間仕切りを減らしすぎて空調が効きづらい
ローコスト住宅では、壁や扉を減らすことでもコストダウンを図っており、必然的にひと部屋は広めのスペースとなります。
また、換気を機械による強制換気に委ねることが多く、7割前後の住宅で使用されています。
この換気システムは、強制的に室内の汚れた空気を外に排出し、排出した圧力差を利用して室内に外気を取り込むものです。
設備費用やランニングコストが安く、計画換気が容易で大量換気もできる点はメリットで、キッチンのレンジフードやトイレ、浴室の換気扇によく使われています。
しかし、室内の暖房、冷房された空気をそのまま排出してしまうというデメリットもあります。
当然部屋の温度も室内の空気排出されることで変化し、エアコンの使用量が増え、ランニングコストが増加していきます。
この換気システムでは、外気温の影響が室内に大きく影響してしまい、空調が効きづらくなると言えます。
オプションが多いと結局高額になる
ローコスト住宅を建築する会社によって標準プランの内容が変わり、一概には言えない事ではありますが、TVの受信に必要なアンテナの設置工事などがオプションの場合などがあり、見積書や工事の打ち合わせでは確認すべきことが沢山あります。
オプションとなる主なものは
- キッチン、トイレなどのアップグレード
- フローリングの床材を無垢材にしたり、珪藻土などの塗り壁にする内装工事
- 耐震仕様にアップグレードする場合
などです。
これ以外にも、契約後の追加オプションの値引きには応じてくれるケースが少ないのです。
契約してくれたお客様が解約することがほとんどないと建築会社が見込むためです。
コストを抑えられる間取りのポイント
シンプルな間取りにする
部屋数が増えると、壁や扉が増えます。
壁や扉が増えると材料と手間が増えるため増額の原因になります。
逆に、部屋数が少ないシンプルな間取りであれば、コストを抑えることができます。
つまり、3LDKよりも1LDKのほうが安く、LDKは一室である方が価格をおさえることができるでしょう。
また、室内空間もできるだけ凹凸の少ない四角い部屋である方が安くできます。
ほかに曲線は価格がアップするため、直線で構成することもポイントになります。
ただし、前章で解説したように間仕切りの少ない家は、広い範囲の空調が必要になり、光熱費が高くなる傾向があるためバランスをとることが大切です。
水回りをまとめる
キッチン、バス、トイレなどの水を使う場所は、できるだけ1か所にまとめます。
水を使う場所には、給水と排水の配管が必要になり、さらにお湯を使う場所では給湯の配管が必要になります。
そのため、水を使用する部屋がそれぞれ離れて配置されていると、配管が長くなってコストアップにつながってしまいます。
できるだけ無駄のない短い配管で済ませるため、水回りは1カ所にまとめることがポイントになります。
また、水道やガスは道路からひくので、道路近くに水回りを配置することでコストをおさえることができます。
さらに、2階によりも1階に水回りをまとめると配管を短くすることが可能になります。
ほかに上下階にトイレを設置する場合は、垂直方向にも水回りをまとめるとよいでしょう。
平屋ではなく階建てにする
平屋の方が安くすむイメージをもたれている方も多いですが、シンプルな形の2階建てにする方がコストをおさえることができます。
平屋にすると地面に接する面積が2階建てより大きくなり基礎工事が増えるほか、屋根が大きくなることで建築費用が高くなります。
最も価格が抑えられるのは、1階と2階が同じ形のキューブ状の2階建ての家です。
ローコスト住宅の寿命はどれくらいか
日本の家屋の平均寿命は約25年から30年で、夏と冬の温度差や湿度の高さが住宅の寿命を短くする要員とも言われています。
ローコスト住宅の寿命について
基本的に建物はメンテナンスをするべき時期に行う事や日々の住まい方で建物の寿命は変わると言われています。
ローコスト住宅であっても30年以上住まい続けることは可能でしょうが、世代交代と共に、建て替えるケースがほとんどです。
ローコスト住宅の骨組みは、か細く感じますが、現代の建築は耐震や結露に対する研究が進み、建築技術も格段に向上しています。
定期的なメンテナンスが建物の寿命を延ばすと考えると、住み方とメンテナンスをまめに行うことが重要と言えるでしょう。
工務店によって住宅の寿命は変わる
工務店やは建築会社によって建物の寿命の長短が決まることは余りありませんが、急成長しているハウスメーカーの中には職人の技術レベルが低すぎたり、現場監督の管理がいい加減で職人に現場を任せっきりというケースもあります。
で完成した住宅は多くのトラブルを抱えていることは事実です。
10年前、20年前にTVでやたらと取り上げた欠陥住宅問題の中にローコスト住宅も取り上げられていたことから、ローコスト住宅=欠陥住宅と決めつけられたような印象がありますが、これは違います。
大手ハウスメーカーや大手建設会社でも欠陥住宅は露見しています。
この様に見ていくと、建物の寿命を決める要因の一つは建てる職人の技量があることは事実です。
しかし、欠陥住宅でなくても、不具合箇所が見つかった時に建築会社や入居されているオーナーの方が早めに修繕したり手当をすることで、建物の寿命は延びます。
一概に建築する会社や業者によって建物の寿命が代わると断言することは出来ません。
家を長持ちさせるポイントについて
戸建て住宅は空き家にすると、たちまち劣化老朽化が進み、廃屋になってしまいます。
家が生きていると実感できる現象だと思います。
ローコスト住宅でも、日々手入れを怠らず、適時な手入れを施せば、長期優良住宅並みに長く暮らせるものです。
例えばキッチンの排水管を高圧洗浄するタイミングは5年に一度とか、ガスコンロ給湯器の交換時期は10年が目安になります。
外壁の塗装やサイディングの継ぎ目のコーキングの打ち直しも10年以内に行う事がベストと言えます。
また、緊急に修理をしなければならない不具合が起きることもあります。
キッチンの推薦の水漏れや水栓金具のハンドルが取れて水が吹き上げる時などは、当日中に専門業者に来てもらう必要があります。
建築を担当した建築会社に連絡が取れない場合は、引き渡し時に内部仕様書と図面を貰っていれば、設備に使われている部品の製造会社が判るので、修理依頼窓口に相談が出来ます。
また、便利屋さんでも対応できるところがあるので、早めに修理依頼をしたほうがいいでしょう。
長らく放置することは家にとってあまり良くないことないと認識しておきましょう
ローコスト住宅の依頼先はどこが良いか

ローコスト住宅の建築契約はどこと結べばよいか悩むところです。
主な契約先には以下のようなものがあります。
1:ハウスメーカー
積水ハウスや住友林業、野村不動産、旭化成等大手は予算に合わせた見積もりを出してくれますが、希望する予算額と大きくかけ離れた見積書の提示を受ける可能性もあります。
全国展開をしていない地場のハウスメーカーの中には外構工事を諸経費に入れてくる会社もあるようなので気を付けなければなりません。
しかし、大手ハウスメーカーは入居後のアフターメンテナンスが充実していて、定期的に訪問して瑕疵を指摘してくれたり、大きな手直しの相談にも乗ってくれます。
2:工務店
比較的地元に根差した営業展開をしているので土地の長所や短所を良く分かっていて、細かい相談にものってくれることがあります。
工務店を経営される多くの方は大工さんや設計士等の職人集団とも言えます。
水道、電気、ガスなどの業者さんは工務店との付き合いが長く、気心が知れているため仕事がスムーズに捗ります。
地元であるが故に仕事が丁寧な工務店を多く見付けることが出来ます。
3:設計事務所
設計士が監理する住宅はデザイン性が優先され、住みやすさが後回しになると思う人や設計料が高いと決めつけている人がいると思いますが、施主の相談には適切なアドバイスをしてくれることがあります。
ただし設計から施工、完了引き渡しまでの時間が掛かるため、敬遠される方が多くいます。
通常、戸建て住宅は3か月強から1年ほどで完成しますが、設計事務所の場合最長3年以上という例もあります。
ローコスト住宅を建てるにあたり、依頼先は多岐にわたりますが、少なくとも数社の建築会社や工務店から見積もりを取り寄せ、各社の営業担当と話を重ねてみましょう。
相談をすすめるうちに、必然的に建築に関する知識と見極めが育ってくるので、打ち合わせを重ねることに損はありません。
建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?
ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。
注文住宅の設計プランや費用は、施工店によって大きく異なることがあります。
そのときに大事なのが、複数社に見積もりを依頼し、「比較検討」をするということ!
実際に注文住宅を建てるには時間がかかるので、この記事で大体の予想がついた方は早めに次のステップへ進みましょう!
「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」
「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」
そんな方は、簡単に無料で一括査定が可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。
一生のうちに注文住宅を建てる機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!
一括見積もりをする