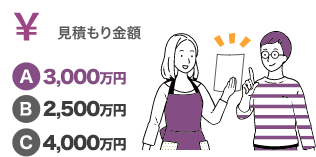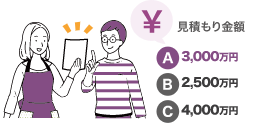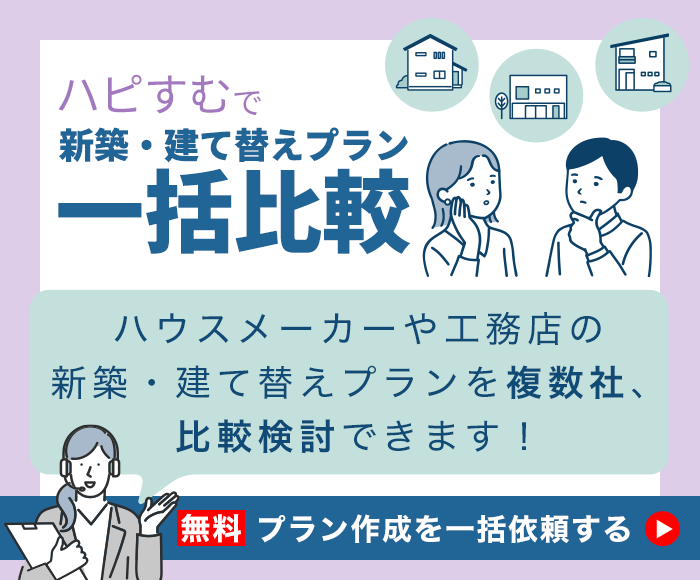2023年12月18日更新
ローコスト住宅のメリット・デメリットを解説!後悔しないためのポイント!
目次
- 1 ローコスト住宅の住み心地は良い
- 2 なぜローコストで家が建つのか?
- 3 ローコスト住宅は危険なのか
- 4 格安の注文住宅「ローコスト住宅」を請け負う業者の種類
- 5 フランチャイズメーカーに依頼しローコスト住宅を建てる場合のポイント
- 6 標準仕様の特徴とは?ローコスト住宅メーカー次第で変わる内容
- 7 ローコスト住宅メーカーの標準仕様のコストカット方法とは?
- 8 ローコスト住宅の見積もりチェックポイントと値下げ交渉について
- 9 ローコスト住宅の標準仕様の問題
- 10 ローコスト住宅のコストによる問題点
- 11 ローコスト住宅のデザインや間取りによる問題点
- 12 間取りをどう決めたらいいか知りたい
- 13 平屋で注意すべきポイントを押さえて快適な家づくり
- 14 ローコスト住宅の保障面での問題点
- 15 ローコスト住宅を購入する際の注意点
- 16 ローコスト住宅で後悔しないポイント
ローコスト住宅の住み心地は良い

住宅を建てたいけれどあまり予算をかけられないとき、ローコスト住宅であれば比較的安価に住宅を手に入れることができます。
「ローコスト住宅」と聞くと、建物の安全性や住み心地について何か問題があるのではないかと気にする方もいるようです。
しかし、ローコスト住宅であるからといってそのような心配は必要ないでしょう。
ローコスト住宅について詳しく知り、住み心地の良い住宅を安価で手に入れましょう。
ローコスト住宅も住み心地の良い家を建てられる
ローコスト住宅であっても住み心地の良い家を建てることは可能です。
たしかにローコスト住宅では、使用する建材や備え付けの設備等は高級住宅よりも選択の幅が狭まります。
しかし、ローコストであるからといって必ずしも質が劣るというわけではないのです。
ローコスト住宅では建物の構造がシンプルになったり外装にオリジナリティを反映し辛い部分はありますが、その分建築費用を安く抑えることができます。
安く抑えられた費用を内装や家具などに充当することができるため、外からの見た目以上に住み心地の良い家を実現することができるでしょう。
なぜローコストで家が建つのか?

それでは、なぜローコスト住宅は安い工事費で住宅を建てられるのでしょうか。
その秘密を探っていきましょう。
材料費のコストダウン
ローコスト住宅は、フランチャイズ工務店が実際の施工をしています。
しかし建築資材は、大元のハウスメーカーがまとめて材料を受注しています。このため材料費を安く仕入れることができるのです。
たとえば、アルミサッシは同じサイズの製品を固定化して大量に仕入れているため、仕入れ単価をさらに下げることが可能なのです。
このためローコスト住宅では、一戸の住宅内で同一サイズのアルミサッシが取り付けられます。
しかもアルミサッシを取り付けるよりも、外壁として仕上げた方が工事費が安くなるため、ローコスト住宅では開口部が少なくなる傾向があります。
設備・仕様のグレードダウン
衛生機器、浴槽、システムキッチン、給湯器といった設備機器は、グレードの低い製品を標準仕様としています。
その上、設備メーカーが販売している既製品をそのまま採用しているので安い単価で仕入れることができるのです。
しかも代理店を通さずにメーカーと時価取引をしていますから、価格は相当引き下げられています。
規格住宅が多い
ローコスト住宅では、自由設計の住宅は取り扱いません。予め規格化された住宅を建てることで、コスト削減を図っているからです。
規格化された住宅を大量に生産することで、同一の建築資材を大量に安く仕入れられるのです。
人件費・広告宣伝費の削減
ローコスト住宅では、人件費も削減しているので、現場監督の数も少なくしかも経験年齢の浅い人達が中心になっています。
現場で施工する大工も経験年数の浅い人が多く、ベテランの技術を伝承するという雰囲気は皆無です。
またTVCMは、一部のハウスメーカーを除けば広告費の高い全国ネットでは流しません。
広告費の安い地域限定のローカルエリアを中心に流すことで広告費を削減し、原価を抑えているのです。
諸経費など
注文住宅を建てる際には諸経費が必要となります。
この諸経費とは様々な細かな費用が含まれますが、部屋の間取りをシンプルなものにしたり部屋の数を減らすことによって抑えることができます。
多くのローコスト住宅では建物の形状が矩形であるなど、あまり複雑な形状をしていないものが多いのはそのためです。
他にも、ローコスト住宅では限られた施工業者が一貫して建築工事や水道工事、電気工事などの工事も行うことによってコストの削減を図っています。
工事の内容毎に複数の業者へ発注を掛けているとそれだけ諸経費も掛かってしまいますが、自社で全て完結させることによって諸経費を抑えることができるのです。
ローコスト住宅は危険なのか
ローコスト住宅と聞くと、コストを抑えて建築できる代償として危険な住宅なのではないかと疑われてしまうことがあるようです。
しかし、ローコストであるからと言って手抜き工事を行っていたり、基準を満たしていない建材を使用しているというわけではありません。
どういうことかについて説明します。
安い=危険とは限らない
ローコスト住宅は低価格で建築できるからと言って危険であるとは限りません。
たしかに工事を行う技術者が未熟であったり、使用する建材が安全基準を満たしていない場合は危険性があるかもしれません。
しかし実績があり、それなりに名の知れているハウスメーカー等であればローコストであるからといって品質について心配する必要はないでしょう。
安いということと危険であるということには直接の因果関係はありません。
なぜローコスト住宅は安いのかということを正しく理解することが、安心してローコスト住宅を建てることに繋がります。
家づくりの自由度は下がる
ローコスト住宅は価格を抑えるために建物の間取りやデザインがある程度規格化された物が多いでしょう。
予めハウスメーカー等によって決められたパターンの中から気に入った物を選んで組み合わせることで住宅にオリジナリティを持たせることはできます。
しかし、決められた範囲内でしか自由に選択することができないため、ローコスト住宅では施主の全ての要望を反映させることは難しいでしょう。
二世帯住宅でもローコスト住宅は建てられるの?
二世帯住宅でもローコストで建てることができます。ただしローコストで建てる場合、基本的には完全同居型となります。
やはりローコストになりますので何でもできるわけではありませんが、条件付きで建てることは可能です。
では、完全同居型とはどんな二世帯住宅なのでしょうか?価格の相場と共に特徴を紹介していきます。
完全同居型とは?
完全同居型とは、一般的な戸建て住宅に二世帯が同居するタイプの二世帯住宅です。一般的な戸建て住宅より広さを必要としますが、設備は一つで済みますのでコストを抑えることができます。
基本的に各自の部屋はありますが、お風呂やキッチン、ダイニングなどは共用になります。トイレは2か所以上設置することもできますが、それ以外は基本的に1つになりますので、二世帯住宅でプライバシーなどを気にする人は予め注意が必要です。
二世帯住宅をローコストで建てた場合の相場は?
一般的にローコストで完全同居型の住宅を建てる場合、1000万円台が一つの目安となります。坪単価ですと約20万~40万円で、広さは約35坪を基準に検討するとある程度イメージできるかもしれません。
実際にローコスト住宅を建てる場合は、しっかりと業者と相談をした上で進めていきましょう。妥協する所としない所のメリハリを付けて理想の二世帯住宅を建ててください。
信頼できる業者に依頼しよう
ローコスト住宅は大手ハウスメーカーだけでなく中小規模のハウスメーカーや工務店等、多くの建築業者が販売を行っています。
そのためローコスト住宅を建てたいと考えた時にどの業者に建築を依頼すれば良いか迷ってしまうこともあるかもしれません。
建築を依頼する業者を選ぶ際には、業者の用意したカタログ等で完成後のイメージを確認しながら良し悪しを判断します。
信頼できる業者であれば問題ありませんが、良く知らない業者へ依頼しようとする場合には注意が必要です。
実際に完成したものを確認した時にイメージと違っていたり、予め確認して選択したはずの材料がなくなって代用品を提案されたりといったトラブルがあるかもしれません。
納得いく住宅を建てるためにも、建築を依頼する際には信頼できる業者に依頼するようにしましょう。
格安の注文住宅「ローコスト住宅」を請け負う業者の種類

ここまでローコスト住宅についていくつかご説明してきました。
それでは実際にローコスト住宅を建てるには、どのような業者に依頼すれば良いのでしょうか。
ローコスト住宅の建設を請け負っている業者として、ハウスメーカー、ハウスビルダー、そして工務店が挙げられます。ここではそれぞれの業者の特徴について確認しておきましょう。
大手ハウスメーカー
ハウスメーカーとは全国展開している大手の住宅建設会社のことです。
ハウスメーカーの特徴としては、自前で生産設備を有しており一部の建材を大量生産するなどとにかく会社の規模が大きいということが挙げられます。そのため工期が比較的短く、一定の品質が保たれるなどのメリットがあります。
しかし、大手のハウスメーカーではローコスト住宅を扱っていないケースも多いため、事前に確認しておきましょう。
ハウスビルダー
ハウスビルダーはハウスメーカほどの規模はないものの、地方都市を中心に展開している中堅の住宅建設会社のことを指します。
特定のエリアではトップシェアを持っていたりハウスメーカー以上に信頼の厚い会社も少なくありません。
ハウスビルダーは地域に根ざした会社であり、価格も地域の水準に合わせて比較的リーズナブルに抑えています。ローコスト住宅を扱っている業者の多くもハウスビルダーに分類できるでしょう。
住まい関連の事業をトータルで手掛けていることも多いため、住宅の建設についてだけではなく、土地探しなどについても対応できるケースがあります。
工務店
工務店は地域密着型の大工と職人の集団です。地域に根差した家づくりを得意としており、その地域の特性に合った住宅を提案してもらうことができます。
工務店によっては、ローコスト住宅を売りにしているところもあるため、このような業者を選べば、満足度高く費用を抑えた住宅を建てることができるでしょう。
フランチャイズメーカーに依頼しローコスト住宅を建てる場合のポイント
ローコスト住宅を可能にしたフランチャイズ方式

ローコスト住宅とは、従来の家づくりよりも価格が低く抑えられている住宅のことです。
なぜ安く家を建てられるのでしょうか。
品質の悪いを資材を使っているからなのか、それともまさか手抜き工事をしているからなのかなどと疑ってしまいそうになりますが、そうではありません。
ローコスト住宅とは、これまでの建築業界にあった無駄な部分を省いたから実現したのです。
その無駄を省く方法として、多くのローコスト住宅メーカーはフランチャイズ方式を採用しています。
では、そのフランチャイズ方式とはどのような仕組みになっているのでしょうか。
フランチャイズ方式とはなにかを解説します。
フランチャイズ方式とは
フランチャイズ方式とはコンビニやファミリーレストランなどの飲食業に多く採用されているシステムで、本部と加盟店で構成されています。
本部が商品開発から仕入れ、営業のノウハウやサービスに関わる全てを構築して、それらを加盟店が使う権利を得て営業するという仕組みです。
フランチャイズ方式が可能にするコスト削減
このフランチャイズ方式を住宅業界が取り入れることのメリットは、何よりも無駄なコストを削減できることです。
本部が資材を一括購入したり、人件費を抑えるために資材を事前にプレカットして部品化することで組み立ての手間を省きます。
また広告費は本部が一括して受け持ちます。
そうした従来の建築業界では当たり前となっていたコストを少しでも削減する努力の結果、従来よりも安い建築費用で住宅を建てられる「ローコスト住宅」を可能にしました。
中間マージンを抑えて低価格を実現
住宅の建築で最も費用がかさむのが、資材費と人件費、そして諸経費です。
諸経費には広告費用や業者の利益分などが含まれるのですが、ローコスト住宅のフランチャイズメーカーは、大手メーカーに比べてこの中間マージンを抑えるようにしています。
テレビなどのCMなど大々的な宣伝をしていないローコスト住宅メーカーは珍しくありません。
こうした中間マージンを抑えることで、住宅の建築価格を下げられたのです。
フランチャイズメーカーに依頼してローコスト住宅を建てるメリットとは
フランチャイズ式のハウスメーカーだからこそ得られるローコスト住宅のメリットとは何でしょうか。
安く家を建てられるというだけでも大きな魅力ですが、メリットはそれだけではないようです。
そこでフランチャイズメーカーに依頼した場合のローコスト住宅を建てるメリットについて紹介します。
コストダウンに成功
ローコスト住宅の最大のメリットは、低い予算で高品質の家を建てることができることです。
まずローコスト住宅と言われる由縁の、低い価格を実現している理由は次の通りです。
ひとつは、資材や設備の種類を限定して大量発注すること。
これにより仕入れのコストダウンに成功しています。
そして資材をすでに加工、部品化して提供するため組み立てるための人件費を抑えていることです。
さらに宣伝費用なども削減して諸経費をカットしていることでも低価格を実現しています。
クオリティを下げるのではなく、そうした企業努力によってローコストにしているのです。
そのため価格は低くても品質は維持された住宅を建てられるのです。
ローコストでも高品質な住宅が実現
ローコスト住宅は規格住宅になるため、間取りや設備などをカタログを見ながら選んでいきます。
プロの目により厳選されたプランから選んでいくので納得のいく仕上がりが期待されます。
またフランチャイズメーカーのメリットとして工務店と比べると最新の技術を取り入れているケースも多く見られるという点でも、高品質が期待されます。
安全性でも劣らないローコスト住宅
ローコスト住宅も一般の建築物に適用される建築基準法の規定をクリアしなくてはなりませんので、安全性においても信頼できます。
さらには耐震構造や住宅金融支援機構の基準をクリアした耐火構造を持つローコスト住宅も提供されていますので、低価格でも安心のできる品質の家が手に入ります。
アフターフォローもあって安心
ローコスト住宅メーカーだと、家を建てるまではいいけれどその後のサービスがよくないのではという不安がよく聞かれます。
しかし法律により10年保証は決まっていますし、中には大手メーカーと変わりないほどのアフターフォローサービスを提供しているローコスト住宅メーカーもあります。
フランチャイズメーカーに依頼してローコスト住宅を建てるデメリットとは
ローコスト住宅にはメリットがいろいろとある一方で、残念ながらデメリットもいくつか考えられます。
大切な我が家となる住宅のことですから、契約した後でこんなデメリットがあったと驚く前に、どんなデメリットがあるのかを知っておきましょう。
フランチャイズメーカーに依頼してローコスト住宅を建てた場合のデメリットについて見ていきます。
限定されるプラン
ローコスト住宅は予算を抑えられている理由は、資材の種類を限定して大量に発注しているからです。
その大量発注をするためには、どうしても家の間取りや部屋のデザインなどを限定しなくてはなりません。
そのため、依頼者は限定されたプランから選んで住宅を設計していくのです。
プロの目によって選ばれたプランですから安心して選ぶことができる一方で、どうしても自分の好みに合うプランを見つけることができないということもあるでしょう。
自分のマイホームなのだから自分の理想のプランを実現したいと思っても、思い通りにならないこともあります。
オプションをつけたら高価格
低予算で建てるはずが実は結構割高になったというのは、ローコスト住宅の建設で聞かれる話です。
それは限定されたプラン以外のオプションを追加していったためで、その結果、最終的な予算が膨らんだケースです。
ローコスト住宅の標準プランはデザインがシンプルと言えば聞こえがいいのですが、単純で装飾性が足らないと思われるプランが多いようです。
また設備のグレードが低いなど、設備面で納得のできないこともあるようです。
標準プランに満足ができないのなら、オプションとして別のデザインに変更したり、グレードの高い設備を導入することができます。
しかしそうなると、オプション価格が付け足されるため、ローコスト住宅とは名ばかりの、決して安いとは言えない住宅になってしまうことがあります。
大手メーカーよりも保証が短め
アフターフォローとなる保証は、ローコスト住宅でも法律で義務化されている最低10年の保証が付いています。
しかしローコスト住宅メーカーではない大手のハウスメーカーでは、10年よりも長い長期の保証をつけてより安心して暮らせる環境を提供していることがあります。
それと比較するとローコスト住宅の場合は保証期間は短めという傾向があるため、デメリットのひとつと考えられるでしょう。
ローコスト住宅を依頼するフランチャイズメーカーの選び方
ローコスト住宅を建てようと決めたら、次はメーカー選びです。
しかしメーカーも複数あり、どのメーカーにするのか迷ってしまいます。
そこでローコスト住宅を建てるときのフランチャイズメーカーの選び方をご紹介します。
インターネットなどで各メーカーの評判を読む
インターネットでは各メーカーの口コミや評判を書いたサイトなどが複数存在します。
まずはそういったところから、各メーカーがどのような会社なのか、その特徴や強みなどを確認してみてはどうでしょうか。
もちろん、各メーカーの自社サイトも参考になる情報や物件例などが紹介されていますので、こちらも目を通すのがいいでしょう。
ただしここで気をつけたいことは、口コミや評判がいいからと言って、自分に合った住宅を建ててくれるとは限らないということです。
ご自身が希望とされるマイホームのプランを現実化するお手伝いをしてくれるような住宅メーカーはどこかという視点を忘れないようにして、各メーカーの情報を集めてみましょう。
アフターサービスが手厚いメーカーを選ぶ
家は建てた時だけではなく、建てた後のケアも大切です。
そのためにアフターサービスの手厚いメーカーを選ぶと、後々、問題が起こった時などにすぐに対処してもらえます。
メーカーによる10年保証は法律によって決められていますので、まずはその10年保証が付いているかを確認します。
ただこの10年保証は住宅の基礎部分の保証で、キッチンやバス、トイレなどの水回りは保証外になる場合がほとんどです。
しかし水回りは問題が起こりやすい部分でもありますから、水回りでどのような保証が付けられると安心です。
またフランチャイズメーカーの場合、営業所が急になくなるといったケースもみられ、住宅に問題が起こってから対応してくれるまで数日かかったということも聞かれます。
そのため担当となる営業所がなくなった場合も含めてどのような保証やアウターフォローがあるのかを確認しましょう。
相見積もりを行う場合は坪単価ではなく総額で比較する
ローコスト住宅は規格住宅になり、住宅として必要な部分は標準価格の中で素材などを選ぶことが多いのですが、それ以外のものはオプションとしてつけていくことになります。
そのため建築費用は想像していたよりも高くなることも予想されます。
このことからローコスト住宅の建築費用は、オプション費用も足された総額で他社と比較検討することが大切です。
各メーカーのアピールポイントを比較する
住宅メーカーがいくつもあるということは、それぞれに得意とする分野があったり特徴があるものです。
耐震構造だとか高気密・高断熱を売りにしているなど、各メーカーのセールスポイントやアピールポイント踏まえて、それが自分の好みと合っているか、または納得できるかで、理想の住まいの建設につながります。
そのため自分の好みの家を建てるためにも、各メーカーのアピールポイントを知ることも後悔しないメーカーの選びの方法です。
建設現場を見て職人の態度などをチェック
フランチャイズメーカーでは、人件費を抑えるために、資材をあらかじめ工場でカット・加工をしておいて、家を建てる現場では作業工程を少なくするような努力がされています。
だからと言って、経験を積んでいないような素人にできるわけではありません。
ちゃんとしたプロの手によって建てられてこその住宅です。
そこでどんな職人が働いているのかを確認するというのも、メーカー選びのポイントになるでしょう。
検討されているメーカーが建てている住宅の建築現場に行き、そこでの職人の態度を見てみます。
コーヒーブレイクのときにたばこのポイ捨てをしているような職人がたくさんいるような現場は、あまり感心できません。
プロの職人というのは普段からの態度もちゃんとしているものですから、そうした常識のある行動の職人が働いているかどうかもメーカー選びの材料です。
フランチャイズメーカーに依頼してローコスト住宅を建てる場合の注意点

宣伝価格と実際の価格に乖離がある
宣伝としてこの延床面積に対してこれくらいの価格、といったように、カタログなどに表示されているのを目にすることがあるでしょう。
しかしそれはあくまでも価格の一例にすぎません。
ご自身の建てたい住宅の実際の価格は、それとは大きく違うことがあります。
なぜならローコスト住宅は規格設計内の標準価格に加えて、オプションとしていろいろと後から付け加えることができます。
さらに住宅建築では、ぎりぎりになってからの変更や突発的なトラブルなどで予想外の出費もあるものです。
ですから宣伝価格は参照までに見ておくようにして、実際にプランニングをした後の価格には違いがあることは覚えておきましょう。
広告に出ている坪単価のからくりに注意する
広告には坪単価が掲載されていますが、これも上記で取り上げた宣伝価格と同じように、あくまでも目安となる価格です。
実際にその坪価格の予算のみで住宅が建つことはあまりないと思っておくのがいいでしょう。
特に坪単価は各業者によって計算方法が違います。
坪単価の計算方法は、建築物本体を基に計算した坪単価と、設備などをつけて住める状態になってからの総額から坪単価を計算する方法があります。
この計算方法には規定がないので、どちらの方式で計算するかは業者次第です。
これはどういうことかというと、まったく同じプランで全く同じ条件の下で建てられた住宅にも関わらず、メーカーによって坪単価が変わってくるということです。
ということは、安い坪単価のメーカーと高い坪単価のメーカーでも、最終的な実質価格は同じということが考えられるのです。
ですから坪単価をそのまま鵜呑みにせず、どのような計算方法で計算された坪単価を確認します。
その上で各メーカーの比較材料として坪単価は使うようにしましょう。
住宅価格と土地価格は地域差が大きいため注意する
ローコスト住宅に限らずどの住宅建築にも当てはまることですが、住宅価格と土地価格は、都市部に近ければ高くなり、遠くなれば低くなるという傾向があります。
都道府県によっても価格差がありますので、新築物件の価格例を見るときには地域差があることも考慮しましょう。
同じ条件で同じプランの住宅を建てたとしても、都市部に建てる場合とそうでない場所に建てる場合ではその価格は変わってきます。
カタログや宣伝に使われている価格もその住宅を建てる場所によっては、異なる価格になることがあることを知っておきましょう。
標準仕様の特徴とは?ローコスト住宅メーカー次第で変わる内容

ローコスト住宅の最大の魅力は、低価格で新築の住宅が手に入ることです。
なぜ低価格かというと、住宅を建てるための材料費や建設費、設計費などの工事費用に、照明・アンテナなどの電気工事費、内装工事費用までが「標準仕様」に含まれていることが理由です。
住宅建設で要となる工事費用が、すべて標準仕様として組み込まれているということです。
ただその標準仕様の内容は各メーカーごとに違いがあります。
それらの違いを見極めるために、標準仕様で特化される項目について解説します。
耐震性や断熱性などの基本性能に力を入れているローコストメーカー
ローコスト住宅だからこそ気をつけておきたいことが、住宅の基本性能です。
耐震性が低くて断熱性も一定程度という住宅では、快適に暮らすことはできません。
ところがローコスト住宅メーカーでも、この耐震性や耐熱性に力を入れているメーカーもあります。
高い耐震性や断熱性に加えて、今話題の気密性も高い住宅を提供しているメーカーもあります。
ちなみに、そうした基本性能に重点をおいたローコストメーカーは、大手ハウスメーカーが母体となっていることが多いようです。
水回りの設備に力を入れているローコストメーカー
特に使いやすさ、便利さを求めたいのが毎日使うキッチンやバスルームなどの水回りでしょう。
ローコスト住宅だからと言って、使いやすくておしゃれなキッチンや、清潔なバスルームやトイレをあきらめる必要はありません。
ローコスト住宅メーカーによっては、この水回りに力を入れて、メーカーやカラーも選べるシステムキッチンがあったり、機能性が生かされたシステムバスをチョイスできるメーカーもあります。
またトイレもコーティング加工がされて汚れにくく、フルオートタイプのトイレが標準仕様という場合もあります。
内装に力を入れているローコストメーカー
内装面に特に力を入れているローコストメーカーは、標準仕様の中で内装において選択の幅を持たせて発注者の要望に応えようとしていることもあります。
内装メーカーやクロスメーカーを選べて、好みの内装材を組み合わせることができるというサービスを標準仕様でできるなんて嬉しい限りです。
外壁に力を入れているローコストメーカー
住宅の外観で気になるのが外壁ですが、ローコスト住宅メーカーによっては外壁や屋根にこだわっているメーカーもあります。
注文住宅に劣ることのない見栄えのする外壁で、汚れも落ちやすいコーティング付きの窯業系サイディングを採用してしているメーカーもあります。
またおしゃれなタイル張りを標準仕様として取り入れているメーカーもあります。
外壁に凝ることで、低価格でも安っぽく見えずにデザイン性の高い住宅を建てることができるでしょう。
ローコスト住宅メーカーの標準仕様のコストカット方法とは?
ローコスト住宅メーカーが低価格を実現するためには、どのようにコストカットをしているのでしょうか。
そのコストカット方法を標準仕様に関して解説します。
コストを抑えるなら平屋より2階建て
一見平屋の方が安そうに感じますが、コストを下げるには2階建てのほうが良いと言われています。
平屋で2階建てと同じ床面積を確保しようとすると、基礎部分や屋根の面積が広くなります。そのため、必要な材料が多くなり、工賃がかかるのです。また、必要な土地の面積も広くなるので、その分土地代もかかるでしょう。
また、建設で使われる部材は2階建て用のものが多く流通しています。
階段の位置を変えて廊下の面積を少なくするプラン
階段の位置によっても建築費用が左右されます。
階段を独立させて設置するよりも、壁に沿わせるように階段を設置して階段の仕上げを壁と統一することでコストを抑えることができます。
箱を積み上げるようにして造られた箱階段なら設計費用が比較的安いだけでなく、階段部分を収納として使うこともできるため、階段下を有効活用することができます。
住宅の形状を正方形や長方形などの箱型にするプラン
ローコスト住宅建築の特徴的な設計プランは、正方形や長方形などの箱型に住宅を設計することです。
凹凸のないすっきりとした間取りや外観に設計にすることで、壁や天井などの面積を減らすことができ、コスト削減することができるのです。
延床面積を絞ったプラン
建設費用を抑えるため家を設計する上で大切なことは、延床面積を小さくすることです。
ローコスト住宅の基本設計プランはすでにシンプルになっていますから、さらにローコストを目指すのなら、延床面積を小さくすることにより建築費用を抑えらることができるでしょう。
切妻屋根や片流れ屋根を採用するプラン
屋根の形状によっても建築費用が変わってきます。
一般住宅でよく使われる屋根の種類のうち、切妻屋根や片流れ屋根なら他の屋根よりもローコストで設置できます。
切妻屋根とは、屋根の最頂部の棟から両側にふきおろすような形状をした屋根で、昔から採用されているシンプルなデザインの屋根です。
一方、片流れ屋根とは、平面の屋根で一方に傾いた形状の屋根です。
モダンでおしゃれといった印象がある上に、太陽光発電も設置しやしやすいため実用性も高く、人気があります。
水まわりはまとめて配置
浴室やキッチン、トイレなどの水回りを離れた場所に配置すると配管が複雑になってしまいます。そのため、配管作業や部材等の面でコストがかかってしまいやすいのです。
水回りはなるべく近くに配置するようにすると費用を抑えることができます。
部屋数やコンセントの数などを減らす
住宅の作りがシンプルであればあるほど、建設費用は安く抑えられます。
そのためローコスト住宅では、デザインや間取りをシンプルにする傾向があります。
その一例として挙げられるのが、部屋数を減らし、コンセントの数を通常の注文住宅よりも少なくするという方法です。
間仕切り壁を少なくしたオープンプラン
ローコスト住宅は凹凸の少ない箱型の設計が採用されていますが、間取りもシンプルなプランが採用されています。
間仕切り壁を少なくするオープンプランはよく使われる間取りで、コストを抑えるだけでなく部屋を広く見せる効果もあります。
大きな収納を集中させるプラン
押し入れやクローゼットを各部屋に取り付ければ手間もかかり割高になりますが、ウォークインクローゼットのようにたっぷりとした収納スペースを作ればコストダウンになります。
クローゼットの中は、市販のラックや収納ボックスを工夫したDIYをすれば、さらに安く済むだけでなく自分仕様の使いやすい収納ができるでしょう。
内装材や設備機器のグレードを安全性に影響がない範囲で下げる
ローコスト住宅メーカーは少しでも住宅価格を抑えるために、内装材や設備のグレードを下げる傾向があります。
だからといって安全性までも下げているわけではないので、ご安心ください。
外壁に最廉価なサイディングを使用する
ローコスト住宅メーカーによっては、外壁にも価格を抑える工夫がされていて、最廉価なサイディングを採用しているところがあります。
サイディングの外壁材とは、セメントと繊維質を主原料にした板状の外壁材ですが、耐火性があって価格も安いため、いろいろな価格帯の住宅に使用されています。
建具にアルミサッシや中空のフラッシュドアを選ぶ
窓や出入り口、間仕切りなどにアルミサッシ、またはドアにはフラッシュドアを採用して価格が抑えていることが多いようです。
フラッシュドアとは、はしご上の骨組みの上に面材を張った軽量なドアのことです。
表面も平らですっきりしたデザインです。
柱にホワイトウッドの集成材を選ぶ
ホワイトウッドとは欧州トウヒのことで、割れた部分や大きな節を取り除いて方向を揃えて集成接着した集成材のことです。
ホワイトウッドの集成材は価格が安いため、ローコスト住宅メーカーによっては使用している場合もあります。
天井を張らず屋根裏が見える状態にする
価格を抑える工夫として、天井を張らないという方法が取られることがあります。
実はこれには別のメリットもあります。屋根裏が見えることで空間的に広く感じられ、快適な生活空間を演出することもできます。
間仕切り壁や建具を少なくする
シンプルな設計やデザインというのがローコスト住宅の特徴のひとつですが、その結果、間仕切り壁が少なくなったり、建具も減らせたりします。
それがローコストにつながるうえに、複雑でない生活動線やすっきりとした空間デザインもできます。
ホームセンターの商品や規格品を使用する
大量生産されており、ホームセンターなどにも売られているような規格品を使用することもあるようです。
特殊な商品や希少な商品を使えば、その分コストにしわ寄せがきます。
一方で、規格品ならコストダウンが可能です。
ローコスト住宅の見積もりチェックポイントと値下げ交渉について
ローコスト住宅の見積もりがどれくらいになるのかについて

住宅を建てようと情報を集めている時に目にするのが、「ローコスト住宅」。家を建てるには、何千万円という工事費用がかかります。
ローコストで希望の住宅が建てられるなら、とても魅力的です。
平均的な見積もり金額を見てみましょう。
ローコスト住宅の平均的な見積もり額について
ローコスト住宅の一般的な見積もりは、3項目に分かれています。住宅本体の金額・オプション金額・別途費用の3項目です。
・ローコスト住宅の見積もり金額例:施工床面積40坪の家
| 項目 | 内容 | 金額 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| ① 建物本体金額 | 40坪☓坪単価42万円 | 16,800,000円 | 16,800,000円 |
| ② オプション金額 | 食器洗い機 | 200,000円 | |
| 子供室の間仕切り壁 | 250,000円 | 450,000円 | |
| ③ 別途費用 | アンテナ工事 | 50,000円 | |
| 給排水屋外工事費用 | 450,000円 | ||
| 消費税 | 1,420,000円 | 1,920,000円 | |
| 合計 | 19,170,000円 |
坪単価が安くても、オプション費用や別途費用がかかる住宅もあります。
また、工事床面積が広いと、建物工事費用が2,000万円を超えることがあります。
坪単価が40万円でも施工面積が50坪あると、建物の工事金額は2,000万円になります。
この場合、坪単価から判断するとローコスト住宅ということになります。
ローコスト住宅で見積もりをもらう時の注意点について
ローコスト住宅は、大手ハウスメーカーでも建てています。地元の住宅会社やローコスト住宅専門の会社もあります。
いろいろな住宅会社がありますので、見積もりを出してもらう時には、以下の点に注意して、依頼しましょう。
複数の会社から見積もりをもらう
ローコスト住宅の見積もりは、1社だけでなく複数の会社から見積もりを取るようにしましょう。
複数の会社から見積もりをとる理由は、主に3つあります。
一つは、ローコスト住宅といっても、色々な会社があるからです。住宅のデザインも間取り・仕様もそれぞれ違います。
1社だけでなく、複数の会社から見積もりをとり、デザインや仕様など比較・検討しましょう。
複数社から見積もりを取ることで、いろいろなタイプのローコスト住宅があることやそれぞれの住宅に特徴があることがわかります。
比較・検討することで、どんなローコスト住宅が家族にベストなのかわかります。
二つ目は、比較・検討することで金額の妥当性がわかるからです。
建築工事費用には定価がありません。1社だけでは、金額が高いのか、リーズナブルでお得なのかわかりません。
2社以上の見積もりを比較することで、金額の妥当性を判断することができます。
三つ目は、複数社見積もりをとることで、金額の交渉が可能になり、値引きをしてもらえる可能性があるからです。
キャンペーンや決算期、他にライバル会社がいることで値引きのお話がある会社があります。
複数社に見積もりをお願いすることで、より良い住宅になります、面倒がらずにお願いしましょう。
何社ぐらいから見積もりをもらえばいい?
見積もりは、何社ぐらいとるのが良いのでしょう。見積りをたくさんの会社から取った場合、打合わせ回数が多くなります。
お休みのたびにどこかの会社と打ち合わせをすることになります。
そうなると、比較・検討する時間がなくなってしまいます。また、比較することが多くなりすぎると肝心の要点がわからなくなってしまいます。
また、実際に契約する会社以外は、契約しないことを伝えなければなりません。お断りの連絡をするわけですが、なかなか言いにくいものです。
見積もりをとる会社の数は、最低2社、できれば3社、多くて4社にお願いすると良いでしょう。
間取りの良い会社や営業マンの対応が良い会社など、3社か4社に絞って見積もりをお願いしましょう。
同じ条件で見積もりをもらうのがポイント
住宅会社の見積もりは、会社により見積もりシステムが違い、見積もり書の形式も会社により様々です。
また、会社によって、見積もりに含める金額や書き方が違い、比較が難しいものです。
見積もりを効率よく、的確に検討するには、できるだけ同じ条件で見積もりをもらうようにしましょう。
間取りや面積をできる限り同じにし、見積もりに含めるもの含めないものなどの確認もしておきましょう。
また、必要なものは概算でもよいので見積もりしてもらい、比較・検討できるようにしておきましょう。
見積もり書の項目はしっかり説明してもらう
見積もり書がでてきたら、打合わせをしながら、見積もり内容をしっかり説明してもらいましょう。
建築用語はむずかしいものもありますが、わからないことをそのままにしておくと、後々トラブルになることがあります。
不明な点は何でも質問するようにしましょう。また、説明をしてもらう時には、メモを取っておきましょう。
ローコスト住宅の見積もりで注意すべきポイントについて

住宅の見積もりをもらう時、「高かったら、どうしよう」、「予算はオーバーしないだろうか」など、期待もありつつ不安なものです。
見積もりの打ち合わせをする時に、注意したい点をみてみましょう。
契約に前向きである姿勢を見せる
複数の住宅会社に見積もりを出してもらいますが、家族の間でそれぞれの会社に対して、印象を持っていると思います。
第一候補はA社。B社は間取りもデザインもいいけど高い会社。
C社は見積もり次第で考えよう、などです。
契約前の打合わせでは、どの会社とも契約する前提で前向きな打合わせを行いましょう。
住宅会社の営業マンは、営業のプロです。
打ち合わせをしながら、お客様の真剣度も見ています。
営業マンも前向きなお客様には、真剣に対応してくれます。
良い提案や資金の情報・値引きやサービスは真剣だからこそ得られます。
複数の会社との打ち合わせは大変ですが、いつでも前向きな姿勢で打合わせをしましょう。
おろそかになりがちな事ですが、必ず1度は会社訪問はしておきましょう。
会社の責任者が、喜んで迎えてくれ実績の紹介や見学をさせてくれたり社内の施設がキチンと整理整頓されている会社なら、かなり信頼度は高いと判断できます。
契約前に値下げ交渉しないと意味がない
見積もりの値下げ交渉は、いつ行うのが効果あるのか。住宅の営業マンは、契約を取ることが仕事の成果の一つです。
契約は、「工事請負契約書」にお客様から、署名・捺印をいただくことです。
つまり、営業マンとの値下げ交渉は契約という成果があがる契約前が通りやすいのです。
契約がまとまれば、次は細かい図面の打合わせや住宅ローンの借り入れ・着工の打合わせです。
一番効果の高い値下げ交渉は、契約直前といわれています。
本当に契約したいという会社との値引き交渉は契約直前に行うようにすると良いでしょう。
過度な値下げ交渉は行わない
住宅は、1,000万円以上かかる高額なものです。
少しでもリーズナブルに建てたいと思うものですが、過度な値下げ交渉は行わないようにしましょう。
住宅会社も会社を経営していくためには、赤字で契約するわけにはいきません。
過度な値引き交渉は、仕様のグレードダウンや下請け会社への過度な値下げ交渉につながります。それらは、住宅の品質にかかわります。
他の会社の見積もり書と比較しながら、適正な範囲の値下げ交渉を行うようにしましょう。
ローコスト住宅の標準仕様の問題
ここではローコスト住宅の標準仕様で見られる問題点を取り上げます。
安価な断熱材「グラスウール」の使用は問題!
断熱材は、エアコンなどによって暖められたり冷やされたりした空気を外に放出することを防ぎ、外部気温の影響を室内に受けにくくするための重要な材料です。
断熱材がきちんと入っていないと、エアコンをフルに稼働させても寒かったり暑かったりして不快ですし、光熱費も高くなってしまいます。
ローコスト住宅でも断熱材が入っていないということはありませんが、断熱材の種類と施工方法が問題です。
ローコスト住宅では、価格の安い断熱材「グラスウール」が使われるのが一般的です。
「グラスウール」とは、ガラス繊維の中の空気層を利用して断熱するものです。グラスウールは安くて高い断熱性能が望める材料ですが、湿気に弱いという弱点があります。
そのため施工方法によっては、断熱の効果が発揮できないばかりかカビの原因になり健康被害に結びつく可能性があります。
グラスウールの空気の中に湿気が入ると、湿気を排出できません。
つまり一度グラスウールが湿ってしまうと、壁の中がいつも濡れた状態になってしまいます。
その結果、グラスウールに接した木材が腐ったり、カビが発生したりする状態になります。これはつまり、建物の寿命が短くなり、体に悪い環境を作り出すということになるのです。
グラスウール対策は湿気対策と高気密性
もしも断熱材にグラスウールが使われていたら、十分な湿気対策をしましょう。また気密性を高めた設計にしておけば安心です。
もしもそうした対策を取りたくないならば、断熱材素材にグラスウール以外のものを使うことを検討してみましょう。
湿気を遮断する袋に入ったグラスウールを使用するという方法です。
この場合は、壁内にあわせてグラスウールをカットするときに、切り口から湿気が入らないように切り口をふさぐ丁寧な施工が必要です。
また、壁内の柱などの間にグラスウールが隙間なくきっちり入っていないと断熱効果が望めないので、職人の施工技術も大切になります。
ローコスト住宅の中には、断熱材が入っているもののスカスカで隙間がある場合や、湿気対策をしない業者もあるため、注意が必要です。
「第三種機械換気」の不効率な換気
「第三種機械換気」とはアパートやマンションでよく使われている換気システムのひとつですが、設備価格が低くランニングコストも低いとあって、ローコスト住宅でも使用されているケースがあります。
住宅の中で人が生活をすると空気は汚れていきます。そのため、新鮮な新しい空気を外から取り入れて汚れた空気や湿気を排出する必要があります。
昔の日本家屋では隙間から自然に空気が入れ替わったり、窓を開けたりすることで換気を行っていました。
現在は、住宅の気密性が上がっているせいで自然に換気ができないため、計画的に機械で換気をします。この機械換気には種類があり、ローコスト住宅では「第3種機械換気」の採用が一般的です。
「第3種機械換気」とは、汚れた空気を外に出す換気扇を設け、ガラリなどの給気口から新鮮な空気を取り入れる方法です。
第3種機械換気はファンなどの機械も排出部分だけで、配管の必要がないため価格も安くすみます。
しかし、空調された空気を室内から出してしまい、外気を吸い込むので、外の気温や湿気の影響を強く受けてしまいます。
たとえば冬であれば、暖められた空気が換気扇により外に排出され、給気口からは外の冷たい空気が入ってくるため、エアコンをつけていても冷たい風を感じる原因であることが考えられます。
雨の日であれば、湿気を含んだ空気が入ってきてしまうでしょう。
ほかにも、気密性が低い住宅の場合には、あちこちの隙間から給気されてしまい計画的な換気ができず、空気がよどんだ場所ができてしまうこともあります。
近年では給排気をともに機械換気を行う「第1種機械換気」を採用して、さらに熱交換により給気と排気の温度を調整するという方法がとられることが増えてきました。
「第1種機械換気」であれば、快適な室内環境が実現でき、電気代などの光熱費をおさえることができます。
ただし、機器が増えるぶん配管が必要となり価格も高くなるため、ローコスト住宅では設置されることはまずありません。
接着剤「VOC」濃度の問題点
「VOC」(揮発性有機化合物)は、建材の接着剤やビニール壁紙などの溶剤に含まれる物質です。
このVOCが体内に入ると、吐き気が起こり目がチカチカしたり、アレルギー反応が表れたりします。
先述の換気にもつながることですが、VOCの濃度のガイドラインが設けられており、建築基準法で換気が必要とされています。
室内のVOC濃度を減らすため、JIS規格などで基準が作られています。
この基準が、家具や建材につけられるFマークで、VOCやホルムアルデヒドの放散量を示し最も放散量が少ないのが、F☆☆☆☆(フォースター)の認定を受けたものです。
大手ハウスメーカーや健康住宅をうたう住宅メーカーでは、F☆☆☆☆取得建材を中心に使用しています。
そのため、比較的安心して新築住宅に入居できます。
ローコスト住宅で使われる建材には安価なものが選ばれるため、F☆☆程度が利用されることが多く、室内のVCC濃度が高くなってしまう可能性があります。
耐久性が低く住宅寿命が短い
ローコスト住宅であっても一般的な住宅であっても、住宅にはメンテナンスが必要です。
しかし、ローコスト住宅では安価な材料を使用するため、メンテナンスの時期が早まる可能性があります。
例えば外壁の塗装で比較すると、ローコスト住宅で使われる吹付塗装に比べると、光触媒などできれいさを保てる塗装の方がメンテナンスまでの期間が長いといわれています。
また、安価な壁紙だったために、黄ばみが早く出てしまったこともあるようです。
ローコスト住宅は欠陥住宅ではないので、建物が早く倒壊するということはありません。建築基準法もクリアしており耐震性もあります。
しかし前述のように、断熱材の施工品質によって、壁内の構造体である柱が腐ってしまえば建物の寿命が短くなります。
ローコスト住宅は人件費を節約して成り立つところもあるため、施工品質の確認が重要になります。一般的な住宅に比べて、さまざまな意味で建て替え時期が早くやってくる可能性があるでしょう。
ローコスト住宅の20年後はどうなっている?

誰しも20年後の未来を予測することはできませんが、ローコスト住宅だからといって悲観する必要はありません。
他の住宅が軒並み被害を受けるような大きな災害がない限り、普通に生活ができる状態で建っているはずです。
年配の人達の中には、高度経済成長期に質の悪い住宅が安い価格で大量供給された時代の記憶が残っています。
このため価格が安いというだけで、寿命が短いと推測してしまうのです。
古い時代の印象が悪い原因のひとつには、法整備の不備がありました。
建築基準法が大きく改正された現在、耐震構造の基準も厳しくなり、さらにチェック体制も整えられました。
ほとんどの自治体で、壁を塞ぐ前に専門機関の中間検査を受検しなければ、次の工程に進めなくなったのです。
また金融機関の意識も変貌し、現在では基本的に完了検査済証が交付されないと住宅ローンの融資が受けられなくなっています。
このため、いくらローコストで建てられた住宅であっても、建築基準法で定められた最低基準は守られていますから、通常レベルの地震で住宅が崩壊するということは、理論上考えられません。
もし建物の傾きなどの事態が生じた場合は、ローコスト住宅固有の問題ではなく、地盤の液状化など、別の原因が発生したと考えられます。
ただし外壁や屋根の塗装は、新築時において一般的なレベルの塗装剤が使用されていることから、定期的なメンテナンスが必要になります。
もしまったくメンテナンスなしで使用していたら、早くて10年程度経過した頃から、大雨の際に雨が染み込んでくるなどの事態が想定できます。
仕事のクオリティが低い
ローコスト住宅は、原価を抑えるために人件費も切り詰めています。
このため現場監督は、1人で10件以上の住宅を担当している場合もあり、細部まで目がいきわたっていない可能性があります。
しかも現場監督自身も経験が浅い人も多いようで、工事のツボを理解していないことがあります。
社内の研修期間も短く、ベテランに同行して学ぶ期間もほとんど設けられません。
一般の住宅であれば、経験豊富な大工が技術的な面を補うので、現場監督の経験が不足していても、大きな問題は生じません。
ところがローコスト住宅では、大工も経験の浅い人が多いために、細部の造作で雑な仕事が行われていることがあります。
建築資材のグレードが低い
使う建材は、家の価格を下げるために材料費を抑えているので、グレードが低くなります。屋根の素材や外壁の仕上げなど、どれも最低限のグレードとなるでしょう。
建築資材の中でも、構造に関するものや室内環境に影響するもののチェックはしておいた方がよいでしょう。
ユニットのグレードが低い
建築資材だけでなく、設備機器もグレードが低くなります。
ユニットバスやキッチン、洗面化粧台、トイレなどの設備機器は、機能もシンプルな低いグレードのものになるでしょう。
ただし、グレードは低くてもほとんどの場合はメーカー商品です。使用するにあたって問題はありませんので、強いこだわりがなければクリアできるでしょう。
一般的な住宅に比べて選択肢が少ない
ローコスト住宅のデメリットとして、一般的な住宅と比べて選択肢が少ないということも挙げられます。
建設費を抑えるには、各ハウスメーカーで用意されている中でも標準仕様といわれるものを選ばなければなりません。
しかし標準仕様といわれるものは、あまりバリエーションが豊富なわけではないのです。
つまり標準仕様の中から選ばなければならないという時点で、選択肢はかなり限られてしまっています。
しかも標準仕様ではないものを選ぼうとすると、今度はコストが高くなります。希望に合わせてオプションを付けていくと、通常の注文住宅と変わらないくらいの価格になってしまうことも。
しかし住宅は一生の内でもとても大きな買い物です。どうせ新しく建てるのなら、あれこれ選びたくなることもあるでしょう。
その選択肢が限られてしまうというのは、住宅を建てる上ではかなり痛いですよね。
ローコスト住宅を建てるコツとして、重要視する部分を決めておくことをおすすめします。ここだけは譲れないというポイントをあらかじめ決めておくことで、他の部分の取捨選択もやりやすくなります。
ローコスト住宅を建てるなら自分たちは家のどの部分を大事にするのか、よく検討しておくと良いでしょう。
ローコスト住宅のコストによる問題点
ローコスト住宅を選択したはずが、ローコストにならなかったということが起きることもあります。
この章では、コスト面の注意点を解説します。
広告などの表示価格は限界まで低く設定した価格
家の建設を検討しているときに「750万円で建てられる家」という広告を手にすると、連絡してみようかと思う方も多いと思います。
ローコスト住宅であれば、比較するのは価格であることが多いでしょう。そのため、メーカーはできるだけ手をとめてもらえる安い価格を提示する広告を出そうと考えます。
少しでも安い価格を表示するために、最低限の建物本体価格だけを載せることが多いようです。
生活するためにはガスや電気などを引き込む必要があり、外構工事や地盤調査などもすることになるかもしれません。そういったものすべてが含まれない価格表示の場合があります。
広告だけ見てこの価格で建てられるのであればと連絡をとってみたところ、結局そんな価格では建てられないという結果になることも多くあるのです。
プラン変更やオプションを追加すると価格が跳ね上がる
ローコスト住宅は、メーカーが指定する標準仕様をそのまま建てた場合が一番安くなります。
できるだけ同じ種類で同じサイズの部材を使用し、無駄を省いた大量仕入れが住宅の価格を下げています。
そのため、この標準仕様からはずれるプラン変更やオプション追加は、大きな価格アップにつながるということです。
ほんの些細な希望に対応してもらったら、予算を大きく超えてローコスト住宅でなくなってしまったという本末転倒な話もあります。
また、変形宅地などの場合は標準仕様の家と土地の形が合わず、ローコストでは難しくなることもあるでしょう。
しかしながら、ローコスト住宅だから使いにくい間取りということではなく、標準的な間取です。
つまり、間取りや設備などにこだわるよりも価格にこだわりたい方に、ローコスト住宅は向いています。
グレードアップは慎重に
家を建てると決まると、家に関するさまざまな情報を今まで以上に見るようになり、「これもいいな、あれもいいな」と夢がふくらみます。
たとえば、トイレのカタログを見ていたら少し上のグレードにしたくなったり、キッチンに便利そうな収納を入れたくなったりすることもあるかもしれません。
しかし、ちょっと待ってください。ローコストを目指して家を建てるのであれば、グレードアップには慎重になった方がよいでしょう。
一つ一つは小さなアップでも、気がつけば一般的な住宅価格になってしまっていてはローコストの意味がないのです。
高性能住宅と比べて光熱費が高くなる
高性能住宅とは、高気密高断熱住宅です。
高気密住宅は隙間が少ないため室内の空気を逃がさず、屋外の空気が入る量を換気でコントロールできます。
高断熱住宅は室内の温度を外に放出することなくためることができ、屋外温度の影響もおさえることが可能になります。
つまり、エアコンなどの空調で室内を暖めたり冷やしたりすれば、その温度を長く維持できるのです。
これにより、高性能住宅は光熱費がおさえられます。
高気密高断熱住宅は、資材や設備費用が高くなり、施工品質も求められます。
一方、ローコスト住宅ではそこまでの費用がかけられないため、高性能住宅に比べると光熱費が高くなることが多いでしょう。
特に、寒さや暑さが厳しい地域では、毎月の光熱費をおさえた方が長い目で見ると安くなります。
不具合が起きやすく補修費用などがかかる
ローコスト住宅は耐久性よりも、価格に重点をおいています。
価格が安いという理由だけで選ばれた粗悪な材料は、短期間で不具合が起きやすく補修が必要になる場合があるのです。
たとえばフローリングなどは、価格と耐久性が比例します。安いフローリングの中には、傷がつきやすく、汚れが落ちにくい製品もあります。
結果的に補修費用がかかる場合もあるため、品質を維持しながら安く仕入れるなどの工夫をしているメーカーの見極めが大切です。
国内のメーカーの量産品であれば、ほとんど問題ありませんが、輸入品などの場合は注意しましょう。
ローコスト住宅のデザインや間取りによる問題点
この章では、ローコスト住宅の間取りやデザインについて確認します。
家に対する希望は人それぞれですが、デザインを優先するとローコストが実現できない可能性について解説します。
意匠性や建築デザインには期待ができない
デザインの好みは一人ひとり異なるものです。
ローコスト住宅は、同じ規格の家を多く建てることでコストをおさえているため、デザインは多くの人が受け入れられる無難なものになります。
そのため、デザイン的な要素は逆にそぎ落とされていると考えた方がよいでしょう。
デザインのこだわりが多ければ多いほど、ローコストでの住宅建設は厳しくなります。
複雑な外観を選ぶことが難しい
ローコスト住宅の基本は、四角い箱です。凹凸があると、使う部材も増えて材料費がアップします。
たとえば2階建てなら、1階も2階も同じ形のシンプルな外観が多くなります。
外観が複雑になると、柱や外壁の部材が増えるだけでなく室内の資材にも影響するため、大幅なコストアップにつながるのです。
間仕切り壁を少なくしているためオープンプランになる
部屋数を増やすと、壁や扉の量が増えてしまいます。
壁が増えるとコンセントや照明などの電気設備も増えることになり、コストがアップします。
そのため、間仕切り壁を少なくしたオープンプランであることが多くなるのです。
キッチンは独立させたい、オープンなエリアを仕切りたいなどの規格からはずれる希望がある場合、金額アップは避けられません。
間取りがあらかじめ決まっている
ローコスト住宅で提示されるモデルタイプが低価格の標準となります。
ほとんどの場合で間取りまで決まっており、多少の変更が可能なメーカーもありますが、完全に自由に決められるわけではありません。
エクステリア部分が狭い
ローコスト住宅の問題点として、エクステリア部分が狭いということも挙げられます。
ローコスト住宅の分譲などでは区画の面積が狭くなることも多いようです。それによりエクステリアとして使用できる面積も狭くなってしまいます。
そのため、駐車スペースや庭を確保できないといった問題点が出てきます。
車を複数台所有しているという人は、ローコスト住宅を購入する前にエクステリアに関して検討しておいた方が良いかもしれません。
場合によってはせっかくマイホームを手に入れたのに、車を停めておくための十分なスペースがないため、駐車場を借りなければならないということもありえます。
生活する上で車が欠かせないという方は、よく注意しておいた方が良いでしょう。
庭が欲しいという方にもエクステリア部分が狭いローコスト住宅はおすすめできません。
マイホームで家庭菜園がやりたいという方も多くいますが、区画の狭いローコスト住宅では難しそうです。
他にも騒音問題など、区画が狭い上での問題点は数多く考えられます。
ローコスト住宅を分譲で購入する場合は、自分たちがエクステリアの部分をどのくらい必要とするのか検討しておくとよいでしょう。
間取りをどう決めたらいいか知りたい
家を建てる計画があるなら、ハウスメーカーに相談に行ってみると、その場である程度簡単な間取りをPCで作成して見せてもらえることがあります。
ただのシンプルな間取りでは後悔しがち
家でくつろげる快適さを決めるのは、広さではなく動線であると言われています。
間取りで大事な点は、生活動線や家事動線が快適になるよう考えられているかどうかです。
玄関を入ってからリビング、各部屋に行くのに遠回りをさせられると感じる間取りはストレスの元になります。
家事動線も同様で、なるべく最短距離でキッチンや洗面所に移動したいものです。
また、生活動線と家事動線は別ルートになるのが理想的とされています。
壁は目隠しになり、来客時のプライバシー保護にも役立ちますが、動線を考えると時には邪魔になるものでもあります。
ローコスト住宅の特徴の一つは壁を少なくして、コストダウンを図っています。
理想的な間取りはシンプルかつ動線に無駄がない間取りと言えるでしょう。
家族の生活動線を具体的に考える
生活動線とは、玄関の出入りからリビングや部屋の移動、トイレ、浴室など生活する場において動くラインを言います。
生活動線は、その家で生活されている方が家の中を通る時に移動する線と言えるでしょう。
これとは別にキッチンと洗面所、トイレ、浴室の清掃などで移動する動線を家事動線と言います。
生活動線と家事動線はクロスするようなことがあれば、朝の出かける前の慌ただしい時間、双方が交差することがストレスになりやすくなってしまいます。
このような事を避けるため、生活動線と家事動線が別のラインで動けるように間取りを考えるのがおすすめです。
生活動線で注意するべき点は、家具や収納位置を最適な場所にすることで、収納しているものの出し入れや片付けを楽にする点です。
日常生活における移動も無駄な動きが少なくなり、あまりストレスを感じなくなります。
背の高い家具で可動式の間仕切りにする
可動式間仕切りには折れ戸や引き戸、アコーディオンカーテン、家具、棚システムなど多岐にわたりあります。
この様な可動式の物を用いる場所は、子供の部屋を仕切る時や寝る場所の目隠しとして使われる場合が多いようです。
リビングの一部を書斎に使いたい時には、背板のない書棚を部屋の間仕切りで使うとおしゃれな空間の演出になります。
本をたくさん並べれば壁のようにもなりますし、多少の隙間があれば、人の気配を感じたり、声が聞こえたりします。
平屋で注意すべきポイントを押さえて快適な家づくり

ローコスト住宅で平屋にする場合は、減築を意識したほうが良いでしょう。
例えば夫婦2人なら平屋で十分快適な生活が出来ますが、子供が1人、2人、3人いる場合は、平屋より2階建ての方が建築費が安く済むことがあります。
家族構成が多くいると、延べ床面積が広がり、屋根材もたくさん必要になることからローコスト住宅の予算を超える可能性が出てきます。
庭と建物のバランスを考える
2階建て住宅に比べて平屋建ては比較的重量が軽く、地震の多い日本においても、地震に強い構造と言えます。
その構造を生かして、庭側の開口を広くとることができ、庭との一体感を生み出しやすい間取りを作ることも可能です。
庭への出入りする窓を大きく取ることで、風の通り抜ける道が生まれます。
採光と防犯のバランスをプロにも相談する
平屋建ての欠点に、建物を大きくすると、建物の中心部の採光が取れにくいことがあります。
これは、建物の中心部が部屋に囲まれてしまう事から起きる問題です。
解消するには、建物をコの字型にする、建物の中心部を中庭にする、屋根にトップライトをつける等で光を取り込む方法が取られますが、施工費が割高になる可能性があります。
防犯上最適の方法は、各窓にシャッターを取り付け、夜は必ずシャッターを下ろすことです。
しかし、浴室や洗面所の窓は、シャッターの取り付けをしない場合が多くこのような箇所は、防犯フィルムを貼る、センサーライトをつけるなどの予防策を講じる必要があります。
最近は高性能で価格も安くなった防犯カメラの設置も防犯にはとても有効です。
プライバシーの確保のために外から全く見えないようにと、樹木を植えたり、目隠しの塀を建てる事は、泥棒側にしてみれば最も侵入しやすい場所を提供することになります。
泥棒の侵入を防ぐには、死角を作らないことです。
面格子は防犯には何の役にも立たないことを知っておくべきでしょう。
大開口の窓は外から見えにくい場所に設置する
開口部が大きいとどうしても外から丸見えになってしまうと危惧される方が多いと思います。
しかし、外からの視界が遮られると、泥棒が侵入しやすくなるので、防犯上リスクがあると言わざるを得ません。
敢えて外の視線を受けない箇所に大きな開口部を設ける場合は、防犯性能の高い2重サッシや窓の中央部に取り付けるクレセント錠以外に補助錠を窓の上部により付けて、侵入を防ぐことです。
すぐに戻るような外出時にも、必ず窓にはダブルロックを掛けておくことです。
また、費用は高くつきますが、防犯ガラスをはめ込んでおくのも一つの方法です。
防火上使われる網入りガラスのサッシ窓は、防犯能力が低いので過信しないことです。
外から見えない位置に掃き出し窓があっても大丈夫なように、それなりの防犯対策を講じておきましょう。
ローコスト住宅の保障面での問題点

ここまで性能、コスト、デザインの問題点を確認してきました。
この章では、保障面の問題点を解説します。
一般的な住宅に比べて保証期間が短い
住宅の引き渡し後10年の間は、住宅を建設した工務店や住宅メーカーに瑕疵担保責任が義務付けられています。
瑕疵担保責任は住宅に住めなくなるような構造上の重要な欠陥や、雨水が入ってくるなどの欠陥があった場合に責任をもって修理するというものです。
しかし、瑕疵担保責任の範囲以外の保証は、工務店や住宅メーカーによって異なります。
一般的な住宅メーカーの場合、点検やアフターサービスを定期的に行うサービスがあり、30年や60年という長期保証が提供されます。(一定年月が過ぎると有償になります)
なかには24時間コールセンターで受付というサービスを提供するメーカーもあります。
ローコスト住宅を提供する工務店やハウスメーカーでは、この保証期間が短く2~10年というものが多いでしょう。
また、連絡してもなかなか対応してもらえなかったり、保証期間が過ぎると対応自体してもらえなかったりする心配もあります。
10年間の瑕疵担保責任の義務の部分はもちろん、それ以外の補償やアフターサービスについても必ず確認することをおすすめします。
ローコスト住宅を購入する際の注意点

ローコスト住宅を購入するときの注意点として、標準仕様に関するものは次のようなことです。
仮契約をしなければプランを作ってもらえないことがある
材料調達の工夫や設備機器のグレードを下げ、人件費や広告費を削減することでローコスト住宅が実現されます。
そのため、一般的な住宅メーカーではサービスとして行われるような契約前のプラン作成などがカットされていることがあります。
プラン作成には経費や人件費が必要になりますが、契約ができなければそれが無駄になってしまうからです。
住み始めて数年経ってから後悔する場合がある
ローコスト住宅のメリットは低い価格です。
資金があってもなくても、希望をすべてかなえた住宅を建てられるということはまずなく、価格面から諦めることも必要になります。
自宅の建設は何度もできるわけではないので、後悔することもあるでしょう。
実際に住み始めて数年が経ってから、ローコスト住宅を選択したことを後悔する方も少なからず存在します。
もしもローコストで家を建てると決めたのであれば、優先順位を明確にして後悔のないものになるよう比較検討することが重要です。
オプションになっていないかを確認
ローコスト住宅の購入時によくある問題が、「低価格を期待していたのに予定よりも高くついてしまった」というケースです。
ローコスト住宅は標準仕様内で選んでいる限りでは低価格が実現できるのですが、オプションとして設備や機能などを上乗せすると、価格が注文住宅と変わらないほどの価格になることも考えられます。
そのため標準仕様の詳細とオプションを区別して、設備などを整えていきましょう。
注文住宅の情報は参考までにとどめる
このよくある問題を引き起こしてしまう理由には、通常のハウスメーカーで標準仕様で付いているものだからと安易に選んだ結果、オプションで追加されていたというケースです。
ローコスト住宅にはローコスト住宅の良さがあるのですから、注文住宅で得た情報は参考までにして、自分たちの住みたい家を考えながら建築計画を立てましょう。
そうすればローコスト住宅の魅力を最大限に活かした家づくりができるはずです。
ローコスト住宅で後悔しないポイント

ローコスト住宅は一般的な住宅よりも低価格で建築できるとは言え、高額な買い物であることには変わりありません。
妥協を重ねすぎたり事前の確認が不十分であれば満足いく住宅を建てることができずに後悔してしまうかもしれません。
せっかく住宅を建てるのであれば、納得した上で満足のいく住宅を建てたいものです。
失敗談から見えてくるローコスト住宅を建てる際の注意ポイントをご紹介します。
購入してから後悔・・・ローコスト住宅の失敗談!
それでもローコスト住宅を購入して後悔している人がいないわけではありません。
体験者の話を聞いてみましょう。
30代女性(専業主婦)のケース
この女性は、友達がローコスト住宅を建てて、快適に暮らしているということだったので、同じハウスメーカーのローコスト住宅を建てることにしました。
最初に違和感があったのは、営業マンが訪ねてくるのが約束の時間から1時間ばかり過ぎていたことです。
その時はやむを得ない事情があったのかと思いましたが、その後はむしろ約束の時間どおりに来る方が稀有な状態でした。
後で気がついたのですが、同じハウスメーカーであっても、実際に工事をするのは友人の家を手掛けた施工会社とは、まったく別の会社だということです。
しかも、最終責任や保証もハウスメーカーが負うのではなく、この施工会社がすべて担うということでした。
フランチャイズ制というらしいのですが、ハウスメーカーは単にブランドの使用だけであり、実質この施工会社に依頼する形です。
ある程度名の知れた大きな会社に依頼したつもりだったのに、名もない工務店と契約を交わすことになるのは想定外でした。
工事中は、この工務店が倒産しなければと、そればかりを祈っていました。
工事現場は、若い大工さんが多かったように思います。
現場を見に行っても、一切愛想を言われることもなく、むしろ憮然とした対応で、邪険にされた印象です。
現場監督は一度も見かけたことがありませんでした。
現場で気になったことがあって、営業担当の人や現場監督にも伝えたのですが、こちらの言い分を聞いてもらったという実感は皆無でした。
40代男性(会社員)のケース
こちらのかたは、価格が安くても断熱効果が高いという点に期待していました。
新築入居した最初の頃は、暖房もよく効いて断熱効果を実感できたのですが、半年程過ぎて真夏になると、前の家とほとんど変わりなく、冷房の効きが悪い印象になりました。
後から聞いた話によると、高密度仕様ではないので、隙間にテープを張る作業はしておらず、おそらくそれが冷暖房効率の悪い原因ではないかということでした。
また、ローコスト住宅とはいいながら、最終的にはそこまでローコストにおさえることができなかったそうです。
システムキッチンの仕様の中で、オーブンや安全装置の機能が満足できなかったので、オプション品をつけてもらいました。
さらにバスユニットもバスタブの形と素材がどうしても馴染めなかったので、こちらもオプション品を選択。
それらの価格が工事費に反映された結果、最初から普通の木造住宅を建ててもあまり価格が変わらなかったくらいになってしまったと言います。
サッシもカラーフレームの落ち着いた感じにして、リビングの窓の大きさももう少し大きなものにしたいなどの希望もあったようですが、予算的に断念したそうです。
こだわりたい部分は妥協しない
ローコスト住宅は住宅の間取りやデザイン、使用する建材等を簡素化し、グレードを下げることによって低価格を実現しています。
そのため、価格が安い住宅を建てたくてローコスト住宅の建築を選んだ人にとっても多少物足りなさを感じてしまうことがあるかもしれません。
そのような場合は費用を抑えるために全てを妥協するのではなく、費用を掛けるべきところにはかけるといったようにメリハリをつけると良いでしょう。
たとえば建物の外観についてはグレードを下げてコストを抑える代わりに、内装や家具については妥協せずに自分の気に入った物を選ぶという選択も可能です。
標準仕様について確認しておく
ローコスト住宅についてモデルハウスやカタログで確認する際のイメージは標準仕様でなく、グレードアップされた仕様だと考えた方が良いでしょう。
ローコスト住宅ではできるだけ費用を抑えるために標準仕様は最低グレードとなっていることが多いようです。
見本が魅力的であっても見本通りに実現するためには標準仕様から大幅なグレードアップが必要かもしれません。
せっかくローコスト住宅で家を建てるのにあちこちグレードアップした結果、通常の住宅と建築費用がさほど変わらないということにもなりかねません。
ローコスト住宅で建築する場合には標準仕様がどのようなものであるかについて確認するようにしましょう。
建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?
ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。
注文住宅の設計プランや費用は、施工店によって大きく異なることがあります。
そのときに大事なのが、複数社に見積もりを依頼し、「比較検討」をするということ!
実際に注文住宅を建てるには時間がかかるので、この記事で大体の予想がついた方は早めに次のステップへ進みましょう!
「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」
「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」
そんな方は、簡単に無料で一括査定が可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。
一生のうちに注文住宅を建てる機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!
一括見積もりをする