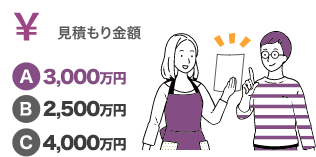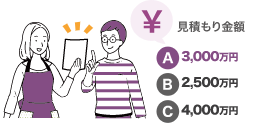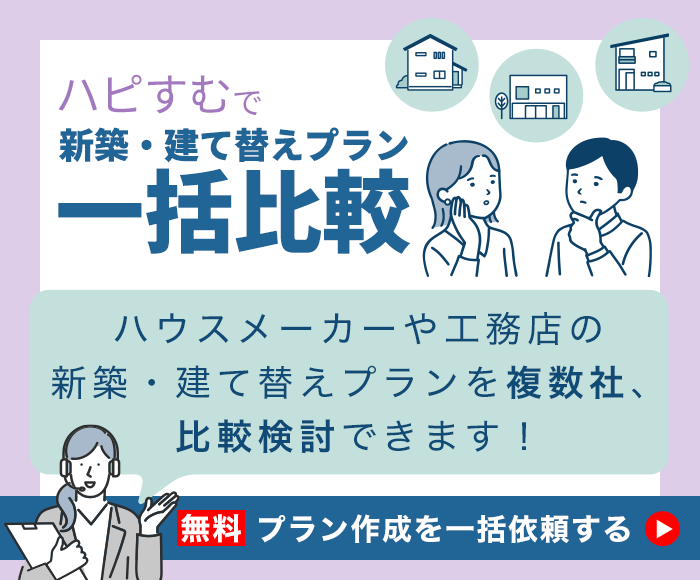2023年12月18日更新
家の着工から上棟や竣工までの期間は?着工時期の決め方も解説します
家を建てる際に着工から竣工までの期間はどれほどかご存じでしょうか。本記事では、工事の着工から引き渡しまでにかかる期間や流れについて紹介します。家の建て替えや新築を検討している方はぜひチェックしてみてください。
「家の建て替えを検討しているが、着工から引き渡しまでの期間を知りたい」
「建て替えの際の工事の流れがわからない」
上記のように家の建て替えについて疑問をお持ちの方もいるでしょう。
本記事では家の建て替えの際に引き渡しまでにかかる期間や工期が遅れてしまう原因などについて解説しています。
この記事を読むことで建て替え工事の流れを把握することができるため、建て替えの計画をスムーズに立てることができるでしょう。
家の建て替えや新築を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。
目次
- 1 家を建て替えるタイミング
- 2 建て替えの流れと把握しておきたい期間とは
- 3 建て替えに必要な各種手続きにかかる期間の目安
- 4 建て替えの際に利用するローンの審査期間の目安
- 5 建て替えにともなう解体期間の目安
- 6 建て替えの際に行う土地の調査期間の目安
- 7 建て替えにともなう建築期間の目安
- 8 建て替え期間中に借りる仮住まいとは
- 9 着工・上棟・竣工の意味
- 10 着工から竣工までの工事期間は
- 11 工期が遅れる主な原因は
- 12 着工までにするべきこと
- 13 上棟までにするべきこと
- 14 着工時期の決め方は
- 15 家の建て替えにかかる各費用の目安
- 16 家の建て替え前に確認するべきポイント
- 17 家の建て替え費用を安く抑える方法
家を建て替えるタイミング
ここでは、家の建て替えを考えるタイミングとしてよくあるケースを2つ紹介していきます。
建物の老朽化
建物が老朽化している場合は、家の建て替えを検討するタイミングです。
一般的な建物の耐用年数は以下のとおりです。
- 木造:約30年
- 鉄骨造:約30年〜約50年
- 鉄筋コンクリート:約40年〜約90年
建物の構造部分に劣化や腐食が進行していたり、雨漏りが発生していたりする場合は、建て替えを考えましょう。
耐用年数が近づいていたり、耐用年数以上経っている場合も、家を建て替えるタイミングと言えます。
大幅に間取りや設備を変更したい
大幅に間取りや設備を変更したい場合は、家の建て替えを考えましょう。
建て替えをすることで、間取りや設備を一新できます。
ライフスタイルの変化などによって、現状の間取りでは使い勝手が悪かったり、設備が古くなっていたりするようであれば、家の建て替えがおすすめです。
建て替えの流れと把握しておきたい期間とは

建て替えとは、今住んでいる住宅を一度取り壊して新たに住宅を新築することです。
建て替えの期間中は今の住居に住むことができないため仮住まいも必要になります。そのため、建て替えの際には既存住宅の解体費用と新築工事費用の他に、仮住まいのための費用も必要になります。
仮住まいのための費用とは、仮住まいへの引越し費用や、仮住まい先を借りるための諸経費並びに賃料、新居への引越し費用等です。
建て替え期間を把握することは、資金計画やスケジュールを立てるためにもとても重要なポイントになります。ここでは、その建て替えの流れと、把握しておきたい期間について見ていきましょう。
建て替えの流れ
建て替えの際の一般的な流れは下記のとおりです。
1.業者選定
2.敷地調査とプランニング
3.最終見積りを確認して契約
4.:建築確認申請書の提出とローン審査申し込み
5.仮住まい先を探して引越し
6.既存建物の解体工事
7.「建物滅失登記」手続き
8.地盤調査
9.新築工事
10.工事完了後登記手続き (「建物表題登記」・「抵当権設定登記」)
11.新居に入居
建て替えの際把握しておきたい期間
建て替えには色々な手続きや工事が伴います。その中でも特に建て替えの際に把握しておきたい期間は、以下の5つです。
1.各種手続きにかかる期間
2.ローンの審査期間
3.土地の調査期間
4.解体工事期間
5.新築工事期間
これからこの5つの期間について見ていきましょう。
建て替えに必要な各種手続きにかかる期間の目安
建て替えに必要な手続きはいくつかあります。また、建て替えに関する各種手続きは、一方的に申請して終わりではなく、その申請が受理されて初めて完了となり、次のステップに進ことができます。
では、各種手続きで必要なものや費用、期間の目安についてみていきましょう。
「建築確認」の手続き
建築確認の手続きは、着工前に施工業者や建築士事務所を通じて建築確認申請を行います。書類審査に問題がなければ「建築確認済証」が発行されます。また、工事完了後には完了検査を申請し、問題がなければ「検査済証」が発行されます。
【提出書類】建築確認申請書、建築計画概要書など
【費用】約3万円 ※自治体により異なり、一般的には床面積の広さで決まります。
【申請から完了までの期間】建築確認申請…約7日間、完了検査申請…約7日間
建築確認の詳細については、以下にまとめました。
| 必要書類 | 確認申請書 建築計画概要書 委任状 建築工事届 受付表 建物図面 その他 |
|---|---|
| 申請のタイミング | 新築工事着工前 |
| 費用 | 約3万円〜約8万円 |
| 期間 | 通常約7日 |
「建物滅失登記」の手続き
建物滅失登記の手続きは、建物解体後1ヵ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると過料を課せられることもありますので、注意が必要です。また、書類の準備には約1~2週間を要するので、事前に準備をしておきましょう。
【提出書類】登記申請書、所在地の分かる住宅地図、取毀し証明書、解体業者の資格証明書と印鑑証明書など
【費用】約4~5万円
【申請から完了までの期間】約7日間
建物滅失登記の詳細は下記にまとめました。
| 必要書類 | 建物滅失登記の登記申請書 滅失した建物の登記簿謄本や公図など 建物滅失証明書 解体業者の代表事項証明書と会社の印鑑証明書 滅失した建物の周辺地図 委任状 現地写真 その他 |
|---|---|
| 申請のタイミング | 建物を解体してから1カ月以内 |
| 費用(司法書士に依頼した場合) | 約3万円〜約5万円 |
| 期間 | 約1週間〜約2週間 |
「建物表題登記」の手続き
建物表題登記の手続きは、建物取得後1ヵ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると過料を課せられることもありますので、注意が必要です。また、書類の準備には約1週間を要するので、事前に準備をしておきましょう。
【提出書類】所有権証明書、住所証明書、委任状、建物図面、各階平面図など
【費用】約8~17万円 ※建物の形状や所有権証明書の有無などにより変動
【申請から完了までの期間】約10日間
建物表題登記の詳細は下記にまとめました。
| 必要書類 | 検査済証 建築確認通知書 施工業者の工事完了引渡証明書 施工業者の印鑑証明書・登記事項証明書 住民票 登記申請書 建物図面・各階平面図 案内地図 委任状 |
|---|---|
| 申請のタイミング | 建物の所有権を取得してから1カ月以内 |
| 費用(司法書士に依頼した場合) | 約8万円〜約12万円 |
| 期間 | 約1週間〜約2週間 |
建物表題登記が完了すれば、建物の所有権を保存する登記を行います。
所有権保存登記は、司法書士に依頼することが一般的です。
「抵当権設定登記」の手続き
建て替え時に住宅ローンを利用する場合には抵当権設定登記の手続きが必要です。登記の手続きには専門知識が必要になるため、司法書士に依頼することが多く、その場合は手数料がかかります。
【提出書類】印鑑証明書、登記原因証明情報、金融機関の資格証明書、委任状、権利証、住宅用家屋証明書など
【費用】登録免許税…借入額×0.4%、司法書士報酬…
約5~約7万円、その他
【申請から完了までの期間】約7~14日間
抵当権設定登記の詳細は下記にまとめました。
| 必要書類 | 抵当権設定契約書 委任状 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの) 不動産の登記済証 その他 |
|---|---|
| 申請のタイミング | 抵当権設定契約締結後 |
| 費用(司法書士に依頼した場合) | 約10万円〜約20万円 |
| 期間 | 約1週間〜約2週間 |
抵当権設定登記は、金融機関指定の司法書士に手続きを依頼するケースが大半です。
住宅ローンの返済が滞った場合は、建物と土地を金融機関によって競売にかけられるおそれがあるので、返済は滞りなく行うようにしましょう。
建て替えの際に利用するローンの審査期間の目安
建て替えの際にローンを利用する場合は、その審査期間を把握しておくことも大切です。
ローンの審査には、「事前審査」と「本審査」の2つがあります。ローンを利用するための審査期間は金融機関や与信力、担保力などにより異なります。事前審査は比較的早く回答が出ますが、本審査になると長いところでは約1ヵ月かかるケースもあります。
メガバンクや地方銀行の場合は具体的な審査期間を明示していない場合が多いのですが、一般的に事前審査には約3~7日ほどかかるでしょう。ネット銀行の中には即日回答が可能な銀行もあります。
ローン審査の詳細は下記にまとめました。
| 事前審査の場合 | 本審査の場合 | |
|---|---|---|
| 必要書類 | 本人確認書類 健康保険証 前年分の源泉徴収票など収入確認用書類 その他 |
本人確認書類 住民票 印鑑証明書 前年分の源泉徴収票など収入確認用書類 建物請負契約書など その他 |
| 申請のタイミング | 初回審査依頼時 | 建物請負契約書締結後 |
| 費用 | 不要 | |
| 期間 | 約1週間 | 約1週間〜約2週間 |
審査の内容によっては資料の追加提出を求められる場合もあるので注意しましょう。
審査が長引く要因
ローンの審査が想定より長引くのには、いくつか要因が考えられます。審査が長引く代表的な要因を5つ紹介していきます。
【要因1】申し込みが集中している
金融機関への申し込み件数が増えると、審査をするのに時間がかかりやすくなります。特に、住宅ローンの繁忙期である1~3月は長引きやすくなります。
【要因2】追加書類が必要になる
申込時に必要な書類がそろっていない等で、追加書類のやり取りが必要となった場合、審査結果が出るまでに時間を要する場合があります。
【要因3】返済負担率がギリギリの場合
収入に対して返済負担率が高くなると、審査がより慎重になるため時間が長くかかるケースがあります。
【要因4】個人信用情報に問題がある
ローンの事前審査のときに、個人信用情報に何か問題点があると、審査をするのに時間がかかる場合があります。
【要因5】事前審査の時から申込人の状況が変わっている
例えば、事前審査の時から転職をして収入が減少したり、その他の理由で収入が安定しなくなった場合など、事前審査の時から申込人の状況が変わっていると、審査が長引いたり、場合によっては審査が通らなくなる可能性もあります。
建て替えにともなう解体期間の目安
建て替えをする場合は、既存住宅の解体工事が発生します。そのため、建て替えを考える場合は、この解体工事の期間についても把握しておくことが重要です。
解体の流れと期間の目安
解体工事の流れとそれぞれの工程の期間の目安は、一般的に以下のようになります。
1.解体業者との契約:約1日
2.近隣住民への挨拶:約1日
3.外構の解体工事:約1日 ※外構の面積や構造物により異なります。
4.建物の解体工事:約3~10日 ※建物の面積や構造により異なります。
5.基礎の撤去:約2~5日 ※基礎のボリュームや埋設物により異なります。
6.整地と清掃:約1日
解体期間についてはあくまで目安であり、様々な要因により期間は前後しますので、詳細は解体業者に確認しましょう。
解体工事が長引く要因
解体工事は長引く要因として代表的なものは、天候です。雨天の場合は解体工事が進められない場合がありますので、工事期間が長引く原因となります。
また、住宅の建材としてアスベストが使用されていると、さまざまな手続きが必要になり、また、特殊な工法によって解体する必要がでてきます。そのため解体期間も長引く可能性が高くなります。
その他、工事を進める中で地中埋蔵物が見つかった場合には除去する必要があるため、想定よりも工事期間が長引くケースがあります。
解体工事は自分で依頼する方がお得?
家を建て替える場合、解体工事の業者は家を建て替える施工業者が手配することが一般的です。
しかし、解体工事を自分で依頼する方法もあり、その場合のメリットとデメリットを紹介していきます。
メリット:費用を安く抑えることができる
解体工事を自分で依頼することで費用を安く抑えることができます。
施工業者が手配すると中間マージンが発生してしまいますが、直接依頼することで中間マージンを削減できます。
デメリット:工事の仕上がりに不安が残る
素人が発注することになるため、解体工事の仕上がりが不十分になる可能性があります。
手間やリスクがあるため、不安な場合はプロによる正確な発注が安全であるため、施工業者に手配してもらうようにしましょう。
建て替えの際に行う土地の調査期間の目安
建て替えの際に行う土地の調査には、解体前に行う「敷地調査」と解体後に行う「地盤調査」があります。2つの調査を実施しないと建て替えをすることはできません。また敷地調査は解体後に行なうケースもあります。
敷地調査の目安期間
敷地調査とは、家の建て替えを検討している土地を調査することで、下記の内容を主に調査します。
- 敷地の形状や面積
- 前面道路との関係
- 電柱や電線の位置関係
- 水道やガス管、電気の配線などの引き込み
- 周辺の建物状況や隣地の建物の窓の位置など
現地に訪れて調査したり、市役所や水道局などで図面を取得し、調査します。
敷地調査は約1日〜約2日で行います。
地盤調査の目安期間
地盤調査とは、土地の地盤の強度を専門的な重機を使い調べることです。敷地形状などにより工法はいくつかあり、調査期間も異なります。
地盤調査の期間の目安は約10~20日間です。
建築工事の着工が遅くなる地盤改良
地盤調査の結果や、計画している住宅の規模や構造によっては地盤改良が必要になるため、その場合、建築工事の着工が遅くなることがあります。
地盤改良にかかる期間は土地の状況や面積、新築する住宅の規模などにより異なるため、専門業者に確認すると良いでしょう。
また、地盤改良工事にもいくつか方法があるので、着工を急ぐ場合には短工期で可能な方法がないか相談することをおすすめします。
建て替えにともなう建築期間の目安

建て替えで新築住宅を建築する期間の目安は、住宅の面積や工法により異なります。ここでは代表的な構造や工法での建築期間についてご紹介していきます。
建築期間の目安
新築工事の一般的な目安は、約4ヵ月~6ヵ月と言われています。建築期間に幅があるのは、住宅の階数や間取り、使われている資材、工法などにより異なるためです。
主な構造・工法と工期の目安
ここからは代表的な住宅の構造や工法の特徴、工期の目安について見ていきましょう。しかし、工期についてはあくまでも目安であるため、具体的な工期については、施工業者に確認する必要があります。
在来工法
在来工法とは、日本に古くからある伝統工法を簡略化し発展させた、木材を使用する建築方法です。在来軸組工法とも言われ、柱と梁を組み、家の骨組みを造ります。間取りの自由度が比較的高い点が特徴です。
日本で古くから取り入れられてきた工法ですので、多く業者が扱っています。しかし、2×4工法に比べると工事期間が長くなる傾向にあります。
工期の目安:約4~約5ヵ月
2×4工法
2×4工法(ツーバイフォー工法)とは、アメリカで発達し普及した合理的な工法で、あまり難しい技術を必要とせずに、安定した高品質な住宅を建てることができます。
職人の技術や経験にあまり左右されず、量産され材料を現場で組み立てる工法ですので、工期を比較的短くすることができる工法と言えます。また耐震性に優れており、在来工法の約1.5~約2倍とも言われています。
工期の目安:約2~約4ヵ月
軽量鉄骨造
軽量鉄骨造とは、厚さが6mm以下の鋼材の軽量鉄骨が利用されている住宅です。
工場で部材を作って現地で組み立てて設置する「プレハブ工法」で建てられます。
一般的な住宅の場合、軽量鉄骨造でかかる期間は約4カ月です。
鉄骨造
鉄骨造の中でも種類がありますが、住宅で用いられる鉄骨造は一般的に軽量鉄骨造です。厚さ6mm未満の軽量鉄骨をさまざまに折り曲げたフレームを軸組として、量産型のパネルを現場に運び込んで、組み立てます。
この工法は、在来工法のような職人の技術を必要としないため、一定の品質を保つことが比較的容易な工法と言われています。また、現場で組み立てる工法ですので、工期も在来工法などに比べると短くすることができます。
工期の目安:約2~約4ヵ月
鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造とは鉄筋で補強したコンクリートが構造体になっています。鉄筋とコンクリートが互いの弱点を補い合うことで、高い強度を実現できることが一番の特徴です。
耐震性や遮音性、気密性、耐火性に優れており、またデザインの自由度が高いことも特徴です。しかし、工事費用が高くなる傾向にあり、構造自体が重たいため、地盤を強固にする必要があります。
工期の目安:約5~約6ヵ月
建て替え期間中に借りる仮住まいとは
建て替えの際には、既存住宅を解体する前に、仮住まいを見つける必要があります。仮住まいとして利用できる場所は、ホテルやウィークリーマンション、一般的な賃貸住宅などがあります。
ペットに対応している仮住まい先は多くないため、見つけることがなかなか難しいのが現状です。
敷地内にプレハブを建てて工事期間中だけ住む、ということは建築基準法では認められておらず、プレハブで仮住まいをする場合、別に建築確認申請を取得する必要があり、現実的ではありません。
ホテルなどで仮住まいする場合には、家財を保管するための倉庫なども必要となります。また、賃貸を利用する場合には契約手続きなども必要です。
仮住まい先については余裕をみて、解体工事を行う2~3ヵ月前には探し始めるようにすると良いでしょう。
家の建て替え期間中の仮住まいについて
ここでは、家の建て替え期間中の仮住まいについてのポイントや注意点を解説していきます。
約半年~1年住むことを前提に検討する
約半年〜約1年住むことを前提に検討しましょう。
解体から新居に引越しするまでにかかる期間は約5カ月〜約8カ月です。
工事は天候不順などにより順延する可能性もあり、余裕を持ったスケジュール管理が必要になります。
そのため、仮住まいに住む期間も約半年〜約1年を想定しておきましょう。
余裕をもって物件探しをする
建て替えが決まったら、できるだけ早く物件探しを始めましょう。
条件が増えれば増えるほど物件探しは難航してしまいます。
条件においても優先順位をつけるなどして選ぶようにしましょう。
ここで時間をかけ過ぎてしまうと、その分新居の引渡しも遅くなってしまいます。
仮住まいの選択肢
仮住まいの選択肢としては、下記があります。
- 賃貸マンション・アパート
- マンスリーマンション
- ホテルや民泊など短期賃貸物件
マンスリーマンションとは、1カ月単位の短期の入居から利用できるマンションのことで、家具や家電が付いているマンションが一般的です。
賃貸マンションやアパートと比べると、敷金や礼金がかからないメリットがあります。
短期賃貸物件とは、ホテルやシェアハウス、民泊など短期で賃貸できる物件のことです。
契約の手続きが手軽であり、プランを活用することで賃貸マンションなどよりも初期費用がかからず安く利用できるケースもあります。
仮住まいの探し方
仮住まいの物件は、一般的な賃貸に比べても物件数が少なく、探すのに苦労する可能性があります。
仮住まいはインターネットで検索したり、地域の不動産業者や仮住まい専門の不動産業者に聞いたりなどして探してみると良いでしょう。
トランクルームも利用する
トランクルームなどを利用すれば、仮住まいに家具や家電などの荷物を移動させる必要はありません。
トランクルームは自宅の収納の延長として利用ができる収納サービスです。
荷物の量に応じて有効に活用しましょう。
仮住まいの費用は住宅ローンが利用できない
仮住まいの家賃や引っ越し費用は、住宅ローンに充てることはできません。
これらの費用は自己資金で支払う必要があるので、それを念頭に置いて仮住まいを検討しましょう。
着工・上棟・竣工の意味

建て替えの際に使用される用語で、着工・上棟・竣工の意味はご存じでしょうか。ここではそれぞれの意味を紹介します。
着工は工事を始めた段階を指して使用される場合が多いです。
建て替えを行うにあたり地盤改良工事や杭打ちを開始した時点で着工と見なされます。
上棟とは柱や梁などの建物の構造部分が完成し、棟木という屋根を支える部材を取り付けることを指します。
鉄骨などの建物の場合でも建物の骨組みが完成した際に上棟として扱われます。
竣工とは建物の建築工事が完了し、検査も終了した時点で建物を施主に引き渡すまでを表します。
ここで行う検査とは自主検査、社内検査、完了検査、施主検査などを指します。
上棟式とは
上棟式とは、棟上げを終えたタイミングで無事に終えたことに感謝し、家の守護神と大工の神を祀る儀式です。
施主は建設現場の関係者に対して料理やお酒を振る舞ったりご祝儀を渡したりします。
近年では上棟式が行われるケースは珍しくなっていますが、住んでいる地方によっては文化として残っているケースもあります。
また住んでいる地域によって風習が異なるケースもあるため、不明点がある場合はハウスメーカーなどに相談しても良いでしょう。
着工から上棟までの工事期間は
建物の建築を行い、着工から上棟までにかかる期間は約1カ月〜約1カ月半です。
この期間は天候や季節、担当する大工のスケジュールによって日数が変動します。
この期間には家の基盤となる基礎を作り、基礎にはコンクリートを固めたものが使用されます。
また、上棟は住宅の構造となる柱や梁などの基本構造が完成した後に屋根を支えるための棟木を取り付けることで完成します。
着工から上棟までの工事の流れ
着工から上棟までの工事の流れを知りたいという方もいるでしょう。
ここでは着工から工事までに行われる工事内容と期間について紹介します。
地盤調査

| 地盤調査 | 約1日 |
|---|
土地に建設許可が降りたらまず初めに行われるのは地盤調査です。
地盤調査は建物の建設前にその土地の地盤の強度を確認するために行います。
基本的には新築する建物の隅4箇所部分と建物中央部分を調査します。
この地盤調査は約1日で終了しますが、検査の結果が出るまでに約1週間かかります。
この検査結果で地盤が弱い場合には地盤改良工事を行う必要があります。
地鎮祭

| 地鎮祭 | 約1日 |
|---|
地鎮祭はその土地の神を祀る儀式であり、工事を無事に終えられることや建物の安全などを祈るために行われます。
施主以外にも工事の関係者などが立ち会って行います。
地鎮祭が終了したら、近隣住民へ工事を開始する挨拶なども済ましておくと良いでしょう。
騒音が発生してしまうことに対して事前にお詫びし、近隣住民とのトラブルを回避しましょう。
一般的には大安、先勝、友引などの吉日の午前中に行うことが縁起が良いとされています。
日程調整が難しい場合はその他の日程で行われることもあります。
基礎工事

| 基礎工事 | 約1カ月 |
|---|
基礎工事は建物の土台となるため非常に重要な工程になります。
基礎工事の工程は配筋工事、配筋検査、土間コンクリート工事、型枠工事、仮設足場設置などの工程で行われます。
配筋工事、検査では基礎となる鉄筋コンクリートの鉄筋を配置し、検査にて確認を行います。
ここでは鉄筋の太さや間隔などを検査します。
この検査は設計管理者やJIOと呼ばれる期間によって行われます。
土間コンクリート工事では地盤をコンクリートで埋め、木材をシロアリから守るための処理などを行います。
型枠工事では建物の基礎部分に型枠を設置し、コンクリートで固定します。
その後基礎となるコンクリートを木の柱と繋げるボルトを設置し、コンクリートが固まるのを待ちます。
この乾燥期間は季節によって異なります。
仮設足場設置では、住宅の建築を行う際に必要な足場を設置していきます。
ここでは足場を設置する専門業者が工事を行うケースが多いです。
棟上工事

| 棟上工事 | 約1日〜約3日 |
|---|
棟上工事では、家の構造となる柱や梁などの骨組み部分を組み立てます。
棟上工事では最終的に屋根を支える棟木を取り付けることで工事が完了となります。
一般的には工場で生産された柱などを搬入し、手早く組み立てを行うため、かかる期間はそこまで長くありません。
上棟式

| 上棟式 | 約半日 |
|---|
近年上棟式は略式で行われるケースが多く、集まった大工に施主が感謝を伝える機会となっています。
ここ近年では、上棟式は現場監督やハウスメーカーの担当者が代わりに行う場合が多くなっているため、上棟式を行おうと考えている方は、まずは工事の担当者に聞いてみると良いでしょう。
着工から竣工までの工事期間は

竣工までの期間は、上棟から約3カ月〜約4カ月、着工からだと約4カ月〜約5カ月かかります。
この工事日程は入居希望時期によって決定されますが、工事を避けた方が良い時期などと被る可能性があるため注意が必要です。
工事期間は基本的に短縮することが難しいため、希望の時期に合わせて引き渡しを行うためには入念な打ち合わせが必要になります。
打ち合わせにも時間を要するので、なるべく早い段階から準備を進めましょう。
上棟後に行われる工事の流れ
上棟後に行われる工事の流れは主に3つに分けることができます。
ここでは上棟後の工事の流れを紹介します。
外装仕上げ工事
| 外装仕上げ工事 | 約2週間〜約2カ月 |
|---|
外装仕上げ工事とは建築物の外観を綺麗にするだけでなく、雨風や日光の影響を軽減するための工程です。
その工事内容は防水工事、外壁工事、石工事、左官工事などです。
防水工事では建築物にシートやゴムなどで防水層を形成します。
外壁工事では外壁材を現場で取り付けます。石工事では薄い石才を骨組みに取り付けます。
左官工事はコテを使用してモルタルや壁土の塗りを行う工事です。
外装仕上げ工事は内装仕上げ工事と同時に進めていくケースが多いです。
内装仕上げ工事
| 内装仕上げ工事 | 約2週間〜約2カ月 |
|---|
内装の仕上げ工事では、一般的には内装の工事と同じ意味で使用されます。
建物の内部の仕上げに必要な工事をまとめて内装仕上げ工事と呼びます。
内装とは、壁や床、天井、ドア、窓、塗装などの仕上げ工事です。
インフラ設備の工事もこの内装仕上げ工事に含まれる場合もあり、この場合には電気、ガス、水道などの設備が含まれます。
竣工検査~引き渡し
| 竣工検査〜引き渡し | 約2週間 |
|---|
竣工検査〜引き渡しまでには約2週間かかります。
竣工検査では建物の仕上がりが図面や希望通りになっているか、内装や外装など建物の仕上がりに不具合がないかという点が重要です。
その後引き渡しでは代金の支払いから名義変更、補修状況の確認などを行います。
ここで正式に建物が施主に引き渡されます。
工期が遅れる主な原因は
工事の工期が遅れる主な原因を知りたいという方もいるでしょう。
ここでは工事の期間が延びてしまう原因について紹介します。
設計変更や設計ミスによる遅延
工期が遅れてしまう原因の1つに設計の変更や設計ミスによる遅延があります。
当初の計画で工程が進まないことで、計画が崩れその修正にも時間が必要になるため、設計の変更やミスは避けたいところです。
設計の変更をなるべく行わないために、事前に施工会社やハウスメーカーと入念に打ち合わせを行いましょう。
また工事の期間が遅れてしまうと、予定していた日程を確保していた職人をキャンセルし、再度日程調整を行わなければならないため工期に遅れが生じてしまいます。
人手や資材の不足による遅延
工事の時期やタイミングによっては人手や資材の不足によって工事が遅延してしまうことがあります。
資材が不足していると作業の工程が進まなくなってしまい、計画が大幅に遅れてしまいます。
また、職人のスケジュールも他の工事との兼ね合いによっては確保することが難しいケースがあります。
自身の希望通りのタイミングで工事を行うためには事前の入念な打ち合わせが重要です。
この打ち合わせにも時間がかかるため、なるべく早い段階から準備を進めると良いでしょう。
天災による遅延
建築工事は台風や大雨などの天災による影響を受けます。
悪天候下では建築作業を行うことができないため、その分工事が遅延してしまいます。
近年では災害級の天候になることもあるため、梅雨の時期や台風の時期は特に注意が必要です。
これらの時期での工事を検討している方は工期に余裕を持たせるなどの対策を行うことをおすすめします。
着工までにするべきこと

工事の着工前に行うべき準備がわからないという方もいるでしょう。
ここでは着工までにしておくべき準備を紹介します。
契約業者と家の設計を決定する
着工前には契約業者と家の設計を行うことが重要です。
一般的には必要な部屋の数や間取りなどは自身で決定することが一般的です。
また家の向きなども決定する必要があります。
これらは家庭のライフスタイルや外からの視線、景観などを考慮に入れて決定する必要があるため、事前に契約業者との入念な打ち合わせが必要になります。
建築場所の整地
建築する土地が整地されていない場合には、建築場所の整地が必要になります。
整地が適切に行われていないと建物の設計や耐久性に関わります。
これは土地の状況によって作業が異なります。
特に注意したいのは、地中に残置物がないかという点です。
土地によっては浄化槽などが残されていたなどのケースもあります。
地中残置物があることで地盤が弱くなってしまうため、事前に確認が必要です。
地縄張りや地鎮祭の手配
実際に着工する前には地鎮祭や地縄張りを行います。
地縄張りとは、建物の大きさや配置を確認するという目的で敷地内に縄を張り、地面に建築の印をつける作業です。
これらは任意で行うものであり、自身で準備が必要です。
その後地鎮祭を行う場合には、その土地や大工の神を祀り、建築がうまくいくように儀式を行います。
地鎮祭に関しては近年略式で行われることが増えており、事前にハウスメーカーの担当者などに確認すると良いでしょう。
上棟までにするべきこと
上棟までにするべきことがわからないという方もいるでしょう。
ここでは上棟までの準備をスムーズに進めるために確認するべきことを紹介します。
建築設計の確認
建築設計の確認では、決定している設計で自身の希望通りにいくかという点を考慮する必要があります。
本来であれば設計の確定は着工を行う前にするべきですが、細かな変更は早めの相談によって対応可能なケースがあります。
希望通りの家づくりを行うためにも、何度か計図を見直して自身の生活導線など暮らしやすい建物について検討してみましょう。
建築現場の見学
建設現場の見学も行っておきましょう。
工事現場の見学に行くことで工事ミスや修正箇所を発見することができます。
工事の早い段階でミスを発見すれば、修正にかかる時間や手間も最小限になります。
また建築現場の見学に行く際には事前に連絡をし、工事の邪魔にならないことや追加の要望などは現場で伝えるのではなく担当者に直接伝えることなどが重要です。
見学に行く際は作業を妨げないように注意しましょう。
上棟式の準備
上棟式を行う場合には、当日の職人の人数などを確認して差し入れするお菓子や飲み物などを決めておくと良いでしょう。
上棟式は施主が工事関係者に感謝を示すものであるため施主が主催者となります。
場合によっては施主が供え物を準備するケースもあり、その場合は事前に準備をしておく必要があるため事前に担当者に確認をしておくと良いでしょう。
着工時期の決め方は
着工時期の決め方がわからないという方もいるでしょう。
ここでは適切な着工時期の決め方について紹介します。
季節的に最適な着工時期とは
工事を行う際には最適な着工時期があります。
建物の基礎工事に使用するコンクリートは気温によって固まる速度が異なり、木材の場合は雨などの影響を受けることもあります。
特にコンクリート打ちは冬場では凍害を起こしてしまう可能性があり、夏場にはひび割れが起きてしまう可能性があります。
上記の点と職人の負担などを考慮に入れると、着工に適している時期は春や秋がおすすめです。
工事に影響を及ぼさないために真夏や真冬を避けて中間的な時期を選ぶと良いでしょう。
家族の状況から着工時期を決める
着工を家族の状況に合わせて決めることも重要です。
学校に通っているお子さんがいる場合は引っ越しによって学区が変わってしまうこともあるでしょう。
そのような場合は10月〜11月の着工にし、4月の新年度のタイミングに合わせるなどして時期を調整しましょう。
また、妊娠中の家族がいる場合にも着工時期を検討した方が良いでしょう。
妊娠中期や後期は、転居に関する手続きなどで心身になるべく負担がかからないようにし、産後4カ月以降に引っ越しを行うことがおすすめです。
固定資産税の課税タイミングから着工時期を決める
土地や建物は固定資産税がかかります。年内に土地を購入し、建物が1月1日時点で未完成の場合は更地として固定資産税を支払わなければならないため、土地の固定資産税の軽減を受けることができません。
年内に土地を購入していて、土地の固定資産税の軽減を受けるためには12月31日よりも前に竣工することが必要です。
また1月2日以降に土地を購入し、建築を完了することで建物と土地の固定資産税を1年分軽減するということもできるため、土地の購入タイミングや竣工するタイミングには注意が必要です。
家の建て替えにかかる各費用の目安

家の建て替えにかかるそれぞれの費用の目安と、支払うタイミングについて解説していきます。
設計費用
建て替え工事では家を新しく新築するため、設計費用がかかります。
一般的な設計費用の目安は、依頼先によっても異なります。
ハウスメーカーや工務店の場合は、建築費用の約2%〜約5%前後が目安です。
設計事務所や設計士に依頼した場合は、建築費用の約10%前後が相場となります。
設計費用の支払うタイミングと金額の割合は、設計事務所などによって異なりますが、一般的には下記の流れで支払います。
- 設計業務委託契約時:2割
- 基本設計完了時:2割
- 実施計画完了時:3割
- 工事の中間時:1.5割
- 建物引渡し時:1.5割
他にも、設計契約時、工事契約時、建物引渡し時にそれぞれ3分の1ずつ支払う場合もあります。
支払うタイミングと金額の割合は事前に確認しておくと良いでしょう。
解体工事費用
解体工事費用の1坪あたりの目安は下記のとおりです。
- 木造:約3万円〜約5万円
- 鉄骨造:約5万円〜約7万円
- 鉄筋コンクリート造:約6万円〜約8万円
あくまで目安のため、建物の規模や構造などによって費用は変動します。
解体工事費用は、解体工事が完工した際に支払います。
新築工事費用
新築工事費用の1坪あたりの目安は下記のとおりです。
- 木造:約50万円〜約60万円
- 鉄骨造:約70万円〜約95万円
- 鉄筋コンクリート造:約75万円〜約100万円
新築工事費用は、主に3回のタイミングに分けて支払うことが多く、内容を以下にまとめました。
| 回数 | 名称 | 支払いのタイミング | 新築工事費用のうち 支払う金額の割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 着手金 | 新築工事が着工した際に支払う | 3分の1 |
| 2 | 中間金 | 工事の中間時に支払う | 3分の1 |
| 3 | 最終金 | 建物を引き渡した際に支払う | 3分の1 |
タイミングや支払う費用の割合は目安となり、ハウスメーカーによってはより細かいタイミングで支払うケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
外構工事は別業者に依頼する方がお得?
外構工事は、ハウスメーカーや工務店などの施工業者が行ったり、協力業者が施工することが一般的です。
しかし、ここでは外構工事を別業者に依頼するメリットやデメリットを紹介していきます。
メリット:専門業者ならではのこだわった外観にできる
外構工事を別業者に依頼することで、専門業者ならではのこだわった外観にできます。
外構工事に対しての知識や技術が豊富でないと、積極的に提案やアイデアが出てきません。
外構工事にこだわりを持ちたい方にはおすすめです。
デメリット:工事期間が長くなる
建物の施工業者とは別の専門業者に依頼するため時間がかかってしまい、工事期間が長くなるおそれがあります。
タイミングが合わない場合は、入居後に外構工事が着工するケースもあるので注意しましょう。
引っ越し費用
引っ越し費用は、一般的な相場では約10万円〜約30万円が目安です。
なお、引っ越しは仮住まいへの引っ越しと、新居への引っ越しと2回必要になるので注意しましょう。
仮住まいの家賃
仮住まいの家賃は、解体工事に着工してから新築の建物が引き渡されるまでかかってきます。
賃貸住宅の場合は、家賃の他にも敷金や礼金、仲介手数料などがかかり、6カ月では約120万円〜約130万円かかります。
仮住まい時は、家賃を毎月支払う必要があり、その他は賃貸契約時にかかります。
他にも契約内容によっては、鍵の交換代やハウスクリーニング費用などの支払いを請求される場合があるので、見積もり時に必要な費用を確認しておきましょう。
不動産取得税、印紙税、登録免許税
家の建て替えには主に3つの税金がかかります。
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
印紙税は、工事請負契約書など課税対象となる文書の作成時に納税義務が発生する税金です。
収入印紙を課税文書に貼り付ける形で納税します。
印紙税は約1万円〜約6万円かかりますが、軽減税率があれば通常よりも税金が安くなります。
登録免許税とは、家の建て替えにより新たに所有権の保存の登記をしたり、住宅ローンによる抵当権の設定の登記をしたりする場合にかかる税金です。
登録免許税は約2万円〜約30万円かかります。
手続きを司法書士に依頼した場合は司法書士への報酬も支払う必要があり、登録免許税とは別で約2万円〜約5万円かかります。
不動産取得税とは、新たに不動産を取得した際にかかる税金です。
不動産を取得してから約半年〜約1年後に支払うのが一般的です。
建て替えの場合は条件を満たせば軽減税率が適用される場合があるので、内容を確認しておきましょう。
不動産取得税は0円〜約50万円かかります。
家の建て替え前に確認するべきポイント
ここでは、家の建て替えをする前に確認するべきポイントを2つ紹介していきます。
「再建築不可物件」「既存不適格建築物」ではないか確認する
家の建て替えをする土地や建物が、「再建築不可物件」や「既存不適格建築物」に該当していないか確認しておきましょう。
それぞれについて詳しく説明していきます。
再建築不可物件とは、今建っている家を解体して更地にしてしまうと、その土地に新たに建物を建てることができない土地のことを指します。
既存不適格建築物は、事実上建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされる建築物のことです。
建て替えの際は、違反していた内容を是正する必要があります。
ライフラインの変更に関する手続きを確認する
家の建て替えをするにあたって、水道や電気、電話線などのライフラインの変更に必要な手続きを確認しておきましょう。
建て替えの場合は、基本的に電気は工事着工前に停止手続きをしておきます。
水道は建て替えの工事で使うため、開栓のままにしておくことが一般的です。
家の建て替え費用を安く抑える方法

家の建て替え費用を安く抑える方法を2つ紹介していきます。
税金の特例や控除を受ける
税金の特例や控除を受けることで、家の建て替え費用を安く抑えることができます。
建て替えで使える代表的なものは、贈与税の非課税や固定資産税の軽減などがあります。
贈与税の非課税とは、自分の父母や祖父母から住宅の新築のために贈与された資金が、一定額までは非課税となる制度です。
令和5年12月31日までは、省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の一般の住宅の場合は500万円まで住宅用家屋の新築資金の贈与が非課税となります。
固定資産税の軽減とは、要件を満たせば、住宅として使われる土地の固定資産税を軽減する措置です。
令和6年12月31日までに新築住宅を取得した場合は、新築住宅にかかる固定資産税を3年間2分の1に減額できます。
このような税金の特例や控除を有効に活用すれば、費用を抑えることができるでしょう。
詳しくは施工業者や税理士に早期に確認しておくことがおすすめです。
相見積もりをとる
解体工事や引っ越しなど依頼する業者を選ぶ際は、金額や内容を比較するために、複数の業者に依頼して相見積もりを取るようにしましょう。
1社だけでは見積もりの金額が適正かどうか判断することが難しく、業者によって提示の金額も異なるので、複数の業者の金額や内容をしっかり比較検討することが大切です。
1社1社見積もりを依頼するのは手間と時間がかかり面倒だという方は、建て替え一括見積もりサイトの「ハピすむ」を活用しましょう。
ハピすむは、一度の依頼で最大3社から建て替えの見積もりを無料で取得することができます。
ハピすむには、厳正な加盟審査を通過した全国1,000社以上の優良な建築会社が加盟しているので、納得のいくまで建築会社を比較検討できます。
簡単に無料で見積もりが出来ますので、ぜひこちらからリフォーム費用の無料相見積もりをご利用ください。
建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?
ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。
実際に建て替えをするべきなのか、リフォームをするべきなのかを検討するためには、プロに現状を相談し、「プランと費用を見比べる」必要があります。
そのときに大事なのが、複数社に見積もりを依頼し、「比較検討」をするということ!
この記事で大体の予想がついた方は次のステップへ行きましょう!
「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」
「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」
そんな方は、簡単に無料で一括査定が可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。
一生のうちに建て替えをする機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!
この記事の監修者プロフィール
2級建築士、インテリアコーディネーター、住環境福祉コーディネーター。ハウスメーカー、リフォーム会社での建築業を幅広く経験。主婦・母親目線で様々なリフォームアドバイスを行う。主な担当は水回り設備リフォーム、内装コーディネート、戸建てリフォームなど。
一括見積もりをする