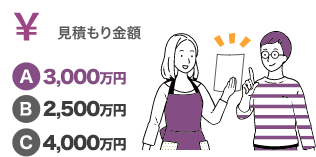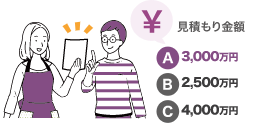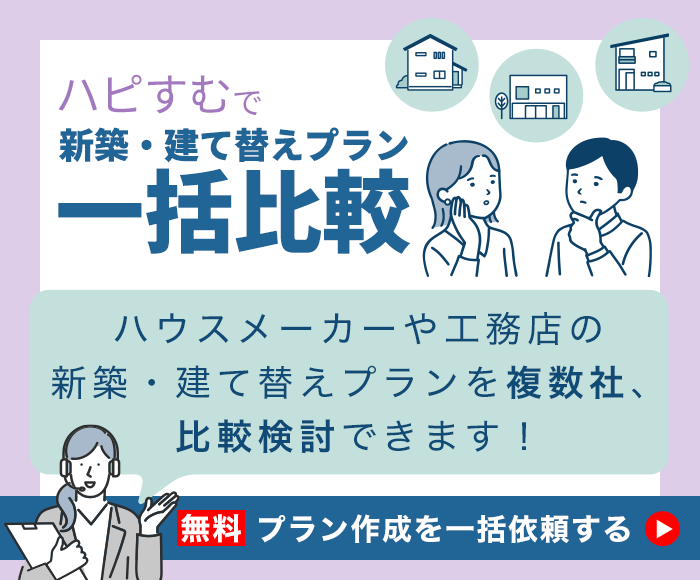2023年12月14日更新
建て替えると建ぺい率で広さは変わる
目次
建て替え出来る面積は建ぺい率で決まる

「建ぺい率」とは、土地の広さに対して建てることができる建物の面積割合を表すものです。
例えば、建ぺい率が70%の土地に建物を建てる場合、建築面積は土地の70%、つまり100平方メートルの土地なら70平方メートルの大きさの建物まで建築することができます。
建ぺい率については、建物が敷地をどれだけ占めているかで計算するため、何階建てでも建築面積が同じなら建ぺい率は変化しません。
そのため、上の例で考えた場合、1階建てなら延べ床面積は70平方メートルですが、2階建てなら同じ建ぺい率でも140平方メートルまで延べ床面積を増やすことができるのです。
しかし、建物の延べ床面積については、建ぺい率と同様に別の数値で制限されており、こちらは容積率といいます。
「容積率」は、建ぺい率のようにパーセンテージで表記され、例えば容積率が100%の場合、上記の100平方メートルの土地なら、延べ床面積は100平方メートルに制限されることを意味します。
もし、建て替えにともなって建ぺい率の制限に引っかかり、建築面積が狭くなってしまったとしても、容積率に余裕があれば階数を増やすなどして既存住宅より住宅の延べ床面積を増やすことが可能です。
建ぺい率の計算から除外される部分とは
建築面積は建ぺい率で制限されていますが、建物の中でも特定の設備については建ぺい率に含まれません。
建ぺい率について定めた法律では、出幅が1m以内の軒、ひさし、バルコニーは建築面積に含まれず、ウッドデッキは屋根なしまたは屋根有りの場合でも、三方が開放的で建物からの長さが2m以内なら対象外です。
容積率に含まれない部屋とは
容積率も建ぺい率と同様に家の広さに大きく関わる制限ですが、こちらも特定の構造の部屋の場合、算入面積を減らすことができます。
容積率では、地下室がある場合には、住宅として使用する部分の床面積の3分の1、ビルトインガレージがある場合には、床面積の5分の1までを計算から除外することができるため、倉庫を地階に作ることで容積率に余裕を作り、部屋として使える面積を増やすことが可能です。
建ぺい率で建て替え後の広さは

建て替えを行うことで、家の広さはどうなるのでしょうか?
建て替えで家の広さが変わる条件についてご紹介します。
建て替え前よりも広くなる場合
建て替えによって以前の住居より家が広くなる場合は、どのような条件が考えられるのでしょうか?
まず考えられるのは、既存の家が敷地の建ぺい率に比べ、小さい建築面積で作られていた場合です。
このような家を建て替えた場合、元々の家より広い建築面積で家を建てることができるでしょう。
もうひとつの条件は、建築面積はそのままで地階を作ったり、階数を増やしたりした場合です。
容積率に余裕があれば、2階建てを3階建てに建て替えれば、延べ床面積を増やすことができ、結果的に居住空間を拡張することができるでしょう。
容積率について余裕がない場合でも、地階部分は一定面積まで容積率に算入しなくて済むため、地下室を活用すれば居住空間を広くすることができます。
狭くなる場合
建築基準法や自治体の条例は定期的に変更が加えられているため、既存の家を建てたタイミングと、建て替えのタイミングで建ぺい率が減少しているということがあります。
このような場合に建て替えを行うと、減少した建ぺい率に合わせて建築面積を決めなければならないため、家が小さくなるでしょう。
しかし、建ぺい率が下がったとしても、容積率に余裕があれば階数を増やすなどの方法で延床面積そのものを増やすことが可能です。
また、基礎や構造物が残っていれば建ぺい率を以前のままで計算するという制度があるため、スケルトンリフォームを行って基礎部分などの構造を残しつつほぼ新しい家にするという方法も用いられています。
建て替え時に問題となるセットバック規制とは
建築基準法では、敷地に接する道路は幅4m以上であることと定められています。
しかし、この法律ができる以前に建てられた住居などでは、敷地に接する道路の幅が4mに満たない場合も多いのです。このような住宅では基本的に建て直しができません。
このような状態を将来的に解決するために導入されたのが、「セットバック」という方法です。
全面道路の幅が4mに満たない敷地にある建物を建て替える際には、敷地を全面道路の中心線から2mまで後退させて道幅を確保すれば、建て替えが可能になります。
これは、あくまで建て替えや新築の際に敷地を道路中心線から後退させるというもののため、家を建て替えなければそのままの敷地を維持することができます。
容積率以外の理由で延べ床面積が増やせない場合もある
建物の広さを決めるのは、建ぺい率や容積率だけではありません。
地域によっては建築物に高さ制限が設定されており、この高さを超える建物を建てることができないため、階数を増やして延べ床面積を増やすことができないのです。
また、道路斜線制限というものもあり、こちらは敷地に接している道路の反対側境界線より、一定の勾配の範囲にしか建物を建てることができないという制度です。
勾配は用途地域によって変わりますが、住居系地域なら1.25倍、その他の地域なら1.5倍に設定されています。
ただし、道路斜線制限は適用距離という制度も導入されており、道路から一定以上離れた場所については制限がかかりません。
そのため、建物の一部を斜めに設計し、斜線制限部分に沿うように設計すれば、道路斜線制限をある程度回避することができます。
建ぺい率の緩和措置について
建ぺい率は、敷地の状況や建物の構造によって緩和される場合があります。
ひとつ目の緩和措置は、防火地域内に耐火建築で家を建てた場合で、元々の建ぺい率に10%が上乗せされます。
ただし、地域によっては緩和が受けられない場合もありますので、建て替え前に確認しておきましょう。
また、角地についても建ぺい率が緩和される措置がとられており、角地なら他の敷地に比べ、10%建ぺい率が緩和されます。
建築物の容積率について知ろう

まずここでは、容積率の概要について詳しく解説していきます。
容積率とは
容積率とは「敷地面積に対する延べ床面積の割合」のことを言います。
延べ床面積は、各階の面積の合計のことです。
1階が100㎡、2階が80㎡であれば、延べ床面積が180㎡となります。
希望する延べ床面積の建物にできるかどうかは、その土地の広さと容積率によって決まってくるため、容積率は建て替えの際などの重要な指標になります。
容積率の制限を設ける理由
なぜ容積率には制限が設けられているのでしょうか?
容積率がなければ、3階建や5階建など好きなだけ大きな建物を建てることができます。
そうすると日当たりや風通し、さらには防火対策の面でも快適な暮らしが阻害されてしまいます。
また建物がいくらでも大きくできるということは、そこにたくさんの人が住めるということを意味します。
そうすると人口が増えすぎてしまい、電力消費や下水処理などにも問題が生じてくる危険性があります。
快適な生活を守るために容積率に制限が設けられているのです。
容積率の計算方法
容積率は、
延べ床面積÷敷地面積×100
で求めることができます。
1階が100㎡、2階が80㎡、敷地面積が200㎡の土地の場合の容積率は
(100㎡+80㎡)÷200㎡×100=90
となり、容積率は90%になります。
容積率と建ぺい率の違い
容積率と一緒によく聞くものに「建ぺい率」というものがあります。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建物面積(建物を真上から見たときの面積)の割合で「敷地面積に対する平面的な広さの割合」のことを言います。
異なる用途地域にまたがる場合の容積率
建築物の敷地が2つ以上の異なる容積率の制限を受ける地域にまたがる場合、それぞれの地域の敷地部分の面積割合をそれぞれの地域の容積率でかけ、それらの数値を合計し、敷地全体の面積で割ったものをその敷地の最高限度の容積率とします。
例えば敷地面積の40㎡は指定容積率が80%、敷地面積の60㎡は指定容積率が300%だとします。
その場合は、
40㎡×80%=32㎡、60㎡×300%=180㎡
32㎡+180㎡=212㎡
212㎡÷100㎡で容積率は212%となります。
容積率によって建てられる家も変わる

同じ100㎡の敷地でも、建ぺい率と容積率によって建てることができる家の種類や構造も変わってきます。
ここでは具体的な建ぺい率と容積率の数字からどのような家を建てることができるかについて解説していきます。
建ぺい率60%・容積率80%の場合
100㎡の土地で建ぺい率60%・容積率80%の場合、建物を建てることができる広さは60㎡までで、延べ床面積は80㎡までになります。
2階建にする場合には、1階2階ともに40㎡の建物を建てることが可能です。
1階を60㎡にして、2階を20㎡にするなどもできます。
建ぺい率50%・容積率100%の場合
100㎡の土地で建ぺい率50%・容積率100%の場合、建物を建てることができる広さは50㎡までで、延べ床面積は100㎡までになります。
2階建にする場合には、1階2階ともに50㎡の建物を建てることが可能です。
また3階建にする場合も、計算上では1階50㎡、2階3階ともに25㎡などの建物を建てることが可能になります。
建ぺい率40%・容積率80%の場合
100㎡の土地で建ぺい率40%・容積率80%の場合、建物を建てることができる広さは40㎡までで、延べ床面積は80㎡までになります。
2階建にする場合には、1階2階ともに40㎡の建物を建てることが可能です。
容積率が80%と同じでも建ぺい率が60%と40%の場合では建てることができる家の広さが異なります。
延べ床面積の合計が同じ80㎡まででも、建ぺい率が60%と40%では、1階の床面積が最大60㎡と40㎡と異なってくるのです。
容積率に算入されない具体的な設備
容積率の制限があったとしても、なるべく広い家を建てたいですよね。
家の設備の中には、容積率の中に算入されないものがあります。
ここでは空間を有効に利用して制限内でなるべく広い家を建てられるように、容積率に含まれないものと条件などについてご紹介していきます。
地下室

地下室は建築基準法で「建物の合計床面積の3分の1までは容積率に算入しなくていい」という決まりがあります。
この緩和を適用する際の条件としては、地下室の天井が地盤面の上に出ている高さが1m以下であること、住宅として使用されることなどがあります。
地下室は音が漏れず外の騒音も聞こえにくいため、楽器演奏やシアタールームなどにも最適です。
そのほかにも収納部屋や室温を均一に保つことができるという特徴からワイン貯蔵庫にするなどの用途もおすすめです。
地下室を作る際には湿気や換気対策が必要な点、コストがかかる点には注意しましょう。
車庫・ガレージ

車庫も容積率には算入されないスペースの一つですが「延べ床面積の5分の1まで」という制限は守る必要があります。
車庫には建物に組み込まれているビルトイン型の車庫、単独車庫、柱と屋根によってできているカーポート形式の車庫など色々な種類がありますが、どのようなタイプでも用途が車庫であれば容積率緩和の対象となります。
車庫の位置などによっては、自宅の間取りが制限されてしまったり、エンジン音が部屋に響いてしまうこともあるため、設置の際には場所などに注意しましょう。
バルコニー・ベランダ

バルコニーやベランダも容積率には算入されません。
バルコニーは外から張り出している屋根のないスペースのことで、専用の屋根を設置する場合はベランダと言います。
条件としては、外壁から2m以上突出している必要があります。
2mを超える幅の場合には、全体の幅から2mを差し引いた残りの部分が床面積に算入されます。
屋内の一部をバルコニーとするインナーバルコニーやバルコニーに格子を設ける場合は原則として床面積に算入されるため注意しましょう。
ロフト・屋根裏収納

ロフトや屋根裏収納も容積率に算入されないものの一つです。
ロフトや屋根裏収納とみなされるためには、下記の条件を満たしている必要があります。
- ロフトの床面積がロフトのある会の床面積の2分の1未満であること
- 天井の高さが1.4m以下であること
- ロフトの内部に収納がないこと
- ロフトの内部に電話やテレビ、インターネットのジャックがないこと
- ロフトの床の仕上げは、畳、絨毯、タイルカーペットなどではないこと
- 上記以外にも居住用に使用される使用にしないこと
居住スペースとしては利用せず、あくまでも物置であることが前提となっています。
吹き抜け

吹き抜けは2階などの一部に床を設けず高い天井にした、開放感のあるスペースのことです。
吹き抜け部分も容積率には算入されません。
例えば1階リビングの一部が2階まで吹き抜けになっている場合、1階の面積は床面積に含まれますが、吹き抜け部分は1階の面積にも2階の面積にも算入されません。
吹き抜けに上階の一部と一部を結ぶ渡り廊下がある場合には、渡り廊下は床面積と判断されることがあります。
また吹き抜け部分にある収納棚が2階まで高さがある場合なども床面積に算入される可能性があるため注意しましょう。
用途地域ごとの容積率の制限
都市計画法に定められている用途地域のうち、住宅建築可能な用途地域についてそれぞれの内容や容積率について解説していきます。
ここで紹介する数値は地域によって細かい違いがある点には注意してください。
第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地は低層住宅のための地域で、住宅のほかにも、小・中・高校や老人ホーム、図書館なども建築可能です。
また建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されているのも、この地域の特徴です。
容積率:50%・60%・80%・100%・150%・200%
第二種低層住居専用地域
この地域は第一種低層住居専用地域で建築できるものに加えて、喫茶店や理髪店、日用品販売店舗や、2階以下で作業場の面積が50㎡以下のパン屋なども含まれます。
この地域も、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されています。
容積率:50%・60%・80%・100%・150%・200%
第一種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅のための地域になります。
第二種低層住居専用地域で建築できるものに加えて、大学や病院、公衆浴場、飲食店や銀行なども建てることができます。
容積率:100%・150%・200%・300%
第二種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域では、店舗なども業種に関わらず2階以下かつ1500㎡以下という条件を満たせば建てることができるようになります。
事務所なども店舗と同じ条件で建設が可能です。
容積率:100%・150%・200%・300%
第一種住居地域
第一種住居地域は、住環境を保護するための地域ですが、大規模ではない店舗や事務所も建てることができます。
住宅が6〜7割、店舗や事務所が3〜4割ほどで、利便性が高く生活しやすい地域が多いです。
容積率:200%・300%・400%
第二種住居地域
第二種住居地域は、住宅と店舗・事務所の割合が5:5程度と、第一種住居地域よりも店舗や事務所の割合が高いことが多いです。
利便性はよくなりますが、第一種住居地域よりも騒音などは気になるかもしれません。
容積率:200%・300%・400%
準住居地域
準住居地域は国道や県道などの幹線道路沿いに指定されることが多い地域です。
大規模な店舗や事務所に加えて、自動車関連施設などが多く見られ、住居地域というイメージはあまり持たれません。
住居専用地域ではないので、日当たりなどに関する制限がそれほど厳しくなく、マンションなどが多いです。
容積率:200%・300%・400%
田園住居地域
田園住居地域は2018年に新しく追加された用途地域で、住居と農地が調和しながら発展する居住環境を目指して定められたものです。
制限内容そのものは、第二種低層住居専用地域とほぼ同じになります。
容積率:50%・60%・80%・100%・150%・200%
近隣商業地域
近隣商業地域はマンションや戸建、飲食店・店舗、事務所、オフィスなどが混在しています。
駅周辺や商店街などがこれにあたり、近隣住民の利便のために、メインに店舗が立地する地域です。
容積率:200%・300%・400%
商業地域
商業地域はターミナル駅周辺や大都市の都心部が指定されることが多く、タワーマンションや高層ビルなどが密集した地域が多いです。
近隣商業地域と異なる点は、日影規制がない点と風俗営業店などの建築も可能な点です。
容積率:200%・300%・400%・500%・600%・700%・800%・900%・1000%
工業地域
工業地域はどんな工場でも建てられるように指定された地域で、住宅も建てることはできますが、住居のために優先される地域ではありません。
地価が安い傾向にあることから、工場の跡地にマンションが建設されることがよくあります。
容積率:200%・300%・400%
前面道路による容積率の制限とは

ここでは前面道路の幅が容積率にどのように影響するかについて、また特定道路に接する場合について解説していきます。
道路の幅(幅員)が12m未満の場合
前面道路の幅員が12m未満の場合、用途地域の区分にしたがって容積率に上限が設けられます。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は4/10、それ以外は6/10を道路の幅にかけた数値が容積率の上限になります。
第一種低層住居専用地域で指定容積率が200%の土地が幅4.5mの道路に面している場合、基準容積率は、4.5m×4/10で180%となり、この土地に家を建てる場合には容積率が180%以下でなくてはなりません。
道路の幅(幅員)が4m未満の場合
前面道路の幅員が4m未満の場合には、道路の境界線から敷地を後退させる必要があります。
後退させた部分は道路とみなされ、実際の敷地面積からは除かれるため、その分敷地面積が狭くなり容積率が制限されることになります。
特定道路に接する場合
敷地の前面道路が6m〜12m未満かつ、敷地の位置から70m以内に幅員15m以上の特定道路と接している場合、容積率が緩和されます。
土地の目の前の道路の幅員が狭かったとしても、すぐに大きな道路に出られる場合などは容積率が緩和されるのです。
容積率に関する注意点

容積率に関する注意点について見ていきましょう。
容積率以外の建築制限
容積率以外にも建物を建てる際には建築制限があります。
絶対高さ制限
絶対高さ制限は特定の地域のみで適用される建物の高さの制限のことです。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域が適用される地域となります。
この地域では原則として10mまたは12mを超えて建物を建てることができません。
周囲に広い公園があり、他の住居の環境を害する恐れがないと認められた場合や、学校など用途によってやむを得ないと認められた場合には、高さ制限が緩和されます。
斜線制限
斜線制限には3種類あります。
まず「隣地斜線」は隣家の日当たりや採光、風通しなどの環境を守るため建物の高さを規制したルールです。
次に「道路斜線」は道路の日当たりや採光、風通しに支障をきたさないように、また周辺に圧迫感を与えないように建物の高さを規制したルールです。
最後に「北側斜線」は北側に建つ建物の採光条件を確保するために、建物の高さを規制するルールになります。
それぞれ用途地域や道路の幅員などによって制限が異なるため注意が必要です。
日影規制
日影規制は冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、全く日が当たらないことのないように建物の高さを制限する規制です。
建物の用途地域と高さからこの制限は決められています。
また地域によって環境や土地の事情が異なるため、自治体の条例によって指定されている場合もあります。
容積率をオーバーした場合のリスク
容積率をオーバーしてしまった場合にはどのようなリスクがあるのでしょうか?
住宅ローンを組むことができない
容積率をオーバーしている物件は、金融機関の規定により住宅ローンの審査が厳しく通りづらいです。
基準は金融機関によって異なりますが、超過率が10%〜20%程度であれば審査に通る可能性はありますが、20%以上の場合には融資を受けられない可能性が高いでしょう。
違法建築物になるので売買ができない
容積率をオーバーしている建物は、違法建築物という扱いになります。
違法建築物には時効がなく、経過書類などは永年保存されることになり、違法建築物を購入した場合には新しい所有者にも違反の是正義務が発生します。
違法建築物も買主さえ見つかれば、問題なく売却することは可能です。
しかし住宅ローンも期待できず、違反の事実を知りながらその物件を購入してくれる買主を探すのはなかなか難しいでしょう。
建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?
ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。
実際に建て替えをするべきなのか、リフォームをするべきなのかを検討するためには、プロに現状を相談し、「プランと費用を見比べる」必要があります。
そのときに大事なのが、複数社に見積もりを依頼し、「比較検討」をするということ!
この記事で大体の予想がついた方は次のステップへ行きましょう!
「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」
「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」
そんな方は、簡単に無料で一括査定が可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。
一生のうちに建て替えをする機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!
この記事の監修者プロフィール

タクトホームコンサルティングサービス
亀田融一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。
一括見積もりをする