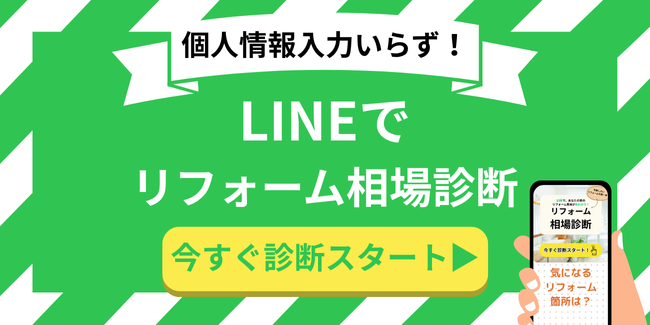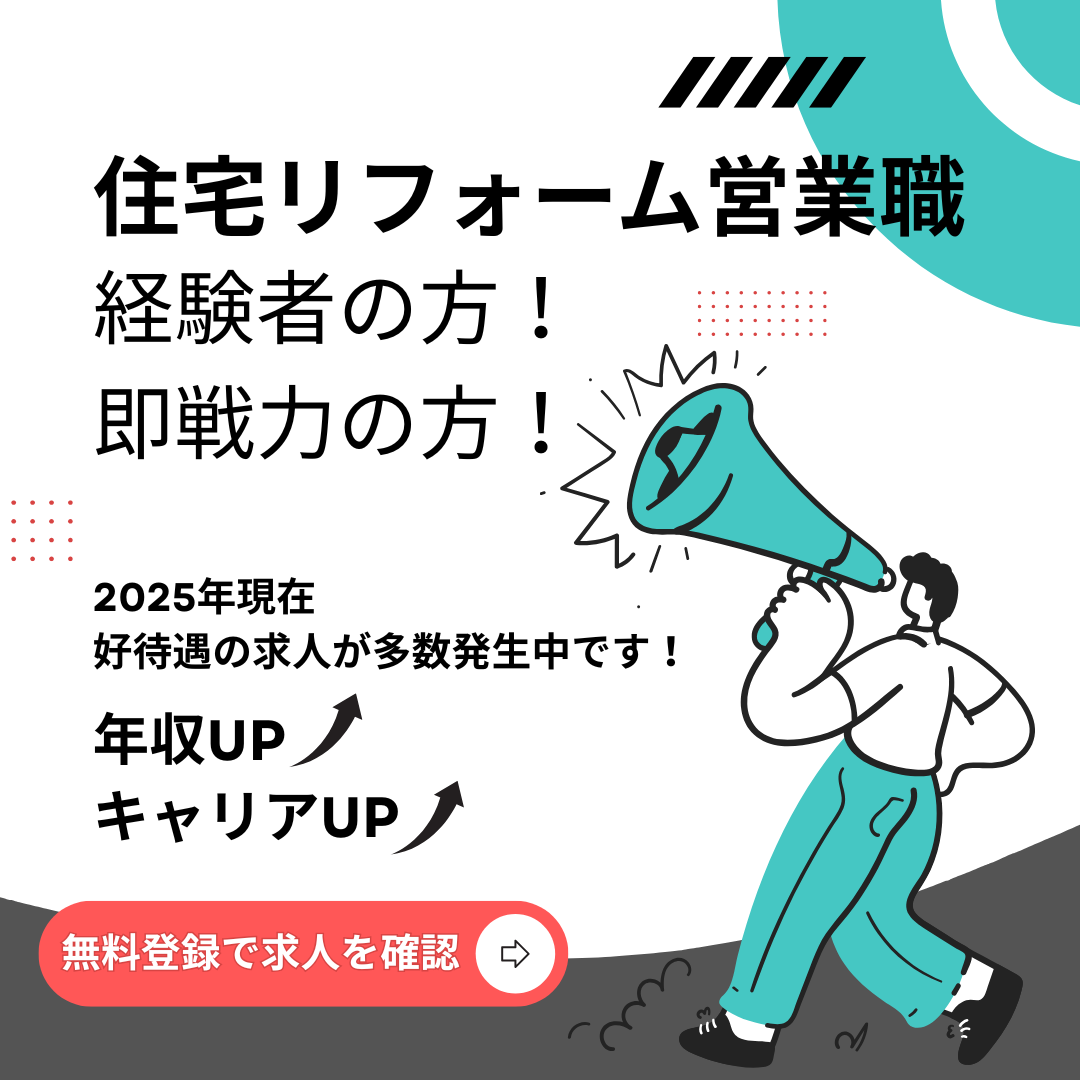八ヶ岳や南アルプス、富士山を眺めながら、四季折々の景色を楽しむ暮らし
長野県南東部、八ヶ岳の南西麓に位置し、富士山を望む富士見町。自然豊かな環境である一方で、特急「あずさ」の利用で新宿から約2時間という交通の便があり、スーパーや飲食店、そして総合病院も揃います。駅を中心に医療や介護等の暮らしに必要な施設が整っているのは特筆すべき点です。
今回は、平成29年から町長を務め、現在2期目の名取重治町長にインタビュー。テレワーカーに注目されているコワーキングスペース「富士見 森のオフィス」を中心とした移住施策のほか、注力しているという子育て施策などについても伺いました。
目次

目次
目次
新宿からおよそ2時間でたどり着く高原の町
──富士見町はどんなまちでしょうか?
長野県富士見町は八ヶ岳の南西麓に位置し、生活圏の標高は700~1,200mといういわゆる高原の気候ですから、夏は冷涼な気候で避暑地となります。町長室にクーラーはまだ設置していないですね。一方で冬は寒いのですが、太陽光が降り注ぐ高い晴天率を誇ります。
特急「あずさ」を利用すれば新宿からおよそ2時間、中央自動車道では八王子からおよそ1時間30分、また、静岡市からもおよそ2時間、名古屋市からおよそ約2時間半の距離です。都会から近すぎず遠すぎない、ほどよい距離感が、旅行者やテレワーカー、二拠点居住者の方々から評価されています。別荘地としても人気がありますね。
さらに、2034年以降に予定されているリニア中央新幹線の開通により、新山梨県駅経由で都心まで約60分圏内となる見込みです。これにより、首都圏への通勤や通学圏としての可能性が広がり、町の魅力がさらに増すと予想されています。

──この町の名前が「富士見」とあるように、町中のあらゆる場所から富士山を望むことができますね。
富士山だけでなく南アルプスや八ヶ岳といった名峰も含めて、非常に恵まれた眺望環境で、まさに日々の通勤・通学路が絶景スポットです。この景観は関東の富士見百景にも登録されていて、特に移住者の方は「こんな素晴らしい景色の中で生活できるとは」と感動されます。
いろんな山の見え方がありますが、私のお気に入りは西の方から広く八ヶ岳を望む眺望です。昨今では季節感が薄れていると言われますが、標高の高さによって生まれる四季のはっきりとした移り変わりを、山々の彩りによって感じられるのは魅力ですね。

自然を活かした観光リゾートにも注目
──自然や歴史を活かした観光資源もありますね。
四季を通じてアクティビティを満喫できる「富士見パノラマリゾート」と「富士見高原リゾート」は、町の東西に位置する2大観光リゾートです。
「富士見パノラマリゾート」は首都圏から日帰りの入笠山トレッキングができて、120万本を超える町花スズランの群生や100種類以上の色とりどりの山野草がご覧いただけます。
そして「富士見高原リゾート」はゴルフコース、陸上競技場、温泉、ホテルを備えています。どちらにもスキー場があり、ウィンタースポーツも楽しんでいただけます。

さらに縄文文化の発信拠点として「井戸尻考古館」と多くの遺跡群があり、出土した貴重な土器や石器、再現した住居などを展示しています。こちらは現在リニューアルを計画していますので、今後の観光は3つの柱で打ち出していく予定です。
スーパーや総合病院。暮らしに必要な施設 が揃う
──暮らしについても教えてください。
富士見町は、コンパクトシティとしての利便性があります。町の中心部に行けば、スーパーやコンビニはもちろん、体育館、図書館、病院、役場など、生活に必要なあらゆる施設が揃っています。産業においては農業や観光のほか、日本全国や世界へ製品を届ける精密機械産業などが盛んです。
そして暮らしの安心を支えるのは「富士見高原病院」という総合病院。小さな地方の町で救急搬送の受け入れや病児・病後児保育などを実施をしている医療施設があるのは非常にありがたいことです。また、高齢者や障がい者を支える福祉・介護施設の整備や社会福祉協議会の活動などにより、医療・福祉・介護の体制が高いレベルで維持されています。
さらに、駅前商店街に整備した地域共生センター「ふらっと」は、総合福祉拠点として総合相談窓口を備えおり、開所以来、子どもからお年寄りまで多くの方に利用されています。子ども達には学校でも家庭でもない第3の居場所として、高齢者や障がい者には安心して利用できる地域や社会との関わりを持つための場所として認知されてきています。

ふらっと立ち寄れる駅舎内の移住相談施設
──富士見町は、移住施策が手厚い印象があります。施策について、具体的に教えていただけますか?
「ウツリスムステーション」という移住相談窓口を「富士見駅」舎内に設けています。駅舎を改装して設置されているため、移住を考える人々が訪れやすいのが特徴です。住む場所や仕事についてはもちろん、移住のお困りごとなど、幅広い疑問や不安の相談に乗っています。
相談者の層も幅広く、若い単身者やファミリー層、子どもが手を離れたことをきっかけに移住を検討する夫婦など、さまざまな背景を持つ移住希望者が訪れています。時には富士見町の魅力を山登りで知って、その帰りに立ち寄るケースもあるようです。

また、移住体験施設「夢想庵」をご利用いただけます。夏だけでなく「やっぱり冬を体験したい」いう方も多いですね。こちらの寒さは厳しいですので、一度体験していただくのは大事だと思います。
──移住者に向けた、施策・支援はありますか?
移住の方が定住していただけるよう「空き家改修補助金」としての最大100万円や、「新築住宅補助金」としての最大100万円、断熱性能を高めるための「省エネ住宅リフォーム補助金」などの補助と移住者向けの加算を行っています。
あわせて「富士見 森のオフィス」のコワーキングスペースを日常的な仕事場として利用する移住希望者には、1ヶ月の家賃と、光熱費相当の月額83,000円を補助する「移住&テレワーク支援補助金」などを設けています。

自然豊かな環境に、ビジネスや人々が集まる交流拠点
──コワーキングスペース「富士見 森のオフィス」も町の特徴的な施設ですよね。
働く場所・仲間づくりの場となるコワーキングスペース「富士見 森のオフィス」を整備しています。テレワークなどの仕事場として、移住者を中心に多くの方に利用されていますし、移住後の仲間づくり、コミュニティ形成の場所としても機能していて、2015年に設立されてからはONEDAY会員を含めて、これまで2,000人ほどの方にご登録いただいています。
こういったテレワーク施設の多くは、中心市街地にあることが多いのですが、こちらは市街地から少し離れた立地で森に囲まれたロケーションです。また、併設する宿泊棟「森のオフィスLiving」があり、テレワークしながら観光を楽しむワーケーションの需要にも応えています。
多様な人々を繋げるハブとしての機能を果たし、これまでに仕事や地域活動など300件近いプロジェクトが生まれています。報告に上がっていないそのほかの小さな取り組みや繋がりは、倍以上存在しているようですね。
設立時より行政と民間の連携で事業を行ってきていて、当初よりスタッフに恵まれたことから、このような地方でも時代に先駆けてコワーキング施設を整えることができました。

移住者の交流拠点は、移住のきっかけにも
──移住のきっかけにもなっているのでしょうか?
移住の大きなきっかけになっていると感じていますね。移住を検討している方々が相談に訪れることもあり、ある地域おこし協力隊のメンバーは、富士見町を選んだ理由の一つが「森のオフィス」の存在だったと聞いています。移住先で知り合いをどう増やすのかといった不安があるなかで、多くの人と繋がれるコミュニティがあることに魅力を感じられたそうです。このような交流拠点があることで、新しい土地での生活をスムーズにスタートできますし、移住の先輩方による地域での活動も間近で見られるので参考になると思います。
──ビジネスや人々が集まる交流拠点がしっかりと機能しているのですね。
スタッフは会員と密接なコミュニケーションを取り、そのスキルや仕事の内容を細かく把握しています。例えば、IT系といってもさまざまな仕事がありますよね。イラストレーターのスキルがあるのか、プログラミングのスキルがあるのか、など詳細まで把握しています。仕事の斡旋の場ではないのですが、必要な場面があれば、その情報をもとにコラボレーションを促進しています。
例えば地域の方々とも関わりがあるので、地元企業からのご相談を引き受けて、会員に声をかけることでプロジェクトが生まれることもあります。

自然を活かした屋外保育で、元気いっぱいに育つ子どもたち
──子育て支援にも注力されています、施策に力を入れている背景を教えてください。
120人前後で推移していた出生数がだんだんに減り、平成27年(2015年)の出生数は100人を下回り、当時は大きなショックを受けました。その後も減少が続き、富士見町の直近の出生数は、10年ほど前の半分程度の50人前後に減少しています。
一方で移住者が増えているので、小学校入学の子ども達は、出生時よりも増えている状況もあります。
──子育て支援の施策について教えてください。
「出会い・結婚・出産・子育て・居場所づくりパッケージ」という枠組みで、重点的に支援しています。具体例としては「出産お祝い金」に10万円、「就学祝い金」に10万円の支給。町長からお祝いの気持ちを伝える、出生時の直筆のメッセージカードや入学祝カードをお渡ししています。
さらに令和6年度からは、子育て世帯の声から1年あたり2万4,000円の「おむつ購入補助金」も開始しています。
そのほか子育て世代の憩いの場や、遊び場となる「ゆめひろばふじみ」や「ふらっと」、児童福祉関係と母子保健関係を一体的に運営する「こども家庭センター」、病気や回復期のお子さんの一時預かり「病児病後児保育事業」など、さまざまな支援を設けています。
──自然豊かな環境を活かした教育機会はいかがでしょうか?
森林や草むらで遊んだり、バリエーション豊かな自然保育を行っています。
町内5ヶ所すべての保育園が、信州の豊かな自然環境を生かした屋外活動を中心に、地域の伝統文化などを日々の保育に取り入れた特徴ある取組みを実践する「信州やまほいく(信州型自然保育認定制度)」の認定を取っています。なお公立保育園の待機園児はゼロです。
また、小学校においても米作りや登山、ひまわりを育ててひまわり油を作って販売するなど、自然を活かした学習をしています。
目指すは、総合力を高めるまちづくり
──町長がこれから目指すまちについてお聞かせください。
町の目指すべき姿として「住み続けたいまち・住んでみたいまち・帰りたくなるまちづくり」を重点テーマとして掲げています。すべての行政施策は人口減少対策に通じるという考え方のもと、全体的な行政サービスの水準を引き上げていきたいと考えています。特定の分野だけが優れているのではなく、富士見町の総合的な魅力を高めることが、この地域に住み続けたいと思う人々を増やし、さらに移住者を呼び込む鍵となります。
IターンのほかにもFターンに力を入れていて、富士見町版Uターンを"富士見町"と"ふるさと"の頭文字をとって「Fターン」と名付けています。このFターンに注力する理由は、出身者は地域への思いを強く持っていただけることからです。若者へのアンケートによると、約5割は「いずれ町に帰りたい」という意向があり、その希望を叶えたいと考えています。

JR駅の充実を活かして、公共交通の強化を図る
──具体的に実行されていくことを教えてください。
特に力を入れている課題の一つが公共交通。かつて存在していたバス路線を再び整備し、定時定路線のバスを復活させたいと、昨年から実証実験が始まりました。富士見町には3つのJRの駅があり、各集落から最寄り駅までバスで20分以内で到着できます。
富士見町では予約制の「デマンド交通」がすでに20年ほど運用されていて、このシステムは必要に応じて利用者を迎えに行く仕組みは、全国的にも先進的とされています。そのほか、子どもたちが利用するスクールバス、買い物バスなどが運航していますが、これらの組み合わせにより、家族の送迎負担軽減や、駅周辺の渋滞を緩和する狙いがあります。そしてバスの利用を通じて、地域内でのふれあいや世代間交流も生まれると嬉しいですね。
──最後に、町民や移住を検討されている方へのメッセージをお願いいたします。
富士見町には39の集落があります。それぞれの地域では、氏神や道祖神を祀る小さな地域祭りから、壮大な御柱祭りまで伝統文化が守り続けられています。それらがつながってきた理由は、厳しい自然環境の暮らしから育まれた、自然への感謝と畏敬の念、そして勤勉で協力し合うという、町民の精神性が存在しているからでしょう。移住者の方にも、そこから生まれたコミュニティに魅力を感じていただけると私は思っています。
来年度は町制施行70周年となります。富士見町でこれまでつないできた人間力、地域力を次世代へ引きついでいくのも私の使命です。

※2024年取材時点の情報です
(取材・執筆・撮影/竹中唯)