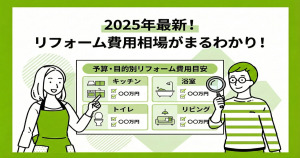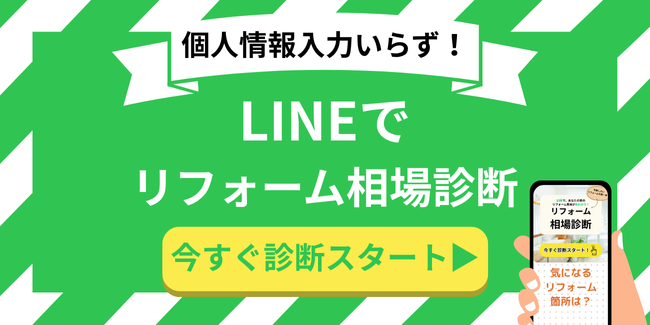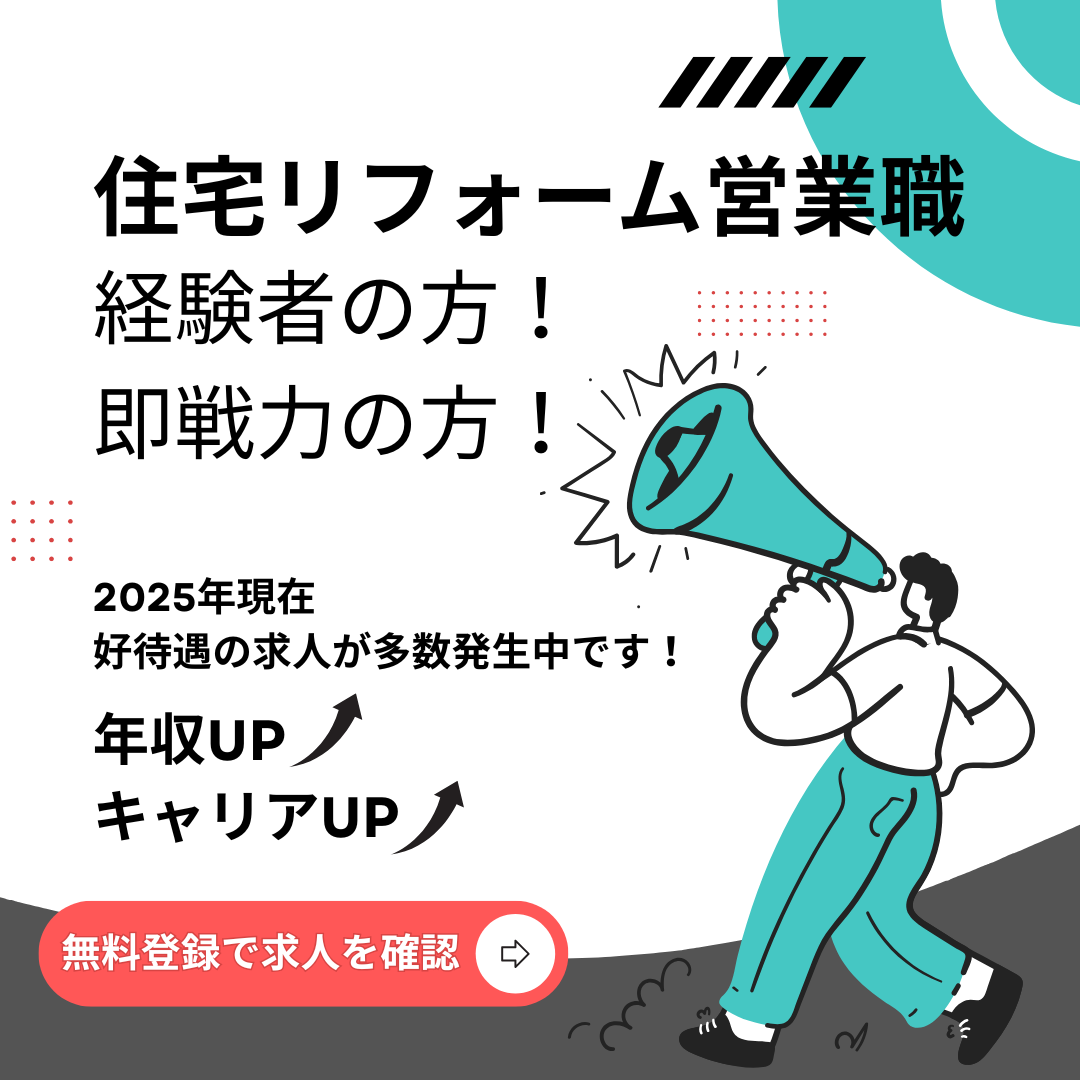本に囲まれた、図書館のような仕事場を持つのが夢でした
《前編》住まいをテーマにお話を聴く『ハピすむ特別インタビュー』。第4回のゲストは、ジェンダー研究の第一人者として日本のフェミニズムを牽引、論客として数々の論争を巻き起こし「日本一ケンカの強い学者」と呼ばれ、2019年の東大入学式祝辞でも話題をさらった社会学者で東大名誉教授の上野千鶴子さん。
上野さんは、約20年前に山梨県・八ヶ岳南麓にお住まいを建て、現在は東京と山梨を行き来しながらアクティブな山暮らしをされているという。そして昨年、二拠点生活についてのエッセイ『八ヶ岳南麓から』を出版。今回は八ヶ岳南麓の山荘にお邪魔し、ご著書について、そして上野さんならではの暮らしのこだわりやご自宅の建築秘話を語っていただきました。
さらに、後編ではおひとりさまブームを巻き起こした75万部ベストセラー『おひとりさまの老後』の著者でもある上野さんに「おひとりさま」のシニアライフを充実させるヒントについてもお話しを伺います。
目次

目次
目次
「八ヶ岳南麓」は、東京から2時間で来られるバンクーバー
──はじめに、八ヶ岳南麓との出会いを是非教えてください。
上野千鶴子(以下、上野) この土地を購入したのは約30年前です。ここを選んだ理由が2つありました。
まずひとつは、知っている人がすでにいたこと。私の友人がこの「八ヶ岳南麓」に定住していたんですが、ひと夏イギリスに行くので家が空くから借りて住んでみないかと言われて、1か月暮らしてみたらハマった、という偶然があったこと。
ふたつめは首都圏からの距離。長野県の蓼科や軽井沢の話は別荘を持っている人からいろいろ聞いていましたが、私は基本的に一人で車を運転して移動するので、運転に疲れても代わってくれる人がいない。そうなると長野県はちょっと遠い。山梨は東京から2時間くらいと、適当な距離だったことです。
実は、その前にもカナダのバンクーバーで家探しをしていたんです。もう日本に嫌気が差して、どっか外国に出てっちゃおうと思って(笑)。幾夏かをバンクーバーで過ごして、家を買うのにいいなと思ったからです。
今は高くなりましたけど、当時のバンクーバーでは庭とプール付きの一戸建てが東京のマンションぐらいの値段で買えました。それに移民社会だからアジア人が多くて、人種差別もなく、みんな英語が下手くそなのもよかった(笑)。
この八ヶ岳南麓は緑も多くて、夏涼しく、東京から近い。「ここは、首都圏から2時間で来られるバンクーバーだ」と。
今回、出版した本『八ヶ岳南麓から』にも書きましたけど、ここは冬が明るいんです。北杜市の年間日照時間は全国有数だとか。冬でも太陽光が窓から入ってきて、日中は暖房いらずで暖かいでしょう。
鬱蒼としていて湿気の多い軽井沢より絶対いいです(笑)。
ここ山梨県北杜市のキャッチコピーが『水と緑と太陽のまち』と、全部タダのものですが(笑)。でも、住むにはこの3つがあれば充分じゃないですか。

ついに、衝動買い。土地選びは「住んで」みないとわからない
──お住まいを建てる前の土地探しの際に重要視したポイントは何でしょうか。
上野 住む土地を決めるうえで、人間関係はすごく大事です。友人の家でひと夏を過ごしたおかげで、友人の友人たちが芋づる式にくっついてきて、この土地に馴染みができちゃったんです。
その人たちが、自分たちの家をどんどん私に見せてくれました。いいところも、失敗したことも全部教えてくださるので勉強になりましたね。
もうその夏の終わりには不動産屋に飛び込んで、土地探しを始めました。旅じゃなく、やっぱり「住んでみた」ってことが良かったんです。
そのお友達の中に、定住族が相当おられました。定住族とは、移住してきてここに定住した人たちです。土地を買う前に、その方たちからいろんな知恵をいただきました。地面に近いと湿気が上がってくるから、建物は基礎をがっちりした上で建てなさいとアドバイスをもらって、基礎を高くして2階から上くらいに建てました。
このあたりに渓流はありませんが、八ヶ岳の伏流水がすごいんです。大泉、小泉と地名にあるくらいで、どこを掘っても水が出ます。
地面に密着した畳部屋を作ったら、一面に真っ青なカビが吹いた方もいます。水が豊かな反面、それぐらい湿気が多い土地なんです。
知り合った定住族の中に、ガーデンデザイナーの中谷耿一郎さんがいらっしゃって、ずっと土地探しに付き合ってくださいました。
この土地を見て「くるみの木がないからここならいいです」と。くるみの木は湿度が高い土地にあるので、植生をみて、ここは湿気が少ないと判断したわけです。
それでこの土地を買いました。いわば衝動買いですね(笑)。

「君が建てないなら、僕が建てる」と友人に土地をハイジャック
──土地を買って、すぐに別荘を建てられたのでしょうか
上野 いえ、しばらくそのままにしてありました。
この土地を買ったとき私はまだ50代でしたから、仕事も忙しかったし、「まぁそのうち考えるわ」と話していました。周りの人から「あんな土地を買ってどうすんだ」と言われました。
そうしたら、古くからの友人である歴史学者の色川大吉さん――そちらに写真もありますが、このおじさまが、「君が建てないなら、僕が建てる」とおっしゃって、さっさと家を建ててしまったんです。
びっくりしましたよ。だって建築確認書を見せてもらったら、この土地の住所は書いてあるんですけど、地権者の名前を書く欄がない。誰の土地に建ててもいいのかよって。つまり私は土地をハイジャックされたわけです(笑)。それで私が後から隣に家を建てて、隣人になったというわけです。
色川さんも勤めていた東京経済大学を定年退職されて、東京から離れたかったんでしょうね。
でも、いざ建物を建てるとなると大変でした。土地は買った時の地目が山林でした。坪単価は安くても、伐採、抜根して整地して、地下水を組み上げるのに地下50メートルまでボーリングして、浄化槽を入れて……と、結局坪単価が2、3万円ほど上積みになりました。

カウンターキッチンが大嫌い。料理する人と食べる人がカウンターで別れちゃうでしょう
──特にお住まいの中で、こだわったポイントを教えてください。
上野 こだわったのは、建物全体をワンボックスにすることですね。キッチンも部屋も、扉を開けたら建物全体がワンボックスになります。
ワンボックスにするメリットは、リビングで薪ストーブを焚くと、暖気が全館に回ること。薪ストーブの良さは定住族の皆さんから話を聞いていて、建てるときにはマストだと思っていました。
大成建設の輸入住宅で建てたんですけど、良かったのはツーバイフォー工法で柱がないから空間が広く取れること。吹き抜けになっていて、天井が高いんです。高い位置に採光のために窓をつけたので、日中は電灯が要りません。
最初は、「こんな寒冷地で吹き抜けなんて非常識だ」「暖房効率が悪くなる」と言われました。
でも実際は、窓からは太陽光が入って温かいし、ストーブの熱が上階に昇っていって、リビングの上にある寝室もむちゃくちゃ温かいんです。
輸入住宅にはモデルプランがいくつかあって、選択肢の中から決められるのはラクでしたが、いくつか設計変更もしました。日本の家はなぜだか、トイレと階段がリビングの扉の外側、玄関の脇にある。
そうなると、どうしてもトイレが寒くなる。だから、トイレはリビングのドアの内側に入れました。
階段もリビング側に入れましたから、暖気がトイレにも上の階にも回る。ほんとに全館ワンルームになるので、ストーブの効果が最大限に得られます。
いろんな人の家を見たから良かったと思うのは、たとえばキッチンですね。キッチンはできるだけ広くして、複数の人間が台所に立てるように広くしました。
カウンターキッチンが大嫌いなんです。
なぜかというと、料理をする人と食べる人がこちら側とあちら側で別れちゃうでしょう。キッチンを広くして、料理や片づけを複数の人と一緒にできるようにしました。

成り行きでおひとりさまの友人の介護責任者に
──ご高齢になったときのことを見越してつくられた部分はありますか。
上野 バリアフリーは考えました。入口のアプローチは、どうしても基礎が高いので階段ですが、1階のフロアは完全にフラット。
トイレも車椅子で入れるほど広いし、床もリビングとつながるようにフラットにしています。
これが結果的にすごく良かった。色川さんは、2016年に大腿骨骨折をして自宅療養生活になりました。
病院と施設を断固拒否されていましたから、1階の広いリビングに色川さんの介護ベッドを入れて、2021年にここで最期を迎えるギリギリまで、ご本人は自分でトイレに行けました。リビング全体がワンフロアですから、これが全部介護居室になったわけです。いいでしょう?
あと、色川さんが薪を運ぶためにベランダにエレベーターをつけたんですが、その際に車椅子が乗れるサイズにしておきました。これも大活躍しましたね。
色川さんは定年後、ここに住み始めたのが70代。コロナ禍の最中に私が最期を看取ったのが96歳でした。
私が色川さんの介護の責任者になったのも成り行きでした。色川さんはおひとりさまでしたから、一番身近な者といえば私しかいませんでした。


60平米ワンルームの静かな書斎は、至福の空間
──普段お仕事をされている仕事場や書庫はどんなところをこだわったのでしょうか?
上野 私の仕事場兼書庫もごらんになりますか?
私の仕事場は60平米のワンルームです。北欧の介護先進国では、高齢者住宅が一人あたり60平米を基準に作られていて、私も自分用にその広さを確保するのが夢でした。
天井まである作り付けの本棚は奥まで3列になってますから、本は見える範囲の3倍の量があります。
ちょっと自慢なのは、本がすべて著者名50音順に並んでいて、必ず探しだせるということ。でも、最近カオスになってきましたね(笑)。
ここで、音楽もかけずに、シーンとしたところで読み書きしているのが最高です。
仕事柄、本に囲まれて過ごすのは好きなので、図書館みたいなところで一人静かに過ごしたいと思っていた夢は実現しました。
こちらには床暖房を入れました。来客用のソファベッドがありますけど、泊まりにきた友人はみんな気持ちいいからと床に寝ちゃいます(笑)。
仕事用のデスクは北向きに設置してあります。日差しの変化を受けないノースライトです、ここはこだわりました。窓の向こうをたまに鹿が通ることもあるんですよ。
八ヶ岳南麓に理想的な土地を手に入れ、そしてひょんなことからおひとりさまの歴史家・色川大吉さんを同じ敷地に迎え入れての二拠点生活を始めた上野千鶴子さん。次回は、二拠点生活の魅力と、ここをリフォームできたら!と考えるポイント、そしてシニアライフを充実させるヒントを伺います。
【インタビュー後編はこちら】上野千鶴子さんが思う「迷い」とは?「この家に来ると暮らしがある」上野さんが考えるおひとりさまの終の棲家
(取材・執筆/牛島フミロウ 撮影/本永創太)

上野千鶴子さんの著書『八ヶ岳南麓から』(山と渓谷社)は好評発売中!
東京⇔山梨。二拠点生活のリアルを綴る
著者初の「山暮らしエッセイ集」待望の書籍化!
四季の景色や草花を楽しむこと、移住者のコミュニティに参加すること、地産の食べ物を存分に味わうこと、虫との闘いや浄化槽故障など想定外のトラブルに翻弄されること、オンラインで仕事をこなすこと、「終の住処」として医療・介護資源を考えること……。
山暮らしを勧める雑誌にはけっして出ていないことまでも語られる、うえのちづこ版「森の生活」24の物語。