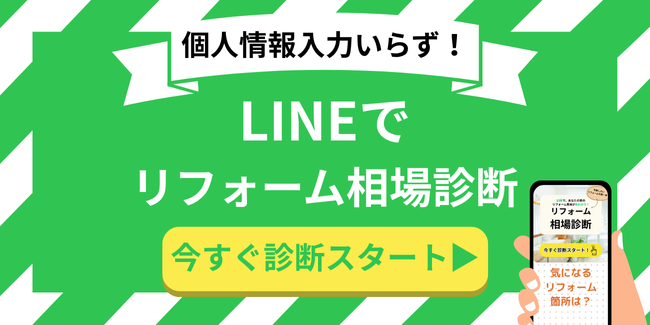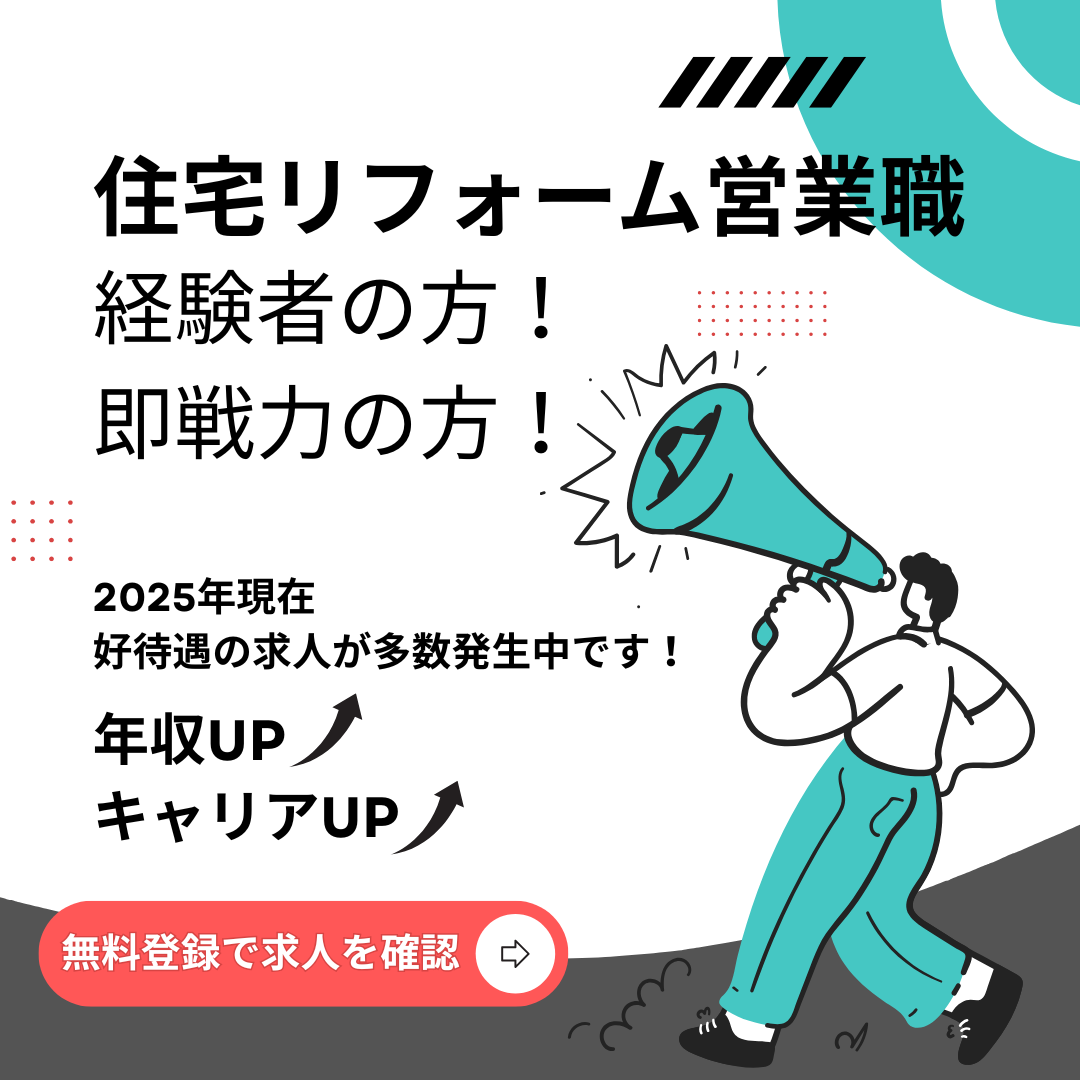75歳で長編小説は終ったつもりだった。まだ作家としての肉体は終わってない
「昔ね、書きたいものを選びに選んで、何歳まで掛かるか計算したことあるんです。そうしたら、123歳まで掛かることがわかったんです。こりゃ駄目だと思ってね(笑)」そう語るのは『弔鐘はるかなり』や『檻』などのハードボイルド小説、そして大河小説・大水滸伝シリーズや『チンギス紀』などの数々の名作を世に出してきた文壇の雄、作家の北方謙三さん。
インタビュー後編では最新エッセイ『完全版 十字路が見える』について、76歳になられた北方先生の「老い」との向き合い方、そして最新作となる長編が完結したばかりの北方先生に次回作の構想についても詳しく語っていただきます。
目次
【インタビュー前編はこちら】「住まいは『マッカーサー元帥の別荘』を改築」作家・北方謙三が語る人生の十字路とは

目次
目次
物語の芽は私の中にある。人間を書くのが物語
――北方先生は小説の「物語の芽」というのはどこで見つけるのですか?
北方謙三(以下、北方) 物語の芽は私の中にあります。突然ひらめくものではありません。
私は人間を書くのが物語だと思ってるんです。
私の中には人間としての弱さとか、強さとか、情けなさとか、いろんなものがあります。それも日によっていろいろ変わる。
それを、ひとつ摘み出して、登場人物に付与していくと、それは私じゃない人間になっていく。
元々は私である人間がどんどん成長したり、駄目になったり、悪くなったりというように。そういう風に人間として変化していけば、物語というものは自然についてくると思うんですよね。
「ハードボイルド小説」に行き詰まりを感じたんです
――ハードボイルドからなぜ時代小説に?
北方 90年から、後醍醐天皇の皇子・懐良親王を主人公にした『武王の門』で時代小説を書きはじめましたが、その前からずっと準備してました。
というのも、ハードボイルド小説というものに行き詰まりを感じたんですよ。
3作目の『檻』という作品を書いた時に、これ以上のものを書けるのかと思ったんです。緊密な世界として書けるのか、と。書けたとしても、縮小再生産になりかねない。
それはハードボイルド小説ですから、現実に準拠しているわけです。ですから拳銃を一丁手に入れるのにも大変なんです。
そうすると、やがてどんどん物語が矮小化されていく。それを避けようとすると主人公の内面に行かざるを得なくなるんですよ。そうすると紛れもなく純文学の形態になっていく。
私は10年間、純文学をやって駄目だったからエンターテインメントを書いてるのに。
それに私の書いていた作品で言うと、時間がリアリティーを侵食しますから。公衆電話が古くなったように、携帯電話だって古くなるかもしれない。時間が経つたびにリアリティーが侵食されていくんですよ。
侵食されないのは何かと考えた時に、歴史の中だと思ったんですね。

中上健次になくて、北方謙三にしかない「物語」を探し続けた20代後半
――その前に、純文学からエンターテインメントへの転機もあったわけですね。
北方 物語、エンターテインメントを書き始めたのは、友人だった中上健次の影響が大きいです。それと宮本輝ですね。
ちょうど中上が『岬』を書いたのと同じ年に、宮本は『泥の河』を書いたんですよ。どちらも、題材がないと書けない作品です。
中上は文学をやるために生まれてきた人間でした。
私は文学をずっとやっていて、結構評価されたんですけど、やはり何かが足りなかった。中上になくて俺にあるものは何かっていうことを、20代後半は探し続けてました。それが「物語」だったと。
後から考えると、物語で行こうが、文学で行こうが最終的に頂上にあるのは小説なんです。
中上がもうちょっと長く生きてくれれば、それをお互いに理解し合えたと思うんですが、彼は46歳で死んじゃいましたからね。
――時代小説に挑戦するにあたって勝算はあったんですか?
北方 そういう計算はありません。ただそこに自分の道があるのを、自分で切り拓けるかどうかですよ。
だからいろんな勉強をしました。ある先生に勧められた『日本の歴史』(中央公論)というのがあって、文学全集の厚さのものが全28冊(全26巻+別冊2巻)あるんですが、最初はそれを何度も読んで、一番引っかかるところが南北朝時代だったんです。
そこからいろんな歴史学者にお会いしました。歴史学者の網野善彦さんに書いたものを読んでいただいたら、『いいなあ小説家は。ひとつも間違ってないけど、歴史家はこんな風には書けないんだよ』と。

角川春樹の『自由に飛んでないだろ?』の一言
――題材選びのポイントは?
北方 私の場合は、独立国ですね。『武王の門』でいうと、当時の九州は征西府という独立国なんですよ。
今川了俊の征西府討伐に敗れて統治は終りますが、肥後の菊池氏に松浦水軍が関わっていたことを知った時は、唐津出身として先祖に導かれたような気分でしたよ。
――そこからさらに三国志に行かれますね。
北方 角川春樹がちょうど懲役に行く前の頃に『思う様に自由に飛んでないだろ?』と。
そこで自由に物語を書ける舞台として勧めてくれたのが三国志だったんです。いわゆる王道と覇道の2つがちゃんとある国を作ろうとしている男たちの物語です。
つかえていたものが全部下りていくように三国志を書いて、正史をずっと読みくだいて、正史の中に物語を付与して、今までとは違う三国志が出来上がりました。
中国には今も取材に行きますが、ロシアとは違いますよ。ロシアは神がいるんですが、中国には神がいないんですね。ずーっとドラスティックに、王朝が変わるたびに違う価値観になってるわけです。
島国の日本とは根本的に歩んできた歴史が違うんです。歴史っていうのは調べるといろんなところでダイナミックなものですよ。

次回作は『不屈の日本人の物語』を書かないといけない
――次の構想はさらにスケールアップですか。
北方 スケールは小っちゃくなりますね。日本は地政学的にも大変な場所にいるといわれますが『日本人は不屈であった』という物語を考えています。
元寇です。北条時宗ですよ。向こうにはフビライがいます。
歴史上、ものすごい版図を持ってしまった男の空しさのようなものと、狭い島国を命を懸けて守り抜くと誓った日本人の頑なさというかね。
年はずいぶん違いますが、その2人がどこかで通じ合っているような、そんな物語を考えています。
題材に不足してませんが、いずれ日本人を書かないといけないだろうと思っていたので。ずっと中国史を書いてきて、ちょうどいいものに出会ったと思うんですよ。
最後の長編ですから。完結まで5、6年掛かるとすると、書き終わった時には82、83歳ですよ(笑)!
――長編を書き始める心境は?
北方 懲役5、6年って感じですかね。一旦入ったら出られないということですから、覚悟とか何とかいうよりも仕方なくやるという心境です。出版社との関係性の中で書かざるを得ないという事情もあります。
でもいいんですよ。書くことは好きですから。
作家としての肉体は終わってない。書き続けたら123歳まで掛かる(笑)
――北方先生は、小説家としての「終い方」を考えることはありますか?
北方 私は『チンギス紀』で終ったつもりだったんです。完結して、これで長いのも終わりだと思いました。75歳でしたからね。
でも全然終わってない。作家としての肉体が終わってないんですよ、頭も含めてね。
だから書いてみたかった1編15枚の短編を書いて、書きながら、文体もちゃんと鍛え直しましたよ。
昔ね、書きたいものを選びに選んで、何歳まで掛かるか計算したことあるんです。そうしたら、123歳まで掛かることがわかったんです。こりゃ駄目だと思ってね(笑)。
つまり小説家はね、これを書こう、あれを書きたいなんて思ってる間はどうでもいいんですよ。書き上げたもの、それしかないんですよ。
あれを書きたかったと悔いて死んでも何の意味もないですから。

書いてて面白くなっちゃって。自分のことなんか小説に書かないから
――『十字路が見える』は初エッセイですが、エッセイは先生の中では、どういう位置づけなんでしょうか?
北方 エッセイは実は書いたことがなかったので、書いてて面白くなっちゃって。だって自分のことですから、自分のことなんか小説に書きませんからね。
自分がどっかで転んで、その落差はこれくらいで…なんてことを書いてるんですからね。それで犬が心配してたとかね(笑)。
でも、やってること結構あるなと。映画もずいぶん観ますが、ものを書くなんて考えてなかったから、メモを取るようになりましたね。
――話題作から単館作品、いろんな映画をご覧になってますね。創作物にはあえて触れるようにされてるんですか。
北方 あえてではなくて自然に、ですね。
映画は昔から好きでよく観てます。ただ感想を書くとか思ってませんでしたし、そこには面白いか面白くないかがあるだけの話ですからね。
面白いのは10本のうち2本だけだったりしますが、でも残りの8本が無駄だったかというと、そうではないわけです。
映画は映画で観たいから観る。音楽もそう。あらゆるものを聞きます。
ロックにブルース、『可愛くてごめん』も歌えますよ。
――興味は衰えませんね(笑)。
北方 衰えません(笑)。ただ、映画を観て身につまされる瞬間があったりするんですよ。
デビッド・リンチ監督の『ストレイト・ストーリー』というロードムービーで、主人公の爺さんが若者に酒を勧められる場面があります。
「年取って何かいいことあるか?」って尋ねられた爺さんは「君らみたいな若者たちにこんなに親切にしてもらえる」と答えるんです。次いで「じゃあ悪いことは?」と聞かれた答えがね。
『若い頃の自分を忘れられない』
そこは身につまされましたよ。デビッド・リンチ監督は同い年ですしね。

20歳になっちゃおうと思ってライブハウスでダイブ
――伝説の人気連載『試みの地平線』の読者とすると、エッセイであの頃の北方先生にお会いできた印象があります。
北方 そうですか。『試みの地平線』は正直にやってましたよ。教えるとか何とかいう偉そうなものではなくてね。悩みを持ってるやつの向かいに一升瓶をドンと置いて、一晩飲んで話そうぜってな感じでね。
だから若いやつの気持ちにいつもアンテナが伸びてましたよ。
それが連載をやめたら一切なくなっちゃってね。
これは何とかしなくちゃいけないと思って、ロックのライブに行くようになったんですよ。ライブはエネルギーに満ちてますからね。
下北沢のライブハウスに行って、ダイブを試みたりしてますよ(笑)。
――スゴいですね! 得られるものはどういったものですか?
北方 得られるもの? 何もないね(笑)。
私はいつか20歳の青年を主人公に小説を書かなきゃならないかもしれない。今度だってそうですよ。北条時宗は生まれた時から書かないとなりませんからね。
そうするとね、得られる得られないじゃなくて、20歳もちゃんとわかるよ、あるいはちゃんと体験してるよ、あるいは20歳になっちゃったよっていうのが必要なんです。
だから20歳になっちゃおうと思ってダイブしちゃうわけです。

どこか生活の中で「老い」受け入れているんだと思う
――老化はお感じになりませんか?
北方 どこか生活の中で受け入れているんだと思いますよ。
ホテルのそばは、結構な急坂が多いんですが、私は斜めに上ってますからね(笑)。真っ直ぐのぼると息が切れますよ。
今ね、作業中に転んで肋骨を4本まとめて折っててね、ヒビがなかなか治らない。花粉症の季節ですから、なるべく、くしゃみをしないようにして。
昔だったらケガもすることはなかっただろうに。やっぱり『若い頃の自分を忘れられない』ということです(笑)。
ただね、良いこともありますよ。
私は上腕二頭筋を断裂していて、大体筋力も60%ぐらいに落ちています。
居合抜きをやると、昔は力任せに切ってたのが、今はタイミングよくスパーンと切れるようになった。だから逆にね、見事な太刀裁きになってるんですよ。
(取材・執筆/坂茂樹 撮影/荒木優一郎)

北方謙三さんのエッセイ集『完全版 十字路が見える』(岩波書店/全4巻)は好評発売中!
かつて「小僧」と呼ばれた、全ての同朋へ。人生の歓びと切なさを綴り倒すエッセイの旅路、ここに開幕。
『週刊新潮』の人気連載が生まれ変り、全四巻の「完全版」として堂々書籍化。等身大の北方謙三が人生の歓びと切なさを語り尽くした、光溢れるエッセイ集。第Ⅰ巻には、鮮烈なスペインの旅を綴った「アディオスだけをぶらさげて」、作家人生の岐路を振り返る「薔薇と金魚と十字路」など百一篇のエッセイに加え、アメリカ最南部を舞台とした伝説の中編小説「ブルースがあたしを抱いた」を特典として収録。