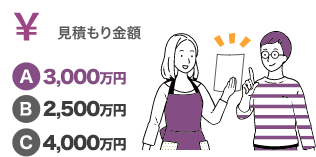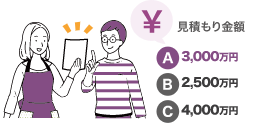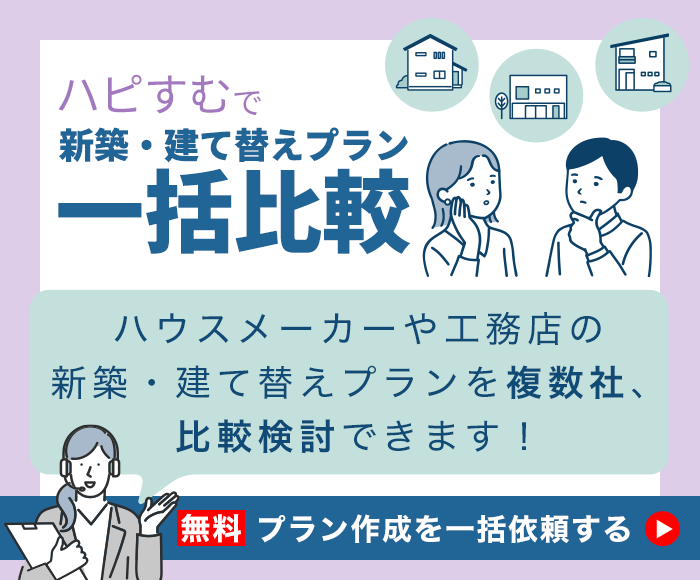2023年12月14日更新
木造3階建て住宅の耐震性やメリット・デメリットについて解説
この記事では木造3階建て住宅に関して耐震性やメリットデメリット、注意点などを踏まえて解説しています。木造3階建て住宅に関する情報が幅広く記されていますので、現在木造3階建て住宅の建築を検討されている場合は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
- 1 3階建て住宅とは
- 2 住み心地を気にしながらも3階建て住宅建設が検討されるのはなぜか?
- 3 木造3階建ての耐震性の耐震性は?
- 4 木造3階建て住宅を建てる際に必要な構造計算とは?
- 5 耐震性の高い木造3階建て住宅の構造や構法とは?
- 6 住宅の耐震性を調べる方法
- 7 耐震性の低い木造3階建て住宅の特徴とは?
- 8 木造3階建てのメリット
- 9 木造3階建てのデメリット
- 10 3階建て住宅によくある後悔ポイントとは?
- 11 木造3階建てに必要な耐震等級とは?
- 12 木造3階建ての費用について
- 13 木造3階建て住宅を建てる際の注意点
- 14 木造3階建て住宅の揺れに対する対策
- 15 3階建て住宅の住み心地をワンランク上げるホームエレベーターとは
- 16 3階建て住宅はどのような人が向いているか
- 17 高さのある3階建て住宅を建てる際のポイント
3階建て住宅とは
近ごろよく見かけるようになった3階建て住宅ですが、3階建ての家という以外に、どのような特徴があるのでしょうか。
まず、3階建て住宅は面積の狭い「狭小地」でよく建てられています。
住宅を建築する土地が狭かったり、建ぺい率の制限があったりして、2階建て住宅では足りないスペースをさらに上の階に作ることで、スペースを確保することが可能となります。
例えば、土地面積20坪、建ぺい率60%の場合、2階建てだと23坪の家にしかできませんが、3階建てにすれば35坪までスペースを確保できるのです。
また、3階建て住宅は、利便性の高い都心で多く建てられています。これは、都市部の地価が高く、家を建てようにも土地代にコストがかかってしまうことが理由です。
そのため、通勤・通学や生活のしやすさなどから利便性の高い場所で住宅を建設したいと思う方は、敢えて狭小地を購入して、住宅を3階建てにして居住スペースを確保しているのです。
ただし、狭小地に住宅を建てる場合、間取りに工夫が必要となります。コストを抑えるために建売住宅を選んだ場合、どのハウスメーカーでもだいたい同じような間取りになってしまいます。
しかし、それぞれのハウスメーカーならではの特徴もあり、工夫とアイデア次第で自分の希望する家を建てることも可能です。
住み心地を気にしながらも3階建て住宅建設が検討されるのはなぜか?

現在の住宅は2階建てが主流ですが、近年ではバリアフリーで使いやすいという理由から、平屋の人気も高まってきています。
しかしながら、3階建てを検討している人も多く、そこにはいくつかの要因があります。
たとえば、そのひとつとして挙げられるのは、2世帯住宅としてのニーズが高まっているということです。
同一フロアで間仕切りによって世帯間を区分するよりも、すっきりとフロアを分けることでお互いのプライバシーを確保することができるため、3階建て住宅が選ばれる傾向にあります。
また、どうしても広い敷地が確保できないという場合にも3階建ての住宅は注目されます。
同じ延べ床面積で見た場合、2階建て住宅よりも3階建て住宅の方が狭い土地面積で十分な生活スペースを確保することができるためです。
さらに店舗付き住宅を建築しようとしている人にとっても3階建ての住宅は検討の対象となります。
1階を全て店舗として利用したとしても、2~3階の十分な面積を居住スペースとして確保することが可能になるためです。
この記事では木造3階建て住宅について、耐震性や耐震性向上の対策などを踏まえて解説しています。
また木造3階建て住宅のメリットデメリットや費用相場についても紹介しています。
この記事を読むだけで、木造3階建て住宅に必要な耐震性や、費用の目安、メリットデメリットなど「木造3階建て住宅における知識」を幅広く身につけることができます。
設計段階で気をつけるべきポイントなども紹介していますので、現在木造3階建て住宅の建築を検討されている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
木造3階建ての耐震性の耐震性は?

地震から受けるエネルギーは建物の重量に左右されるため、重くなればなるほど、受けるエネルギーが大きくなり、受けるエネルギーが大きいほど、建物が大きく揺れることになります。
鉄骨や鉄筋コンクリート造の住宅よりも重量の軽い木造住宅は、そもそも地震から受けるエネルギー自体が小さく、揺れにくくなっているのです。
また木造3階建て住宅を建築する際には、設計の段階から綿密な構造計算が必要であることから、耐震性がしっかり確保された設計になっている状態で建築がなされています。
そのため木造3階建て住宅の耐震性は決して低くなく、基本的には安心して暮らすことが出来るレベルの耐震性を有しているといえるため、性能としては申し分ないでしょう。
木造3階建て住宅を建てる際に必要な構造計算とは?
木造住宅の構造安全性確認方法は、許容応力度計算、性能表示制度、仕様規定の3つあります。
そのうちの許容応力度計算がいわゆる構造計算です。この許容応力度計算は木造3階建て住宅や延床面積が500㎡を超える建物などで安全性を確認するために行われる計算方法です。
方法としては、はじめに建築物にかかる固定荷重や積載荷重などの長期荷重に風圧力や地震力などの短期荷重を想定して、応力と呼ばれる部材内部に生じる抵抗力を算出します。
その後、それぞれの部材がその応力に耐えられるかどうかを許容応力度と呼ばれる部材の限界点と比較していくのがこの許容応力度計算なのです。
基本的に許容応力度計算では構造計算ソフトを使用して柱や梁、接合部の全てにおいて安全性を確認します。
耐震性の高い木造3階建て住宅の構造や構法とは?
木造住宅の構法や構造には様々なものが存在しており、どの構法、構造が耐震性において秀でているのか分からない方も多いのではないでしょうか。
ここでは耐震性の高い木造3階建て住宅を建てるための構造と構法について2つ解説します。
壁式構造
壁式構造とは柱や梁などの枠組みの代わりに壁という面で建物全体を支える構造です。
床と壁が繋がっているため、地震のエネルギーを建物全体で受け止めることができます。
柱や梁などの枠組みはどうしてもそれぞれの線で建物を支える形になりますが、耐力壁という面で支える方が様々な方向からの揺れに対しても強くなります。
そのため、壁式構造で建てられている住宅は耐震性に優れた建物になっているのです。
SE構法
SE構法は従来鉄骨造の住宅に活用されている柱と梁で建物を支えるラーメン構造を木造住宅に取り入れた構法です。
柱や梁で住宅を支えるラーメン構造は耐震性があまり高くない構造ですが、SE構法はこの耐震性を補うべく、地震に強い専用の器具を使用して柱と梁や柱と床の結合を行っているため、非常に高い耐震性を有しています。
また壁で家を支える壁式構造はその構造上、壁の配置に制限があることから壁が多く、部屋の空間が分かれている住宅となってしまうケースが多いですが、SE構法は比較的自由に間取りを決めることができます。
必要な量の柱があれば建物を支えることができるため、壁式構造と比較すると大きな空間を確保することも可能です。
住宅の耐震性を調べる方法
住宅の耐震性を調べる方法には、いくつか種類があります。
新築する場合であれば耐震等級の審査を受けることから、認定された耐震等級に応じて、住宅の耐震性を把握することが可能です。
また耐震工事を専門に取り扱っている業者に依頼することで、耐震診断を実施してくれることから、このような方法でも住宅の耐震性を調べることができます。
なお、耐震等級に関しては一般的に住宅の性能評価書に記載されていますので、確認してみてください。
耐震性の低い木造3階建て住宅の特徴とは?
耐震性の低い木造3階建て住宅には、どのような特徴があるのでしょうか。
ここでは具体的に4つの特徴について解説していきます。
狭小住宅である
狭小住宅の場合、面積が小さい状態となっていることから、高さと幅のバランスが悪く、そもそも揺れやすい住宅であることを認識しておく必要があります。
支えるための土台が小さい以上、揺れに対する影響を大きく受けてしまいますので、耐震性が高いとは言えず、耐震性の低い住宅といえるでしょう。
ただし、3階建て住宅の場合には構造計算も義務付けられていることから、耐震等級3を取得できるレベルの耐震性を有していれば狭小住宅であってもそこまで心配する必要がありません。
ビルトインガレージを有する住宅である
ビルトインガレージを有する住宅の場合には、耐震性が低い可能性があります。
特に駐車場の入り口側に玄関があるような場合、その面の開口が大きく、住宅を支える部分が少ない状態となっています。
住宅を支えるポイントが少ない場合には、どうしても支えている部分に負荷が集中してしまうことから、耐震性が低くなってしまう可能性があるのです。
柱の太さや梁の太さなどで補強しているケースが多いですが、開口が多い面は基本的に強度が弱くなってしまうということを認識しておきましょう。
セットバック形状の住宅である
セットバック形状とは、1階よりも2階の方が小さいような不整形な建物のことを指します。
このような場合、上の階で受けている力を下の階へスムーズに伝達することができないため、地震に対して弱くなってしまうのです。
2階建住宅の場合であれば、このような形状であっても大して問題ありませんが、3階建住宅の場合にはこの上にもう一階層乗っている状態となっているため、力の伝達は耐震性に大きく影響します。
オーバーハング形状の住宅である
オーバーハング形状は前述したセットバック形状の逆で、1階よりも2階が大きいような不整形な建物のことです。
土台となる1階よりも上の階の方が重い場合には当然ながら、バランスが悪くなってしまいます。
バランスが悪い状態では地震で受ける力を分散させることが難しく、結果として耐震性が低くなってしまうのです。
特に上階の方が重い状態は、倒壊などのリスクが高いと言えるでしょう。
木造3階建てのメリット
木造3階建て住宅には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは具体的に5つのメリットを紹介します。
土地の有効活用が可能である
木造3階建て住宅の場合、居住スペースが3階層分あることから、狭い土地であっても十分な居住スペースを確保することができます。
そのため、限られた土地の中に駐車場や庭などのスペースも設けやすいことから、無駄なく土地を活用しやすいのです。
広い土地が確保できる場合でも、狭い土地しか確保できない場合においても土地を有効活用できるという点は大きなメリットといえるでしょう。
土地にお金をかけずに建物にお金をかけられる
前項でも解説していますが、3階建て住宅を建築する場合、狭い土地であっても十分な居住スペースを確保することができるため、あえて狭い土地を選んで建築することができます。
この場合、土地が狭い分土地代が安くなるため、建物に予算をかけられるようになります。
設備機器や住宅性能の面に費用をかけられるというのは、魅力的なポイントの1つです。
建築コストを抑制可能である
3階建て住宅というと鉄骨造や鉄筋コンクリート造で建築しようと考える方も多いですが、木造住宅の場合にはこれらの住宅と比較すると材料費や人件費が安く、建築コストがかかりません。
木造であれば、建築コストを抑制できることから、予算に余裕がない場合でも3階建て住宅を選択することが可能になるのです。
また抑えた予算で設備機器のグレードを上げるなど選択肢を増やすことができるのは木造3階建て住宅の大きなメリットです。
デザインや間取りの自由度が高くなる
3階建て住宅は3層あるということから床面積を広くすることができるため、部屋数や水回りの数など、間取りに対しての自由度が非常に高いです。
また吹き抜けを設けたり、光を取り入れるための採光窓を各所に設置することも可能で、2階建住宅と比較すると理想の間取りとデザイン性を両立させやすいです。
デザインにおいても間取りにおいても自由度が高いことから、こだわり抜いた住宅に仕上げることも可能なため、デザイン性、間取りにこだわりたい方には3階建て住宅はおすすめです。
日照や眺望が良くなる
3階建て住宅は、平屋や二階建て住宅と比較して単純に階高が高くなることから、日照や眺望がよくなります。
特に日当たりの良さに関しては、快適に生活する上でも大切な要素で、洗濯物を乾かす場合など、様々なことに影響を及ぼします。
眺望については土地の状況によってメリットにもデメリットにもなり得る項目ですが、日常生活の中で、お気に入りの場所を作ることもできるため、付加価値をつけられるという点では魅力的と言えるでしょう。
プライベート空間を確保できる
3階建ての住宅であれば階層によって使用方法を区分をすることが可能です。
1階は家族で過ごせるリビングや水回りなどの共有スペースとし、2階は寝室、3階は絵画やプラモデル製作などの趣味の部屋などとすることで、共有スペースとプライベートな空間をしっかりと分けることができます。
使用する階によって共用と個室を区分することで、プライバシーが確保できるため、 メリハリのきいた生活を送ることが可能になるでしょう。
虫の飛来が比較的少ない
2階建て住宅で頻繁に飛び交っていた蚊などの虫も、3階の高さになると飛来してくる数が減少すると言われています。
このため窓を開けて終日過ごすといった使い方も可能になるでしょう。
木造3階建てのデメリット
木造3階建て住宅のメリットについて解説してきましたが、残念ながらいくつかデメリットもあります。
ここからは木造3階建て住宅のデメリットについて5つ紹介していきます。
家事動線が不便になる
3階建て住宅という構造上、家事を行う際に階段の上り下りが必須と言えます。
水回りを1階に集約し、洗濯物を3階に干す場合や掃除用具を1箇所にまとめて収納している場合などは頻繁に階段の上り下りをしなければならず、不便さを感じてしまう可能性があります。
設計の段階で、ある程度家事動線を考えながら設計し、上り下りを軽減することができますが、いずれにしても平屋や2階建て住宅と比較すれば不便さを感じる機会は多くなってしまうでしょう。
各階の温度差がある
メリットの項目に日当たりの良さを挙げさせていただきましたが、どうしても3階と1階では日当たりに差が出てしまう恐れがあります。
特に住宅密集地のような場所では、1階にはほとんど日が当たらず、3階のみ日当たりが良い状況になってしまうというのもよくある事例となっています。
こうなってしまうと各階で室内温度に差が生まれてしまい、生活をする上で快適な状態とはいえません。
各階空調機を稼働させて温度管理を行うなどで、ある程度することが解消できますが、余計な光熱費もかかってしまうため、デメリットの1つといえるでしょう。
老後の日常生活が不便になる
前項でも触れましたが、3階建て住宅の場合避けて通ることができないのが階段の上り下りです。
特に体力が衰えた老後では体に与える負担も大きく、階段の上り下りが苦痛になってしまう可能性があります。
老後を見据えてエレベーターを設置したり、階段昇降機を設置することで階段の上り下りをしなくても良い設備を整えることも可能ですが、大きな費用がかかることから、必ずしも設置できるというものではありません。
対策が難しいため、大きなデメリットの1つと考えられます。
わずかな揺れを感じることがある
3階建ての住宅は、ある程度しなることで建物の強度を確保していることから、風や地震の影響によって、1階部分では感じないような揺れも3階部分では感じられることがあります。
建物の揺れに敏感な人にとっては、やや住み心地の悪い空間になる可能性もあるでしょう。
家族間の連絡が取りにくい
3階建ての住宅では、1階と3階のように階層が大きく異なると、お互いの所在を容易に確認することができません。
留守なのか在宅しているのかの判断もつきにくくなるため、家族間でのコミュニケーションがとりづらく感じられることがあるでしょう。
荷物の搬入が大変
大きな荷物で外出する際や買い物でかさばるものを購入した際には、それらの物品を抱えて玄関から3階の部屋まで移動することになります。
力と体力が必要になるため、高齢になると荷物の上げ下げがさらに大変に感じられるようになることも考えられます。
建築基準法の規制が厳しくなる
3階建て住宅は、建築基準法の規制が平屋や2階建て住宅と比べると厳しくなります。
そもそも土地によっては3階建て住宅を建てられない可能性があるため、事前に不動産に対して確認しておく必要があります。
また構造計算が必要であったり、非常用の進入口を設ける必要があったりと、平屋や2階建て住宅の場合には必要のない規制も増えて建てるためのハードルが上がるため、デメリットといえるでしょう。
開口部が少ないことがある
準防火地域に建つ木造3階建ての住宅は、隣地境界線との距離によって、開口部の面積制限があったり、嵌め殺し窓にしたりする必要があるので、閉塞感や息苦しさを感じることもあるでしょう。
また建物の強度の問題から、3階建ての1階部分には大きな開口部を設けることができないこともあります。
地盤改良工事が必要となるケースがある
平屋や2階建て住宅と比較して重量がある3階建て住宅は、強固な地盤の上に建築しなければならないため、現在の地盤の状態によっては地盤改良工事が必要になる可能性があります。
その際の費用は別途負担する必要があることから、気をつけなければならないポイントです。
3階建て住宅のデメリットを解消!
3階建て住宅には様々なデメリットがありますが、工夫次第で解決できることも。
たとえば、階段の上り下りは発想を変えてスキップフロアを採用することでラクになります。スキップフロアとは同じ空間の中で少しずつ段差をつけ、建物内に中2階や中3階を設ける方法です。
スキップフロアの特徴は、横ではなく縦の空間を活用する点にあります。
スキップフロアの間取りでは段差によって間仕切りを行えるので、一般的な間取りのように廊下を設置する必要がありません。その分、部屋や収納のスペースを多く取ることができます。
空間を無駄なく使うことができるので、建築面積が限られている狭小住宅では有効な方法です。
またスキップフロアを設置した場合、下の空間も有効活用することができます。
重い荷物を上の階まで運ぶのは大変という方は、下の空間を収納スペースとして活用してみるのも良いでしょう。
3階建ての住宅では大きな部屋を確保することが難しいという場合がほとんどです。
そのため、このように縦方向へのスペースを意識してみることが重要になってくるでしょう。
そうすればスキップフロアのように、3階建て住宅のデメリットを解消する方法も自ずと見えてくるのではないでしょうか。
3階建て住宅によくある後悔ポイントとは?
3階建て住宅にはメリット・デメリットがあることはすでに挙げましたが、実際に住んでみて特に困ったと思えることはどんなことなのでしょうか。
そこで3階建て住宅によくある後悔するポイントを見ていきます。
メンテナンスに手間がかかる
3階建て住宅にかかるメンテナンス費用が意外とかかることは、あまり知られていないでしょう。
3階建て住宅の多くが狭小地に建てられているため、隣の住宅建物が迫っていることがほとんどです。そのため住宅の横や裏側へと回りにくいので、劣化を発見しにくい場合があります。
劣化状態が進んでからの改修には費用がかかりますし、また足場を確保するためのスペースが十分になければ、内壁を取り壊して外壁工事をしなくてはならないことも。
もしも足場を組むだけのスペースがあったとしても、3階部分の外壁補修となれば、足場を組むための作業時間がかかり、こうした点でも費用がかさみます。
また災害に遭ったときなど、緊急時の屋根などのチェックも2階建て住宅よりは大変です。
将来的なメンテナンス費用を抑えるためには、3階建て住宅の外壁や屋根材はサビなどに強く寿命が長い素材を選ぶことが大切です。
温度管理が大変
3階建て住宅でのよくある部屋割りは、2階部分にリビングルームとキッチン、バスルーム、3階部分に寝室を配置するケースです。
このように部屋を配置すると、2階では快適に過ごしやすいものの、暑い夏や寒い冬は3階の寝室の温度管理が難しいということがよくあります。
温度管理をしやすくするためには、断熱性と気密性の高い住宅を建てることです。
断熱効果の高い住宅ならば、夏は屋外の高温を遮断して、冬は暖かい室内の温度を逃がさない効果があります。
また気密性を高めることで、さらに冬場の温かい室温を外に逃がさないようにすることができます。
このように断熱性と気密性の高い住宅の場合、一年を通して屋内の気温を安定させ快適に過ごすことができますが、建設費用が高くなるというデメリットがあります。
木造3階建てに必要な耐震等級とは?

耐震性を調べる方法でも触れましたが、耐震性の基準は耐震等級です。
ここでは木造3階建て住宅に必要な耐震等級について、建築基準法に基づく耐震等級と、望ましい耐震等級に分けて解説していきます。
建築基準法の耐震等級について
耐震等級は、1〜3の数字にて耐震性の高さを表しています。
耐震等級1は数百年に1度起こる程度の地震に対して倒壊や崩壊がなく、数十年に1度起こる程度の地震では損傷が起きない程度の耐震性があることを指します。
耐震等級2が耐震等級1の1.25倍、耐震等級3が耐震等級1の1.5倍強い地震が発生しても倒壊、崩壊しないレベルの建物のことをそれぞれ指しています。
その中で、建築基準法を満たす耐震等級は1となっており、耐震等級の中では最低限の耐震性ということになります。
そのため、建築基準法で求められている耐震性は決して高いものではなく、大型地震が起きた際には修繕が必要なものの安全に避難ができるレベルの耐震性なのです。
木造3階建ての望ましい耐震等級について
結論から申し上げると、木造3階建て住宅において耐震等級3をとっておくのは安心材料のひとつです。
木造3階建て住宅の場合、2階建て住宅と比較すると必要な耐力壁の量も多く、間取りの制限をしなければならないケースもあることから、耐震等級3は正直なところハードルが高いともいえます。
しかしながら、熊本地震のような大規模地震が2回続けて発生した場合などには耐震等級1では、想定範囲を超えていることから倒壊する可能性があり、耐震等級2や3であっても倒壊や損傷が発生してしまう恐れがあるのも事実です。
特に木造3階建て住宅は、平屋や2階建て住宅と比べて地震によって受ける影響が大きいことから、ハードルは高いものの耐震等級3が望ましいといえるでしょう。
木造3階建ての費用について

一般的に木造3階建て住宅の場合、2階建て住宅と比較して約2割〜3割程度費用が高くなります。
これは構造計算などの設計料や地盤改良など、2階建て住宅の場合には発生しない諸費用が発生することが要因のひとつです。
それを踏まえて木造3階建て住宅の費用について見ていきましょう。
まずは木造3階建て住宅の場合においても、依頼する工事業者がどのようなところかによっても大きく費用が変わります。
特に大手ハウスメーカーの場合であれば、坪単価は約60万円〜約80万円程度、ローコストハウスメーカーの場合には約45万円〜約60万円と非常に大きな差があるのです。
費用相場としては約45万円〜約80万円程度が一般的となりますが、土地の状況や設計、住宅の規模によっても大きく変動するため、必ず複数社から見積もりをもらって自分なりの費用相場を作成することが大切です。
こちらから無料で簡単に見積もりが出来ますので、ぜひハピすむの新築・建て替え費用の無料相見積もりをご利用ください。
木造3階建て住宅を建てる際の注意点
木造3階建て住宅を建てる場合、いくつか意識しなければならない注意点があります。
ここでは具体的に5つの注意点を紹介します。
家事動線の検討が必要
デメリットの項目でも触れましたが、木造3階建て住宅は階段の上り下りを計算しながら、家事動線を検討しないと、いざ暮らし始めた際に、非常に不便さを感じてしまう可能性があります。
家事をしやすい間取りということを意識して1階や2階に洗濯スペースやアイロンがけ、洗濯物を干すためのスペースをまとめるだけで、3階までの階段を上る必要がなくなり、負担の軽減に繋がります。
また各階に簡易的な掃除用具を収納できるスペースを設けるだけで、荷物を持って階段を上り下りすることを軽減できるため、家事をする上で負担を減らすことができるでしょう。
生活動線
上下の移動が多い3階建ての住宅においては、いかに生活動線をシンプルにするかということが重要です。
特に炊事~食事、洗濯~物干しなどの家事動線はコンパクトにまとめて、移動にかかる負担を軽減する配置が必要です。
リビングの配置
家族全員が利用するリビングは、各個室やトイレ、浴室とも短い移動距離ですむように、家の中心となる2階に配置した方が利用しやすくなります。
水まわりの配置場所
トイレ、風呂、洗面、炊事場などの水回りは、なるべく同一の階にまとめた方が、使い勝手が良くなります。
特に小さいお子さんがいる家庭であればリビングと同一のフロアに水回りを設置することで家事や育児の負担が軽減できるでしょう。
またトイレは、個室のある3階にも設置した方が、睡眠時の利用の際にも便利です。
老後の生活
元気なうちはあまり負担にならなかった部屋の移動も、高齢者になると苦痛に感じることもあるでしょう。
このため将来的に1階部分だけで生活できるように、あらかじめ水回りの配管を準備しておくなど、新築時から老後の生活も想定しておいた方がいいでしょう。
また階段や廊下、浴室、便所などには最初から手すりを取り付けておきましょう。
手すりは場所によって後付けできない場合もあるため、新築時に取り付けていた方が安心です。
家事動線が非効率なら家電を賢く使う
3階建て住宅でよくある問題が、家事動線が複雑になることです。
洗いあがった洗濯物を干すために階上に上がる手間は、毎日のこととなると大変な労力が必要になります。
そのような苦労を減らすためには、洗濯室に乾燥機を取り付けたり、布団乾燥機を買うなど便利な電化製品の購入も検討してみましょう。
毎日のことですから少しでも楽に生活する工夫は、間取りが複雑になりやすい3階建て住宅に必要なものです。
2階建て住宅も検討
これまで3階建て住宅のメリットとデメリットを見てきましたが、いくつかのメリットがあると同時にデメリットがあることも否めません。
そこで検討すべきことは、最初から3階建て住宅を建てると決めずに、2階建て住宅の建築も視野に入れてみるということです。
住宅の建設予定地が狭かったとしても、家族構成によっては2階建て住宅で十分に居住空間が取れることも考えられます。
利便性が悪くても広めの土地に2階建て住宅を建てたとして、居住空間は十分あり、階段も減らせ老後も快適に暮らせるならそれもひとつの選択肢です。
また、3階建て住宅のような温度調節のための大掛かりな設備が必要なく、将来的なメンテナンス費用も抑えることができます。
初期費用として2階建て住宅の方がかかるかもしれませんが、将来を視野に入れれば多くのメリットが考えられます。
2階建て住宅のメリットとデメリット、そして3階建て住宅のメリットとデメリットを総合的に判断して、どのような住宅がご自身に合っているのかを検討することが大切です。
高さ制限に注意する
用途地域という言葉をご存じでしょうか。
用途地域は都市計画法の地域地区の一つであり、用途の混在を防ぐために土地利用を定めているものになります。
実はこの用途地域ごとに建てられる建造物の高さが制限されているのです。
高さ制限においては一番制限の厳しい第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域など様々な地域ごとに定められており、一番制限の厳しい第一種低層住居専用地域の場合、高さ10m以下が基準となっています。
そのため、ハウスメーカーが扱っている3階建て住宅はほとんどが高さ10m以下となっています。
高さ制限の他にも、その他にクリアしなければならない制限が様々あるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
第一種低層住居専用地域で建てられるのは高さ10m以下の3階建て住宅
第一種低層住居専用地域とは良好な住環境を確保するために設定されるもので、地域内では基本的に店舗や工場の建設はできません。
また、住宅の建築に関しても高さや容積率など厳しい制限を受けるため、たとえ自分の土地であっても希望通りの住宅を建築できないこともあるでしょう。
たとえば、建てられる建物の高さ制限に関して、第一種低層住居専用地域内のほとんどの土地では10m以下となっています。
そのため、ハウスメーカーが提案する3階建て住宅のほとんどが10m以下となっています。
第一種低層住居専用地域内で3階建ての住宅を建てることも可能ですが、建てる場合は定められている制限を全てクリアしなければなりません。
高度斜線制限とは?
第一種低層住居専用地域内では高さ制限の他にも北側斜線規制という制限も存在します。
これは簡単に言うと地域内の土地に建物を建てる場合、建物によって北隣の土地への日照を遮ってしまわないようにするための規制です。
北隣の土地のある地点から空へ向けて定められた勾配のついた架空の斜線を引き、その線にかからない建物であれば建築することができます。
高さのある3階建て住宅を建てやすい地域は?
3階建て住宅は各階の高さに加えて基礎や屋根の分の高さも合わさるため、どうしても平屋住宅や2階建て住宅よりも高くなりがちです。
高さのある3階建て住宅を建てる場合は、高さや容積率などに関する規制が緩い土地を選ぶと良いでしょう。
規制の緩い土地を選ぶ際の基準として、特定の用途地域の中から土地を探すという方法があります。
たとえば、次のような用途地域内の土地であればあまり高さなどに関する規制が厳しくないため3階建て住宅を建てやすいでしょう。
商業地域や近隣商業地域
用途地域が商業地域や近隣商業地域であれば3階建ての建物を建てる際に高さによる制限を受けることが少ないでしょう。
これらの用途地域は駅付近や商店街といった町の中心部に設定されていることが多く、住宅系の用途地域よりも高さのある建物が多いという特徴があります。
商業地域や近隣商業地域では良好な住環境の確保ではなく、土地の高度利用を目的としており利便性の高い地域であると言えます。
商業地域や近隣商業地域では高さのある建物が密集することがあるため、高さの低い住宅を建てる場合は窓からの眺望は望めないことが多いでしょう。
また、地域内には商店や事務所といった商業施設も多く林立し、不特定多数の人や車が地域内を往来することになります。
そのため、静かで落ち着いた居住空間の確保やプライバシーの保護に問題があったり、交通事故などのリスクが高くなってしまうかもしれません。
しかし、商業地域や近隣商業地域には閑静な住宅地にはない魅力も多々あります。
たとえば、商業地域や近隣商業地域には様々な商業施設や駅などが集まっているため利便性が高い地域です。
通勤・通学に駅を利用する場合や、買い物に行く頻度が高い人、賑やかな場所が好きな人にとっては居住区として選んでも問題ないでしょう。
構造計算が必要
前述でも度々触れていますが、木造3階建て住宅を建てる場合には構造計算を行わなければなりません。
特に建築確認申請を行う際に構造計算の審査に時間を要するケースが多く、審査時間が長期化してしまうケースがあります。
その上で、2階建て住宅ではかからなかった構造計算費用も発生することになりますので注意が必要です。
防火規定に準拠する
防火地域は市街地における火災の危険を防除するために定められている地域で、商業施設の多い地域や交通量の多い場所、人通りの多い市街地などが該当しています。
そのような防火地域内に木造3階建て住宅を建築する場合、主要構造部が火災時の火熱で損傷しない、もしくは延焼防止の性能を持っている耐火建築物としなければなりません。
耐火建築物の場合には窓サッシや使用される材料が一般的なものよりも高価であることから、費用が高くなってしまう可能性があるのです。
工期の長期化に注意する
木造3階建て住宅は地盤の改良が必要なケースがあったり、そもそも建築するボリュームが大きいこともあり工期が長期化しやすい傾向にあります。
特に施工中に設計内容から変更したい箇所が出た場合には、確認しなければならないことも多いことから、長期間に渡って工事がストップしてしまう恐れがあります。
工事期間を長期化させないためには、地盤改良の必要がない土地を選び、設計で決めたプランを覆さないようにすることが大切です。
木造3階建て住宅の揺れに対する対策
木造3階建て住宅はどうしても階高が高いため、揺れを大きく感じやすいです。
ここではそんな住宅の揺れを抑えるための対策方法を3つ紹介します。
補強工事を行う
まずは木造3階建て住宅は重量が大きく、地震など揺れの原因となる事象から受ける影響が大きいということを認識しておきましょう。
前述でも触れましたが、3階建て住宅の場合には必要な耐力壁の数の問題から、高い耐震等級にすることが難しく、最低限の耐震等級になっている可能性があります。
耐震性が低いことが原因で揺れが大きい場合には、しっかり補強設計を行った上で、補強工事を行うようにしましょう。
2階及び3階の荷物を可能な限り減らす
上の階の重量が大きくなるほど、下の階との重量のバランスが崩れ、揺れやすくなってしまいます。
2階や3階などの上階に重い荷物をおいている場合には下の階に移動するだけで、揺れを緩和させることが可能な場合があります。
耐震等級が高く、上の階に重い荷物を置いている場合にはぜひ試してみてください。
バルコニーに重いものを置かない
バルコニーは住宅の外に当たる部分であるため、ここに重いものを置いてしまうことで建物の重量のバランスが崩れやすくなってしまいます。
先程紹介したオーバーハングしている住宅の耐震性が低いのと同じような状況になるため、現在バルコニーに重いものを置いていて、揺れが気になる場合にはバルコニー内の荷物を1階に移動してみると良いでしょう。
3階建て住宅の住み心地をワンランク上げるホームエレベーターとは

3階分の移動が大変に感じられる場合は、ホームエレベーターの設置を検討するのも良いでしょう。
住み心地がワンランクアップすると言われているホームエレベーターですが、どのような特徴があるのでしょうか。
ホームエレベーターとは
ホームエレベーターとは、個人住宅に設置されるエレベーターのことで、定員は2~3人のタイプが一般的です。
設置に際しては、エレベーター用の確認申請が必要です。
どのようなメリットがあるか
ホームエレベーターを設置することで、上下階の移動が容易に行えます。
車いすが使用可能なタイプの製品を活用することで、車いすでもすべての階の利用が可能になります。
また重量のある荷物も積載できるので、従来クレーンで窓から搬入していたような大型家具も手作業で搬入できます。
設置費用
住宅用エレベーターの設置費用は、約300万円~約500万円が相場です。
ただしこれは、あらかじめ室内を吹き抜け状態にして、設置を準備していた建物に取り付ける場合の費用です。
増築や解体が伴う設置の場合はさらに費用が追加されます。
また増築をして設置スペースを設ける場合は、エレベーターの確認申請とは別に建物の建築確認申請が必要になることがある点には注意しておきましょう。
メンテナンス
建築基準法の定めにより、エレベーターの所有者は定期点検を受ける義務が生じます。
このため、購入時にエレベーターメーカーと購入者がメンテナンス契約を結び、定期的な点検を行います。
点検にかかる費用の相場は、年間約4万円~約7万円です。
3階建て住宅はどのような人が向いているか
では、どのような人が3階建て住宅に向いているのでしょうか。3階建て住宅をおすすめできるのは、次のような条件に当てはまる方になります。
1軒の家を複数の用途で使いたい人
3階建て住宅はフロアごとに分断できるため、それぞれのフロアの独立性を保つことが可能です。そのため、フロアごとに役割を分けて、1軒の家に複数の機能を持たせることができるのです。
例えば、1階部分をお店や事務所に、2階以上を居住スペースにすることで、1つの建物で仕事場とプライベート空間を持つことが可能です。
また、2世帯住宅にも向いています。2階を共有部分にして、1階は親世帯のスペース、3階を子世帯のスペースにすると、各世帯の適度な独立性を保ちながら、一緒に生活することができます。
自宅にいる時間が短い人
3階建て住宅は、共働きの夫婦といった、自宅にいる時間が短い方にもおすすめです。狭小スペースに建てることが多いこともあり、その分お手入れが必要な箇所が少なくて済むからです。
新しい一戸建ての家は欲しいけれども、家事に時間を費やすことが難しいのであれば、3階建て住宅にすることで掃除などのお手入れがしやすくなるでしょう。
都市部に限られた予算で一戸建てが欲しい人
通勤に時間をかけたくない、利便性の高さが最優先という方は、どうしても都市部に住みたいと考えるでしょう。そのような方が限られた予算内で一戸建てが欲しいと思うなら、3階建て住宅がおすすめです。
3階建て住宅であれば、土地の価格が高い都市部でも、狭い土地である程度の広さの家にすることができます。便利な場所に一戸建てを建てて、家族みんなで生活することが可能になります。
高さのある3階建て住宅を建てる際のポイント

3階建ての住宅を建てる場合、隣近所に建っている既存の建物よりも高さのある建物となることがあります。
自分の家のすぐ隣に高さのある建物が建つことによって日照や景観が損なわれてしまう可能性があり、不安に感じる人もいるでしょう。
きちんとした対応を取らずに住宅の建築を進めると、実際に住み始めてから近所付き合いに支障をきたす等といったトラブルの原因となることがあります。
3階建ての住宅を建てる前には次のポイントに注意し、近隣の住人へも配慮してスムーズに建築できるようにしましょう。
3階建て住宅の施工実績が豊富な業者を選ぶ
3階建て住宅は多くのハウスメーカーや工務店が取り扱っている商品です。
しかし、その内容や品質、施工技術は各業者によってまちまちです。
3階建住宅の建築を業者へ依頼する時には住宅の設備や内容だけでなく、施工を担当する業者がどのような業者であるかについてもチェックしましょう。
3階建て住宅を建てる場合は通常は1階建て、2階建て住宅よりも高さのある建物となることが一般的です。
そのため、住宅が建つことによって日照や景観、電波受信の阻害といった問題が生じる可能性があります。
実際には建築する住宅に起因しない問題である場合でも、きちんとした挨拶や説明が無い状態で工事が行われると近隣住人の不満へと繋がってしまうかもしれません。
また、工事中は騒音や振動が発生したり、大型の工事車両が頻繁に行き来するため近隣住人に迷惑を掛けることもあるでしょう。
着工前に近隣への挨拶などを適切にこなし、住宅の建築中に電線や近隣の壁などを傷つけるといった事故が起こらないよう配慮することが大切です。
余計なトラブルを避けて質の高い住宅建築を依頼したいのであれば、施工実績が豊富な業者を選ぶと良いでしょう。
経験豊富な業者であれば住宅の品質が高いことは当然として、工事中に周辺地域への配慮もしっかりと行ってくれるはずです。
建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?
ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。
注文住宅の設計プランや費用は、施工店によって大きく異なることがあります。
そのときに大事なのが、複数社に見積もりを依頼し、「比較検討」をするということ!
実際に注文住宅を建てるには時間がかかるので、この記事で大体の予想がついた方は早めに次のステップへ進みましょう!
「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」
「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」
そんな方は、簡単に無料で一括査定が可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。
一生のうちに注文住宅を建てる機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!
一括見積もりをする