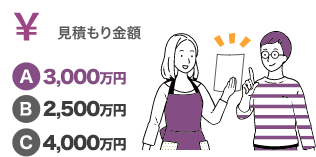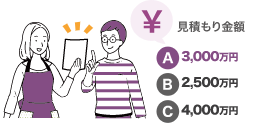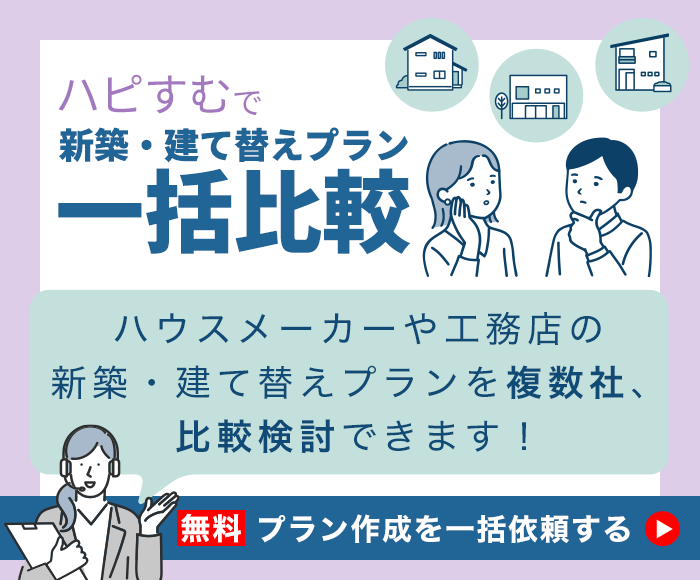2023年12月14日更新
木造軸組パネル工法のメリット・デメリットや注意点を解説
木造軸組パネル工法のメリットやデメリットはご存じでしょうか。本記事では、木造軸組パネル工法のメリットやデメリットなどの基礎知識から、木造軸組パネル工法の注意点などまで幅広く紹介します。木造軸組パネル工法を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。
「木造軸組パネル工法とはどのような工法か知りたい」
「木造軸組パネル工法のメリットやデメリットを知りたい」
木造軸組パネル工法について上記のようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
本記事では木造軸組パネルのメリット、デメリットや木造軸組パネル工法の注意点などを紹介します。
この記事を読むことで木造軸組パネル工法について知識をつけることができるため、自分の希望に近い構造で建物を建てることができるようになるでしょう。
木造軸組パネルに興味がある方や建物の構造決めに迷っている方は、ぜひチェックしてみてください。
目次
木造軸組パネル工法とは何か?

木造軸組パネル工法とは、木造軸組工法と木造枠組壁工法を組み合わせた建築の方法です。
木造パネル工法とも呼ばれます。
木造軸組工法は在来工法とも呼ばれており、柱と梁を縦横で組み合わせます。
また、木造枠組み壁工法はツーバイフォー工法とも呼ばれており、枠組みに面材を貼ります。
これを組み合わせて、縦横の軸組に対して、構造用合板を使用して建築するものが木造軸組パネル工法と言います。
この工法には木造軸組工法と木造枠組壁工法のメリットを組み合わせて持っているという特徴があります。
木造軸組工法とは何か?

木造軸組パネル工法を詳しく説明する前に、「木造軸組工法」について触れておきます。
木造住宅は大きく分けて「木造軸組工法」と「ツーバイフォー工法」の二つに分けられます。
木造軸組工法とは在来工法や伝統工法とも呼ばれ、柱を縦に立てて梁を水平に渡し、筋交いという斜めの材を入れて補強し、点を結ぶように構造物を作っていく工法です。
この木造軸組工法は日本の伝統的な工法であり、法隆寺の五重塔や歴史あるお寺や神社、古民家でも採用されている工法です。
ツーバイフォー工法とは北米から伝わった工法で、木製パネルと角材(2インチ×4インチ)で作ったパネルで壁や床、天井という面を作り、この面を組み立てて作る工法です。
ツーバイフォー工法は「木造枠組壁工法」とも呼ばれており、木造軸組工法とは異なり面を組み立てて作る工法です。
木造軸組パネル工法のメリット
木造軸組パネル工法のメリットを知りたいという方もいるでしょう。
ここでは木造軸組パネル工法のメリットを紹介します。
耐震性が高い
木造軸組パネル工法は耐力壁の筋交いを使用せずにパネルを貼る、もしくは筋交いにパネルを貼り付けることで「点」ではなく「面」で家を支えています。これによって高い耐震性を実現しています。
その他の木造軸組構法などは耐力壁の筋交いで支えているため、構造部分にかかる負荷が集中しやすくなっています。
耐震性の高い構造にしたいと考えている方には木造軸組パネル工法がおすすめです。
気密断熱性が高い
木造軸組パネル工法は気密断熱性が高いという特徴があります。
一般的に木造軸組工法は風通しが良く、湿気などに強いという特徴があります。
しかしながら断熱性や気密性には優れていません。
これは木造軸組構法のように柱と梁のみの構造では隙間が発生してしまうためです。
それに対し、木造軸組パネル工法はパネルを貼ることによって外気が侵入する隙間をできるだけ無くすことにより、気密断熱性を高くすることが可能です。
気密断熱性をさらに高めるために、パネル部分に断熱材が合わせられたものなどを使用するとさらなる性能が高まります。
省エネ性能が高い
気密断熱性が高いという特徴に関連して、木造軸組パネル工法は省エネ性能が高いという特徴も挙げることができます。
気密断熱性が高いことで、内外の熱が伝わりにくいため光熱費を抑えることができます。
この省エネ性能の高さによって、ZEH住宅にも木造軸組パネル工法が採用されています。
ZEH住宅に認定されることによって住宅ローン金利が引き下げられたりするケースもあるため、大きなメリットと言えます。
間取りの自由度が高い
木造軸組パネル工法は間取りの自由度が非常に高いという特徴があります。
これは構造自体が木造軸組工法が基本となっているため、木造軸組構法のメリットである間取りの自由度が確保されています。
また、新築時のみならずリフォームを行う際にも耐力壁を把握しておくことで、壁を壊して実現可能な間取りなど事前に知ることができます。
木造軸組パネル工法のデメリット
木造軸組パネル工法にはデメリットも存在しています。
ここでは木造軸組パネル工法のデメリットを紹介します。
ハウスメーカーによって品質に差がある
木造軸組パネル工法は施工を行うハウスメーカーによって品質に差があるケースがあります。
これはツーバイフォー工法のようにマニュアルがなく、部材の組み合わせも自由に決められることからそれに対応する施工能力が求められるからです。
これによって品質に差が発生してしまいます。
しかしメリットも大きいため、ハウスメーカーに依頼する際には木材軸組パネル工法の施工実績などを事前に確認し、依頼することをおすすめします。
建築費用が高い
木造軸組パネル工法はどのような部材でも組み合わせて建てることが可能であるものの、高品質な部材を使用すればその分価格が高くなってしまいます。
高品質な部材を使用するハウスメーカーなどでは、ローコストハウスメーカーとは価格が大きく異なってくるため、自身の予算と照らし合わせて部材を選ぶと良いでしょう。
実際、部材には耐火性や断熱性に優れているものなどさまざまな種類が存在しています。
木造軸組パネル工法とツーバイフォー工法との違い
木造軸組パネル工法とツーバイフォー工法には違いがあります。
木造軸組パネル工法は柱や梁があるのに対して、ツーバイフォー工法は柱や梁がなく、壁や天井などの面構造を基礎にして作られています。
接合部分も異なり、ツーバイフォー工法では組み立てる際に釘を使用して組み立てを行っています。
また、ツーバイフォー工法は規格化されている構造であるため、品質が安定していますが、木造軸組パネル工法は自由な箇所が多く、施工を行うハウスメーカーによって品質が異なる場合があります。
木造軸組パネル工法と木質パネル工法との違い
木造軸組パネル工法は柱や梁などがありますが、木質パネル工法にはありません。
柱や梁があることによって間取りの自由度が高く、耐震性能も高いという点が木造軸組パネルの特徴です。
一方で、木質パネル工法はツーバイフォー工法のようにパネルを使用して、気密断熱性を高める効果があります。
接合部分ではツーバイフォー工法では釘を使用しますが、木質パネル工法は接着剤を使用します。
工法ごとの費用相場と工期の比較

工法ごとにかかる費用相場や工期を知りたいという方もいるでしょう。
ここではそれぞれの工法にかかる平均的な坪数の費用相場と工期を紹介します。
| 工法 | 費用(万円) | 工期(月) |
|---|---|---|
| 木造軸組パネル工法 | 約1500万円〜約2400万円 | 約4カ月〜約6カ月 |
| 木質パネル工法 | 約1300万円〜約1800万円 | 約3カ月〜約5カ月 |
| ツーバイフォー工法 | 約1600万円〜約2000万円 | 約3カ月〜約6カ月 |
上記で紹介した費用相場と工期はあくまで目安であり、実際は施工する面積や使用する部材などによって費用が大きく変動するため注意が必要です。
また、工期に関しても建築を行う際には気候の影響や施工会社のスケジュールによって変動するため、あくまで目安となります。
具体的な工期や費用相場は施工会社に実際に相談をして把握することをおすすめします。
工法ごとに断熱性、耐震性、耐火性、防音性など比較
工法ごとの断熱性や耐震性などの性能の違いについて知りたいと考えている方もいるでしょう。
ここでは工法を選ぶ際に知っておきたい工法ごとの性能の違いについて紹介します。
断熱性
木造軸組パネル工法、木質パネル工法、ツーバイフォー工法いずれも断熱性に優れており、これは木材の断熱性が優れているためです。
しかし木質パネル工法においては断熱材がパネルの中に入った状態で工場から建設現場に届けられるため、雨によって断熱材が濡れてしまう場合や運搬中に断熱材がずれてしまうことによって断熱性が落ちてしまう可能性があります。
雨に濡れてしまうと断熱性は必ず落ちてしまうのではなく、断熱材が乾いていない状態で使用をすることで断熱性能が落ちるため、万が一濡れてしまった場合は乾燥させると良いでしょう。
耐震性
木造軸組パネル工法、木質パネル工法、ツーバイフォー工法いずれも面で住宅を支えているため、耐震性能に大きな差は生まれません。
しかし木造軸組工法は耐力壁の筋交いのみで負荷が1箇所に集中してしまうため、その分耐震性能が落ちてしまいます。
同じ木造の建物であっても負荷がかかる場所が点か面かによって耐震性能は異なるため、耐震性能の高い構造にしたいと考えている場合には木造軸組パネル工法、木質パネル工法、ツーバイフォー工法がおすすめです。
耐火性
以前はツーバイフォー工法は面が多いことから耐火性能に優れているとされていましたが、現在ではファイヤーストップ材などの最新技術によって、それぞれの工法の耐火性能差が埋まっています。
どの工法でも耐火性能はあまり変わらないため、より耐火性能を高めたいと考えている方は他の設備、建材に耐火性能の高いものを使用することをおすすめします。
防音性
防音性は木造軸組パネル工法、木質パネル工法、ツーバイフォー工法いずれも優れており、同時に気密性にも優れています。
より防音性を高めたいと考えている方は、防音性能を高めつつ断熱性も高める断熱材や窓に二重ガラスを使用することなどをおすすめします。
防音対策は吸音材を使用することでも可能であるため、ハウスメーカーなどの担当者に確認しておくと良いでしょう。
リフォームのしやすさ
リフォームのしやすさにおいては、木質パネル工法およびツーバイフォー工法は面で住宅を支えているため、構造的に移動のできない壁が多く存在しているので柔軟にリフォームを行うことができません。
それに対して、木造軸組パネル工法は柱や梁などが主な構造であるため、間取り変更などを柔軟に行うことができます。
将来的に間取りを大きく変更することが見込まれている場合には木造軸組パネル工法をおすすめします。
木造軸組パネル工法の注意点は?

木造軸組パネル工法の注意点を知りたいと考えている方もいるでしょう。
ここでは木造軸組パネルの知っておきたい注意点を紹介します。
省令準耐火構造の基準をクリアできない場合がある
木造軸組パネル工法は基本的には柱や梁などをベースとしている木造軸組工法であり、木造軸組工法は基準を満たしている部材を使用して、正しくその部材を設置していない場合には省令準耐火構造の基準をクリアできません。
省令準耐火構造とは住宅金融支援機構が定めている耐火性能の基準であり、省令準耐火構造として認められると火災保険料が安くなるというメリットがあります。
依頼するハウスメーカーによっては基準をクリアできない可能性もあるため、施工会社選びの際には注意しましょう。
構造用合板の選定が重要
耐火性能を高めるために注意したい点として構造用合板の選定が重要になります。
これは、耐火性能を高めるために、構造用合板に不燃性の高い加工が施されているかという点の確認が必要になります。
構造用合板は厚さによっても熱伝導が異なるため、厚いものを使用することによって耐火性能を高めることも可能です。
木造軸組パネル工法で住宅を建てるのに向いている人は?
木造軸組パネル工法で住宅を建築することに向いている人の特徴を紹介します。
建築材料を自分で選定したい人
木造軸組パネル工法はツーバイフォー工法などと異なり、使用する部材を自身で選ぶことが可能です。
耐火性能や断熱性能に優れている住まいにしたいと考えている方はこだわって建築材料を選ぶことができるため、自分で建築材料を選定したいという方にはおすすめの工法です。
間取りや窓の配置を自分好みにしたい人
木造軸組パネル工法は間取りや窓の配置を自分好みにすることができます。
これは基礎構造が木造軸組工法で作られているため、柱の太さや配置を設計によって柔軟に変更できるためです。
場合によっては窓のサイズも大きなものを配置することができるため、自分の希望に近い住宅にカスタマイズして作りたいと考えている方には木造軸組パネル工法がおすすめです。
住宅性能も重視したい人
木造軸組パネル工法は、木造軸組工法とツーバイフォー工法の長所を持ち合わせた工法です。
これによって高い耐震性能と気密断熱性を実現しています。
特に、住宅においての気密断熱性は暮らしやすさに直結しており、気密断熱性が高いことによって空調設備が必要なくなるケースなどもあるため光熱費の削減などにもつながります。
住宅性能を重視したいと考えている方には木造軸組パネル工法がおすすめです。
木造軸組パネル工法を取り扱っているハウスメーカー
木造軸組パネル工法は現在日本で多く使用されており、各ハウスメーカーにはそれぞれの特色があります。
ここではそれぞれのメーカーの技術の特徴や強みについて紹介します。
積水ハウス

積水ハウスはシャーウッド構法が特徴的です。
このシャーウッド構法によって鉄骨住宅に引けを取らない耐震性能を実現しており、家全体の強度が高い状態で自由な空間づくりを実現しています。
この耐久性能を実現している理由の一つには、使用されている木材と接合金物があります。
ここで使用されている構造材は厳しい基準で審査されており、素材にこだわった構造になっています。
また、木造でありながら大間口の室内空間を実現することができ、これもシャーウッド構法の耐久性によるものです。
住友林業

住友林業のビッグフレーム構法は木造でありながらも柱の間隔を極限まで拡張しており、大きな窓や広々としたリビングなど間取りの自由さを実現している構法です。
ビッグフレーム構法では大断面集成柱を主要構造として使用しており、高い耐震性を持ちながら柱や壁を少なくした開放感のある空間を作り出しています。
リフォームを行う際にも構造部分以外では間取り変更が行いやすくなっており、柱の間隔が調整されているため高いカスタマイズ性も実現しています。
タマホーム

タマホームはシンプルな設計によって安価で注文住宅を建てることが可能です。
これは施工管理や木材の調達などで無駄を省き、業務の効率化によって可能になったコスト削減によって実現しています。
また一般的に発生しやすい中間マージンをタマホームが直接施工の管理を行うことによって、コスト削減と工期短縮も実現しています。
費用を抑えて注文住宅を建てたいと考えている方にはおすすめのハウスメーカーです。
建て替え・注文住宅に対応する優良な建設会社を見つけるには?
ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。
実際に建て替えをするべきなのか、リフォームをするべきなのかを検討するためには、プロに現状を相談し、「プランと費用を見比べる」必要があります。
そのときに大事なのが、複数社に見積もりを依頼し、「比較検討」をするということ!
この記事で大体の予想がついた方は次のステップへ行きましょう!
「調べてみたもののどの会社が本当に信頼できるか分からない…」
「複数社に何回も同じ説明をするのが面倒くさい...。」
そんな方は、簡単に無料で一括査定が可能なサービスがありますので、ぜひご利用ください。
一生のうちに建て替えをする機会はそこまで多いものではありません。
後悔しない、失敗しない建て替えをするためにも、建設会社選びは慎重に行いましょう!
この記事の監修者プロフィール

atelier comado
岩本 祐子
大学卒業後、建築設計事務所にて主に住宅、公共建築、店舗、マンションの設計に10年以上関わる。
住宅においては、基本設計から監理業務まで一連のフローに携わる。
その後大手インテリア関連企業にて7年間インテリアとリノベーションをメインに業務の幅を広げる。
現在代表をしているatelier comadoでは、インテリアコーディネート、リノベーション、住宅設計をメインに活躍中。
一括見積もりをする