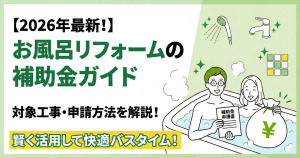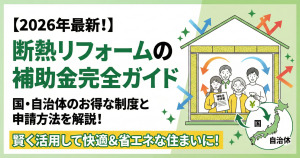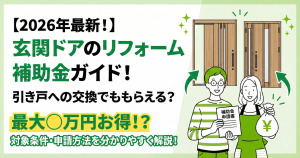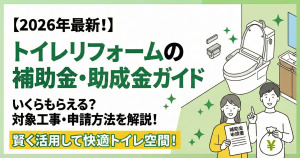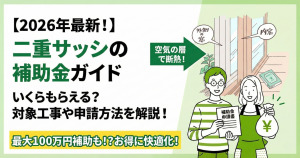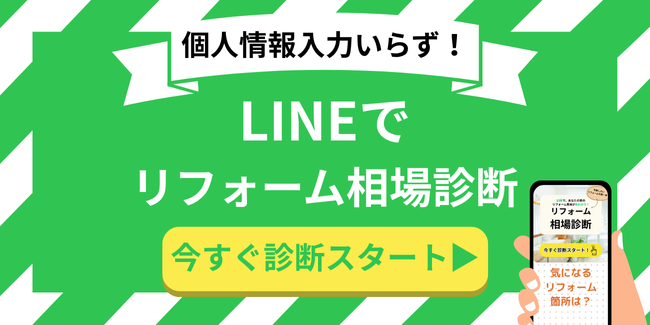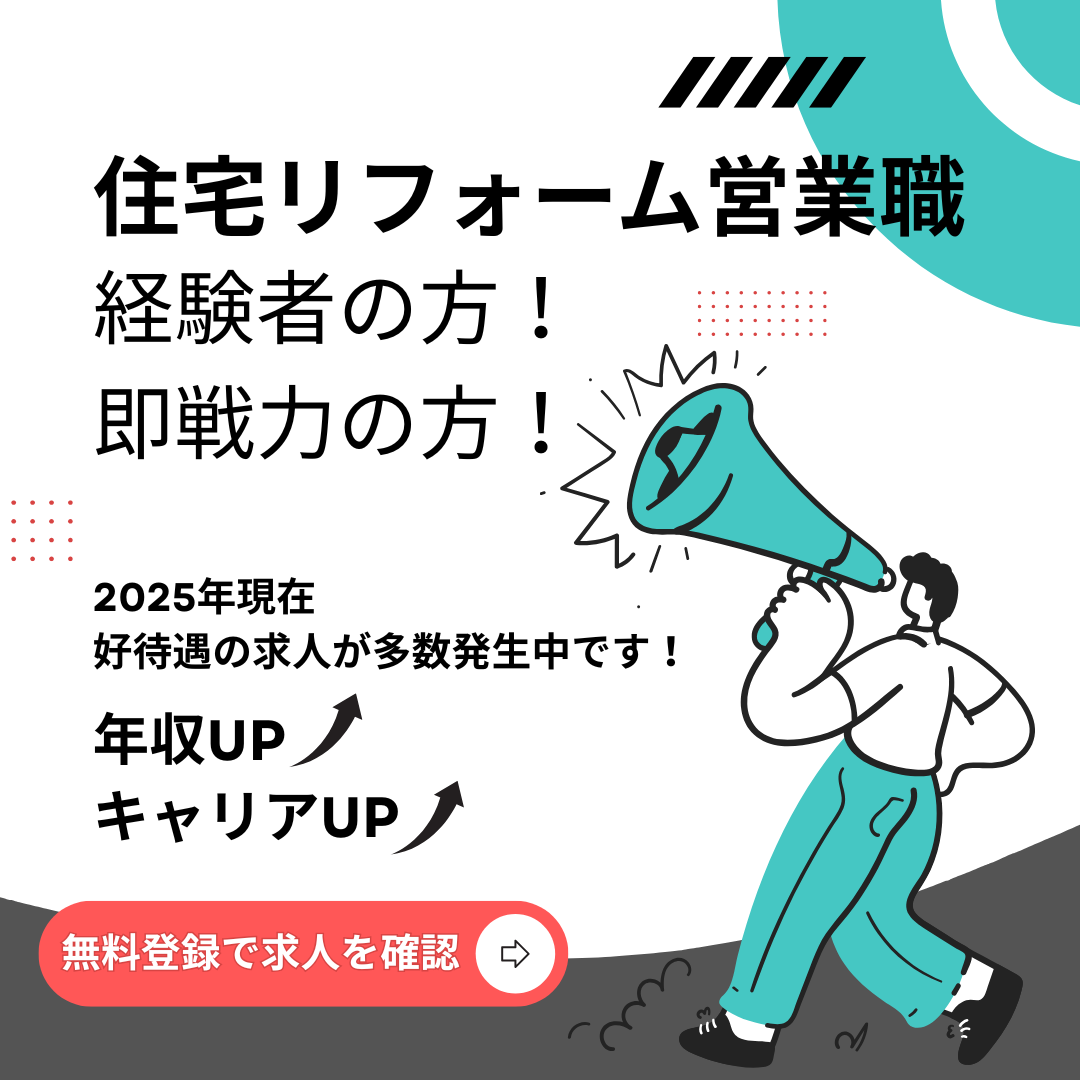-

【受付終了・2025年】先進的窓リノベ2025事業を解説!
-

【受付終了・2025年】子育てグリーン住宅支援事業を活用しよう!
-

【受付終了・2025年】長期優良住宅化リフォーム推進事業を解説!
-

【受付終了・2023年】こどもエコすまい支援事業を解説!
-

【2026年最新!】お風呂リフォームの補助金を一覧解説!国や介護保険の制度を徹底比較
-

【2026年最新】断熱リフォーム補助金の完全ガイド!国・自治体のお得な制度と申請方法を解説
-

【2026年最新!】玄関ドアのリフォーム補助金ガイド!引き戸への交換でももらえる?
-

【2026年最新】トイレリフォームで活用できる補助金・助成金制度は?いくらもらえる?
-

二重窓(サッシ)で補助金がもらえるって本当?申請方法完全ガイド【2026年】
この記事は、2025年6月時点の情報に基づいています。最新情報については、各制度の公式サイトをご確認ください。
【2025年版】「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は2種類ある!どちらを使うべき?
住まいの断熱リフォームに活用できる国の補助金制度は、大きく2種類あります。
- 既存住宅における断熱リフォーム支援事業(環境省)
- 住宅省エネ2025キャンペーン(環境省・国土交通省・経済産業省)
どちらも高性能な建材(断熱材や窓、ガラス、玄関ドアなど)を用いた断熱リフォームに対して活用できる制度です。特に「住宅省エネ2025キャンペーン」は、2025年度注目の大型プロジェクト。
本記事では、それぞれの制度について解説するとともに、どちらが自分にとって最適な制度なのか判断できるようにガイドします。「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」の活用を考えていた方も、選択肢の一つとして「住宅省エネ2025キャンペーン」も視野に入れてみましょう。
「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」と「住宅省エネ2025キャンペーン」の比較
両制度の詳細を確認する前に、まずは全体像を把握しましょう。
| 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 住宅省エネ2025キャンペーン | |
|---|---|---|
| 主な対象工事 | 壁・床・天井などへの断熱材施工、高断熱な窓・ガラスへの交換 | 開口部・躯体の断熱改修エコ設備の設置 |
| 補助額 | 戸建て住宅:120万円/戸 集合住宅:20万円/戸 | 1.上限:100万円 (先進的窓リノベ2026事業) 2.上限:60万円(※) (みらいエコ住宅2026事業) |
| 申請方法 | リフォーム発注者が手続きを行う | 制度の登録事業者が手続きを行う |
| 管轄省庁 | 環境省 | 環境省 国土交通省 経済産業省 |
| おすすめの人 | 住宅全体の断熱改修 窓を断熱改修したい人 | 断熱改修に加え 子育てや三世帯同居のため 住宅改修したり バリアフリー改修したしたい人 |
【選択肢1】既存住宅における断熱リフォーム支援事業
既存住宅における断熱リフォーム支援事業は、高性能な建材(断熱材、窓、ガラス)を用いた断熱改修に特化した補助金制度です。高性能な製品を用いて断熱リフォームするほど補助額が上がるため、住まいの性能をお得に高められます。
- 原則としてリフォーム発注者自身が申請手続きを行う
- 公募期間内に申請が必要
- 補助対象製品の採用
- 補助率はリフォーム費用の1/3
制度の概要
| 対象の工事 (いずれかを選択) | 工事内容 |
|---|---|
| トータル断熱 | 家全体を断熱材・窓・ガラスを組み合わせて断熱改修 (玄関ドアは同時に改修した場合のみ補助対象) |
| 居間だけ断熱 | 窓を用いて、居間をメインに断熱改修 |
| 住宅タイプ | 補助上限額 (トータル断熱・居間だけ断熱) |
|---|---|
| 戸建て住宅 | 120万円/戸 |
| 集合住宅 | 20万円/戸 |
補助対象製品については、以下のサイトで検索できます。
申請から入金までの流れ(事前申請)
まずは、公式サイトで公募期間を確認しましょう。
交付申請は原則、リフォーム発注者が行います。申請書類と記入例は公式サイトにて入手・確認可能です。本制度は申請書内容の事前確認は行っていないため、不明点は申請前に電子メールにてお問い合わせください。メールアドレスはこちらに記載されています。
申請書類が受理され、内容に不備がなければ交付決定通知書が発注者のもとに届きます。
交付決定通知書に記載されている「交付決定通知日」以降に、リフォーム業者と工事契約を行い、補助対象工事を行います。
工事が完了したら、完了実績報告書を提出しましょう。内容をもとに審査を行い、必要に応じて現地調査が入ることもあります。なお、完了実績報告書の提出期限は、補助対象工事の完了日から1ヶ月以内、もしくは2026年8月1日17時までです。
完了報告の内容が確認され、問題がなければ「交付額確定通知書」が届き、補助金が指定の口座に振り込まれます。工事費用の支払いを立て替え払いの委託契約したりクレジット契約にする場合は、財団への事前相談が必要です。
既存住宅におけるリフォーム支援事業は、リフォーム業者との契約・着工前に、補助金の申請と交付決定通知が必要です。工事を開始してから申請しても受理されない点に注意してください。
申請書類の準備から提出まで多くの手続きが発生するため、忙しい方や手続き関係が苦手な方は、リフォーム業者や行政書士のサポートも検討しましょう。
【選択肢2】住宅省エネ2025キャンペーン
国土交通省・経済産業省・環境省が連携する「住宅省エネ2025キャンペーン」も、断熱リフォームに活用できる補助金制度です。断熱リフォームに加えて子育てや三世帯同居がしやすい環境づくりを行う際にも活用できます。
- リフォーム業者が申請手続きをすべて代行する
- 予算が上限に達するまで、または受付期間最終日まで申請可能
断熱リフォームに活用できる事業と補助金額
断熱リフォームに活用できるのは、「みらいエコ住宅2026事業」と「先進的窓リノベ2026事業」の2つです。
| 事業名 | 補助上限額 (1戸あたり) |
|---|---|
| みらいエコ住宅2026事業 | 60万円 (必須工事3つすべて実施した場合) 40万円 (必須工事2つすべて実施した場合) |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 200万円 |
「みらいエコ住宅2026事業」は、開口部の断熱改修、壁・床・天井の断熱改修、エコ設備の設置が必須の工事です。必須工事を実施すれば、バリアフリー改修や子育て対応改修なども補助対象になります。
「先進的窓リノベ2026事業」は、窓の高断熱化に特化した制度のため、最大100万円の補助が出ます。窓の工事と同一の契約・申請に限り、玄関ドアの交換も補助対象です。
建物全体の断熱リフォームを考えている方は、2つの事業を組み合わせることでよりお得に住まいの快適性を高められます。断熱リフォームにかかる費用は高いため、まとめて工事を進めたり補助金を併用したりして、賢く自己負担額を減らしましょう。
申請から還元までの流れ(事後申請)
まずは住宅省エネ支援事業者と「工事請負契約」と「共同事業実施規約」を結びます。リフォーム業者はあらかじめ住宅省エネ支援事業者への登録が必要です。
契約を結んだら工事を開始し、完了したら発注者に引き渡しを行います。
工事の完了・引き渡しを終えたら、住宅省エネ支援事業者が交付申請を行います。ここからはワンストップで申請書の受理・審査が行われ、不備があれば各事務局から問い合わせが来ます。
交付決定後、補助金は住宅省エネ支援事業者に交付されます。リフォーム発注者には、住宅省エネ支援事業者から還元される仕組みです。
「住宅省エネ2025キャンペーン」は、契約・工事完了後に交付申請を行います。申請は住宅省エネ支援事業者が行うため、リフォーム発注者が行うのは業者選びと必要書類の準備です。既存住宅におけるリフォーム支援事業よりも格段に手続きの手間が少ないため、忙しい方や手続き関係に苦手意識があっても安心です。
【結局どっち?】あなたの状況に合った補助金の選び方
ここでは、ご自身に適した制度を判断できるよう、Q&A形式で疑問でよくある質問にお答えします。
- 申請の手間が少ないのは?
-
原則、登録事業者が申請手続きを行う「住宅省エネ2025キャンペーン」です。
- 壁や床の断熱に、できるだけ多くの補助金が使えるのは?
-
「既存住宅における断熱リフォーム制度」です。
- 断熱改修とあわせて、バリアフリー改修や子育てしやすい環境にリフォームするなら?
-
「住宅省エネ2025キャンペーン」の「子育てグリーン住宅支援事業」が適しています。バリアフリー改修や子育て対応には補助額が加算され、お得にリフォームできます。
- リビングの掃き出し窓にだけ内窓を設置するなら、どっちのほうが補助額が大きい?
-
「住宅省エネ2025キャンペーン」の「先進的窓リノベ2026事業」です。
【具体例】2つの制度のシミュレーション
どちらの制度も、建物の開口部や躯体の断熱性能向上に特化しています。しかし、同じ工事内容でも補助額が異なる場合も少なくありません。賢くお得に断熱リフォームするには、工事に対する補助額を把握することが大切です。
具体的な費用感がわかるように、シミュレーションしてみましょう。
【1】「既存住宅におけるリフォーム支援事業」の場合
| 工事内容 | 工事費用ー補助額=自己負担額 |
|---|---|
| 1.内窓の設置 (Uw・2.3以下) | 20万円ー3万円=11万円 |
| 2.窓ガラスの交換 (Uw・1.2〜1.5以下) | 20万円ー4万円=16万円 |
| 3.床の断熱改修 (20坪) | 30万円ー10万円=20万円 |
| 4.天井の断熱改修 (20坪) | 60万円ー20万円=40万円 |
【2】住宅省エネ2025キャンペーンの場合
| 工事内容 | 工事費用ー補助額=自己負担額 |
|---|---|
| 1.内窓の設置 (Mサイズ、Uw・1.5以下) | 20万円ー4.4万円=15.6万円 |
| 2.窓ガラスの交換 (大サイズ、Uw・1.5以下) | 20万円ー3.6万円=16.4万円 |
| 3.床の基礎断熱 (20坪) | 30万円ー10.5万円(対象工事の1/3)=19.5万円 |
| 4.天井の断熱改修 (20坪) | 60万円ー6万円(対象工事の1/3)=54万円 |
【要確認】2つの制度に共通するルールと注意点
ここでは、それぞれの制度に共通する併用ルールや業者選びの注意点を解説します。正しく補助金を活用するためにも、注意点を押さえましょう。
【注意点1】国の補助金同士の併用は原則NG
既存住宅における断熱リフォーム支援事業と「住宅省エネ2025キャンペーン」は、原則同じ工事箇所に対しては併用できません。例えばリビングの掃き出し窓に対して補助金を活用する場合、両方の補助金は利用できないというわけです。
ただし、工事箇所が別であれば併用できる場合もあります。「住宅省エネ2025キャンペーン」は、4事業内で工事箇所が被らなければ併用可能です。併用する際は請負工事契約は別にするなど手続きが複雑になるため、制度に詳しいリフォーム業者への相談をおすすめします。
【注意点2】地方自治体の補助金と併用できる可能性もある(東京都など)
国の補助金と、お住まいの市区町村が独自に行う補助金は、財源が異なれば併用できる可能性があります。
例えば東京都が実施する「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」は、併用可能です。公式サイトでも併用可能である旨が記載されています。東京都の制度と国のキャンペーンを賢く併用すれば、補助額をさらに上乗せできるでしょう。
ただし、クール・ネット東京が実施する他の同種制度とは併用できないため注意が必要です。
【注意点3】業者選びのポイントは制度によって違う
どちらの制度を選ぶかによって、業者に求めるべき役割は異なります。
例えば、既存住宅におけるリフォーム支援事業の申請は本人が行うため、書類作成のサポートをしてくれるか、高性能な建材に詳しいかが重要ポイントです。
「住宅省エネ2025キャンペーン」を選ぶ場合は、「住宅省エネ支援事業者」である必要があります。その上で、申請やリフォーム実績の豊富さをチェックすると、安心して依頼できるでしょう。
【Q&A】断熱リフォーム補助金に関するよくある質問
- 予算がなくなったらどうなりますか?申請はいつまで?
-
両制度とも予算が上限に達し次第、受付終了です。受付期間内であっても補助金は利用できないため、早めに申請することをおすすめします。
補助金制度の種類 申請期間 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 公募のタイミングによる(※1) 住宅省エネ2025キャンペーン 2025年3月31日〜2025年12月31日まで ※ 2025年6月現在の申請期間は「2025年3月24日~2025年6月13日まで」 なお、2025年6月18日現在「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」の公募は終了しています。しかし、公式サイトのお知らせページでは2025年6月13日時点で「次の公募は2025年6月下旬を予定している」と記載されているため、随時更新をチェックしましょう。また「住宅省エネ2025キャンペーン」の公式サイトでは、予算執行状況が公開されています。こちらもこまめに確認しましょう。
- 私の家は補助金の対象になりますか?
-
人が居住している家であれば、補助金の対象です。原則、築年数や建物の構造(戸建て/マンション)に制限はないため、すでに住んでる家であれば利用を検討しましょう。
ただし「住宅省エネ2025キャンペーン」は、対象住宅の条件を設けています。事業者が対象住宅の要件を満たしているか確認するため、まずは制度に詳しい事業者に相談しましょう。
【まとめ】自分に合う補助金制度で断熱リフォームをしよう
断熱リフォームに活用できる国の補助金制度は、「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」と「住宅省エネ2025キャンペーン」の2つです。
- 申請方法や対象工事が異なるため、自分に合うほうを選ぶことが大切
- 同じ工事内容でも補助額が異なる場合がある
- 同一工事ではない場合、補助金の併用ができる可能性がある
- 予算には限りがあるため、早めの申請がおすすめ
断熱リフォームを行うと、住まいの断熱性が高まり冷暖房費の削減や快適性アップなど、長期的なメリットを受けられます。断熱リフォームにかかる費用は決して安くはありませんが、未来への投資と考えると、実施して損はありません。補助金は経済的な負担を軽減してくれるため、積極的に活用しましょう。
どちらの制度を活用すべきか迷う場合は、両制度に詳しいリフォーム業者への相談がおすすめです。ハピすむでは、補助金制度についてわかりやすく説明し、最適な制度をご案内いたします。補助金制度に詳しい優良業者も紹介させていただきますので、まずは無料相談・無料見積りをご利用ください。