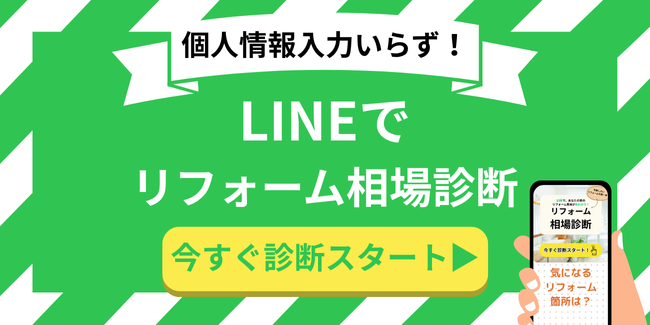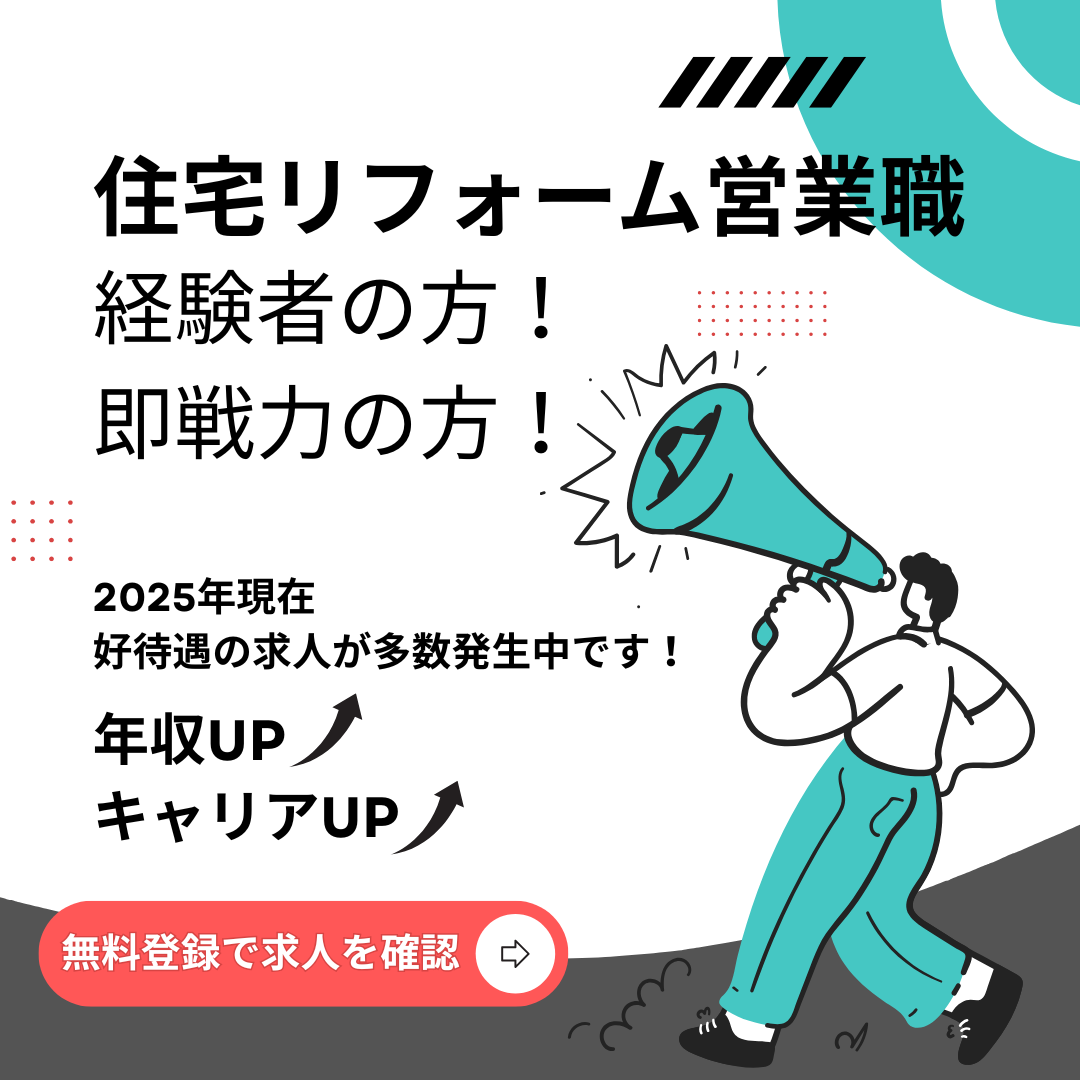目次
床下に水が溜まってしまう原因、水はどこから?
床下に水が溜まることには、いくつかの原因が考えられます。果たして水はどこからきて、床下に溜まってしまうのでしょうか。
原因についてくわしく見ていきましょう。
【原因1】配管からの水漏れ
床下浸水の原因として、配管からの水漏れが挙げられます。
排水管に亀裂が入ったり、つなぎ目が緩んだりすることで水が漏れ、知らないうちに床下に水が溜まってしまうケースもあるでしょう。
配管の劣化は築年数が経過した建物で発生しやすい傾向にあります。
しかし、築年数が浅い建物でも施工不良や地盤のゆがみによって配管がずれ、漏水につながるおそれもあるため注意しましょう。
【原因2】基礎の劣化などによる雨水の浸入
建物の基礎部分の劣化が進むと雨水が知らないうちに床下に侵入し、建物に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 基礎の継ぎ目の隙間
- 排水用の水抜き穴のふさぎ忘れ
- 通気口の位置が低すぎる
これらの問題点は簡単にチェックできない項目のため、専門業者に依頼するのがおすすめです。
【原因3】床下における結露の発生
床下に結露が発生する場合も水が溜まる原因となります。
例えば、梅雨や冬場は外気と室内の温度差が大きくなり、床下の湿気が水滴となって溜まります。
- 換気不足:床下の通気口が少ないや荷物などでふさがれている
- 断熱不足:適切な断熱材が施されていない
- 地面からの湿気:床下の地盤が土のままの状態
長年にわたって結露の発生を放置すると床下に水が溜まってしまうため、結果的に建物の耐久性低下にもつながりかねません。
【原因4】建物の地盤における排水不良
床下に水が溜まってしまう原因の一つに、建物の地盤の排水能力が低いことも床下に水が溜まってしまう原因です。
地盤の排水が悪いと雨が降った際に水が適切に流れず、建物の基礎周辺や床下に水の溜まる状態が続いてしまいます。
- 土地の傾斜が不十分
- 排水設備の不備
- 土壌の透水性が低い
なお、粘土質の土壌など水を通しにくい地盤の場合、水が地面に染み込まず溜まりやすくなるので注意しましょう。
床下浸水した状態で放置するリスク
床下は日常生活であまり気にする機会が少ないため、水漏れなどに気づかず放置してしまうケースも多く見られます。
ここでは、床下浸水した状態を放置するリスクについて解説します。
【リスク1】カビの繁殖や感染症などによる健康被害
床下浸水を放置すると湿度の高い状態が続き、カビの繁殖が進みやすくなります。
床下の木材や断熱材にカビが発生すると、カビの胞子が空気中に蔓延し、健康被害につながる可能性があります。
- アレルギー症状の悪化
- 呼吸器系の疾患
なお、湿った環境では、レジオネラ菌や大腸菌などの病原菌が繁殖しやすい傾向にあります。
特に免疫力が低い人や高齢者などは、感染症にかかるリスクが上がるので注意しましょう。
【リスク2】建物の構造体へのダメージ
床下浸水を放置すると、建物の構造に深刻なダメージを与えてしまいます。
木材が腐朽菌に侵されると強度が著しく低下し、床が沈むなどの住環境に重大な影響を及ぼしかねません。
また、基礎部分のコンクリートが長期間水にさらされると内部の鉄筋がサビて、コンクリート自体が劣化します。
その結果、ひび割れが生じて建物の強度が弱まります。
ひび割れが広がることで構造全体の耐久性が損なわれ、最終的には補修が困難になるおそれもあるため注意しましょう。
【リスク3】シロアリなどの害虫による被害
床下浸水が長期間放置されると湿気がこもり、シロアリをはじめとする湿気を好む害虫の発生するリスクが高まります。
シロアリは木材を食害して家の柱や土台に被害を与えることで、建物の耐久性や構造に深刻な影響を及ぼします。
また、シロアリはおもに木材を好んで食べるため、外見からは被害が把握しにくいという特徴があります。
さらに、表面に見える痕跡も少ないため、早期発見も困難です。
気づかずに放置していると建物全体に広がるため、大規模な修理が必要になるおそれもあります。
【リスク4】漏電の危険性
床下浸水した状態を放置すると、漏電の危険性が高まります。
浸水により電気配線が湿気を含んだ場合、電流が異常に流れてショートサーキットの発生にも注意しなければなりません。
また、感電などにより命に関わる事故などのリスクもあります。
【リスク5】建物における断熱性能の低下
断熱材は本来、湿気を避けて乾燥した状態を維持することでその性能を発揮します。
しかし、床下浸水によって断熱材が水分を吸収すると、断熱材の内部構造が破壊され、空気層が維持できなくなります。
これにより、室内の温度調整が困難になるため、結果的に建物におけるエネルギー効率の悪化につながりかねません。
このように建物全体のエネルギー効率が低下することで、冷暖房費が増加する可能性も考えられます。
床下浸水を確認する方法
建物の耐震や住環境の悪化を防ぐためにも、床下浸水は早期発見が欠かせません。
- 床下における異臭やカビの発生を確認する
- 床のきしみや、沈みこみなどをチェックする
- 壁や柱にシミや変色がないかを確認する
- 床材の隙間や膨らみをチェックする
これらのサインに気づいたら、専門業者に床下点検を依頼しましょう。
床下浸水の応急処置はこちら>>>床下浸水したらどうする?どうなる?そもそも床下浸水とは?定義、対応方法を徹底解説!
床下浸水の補修にかかる費用相場
床下浸水の補修にかかる費用の相場は、以下のとおりです。
| 工事内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 床下清掃 | 1.5万円~ |
| 床下の防腐・防カビ・殺菌消毒 | 0.7万~ (1坪あたり) |
| 防蟻処理 (シロアリ駆除) | 0.3万~1万 (1坪あたり) |
なお、床下の消毒などと同時に防蟻処理(シロアリの駆除)をすることによって、費用が割安になるケースもあります。
そのため、床下を消毒する際はシロアリ被害が見られない場合でも、同時に防蟻処理を検討しましょう。
床下浸水を補修する際の手順
一度床下浸水の被害に遭うと、泥水が床下まで入り込んでいるため、建物内で異臭やカビが発生につながりかねません。
床下浸水は、基本的に専門業者に依頼するのがおすすめです。
しかし、床下浸水を補修する際の手順については、最低限覚えておきましょう。
- 専用の排水ポンプやバキュームを使用して、床下に溜まった水を排水する
- 泥や汚れが残らないように、高圧洗浄をするケースもある
- 業務用の送風機や除湿機を使用して、短期間で乾燥させる
- 温風機は、火災や木材のゆがみの原因になるため使用しない
- 消石灰や業務用の消毒剤を使用して、カビや細菌、害虫などの発生を防ぐ
- 消毒作業は人体に危険が伴うため、防護服や専用の器具を使用する
- シロアリ対策として、防蟻処理を施すこともある
床下浸水の補修を業者に依頼する際のポイント
床下浸水の補修を専門業者に依頼する際は、押さえておくべきいくつかのポイントがあります。
あらかじめこれらのポイントを頭に入れて、万が一の場合にもスムーズに対応しましょう。
【ポイント1】早急に対応できる業者を選ぶ
床下の水分を放置すると、カビや腐朽、シロアリの発生リスクが高まります。
- 24時間対応・即日対応・緊急対応が可能
- 現地調査後すぐに作業を開始できる
- 作業のスケジュールが明確
床下浸水の補修には、まず現地調査(床下点検)が欠かせません。
数日以内に調査が可能な業者を選ぶとスムーズに補修作業へと進めます。
なお、現地調査後、見積もりを出すまでに時間がかかる業者よりも、スピーディーに対応できる業者を選びましょう。
【ポイント2】床下浸水の施工実績があるか確認する
床下浸水の補修には、専門知識だけでなくある程度の施工実績が欠かせません。
- 施工事例を公開しているか確認する
- 床下浸水の補修経験が多いか確認する
- 口コミや評判をチェックする
- 創業年数や業歴を確認する
また、信頼できる業者は公式サイトやSNS等で過去の施工事例を公開しているケースが多く見られます。
そのため、施工写真のビフォーアフターや作業の流れなどから、対応が適切か確認しましょう。
【ポイント3】乾燥・防カビ・消毒まで対応可能か確認する
床下浸水の補修では、単に水を排出するだけでは不十分です。
乾燥・防カビ・消毒まで徹底して対応できる業者を選ぶことが、建物を長持ちさせるために重要です。
- 乾燥まで徹底的に行ってくれる
- 防カビ処理まで対応してくれる
- 消毒や防蟻(シロアリ対策)の対応がある
床下浸水後の乾燥方法はこちら>>>床下浸水の効果的な乾燥方法が知りたい!
【Q&A】床下浸水の放置に関するよくある質問
- DIYによる床下浸水の補修は不可能?
-
DIYによる床下浸水の補修は、専門的な技術を持っていれば不可能ではありません。
しかし、DIYでの床下浸水の補修は極めて難しく、適切な処置をしなければ被害の拡大するリスクが高いといえます。そのため、専門業者に補修を依頼するのがベストです。
DIYが難しい理由- 水が溜まっている場所に入り込めない
- バケツや家庭用ポンプでは排水が追いつかない
- 自然乾燥では2週間以上かかる
- 家庭用の消毒剤では効果が限定的
- 処理が不完全で後からカビが再発する
- マンションの床下で水漏れが発生した際の対処法は?
-
マンションの床下で水漏れが発生した際の対処法は、以下のとおりです。
マンションの床下で水漏れが発生した際の対処法- 水漏れの原因を特定して応急処置する
- 管理会社や専門業者にすぐ連絡する
- 被害状況を記録しておく
- 修理後は床下を徹底的に乾燥・消毒する
なお、後々のトラブルを防ぐために、水漏れの状況を写真や動画で記録しておきましょう。これらは、修理費用の負担を巡るトラブルが発生した際の証拠として使えます。
- 床下浸水は火災保険や補助金・助成金制度の対象になる?
-
床下浸水は、各種条件を満たすことで火災保険や補助金・助成金制度の対象になるケースがあります。
火災保険は「水災補償」が付帯されていれば、床下浸水に適用できることもあります。地方自治体によっては、床下浸水の復旧に関する補助金や助成金が支給されるためチェックしましょう。
地方自治体における床下浸水の補助金・助成金制度のポイント- 「災害救助法」が適用となる地域では、公的支援の受けられる可能性が高い
- 「被災者生活再建支援制度」では、床下浸水の対象外になることが多い
- 床下に水漏れが発生した際の乾燥方法は?
-
床下に水漏れが発生した際の乾燥方法は、以下のとおりです。
床下に水漏れが発生した際の乾燥方法- 床下の通気口を全開にする
- 扇風機や送風機を使って強制的に空気を流す
- 可能なら床下点検口を開け、家の窓も開放する
- 床下に除湿機を設置し、湿気を吸収させる
- 新聞紙や炭を敷くと、水分を吸収しやすい
- 乾燥剤(シリカゲル・炭・消石灰)をまいて湿気を抑える
なお、自然乾燥だと2週間以上かかることもあるため、積極的に送風機を活用しましょう。
床・フローリングリフォームの業者選びで後悔しないために
必ず相見積もりを複数取って比較しましょう!
なぜならリフォームの費用・工事方法は、業者によって大きく異なるからです。
とはいえ「信頼できる業者が分からない」「何度も同じ説明をするのが面倒」と踏み出せない方もいらっしゃると思います。
そのような方こそハピすむの一括見積もり比較を活用しましょう!
大手ハウスメーカーから地場の工務店まで、審査を通過した1000社以上の中から、まとめて見積もりを依頼できます。
また、ハピすむでリフォームされた方には最大10万円分の「ハピすむ補助金」もご用意しています。
詳細はこちら>>>ハピすむ補助金プレゼントキャンペーンの流れ