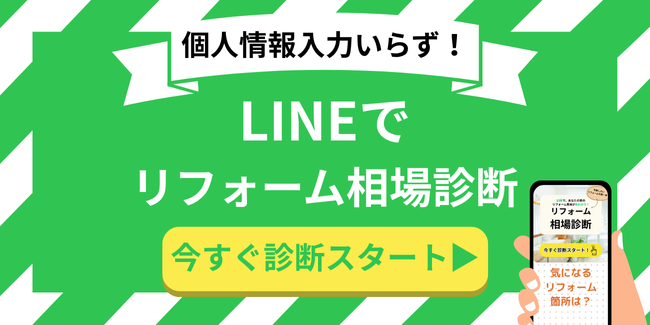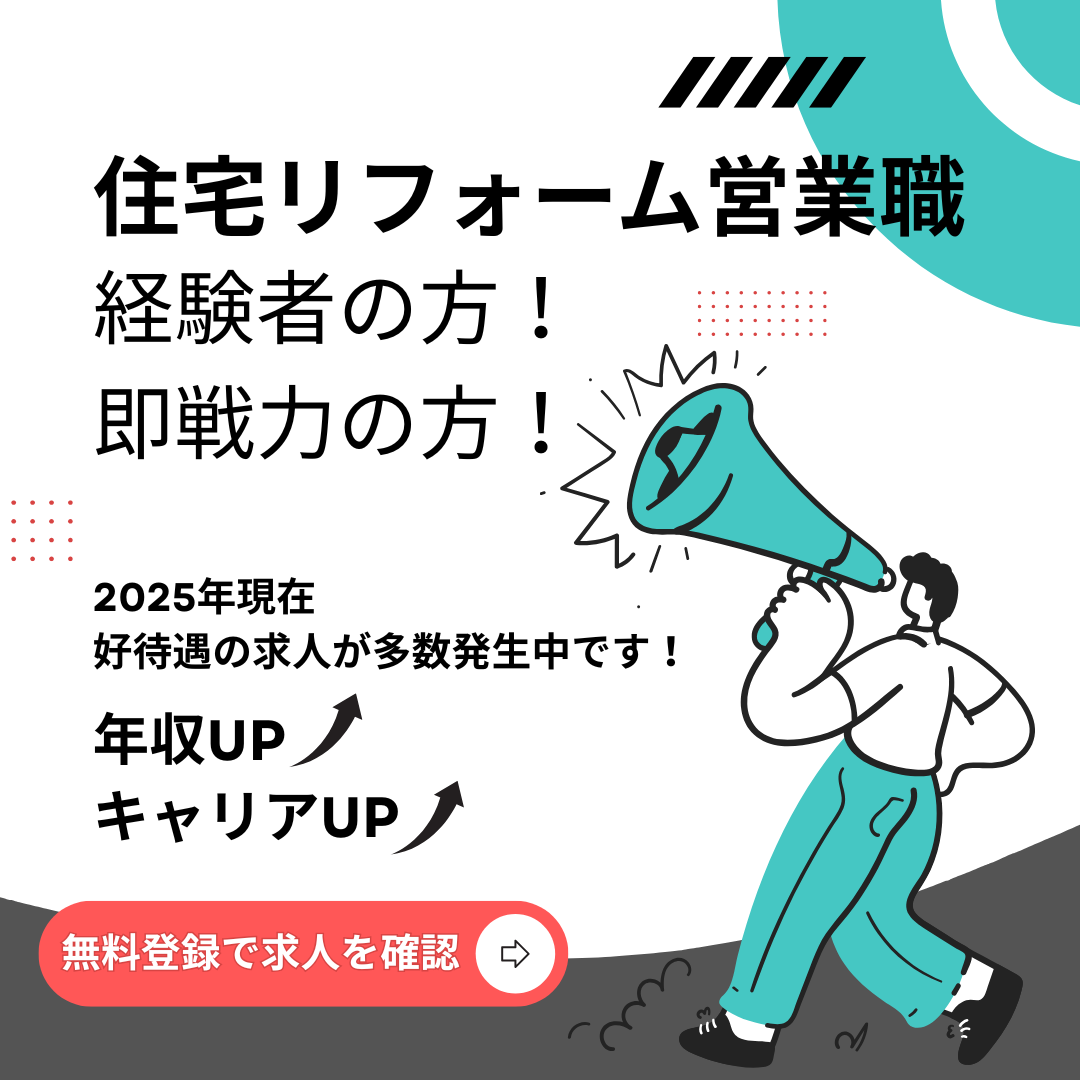目次
【家の傾き、補助金で直せる?】まずはセルフチェックで確認しよう
家の傾きに気づいたとき、「自分の家は補助金の対象になるのか?」と疑問を持つ方もいるでしょう。本記事では、その答えを探る手助けとして、まずはセルフチェックから始めていきましょう。Q&A形式の簡易診断を用意したので、ご自身の状況が支援制度の対象にあたるか、一つずつ確認してみましょう。
なお、このセルフチェックはあくまで目安にすぎません。詳細な補助要件や手続きの流れについては、本記事でわかりやすく解説していきます。
【Q1】家の傾きの原因は、国や自治体が指定した自然災害ですか?
「被災者生活再建支援制度」が使える可能性があります。次のQ2へ。
自然災害以外が原因の場合に使える補助制度があります。「災害が原因ではない場合に使える補助金」の章へ進んでください。
【Q2】お住まいの市区町村から「罹災証明書」を取得しましたか?
「被災者生活再建支援制度」の対象となる可能性があります。「国の制度」の章をチェックしてください。
補助金申請には罹災証明書が必要です。「ステップ1:罹災証明書の申請方法」で詳細を確認しましょう。
【災害後の羅針盤】家の傾き被害から生活再建までの5ステップ
家の傾きという非常事態に直面したとき、何から行動すればいいのかわからない方も多いでしょう。
ここでは、家が傾いてから再建までの道筋を5つのステップにわたって解説します。ステップごとの「やること」「注意点」をチェックすれば、万が一災害によって家が傾いても冷静に行動に移せるはずです。まずは身の安全を確保し、それから再建に向けて行動しましょう。
【ステップ1】全ての支援の起点「罹災証明書」を申請する
まずは、災害の内容や規模、被害の程度などを表す罹災証明書を申請します。罹災証明書を取得しなければ、災害による補助金を受け取れません。
ここでは、罹災証明書をどこでどのように申請するのか、準備すべき書類や必要な手順をわかりやすく解説します。申請手続きは自治体によって若干異なりますが、基本的な流れを押さえておけば、落ち着いて進められるでしょう。
申請窓口と手続きに必要なもの
罹災証明書の申請は、被災した住宅の所在地を管轄する市区町村役場(防災担当課など)が窓口になります。
- 罹災証明書交付申請書:役所の窓口や自治体の公式サイトで入手できる
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など、申請者の現住所が確認できるもの
- 被害状況がわかる写真:次の見出しで解説するポイントを押さえて撮影したもの
- 印鑑:認印で可の場合が多い
- 委任状(※):申請者本人が自署・押印したものと、代理人の本人確認書類
※ 代理人が申請する場合
自治体によって必要書類が異なる場合があります。書類に不備がないように、必ず事前に公式サイトなどで確認しましょう。
申請の前に!被害状況を写真で記録するポイント
家の片付けや修理を始める前に、まずはしっかりと被害状況を写真で記録しておきましょう。これは罹災証明の申請や保険請求の際に重要な証拠になります。
以下の症状が見られる箇所は、写真に残しておきましょう。
- 家の全景(※1):建物全体の傾きや歪み ・基礎:ひび割れ・ズレ(※2)
- 外壁:亀裂、剥がれ、外壁材の浮きや割れ
- 屋根や窓:瓦のズレや破損、窓ガラスの割れやサッシの歪み
- 敷地内:擁壁やブロック塀の亀裂や倒壊、地面の亀裂や液状化の跡
※1:4方向から
※2:ひび割れの幅がわかるようにメジャーを併用するのがおすすめ
- 壁や天井:壁紙の破れや亀裂
- 床:傾きがわかるようにビー玉などを置いた写真や、床材のたわみ、割れ
- 柱や梁:構造部の傾きや亀裂
- 建具:ドアやふすま、窓が閉まらない、または隙間ができている状態
申請から交付までの流れ
まずは申請書に必要書類を添えて被災した世帯主が、市区町村の窓口やオンラインで罹災証明書の申請を行います。
自治体の調査員が住宅の傾きや損傷状況を確認するために訪問します。立ち会いを求められる場合もあるため、前もって当日の流れを確認し、日程を調整しましょう。被害状況がわかる写真や図面を用意しておくと、調査がスムーズです。
現地調査の結果で、住宅の被害程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」などに判定されます。傾きの角度や生活への支障の程度が判断基準になるため、普段の生活の中で困難に感じている部分もあれば伝えておきましょう。
判定結果に応じた罹災証明書が発行されます。なお、申請から交付まで数週間〜数ヶ月かかるのが一般的です。早めに行動して、以前の生活を取り戻しましょう。
【ステップ2】利用できる公的支援制度の全体像を把握する
次に、どのような制度が利用できるのか全体像をつかむことが大切です。中心となるのは国の「被災者生活再建支援制度」。これは住宅被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と、再建方法に応じて加算される「加算支援金」の段階的な支援制度になっています。
さらに多くの自治体では、上乗せ補助や住宅ローンの利子補給など、独自の支援も用意されています。公的支援は複数あるため、まずは「〇〇県 家の傾き 補助金」「お住まいの市区町村 家の傾き 補助金」などで検索して公式サイトを確認し、必要に応じて自治体の窓口に相談しましょう。
【ステップ3】地震保険・火災保険など民間の備えを確認する
公的制度と並行して、民間の保険も確認しましょう。地震による傾きであれば、「地震保険」が対象となります。地震保険は火災保険とセットで契約する必要があるため、現在の加入状況を確認しましょう。
また、地震以外でも台風や土砂崩れ、洪水など自然災害による傾きであれば、火災保険に付帯している「水災」「風災」補償が適用される場合があります。加入中の補償内容をチェックして、適用されるものはあるか一度確認しましょう。
【ステップ4】専門家に見積もりを依頼し修理費用を把握する
補助金や保険の給付額を確認したら、実際の修理費用を把握しましょう。まずは建築士や地盤調査の専門業者に依頼して、家の傾き具合とその原因を特定します。調査結果に基づいて見積もりを取り寄せ、リフォームを進めましょう。
見積もりは、複数社から取り寄せることをおすすめします。価格はもちろん、工法の妥当性を比較検討することが大切です。また、家の修繕で後悔しないためには、業者選びがカギとなります。
- リフォーム実績や資格がある
- 補助金・保険の知識が豊富
- 地元での評判が良い
信頼できる業者に依頼して、良好な関係性を築いていきましょう。
【ステップ5】修理・建て替え・売却など最適な再建方法を判断する
補助金・保険金・自己負担の総額を把握できたら、最終段階に移ります。選択肢は大きく分けて「修理」「建て替え」「売却」の3つ。
被害が軽ければ補修で済みますが、傾きが大きく再発のおそれがある場合は建て替えの検討も必要です。修理費用の捻出が難しい場合は、修理せずに「現況のまま売却」するという現実的な選択肢もあります。最終的な判断は、家族の将来設計や生活環境を踏まえて決めましょう。
【国の制度】被災者生活再建支援制度のすべて(支援内容・金額・期間)
ここでは、国が実施する「被災者生活再建支援制度」の、具体的な支援内容や金額、申請期間を解説します。被災者生活再建支援制度は、自然災害で住宅に重大な被害を受けた世帯を支える国の制度です。
支援金を最大限に活用するには、制度の仕組みを正しく理解し、必要な手続きを期限内に行うことが不可欠です。支援内容を整理しながら、生活再建の第一歩を踏み出す参考にしてください。
補助金の対象となる被害認定基準(全壊・大規模半壊など)
被災者生活再建支援制度を利用するには、まず自治体から「罹災証明書」の交付を受け、一定以上の被害認定(全壊・大規模半壊・中規模半壊など)を得ることが条件です。
| 被害の程度 | 被害の認定基準 | 損害割合 |
|---|---|---|
| 全壊 | ・外壁または柱の傾斜が1/20以上 ・床上の全面が1メートルまで地盤面下に潜り込んでいる | 50%以上 |
| 大規模半壊 | ・不同沈下していて傾斜が1/60以上1/20未満 ・床の全面が地盤面下に潜り込んでいる | 40%以上50%未満 |
| 中規模半壊 | 規定なし | 30%以上40%未満 |
これまで対象外だった「中規模半壊」も、2020年の法改正により一部の条件下で支援対象となりました。被害程度に応じた認定の違いを理解して、制度を正しく活用していきましょう。
支援金の具体的な金額(基礎支援金・加算支援金)
被災者生活再建支援制度の支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の2種類あります。
| 被害の程度 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 全壊 | 100万円 | 200万円 (建設・購入) | 300万円 |
| 100万円 (補修) | 200万円 | ||
| 50万円 (賃借) | 150万円 | ||
| 大規模半壊 | 50万円 | 200万円 (建設・購入) | 250万円 |
| 100万円 (補修) | 150万円 | ||
| 50万円 (賃借) | 100万円 | ||
| 中規模半壊 | なし | 100万円 (建設・購入) | 100万円 |
| 50万円 (補修) | 50万円 | ||
| 25万円 (賃借) | 25万円 |
ただし、これらはあくまで生活再建の支援であり、工事費用の全額をカバーするものではない点には注意しましょう。
補助金の申請期間と手続きの流れ
被災者生活再建支援制度には、厳しい申請期限が設けられています。
- 基礎支援金
- 加算支援金
期限を過ぎると申請はできず、補助金も受け取れなくなります。ただし、災害の内容によっては延長されることも少なくありません。
実際に2024年の能登半島地震では、特例措置により基礎支援金の申請期限が2026年2月2日まで延長されています。補助金を利用する際は、まず申請期限内であるか確認しましょう。
【事例解説】2024年能登半島地震から学ぶ補助金活用術
2024年1月に発生した能登半島地震では、被災者生活再建支援制度に加え、各自治体が独自の支援策を展開しました。国の支援制度だけではなく、地元の支援を組み合わせると、被災者の負担を大幅に軽減することができます。支援制度は今後も実施されることが期待できるため、基礎知識として情報を把握しておきましょう。
ここでは、実際に使われた制度や補助金の活用例を2つ紹介します。
【液状化被害に特化】被災宅地復旧支援事業(新潟市)
新潟市では、液状化による被害を受けた宅地の復旧費用を支援する「被災宅地復旧支援事業」を実施しています。補助対象経費は最大1,200万円、補助率は3分の2、上限金額は766万6千円と、非常に手厚い内容です。
2025年6月時点で申請期限が令和8年2月末頃まで延長されているため、今から行動すれば申請に間に合う可能性があります。
特に地盤の緩い地域にお住まいの方は、家の傾きがないか、地盤に問題がないかなど、この機会にチェックするのもよいでしょう。
【初期費用を軽減】代理受領制度(石川県志賀町)
石川県志賀町では、補助金を業者に直接支払う「代理受領制度」が導入され、被災者の初期費用負担を大幅に軽減しました。
代理受領制度は自治体がリフォーム業者へ補助金を直接支払うことで、申請者は自己負担分のみを用意すれば、工事が始められるという仕組みです。工事費用を立て替える必要がないため、金銭的な余裕がなくてもなるべく早く工事を進められます。
ただし、制度の有無は自治体ごとに異なるため、事前の確認が必要です。
>>石川県志賀町 令和6年能登半島地震の被災により被害を受けた宅地の復旧支援事業
家の傾きの基準を3つの制度で徹底比較(公的支援・保険・法律)
家の傾きを評価する基準は一つではなく、「公的支援」「地震保険」「法律」という3つの異なるモノサシが存在します。制度を利用する前に、まずはそれぞれの目的や傾きの基準、受け取れるお金の種類などを把握しましょう。
| 比較項目 | 公的支援 | 地震保険 | 法律(契約不適合責任) |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 被災者の生活再建を支える | 契約に基づき損害を補填する | 売主等の法的責任を追及する |
| 適用される場面 | 国指定の自然災害 | 地震・噴火・津波 | 売買・建築契約時の隠れた欠陥 |
| 傾きの基準(例) | 1/20の傾斜 | 1度の傾斜 | 6/1000の勾配 |
| 受け取れるお金 | 支援金 | 保険金 | 修繕費用・損害賠償金 |
| 手続きの起点 | 罹災証明書の申請 | 保険会社への連絡 | 売主・施工会社への通知 |
| 重要な注意点 | 申請期間に厳格な期限あり | 火災保険とセット加入が必須 | 時効に注意 |
この表からわかる通り、「家の傾き」と一口に言っても、補助・補償の制度ごとに目的・対象・基準が大きく異なります。自身や自宅の状況に応じて、どの制度に該当するかを正しく見極めることが、適切な支援を受ける第一歩です。
災害が原因ではない場合に使える補助金はある?
ここまで解説してきた補助金制度は、すべて自然災害が原因で家が傾いた場合を対象としています。
しかし、経年劣化や地盤沈下などの自然災害以外の理由でも、活用できる補助金制度はあります。ここで別の支援策を確認し、家の状態と照らし合わせて使える補助制度を探してみましょう。
耐震性を高めるなら「耐震改修補助金」
傾き修正と同時に耐震性を向上させる場合、「耐震改修補助金」が使える可能性があります。多くの自治体で導入されており、特に1981年5月以前に建てられた旧耐震基準の木造住宅が対象になることが一般的です。補助金額や対象条件は地域によって異なるため、最新の情報は「リフォーム支援制度検索サイト」や自治体の公式サイトなどを活用して調べましょう。
自治体独自の支援を探す「リフォーム支援制度検索サイト」
国が実施する補助金制度以外にも、お住まいの市区町村が実施する独自の補助金制度が家の傾き修繕に利用できる場合があります。
- リフォーム支援制度検索サイトを活用する
- 該当する支援分類と支援方法にチェックを入れる
- 都道府県を選択する
- 補助金制度を見つける
支援分類を選択すると、利用できる支援制度を簡単に探すことができます。リフォーム支援制度検索サイトでは家の傾き以外にも、一般的なリフォームに活用できる補助金制度を探すときにも役立ちます。ぜひ今後のリフォームにも生かしましょう。
家の傾きを直す工事の種類と費用相場
家の傾きを修正する工事には、原因や症状に応じたさまざまな工法があり、それぞれに費用や工期の目安があります。
ここでは、主要な3つの工法と相場目安を解説します。受け取れる補助金額と、ここで説明する工事費用を比較することで、自己負担額を把握でき、無理のない資金計画を立てられるでしょう。
【工法1】土台上げ工法(ジャッキアップ)
土台上げ工法は、基礎はそのままにジャッキで家を持ち上げ、傾きを修正した後に基礎との隙間へモルタルなどを充填する方法です。
| 費用 | 200万〜500万円 |
| 工期 | 2週間〜1ヶ月 |
| メリット | ・工事費用が比較的安い |
| デメリット | ・基礎の補強が難しい ・工事中は住めない |
土台上げ工法は、基礎に問題がない場合に適用できる工法です。建物を持ち上げて行われるため、工事中暮らす仮住まい先を見つける必要があります。
【工法2】薬液注入工法(グラウト注入工法)
薬液注入工法は、基礎の下に特殊な薬液を注入し、地盤を強化して建物を持ち上げる方法です。最大約5cmまで傾きを修正できます。
| 費用 | 300万〜600万円 |
| 工期 | 1〜2週間 |
| メリット | ・住みながらの工事が可能 ・コンパクトな機械を使用するため、狭い土地でも採用しやすい |
| デメリット | ・十分に浸透せず、固化しきらない場合がある ・地盤の状態によっては施工が難しい |
薬液注入工法は住みながら工事が可能なため、普段通りの生活を送れるのがメリットです。ただし、地盤の状態によっては施工が難しい場合もあります。地盤に不安がある場合は、地盤調査を行いましょう。
【工法3】アンダーピニング工法
アンダーピニング工法は、基礎の下に杭を打ち込み、深い支持地盤で建物を支える工法です。
| 費用 | 500万〜1,000万円 |
| 工期 | 1ヶ月〜3ヶ月 |
| メリット | ・再沈下のリスクを減らせる ・住みながらの工事が可能 |
| デメリット | ・施工できる業者が少ない ・残土処理が必要になる |
耐震補強も期待できるため、傾きが大きい場合や長期的に安心して住まいたいケースに向いています。
【Q&A】家の傾きの補助金に関するよくある質問
- 家の傾きを放置するとどうなりますか?
-
家の傾きを放置すると、健康や住環境に深刻な影響を及ぼします。めまいや頭痛、吐き気といった平衡感覚の異常からくる不調に悩まされるかもしれません。
また、建物自体も傷み、ドアや窓が開かなくなったり、壁に亀裂が生じたり、地震時に倒壊するリスクも高まります。「傾いた家」は資産価値も大きく下がり、売却が困難になるケースもあります。 - 経年劣化が原因でも補助金は出ますか?
-
経年劣化や地盤沈下が原因の傾きについては、国の「被災者生活再建支援制度」の対象外です。
しかし、自治体が独自に実施している「耐震改修補助金」や「リフォーム助成金」であれば、条件を満たすことで利用できる可能性があります。お住まいの地域で利用できる補助制度については、「災害が原因ではない場合に使える補助金はある?」の章を参考にしてください。 - 補助金の申請は自分でできますか?難しい場合は?
-
補助金の申請は自分でもできます。しかし、必要書類が多く、手続きが複雑に感じられることもあります。そのような場合は、書類作成をサポートしてくれるリフォーム業者に相談してみましょう。また、自治体の窓口や行政書士などの専門家に依頼することで、スムーズに進められるケースもあります。困ったときは一人で抱え込まず、頼れる支援を活用しましょう。
【まとめ】家の傾きは専門家へ早めに相談して、被害拡大を防ぐリフォーム計画を立てよう
本記事では、地震などの自然災害によって家が傾いた場合に利用できる「被災者生活再建支援制度」や、災害以外が原因でも使える自治体の補助制度について詳しく解説しました。
家の傾きは、生活の安全や資産価値に大きく影響する深刻な問題です。被害が小さいうちに対応すれば、補修費用も抑えられ、生活への影響も最小限にできます。まずは罹災証明書の取得や保険の確認など、できることから始めましょう。
制度利用をはじめ、家の傾きを直すには信頼できる業者と連携することが大切です。ハピすむでは、安心できる暮らしを取り戻すために、支援制度の説明から優良業者の紹介、相見積もりのお手伝いまでサポートさせていただきます。ぜひお気軽に無料相談・無料見積もりをご利用ください。
耐震リフォームの業者選びで後悔しないために
必ず相見積もりを複数取って比較しましょう!
なぜならリフォームの費用・工事方法は、業者によって大きく異なるからです。
とはいえ「信頼できる業者が分からない」「何度も同じ説明をするのが面倒」と踏み出せない方もいらっしゃると思います。
そのような方こそハピすむの一括見積もり比較を活用しましょう!
大手ハウスメーカーから地場の工務店まで、審査を通過した1000社以上の中から、まとめて見積もりを依頼できます。
また、ハピすむでリフォームされた方には最大10万円分の「ハピすむ補助金」もご用意しています。
詳細はこちら>>>ハピすむ補助金プレゼントキャンペーンの流れ