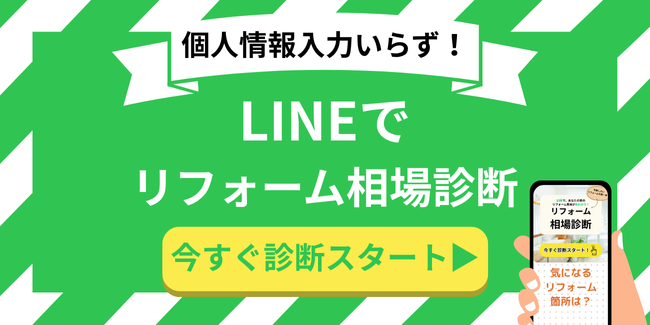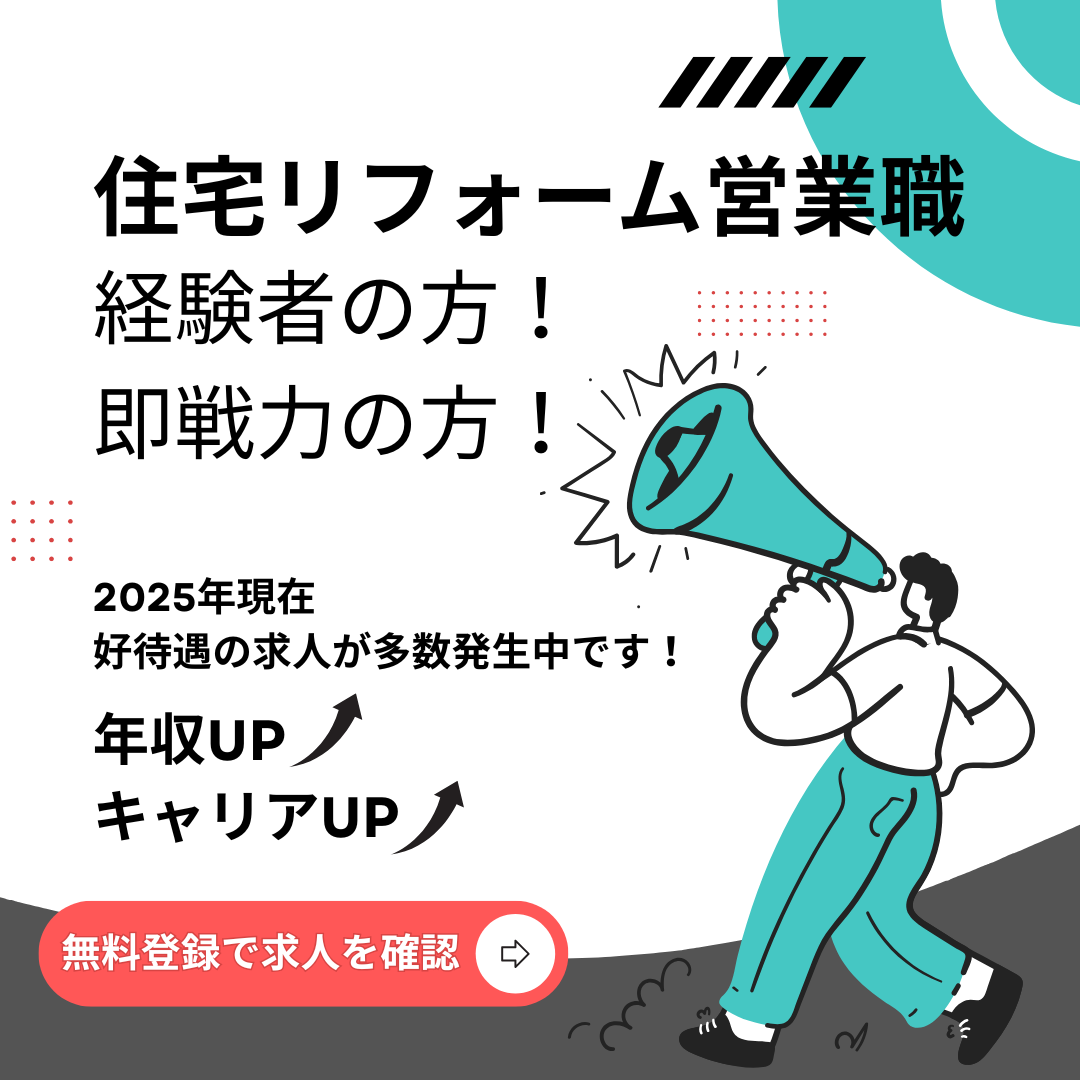目次
- 1 【後悔しないために】マンションの床リフォームで最初に確認すべき2つの絶対ルール
- 2 マンションにおける床リフォームの工法
- 3 マンションで使われる床材の種類
- 4 【工法・床材別】マンションの床リフォームにかかる費用
- 5 【2025年最新】マンションの床リフォームで活用できる補助金制度
- 6 マンションの床リフォームの流れ
- 7 DIYによるマンションの床リフォームをおすすめできない理由
- 8 マンションの床をリフォームする際の注意点
- 9 マンションにおける床リフォームの施工事例
- 10 【Q&A】マンションの床リフォームに関するよくある質問
- 11 【まとめ】マンションの床構造や遮音等級を確認して適切なリフォームを実現しよう
【後悔しないために】マンションの床リフォームで最初に確認すべき2つの絶対ルール
マンションの床リフォームは、部屋の雰囲気を変えたり、防音性を高めたりするのに効果的です。しかし、一戸建て住宅と異なり、マンションには集合住宅ならではの「2つの絶対ルール」があります。このルールを無視して工事を進めると、近隣住民との騒音トラブルに発展したり、最悪の場合、工事のやり直しが必要になったりするといったリスクがあります。
費用やデザインの話から始めるのではなく、まずは今回ご紹介する2つのルールを確認し、マンションの床リフォームを成功させましょう。
【ポイント1】管理規約の防音ルール(遮音等級)
マンションの床リフォームを検討する際、まず確認すべきは「管理規約」です。多くのマンションでは、階下への騒音トラブルを防ぐために、使用できる床材の防音性能が定められています。
この防音性能の基準となるのが「遮音等級(L値)」です。
L値は、床に物を落としたときの「軽量床衝撃音」と、子どもが走り回るような「重量床衝撃音」の2種類に分かれています。L値の数値が小さいほど遮音性が高く、高性能な床材であることを示しています。
一般的に、多くのマンションでは「L-45」以下であることが推奨されています。この基準を満たさない床材を使用すると、工事のやり直しは必要になるおそれもあるため注意が必要です。管理規約に記載されたL値の基準をクリアできる床材を選ぶことが、トラブルなくリフォームを進めるための絶対条件です。
【ポイント2】床の構造(二重床と直床)
マンションの床構造には、「二重床(※1)」と「直床(※2)」の2種類があります。どちらの構造かによって、リフォームにかかる費用や工法、そして選択できる床材が大きく異なります。
コンクリートスラブの上に支持脚を立て、その上に床材を張る構造のこと
コンクリートスラブの上に、直接クッション性のある床材を張る構造のこと
二重床は、床下に配管や配線を通すスペースがあるため、床下の劣化を確認・補修しやすく、リフォームの自由度が高いのが特徴です。床を叩くと軽い音がしたり、サッシとの間に大きな段差があったりすることで、簡易的に判別できます。
一方、直床は床下に空間がないため、リフォームの際に配管や配線の移動が難しいという制限があります。なお、工事費用は比較的安く抑えられる傾向にあります。
リフォーム会社に見積もりを依頼する際は、まずご自宅の床がどちらの構造であるかを把握しておくことが欠かせません。
マンションにおける床リフォームの工法
マンションの床リフォームを検討する際、費用や工期に大きく影響するのが工法の選択です。主な工法には、「張り替え」と「重ね張り」の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、現在の床の状態や予算に合わせて最適な方法を選びましょう。
【工法1】張り替え
張り替え工法は、既存の床材をすべて剥がし、新しい床材を張り直す方法です。張り替えのメリットは、仕上がりが段差なく新品同様になること、そして床下の劣化状態を確認しながら補修できるという点です。また、床材の選択肢が豊富にあることも特徴です。
一方で、デメリットとしては、解体・処分費がかかるため費用が高額になりやすいことが挙げられます。さらに、下地調整が必要な場合は、通常よりも工事期間が長くなることも。
床のきしみや劣化が激しい場合や、床暖房を新たに設置したい場合には、張り替え工法が適しています。
【工法2】重ね張り
重ね張り(上張り)工法は、既存の床材の上に新しい床材を重ねて張る方法です。重ね張りの最大のメリットは、解体費が不要なため費用が安価に抑えられる点と、工事がスピーディーに完了する点です。
一方、デメリットとしては、床が少し高くなるため、部屋の境目などにわずかな段差ができる可能性もある点が挙げられます。また、既存の床が激しく劣化している場合は、この工法を選択することができません。
重ね張り工法は、費用と工期を抑えたい方や、既存の床の状態が良い場合に最適な選択肢といえるでしょう。
マンションで使われる床材の種類
マンションの床リフォームでは、さまざまな種類の床材から選ぶことが可能です。それぞれの床材が持つ特徴を理解し、リビングや水回り、玄関など使用する場所や目的に合わせて最適なものを選びましょう。
床材を選ぶ際は、遮音性や耐久性、デザイン性、費用などを比較検討することが重要です。
【種類1】複合フローリング
複合フローリングは、合板や集成材などの基材の上に、天然木を薄くスライスしたものを貼り合わせて作られた床材です。天然木の美しい木目や質感を楽しみつつ、合板を基材としているため、反りや膨張といった木の欠点を軽減できるのが大きなメリットです。
複合フローリングは、価格と性能のバランスが良く、デザインも豊富であるため、マンションの床材として最も一般的に使用されています。また、傷や汚れに強い塗装が施されているものが多く、手入れがしやすいのも特徴です。
なお、複合フローリングを選ぶ際は、マンションの管理規約で定められた遮音等級(L値)に対応した製品を選ぶことが欠かせません。
【種類2】無垢フローリング
無垢フローリングは、1本の天然木から切り出した木材を加工した床材です。木が本来持つ調湿効果があり、時間とともに風合いが増す経年変化を楽しめるのが最大の魅力です。足触りが柔らかく、温かみがあるため、リラックスできる空間を演出します。
一方で、天然素材のため高価であり、メンテナンスも必要となります。また、反りや収縮が起こりやすく、マンションの遮音規定を満たすのが難しい点にも注意が必要です。
【種類3】クッションフロア
クッションフロアは、塩化ビニール製のシート状の床材です。安価で耐水性が非常に高いため、水回りやトイレなどによく使われます。また、クッション性があり、足への負担を軽減できるというメリットもあります。
木目や石目など豊富なデザインがあり、フローリングやタイルの雰囲気を手軽に取り入れられるのも魅力のひとつ。一方で、傷やへこみにはやや弱いというデメリットもあるため、クッションフロアを選ぶ際は、使用箇所を十分に検討する必要があるでしょう。
【種類4】フロアタイル
フロアタイルは、塩化ビニール製のタイル状の床材です。耐久性が非常に高く、傷に強いのが特徴です。リアルな石目調や木目調のデザインが豊富にあり、高級感のある空間を演出できるため、玄関などで使われるケースも少なくありません。
クッションフロアと比べると硬さがあり、本物の素材に近い踏み心地になります。一枚一枚を床に貼り付けていくため、部分的な貼り替えがしやすく、メンテナンス性も高いのが魅力です。
【種類5】カーペット
カーペットは、繊維を織り込んだり編み込んだりして作られた床材です。防音性と保温性に優れており、足元が冷えやすい場所や、階下への足音が気になる場合におすすめです。足触りが良く、転倒時の衝撃を和らげる効果もあります。
一方で、ホコリが絡まりやすく、こまめな掃除が必要になることや、液体をこぼすと染みになりやすいという懸念点もあります。
カーペットには、床全体に敷き詰めるロールカーペットと、部屋の一部に敷くラグなどがあり、素材によって手触りや機能性が異なるため、用途に合わせて選ぶことが重要です。
【工法・床材別】マンションの床リフォームにかかる費用
マンションの床リフォーム費用は、「選ぶ床材」と「施工方法」によって大きく変わります。以下に、6畳あたりの費用目安を工法と床材別にまとめました。
| 床材 | 張り替え | 重ね張り |
|---|---|---|
| 複合フローリング | 10万〜20万円 | 8万〜15万円 |
| 無垢フローリング | 15万〜35万円 | 12万〜30万円 |
| クッションフロア | 5万〜10万円 | 4万〜8万円 |
| フロアタイル | 6万〜12万円 | 5万〜10万円 |
| カーペット | 5万〜10万円 | 4万〜8万円 |
既存の床材の上に新しい床材を重ねて貼る「重ね張り工法」は、既存の床材を撤去する手間がないため、「張り替え工法」よりも費用を抑えることが可能です。
なお、既存の床構造が「二重床」か「直床」かどうかによっても費用は変動するため、事前に見積もりを取得して正確な金額を把握するとよいでしょう。
【2025年最新】マンションの床リフォームで活用できる補助金制度
マンションの床リフォームで利用できる主な補助金制度として、「子育てグリーン住宅支援事業」が挙げられます。この制度は、子育て世帯や若者夫婦世帯などの全世帯が、高い省エネ性能を持つ住宅の取得やリフォームを行う際に利用できる国の支援策です。
マンションの床リフォームでこの補助金を活用するには、床の張り替え工事に加えて、以下の工事を組み合わせる必要があります。
- 床の断熱改修
- 開口部の断熱改修
たとえば、床の張り替えに加えて、床の断熱工事と内窓の設置を組み合わせることで、補助金の対象となる場合があります。
ただし、補助金は予算に限りがあり、早期に終了する可能性があるため、利用を検討している場合は早めの相談をおすすめします。また、この制度は新しい情報が随時更新される可能性があるため、国土交通省の公式サイトなどで最新情報を確認することが重要です。
マンションの床リフォームの流れ
マンションの床リフォームは、適切な手順を踏むことでスムーズに進めることができます。ここでは、計画段階から工事完了までの一般的な流れを7つのステップで解説します。
まずは、どんな床にしたいのか、予算はどのくらいかなど、大まかな計画を立てます。インターネットや雑誌で情報を集め、理想のイメージを具体化しましょう。
複数のリフォーム会社に連絡し、現地調査と相見積もりを依頼します。2〜3社に依頼するのが一般的です。
依頼した業者が自宅を訪問し、床の状態や広さなどを確認します。この調査に基づき、詳細な見積書が提出されます。
各社の見積もり内容や担当者の対応、これまでの施工事例などを比較検討し、信頼できる一社を選んで契約を交わします。
工事日程が決まったら、上下左右の部屋の住人に挨拶に伺い、工事期間中の騒音や注意点について伝えておきましょう。
契約内容に基づき、リフォーム工事がスタートします。
工事が完了したら、業者と一緒に仕上がりを確認します。問題がなければ引き渡しとなり、リフォームは完了です。
DIYによるマンションの床リフォームをおすすめできない理由
マンションの床リフォームを検討するにあたり、DIYで費用を抑えたいと考える方もいるかもしれません。しかし、マンションの床リフォームをDIYで行うことは「仕上がりが悪くなる」「床の構造自体にダメージを与えてしまう可能性がある」などのリスクを伴います。したがって、安易に手を出さず、専門知識を持つプロに依頼することを強くおすすめします。
これから解説するDIYによるリスクを理解し、適切な方法でリフォームできるよう、プロへの依頼を検討しましょう。
【理由1】素人では仕上がりの品質が不安定
マンションの床リフォームをDIYで行う場合、最も大きなリスクのひとつが「仕上がりの品質がプロに比べて劣ってしまう」ことです。専門的な知識や経験がないまま作業を進めると、床鳴りがしたり、凹凸や段差ができてしまうなどの問題が発生するかもしれません。
これらの問題は、住み始めてから気づくことが多く、一度施工してしまうと後から修正するのが難しくなります。結局、やり直しのための費用や手間がかかり、かえって高くつくこともあるため注意が必要です。
【理由2】管理規約に適合した材料選定は専門知識が必要
マンションの床リフォームをDIYで行う場合、最も難しい点のひとつが「適切な材料の選定」です。一戸建て住宅とは異なり、マンションには集合住宅特有のルールや構造があり、これを無視して材料を選んでしまうと、さまざまな問題が発生する可能性もあります。
たとえば、マンションの管理規約で定められている「遮音等級」の基準を満たさない床材を使用すると、騒音トラブルに発展したり、最悪の場合には再工事を求められたりするリスクがあります。
また、ご自宅の床が「二重床」と「直床」のどちらの構造であるかによって、適した床材や工法を選ぶ必要があるほか、部屋の広さに対して、どれくらいの量の床材が必要かを正確に計算することも求められます。
これらの理由から、マンションの床リフォームはDIYではなく、プロに相談して適切な材料を選定することが重要です。
【理由3】下地へのダメージが懸念される
マンションの床リフォームをDIYで行う場合、専門的な知識や工具がないまま作業を進めると、床の下地を傷つけてしまう危険性があります。
特に、既存の床材を剥がす「張り替え工法」では、専門の工具を正しく扱わないと、床の下地(コンクリートスラブ)に亀裂を入れてしまったり、配管や配線を傷つけてしまったりする可能性があります。これらの下地へのダメージは、後に床鳴りや床の沈み込みといった大きな問題に発展するかもしれません。
最悪の場合、構造体であるコンクリートにダメージを与えてしまうと、大規模な補修工事が必要となり、当初の予定をはるかに上回る費用と手間がかかることになります。そのため、専門的な知識と技術を要する床リフォームは、プロの業者に依頼することが最も安全で確実といえるでしょう。
マンションの床をリフォームする際の注意点
マンションの床リフォームを成功させるためには、事前に確認すべき注意点がいくつかあります。集合住宅特有のルールや、リフォーム後の生活に影響する重要なポイントを把握し、後悔のないリフォームを実現しましょう。
【注意点1】床暖房を設置・交換するなら適切な工法や床材を選ぶ
マンションで床暖房を設置・交換する場合は、工法や床材の選定に注意が必要です。
まず、床暖房を新たに設置する場合は、以下の点に注意しましょう。
- 管理規約の確認
- 床暖房に対応した床材を選ぶ
- 床の高さに注意
次に、既存の床暖房を交換する場合、床暖房の種類が「仕上げ材一体型」か「仕上げ材分離型」かを確認することが重要です。
- 仕上げ材一体型
- 仕上げ材分離型
このように、床暖房の設置・交換は確認すべき事項が多く、リフォームをスムーズに進めるためには信頼できる業者への相談が必要不可欠です。
【注意点2】既存が畳の場合は床の高さに気を付ける
既存の床が畳の場合、フローリングなど他の床材にリフォームする際には「床の高さ」に注意が必要です。畳はフローリングに比べて厚みがあるため、畳を撤去してフローリングを張ると、隣接する部屋の床と大きな段差ができてしまう可能性があります。
このような段差は、つまずいて転倒するリスクがあるだけでなく、見た目の違和感も生じます。段差を解消するためには、フローリングを張る前に畳の厚み分の下地調整を行い、床の高さを揃える作業が欠かせません。
畳からフローリングへのリフォームを検討している場合は、この下地調整にかかる費用や工期についても事前に確認しておきましょう。
【注意点3】既存がカーペットの場合は管理規約を確認する
既存の床がカーペットの場合、フローリングなど他の床材にリフォームする際には、必ずマンションの管理規約を確認することが非常に重要です。
カーペットは、防音性と保温性に優れている床材です。そのため、多くのマンションでは、階下への騒音を軽減する目的で、カーペットが標準仕様として採用されていることがあります。このような場合、フローリングへの張り替えを禁止していたり、特定の遮音等級(L値)を持つ床材の使用を義務付けていたりする可能性があります。
管理規約に違反して工事を進めてしまうと、近隣住民とのトラブルに発展したり、最悪の場合には再工事を求められたりするリスクがあります。リフォームを検討する際は、まず管理規約を確認し、どのような床材が使用できるのかを把握するようにしましょう。
マンションにおける床リフォームの施工事例
マンションの床リフォームの成功事例を知ることは、具体的なイメージを掴む上で非常に役立ちます。
ここでは、ハピすむが手掛けた実際の施工事例を通じて、どのように理想の空間が実現できるのかをご紹介します。ご自身の住まいに近い事例を参考に、リフォームのヒントを見つけてみてください。
【事例1】玄関の床リフォームで明るい空間に


| リフォーム期間 | 1ヶ月間 |
| リフォーム費用 | – |
「玄関を明るい空間にしたい」というご要望から、玄関タイルの交換やドア塗装、シュークロゼットの変更などを行ったリフォーム事例です。
白を基調とした空間でスペースも広く見え、明るい印象に生まれ変わりました。
【事例2】防音対策で暮らしやすさアップ


| リフォーム期間 | 2日間 |
| リフォーム費用 | 約21万円 |
床の劣化をきっかけに、防音効果のある床材に張り替えたリフォーム事例です。
遮音等級の基準を満たした床材を選ぶことはもちろん、ワックス不要でお手入れ簡単な床材を選定しています。
【事例3】洗面所の床張り替えでスッキリした印象に


| リフォーム期間 | 約1週間 |
| リフォーム費用 | – |
経年劣化をきっかけに、水回りをリフォームした事例です。
フロアタイルのほか壁紙も一新し、ナチュラルな雰囲気の洗面所に仕上がっています。
【事例4】耐水性の高いクッションフロアにリフォーム


| リフォーム期間 | 3日間 |
| リフォーム費用 | 約20万円 |
ベニアの状態だったキッチンに、クッションフロアを施工したリフォーム事例です。
フローリング調のデザインを選ぶことで、周囲の雰囲気と馴染み、自然な仕上がりとなりました。
【事例5】床リフォームとあわせて床暖房も交換


| リフォーム期間 | 2週間 |
| リフォーム費用 | 約50万円 |
フローリングの張り替えと合わせて、既存の床暖房を交換したリフォーム事例です。
床と床暖房のリフォームを合わせて行うことで、既存の床の剥がしが一度で済んでいるため、トータルコストの削減にもつながっています。
【事例6】費用を抑えた重ね張りリフォーム


| リフォーム期間 | 4日間 |
| リフォーム費用 | 約30万円 |
経年劣化による床の軋みなどを改善するため、床の重ね張りリフォームを行なった事例です。
「費用を抑えながらリフォームしたい」というご要望を受け、既存の床を剥がす「張り替え」ではなく、「重ね張り」によってトータルコストを抑えています。
【Q&A】マンションの床リフォームに関するよくある質問
- マンションの床は何年でリフォームすべき?
-
一般的に、マンションの床リフォームの目安は15〜20年とされています。しかし、使用している床材の種類や日頃のお手入れ状況、生活スタイルによって、リフォームが必要になる時期は異なります。
以下のような状態が見られる場合は、リフォームを検討するサインです。
床リフォームを検討するサイン- 床の傷やへこみが目立つ
- 歩くときに床がきしむ
- 床が沈み込む感じがする
- ワックスがけをしても光沢が戻らない
特に、お子様がいるご家庭など、床への負担が大きい場合は、早めのリフォームを検討するとよいでしょう。
- 3LDKのフローリングの張り替え費用はいくら?
-
3LDK(約70m²)のマンションのフローリングを張り替える際の費用は、選ぶフローリングのグレードによって大きく変動します。
一般的な目安は、以下のとおりです。
フローリング張り替えの費用相場の目安普及品フローリングの張り替え 60万円〜 高品質フローリングの張り替え 100万円〜 ※ 3LDK(約70m²)のマンションを想定 ただし、この費用はあくまで目安であり、既存の床の状態やリフォームする範囲によっても変わります。正確な費用を知りたい場合は、リフォーム会社に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを取得することをおすすめします。
- なぜマンションのフローリングはふわふわしているの?
-
マンションのフローリングを踏んだ際に「ふわふわ」と沈むような感触がある場合、いくつかの原因が考えられます。
フローリングがふわふわしている原因- 床材の剥がれ
- 下地材の劣化
- 二重床工法の不具合
フローリングの「ふわふわ」した感触を放置しておくと、床材の破損や床鳴り、さらには下地の腐食が進むなど、より深刻な問題に発展するおそれがあります。被害を最小限に抑えるためにも、早めにリフォーム会社に相談し、専門家による点検を受けましょう。
- マンションにおすすめの床材は?
-
マンションの床材を選ぶ際は、見た目の好みだけでなく、管理規約で定められた防音規定や、使用する部屋の目的を考慮することが重要です。
また、各床材の特徴を理解し、ご自身のライフスタイルに合った床材を選ぶことが、快適な住空間を実現する鍵となります。
各床材の特徴は、「マンションで使われる床材の種類」にて詳しく解説しています。
【まとめ】マンションの床構造や遮音等級を確認して適切なリフォームを実現しよう
マンションの床リフォームを成功させるためには、事前に確認すべき「2つの鉄則」があります。それは、「管理規約で定められた防音規定(遮音等級)」と「床の構造(二重床か直床か)」です。これらのルールや構造を無視してリフォームを進めると、近隣住民とのトラブルや再工事のリスクにつながるかもしれません。
床材には、デザインや機能性に優れた複合フローリングから、水回りに適したクッションフロア、高い防音性を持つカーペットまで、さまざまな種類があります。また、工法には、費用を抑えられる「重ね張り」と、根本的な問題を解決できる「張り替え」があります。
ご自身のマンションのルールを理解した上で、用途や目的に合った最適な床材と工法を選ぶことが、理想の住空間を実現する鍵となります。DIYではなく、専門知識を持つプロの業者に依頼し、適切なリフォームを計画しましょう。
床・フローリングリフォームの業者選びで後悔しないために
必ず相見積もりを複数取って比較しましょう!
なぜならリフォームの費用・工事方法は、業者によって大きく異なるからです。
とはいえ「信頼できる業者が分からない」「何度も同じ説明をするのが面倒」と踏み出せない方もいらっしゃると思います。
そのような方こそハピすむの一括見積もり比較を活用しましょう!
大手ハウスメーカーから地場の工務店まで、審査を通過した1000社以上の中から、まとめて見積もりを依頼できます。
また、ハピすむでリフォームされた方には最大10万円分の「ハピすむ補助金」もご用意しています。
詳細はこちら>>>ハピすむ補助金プレゼントキャンペーンの流れ