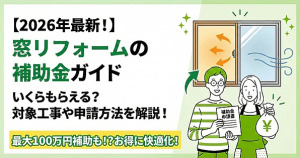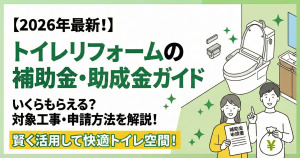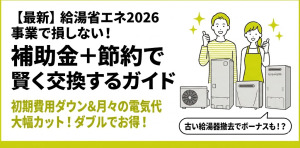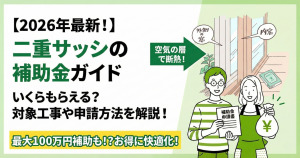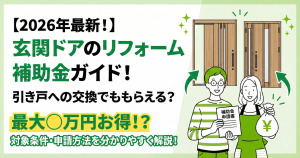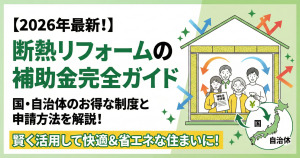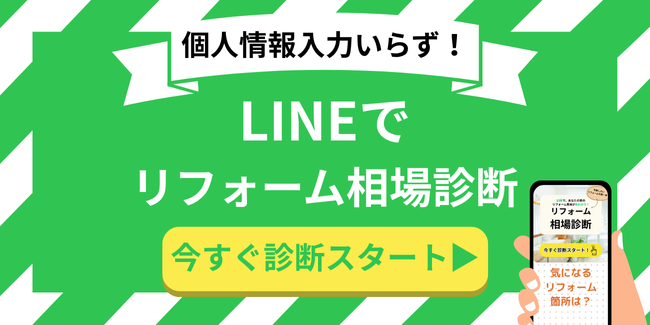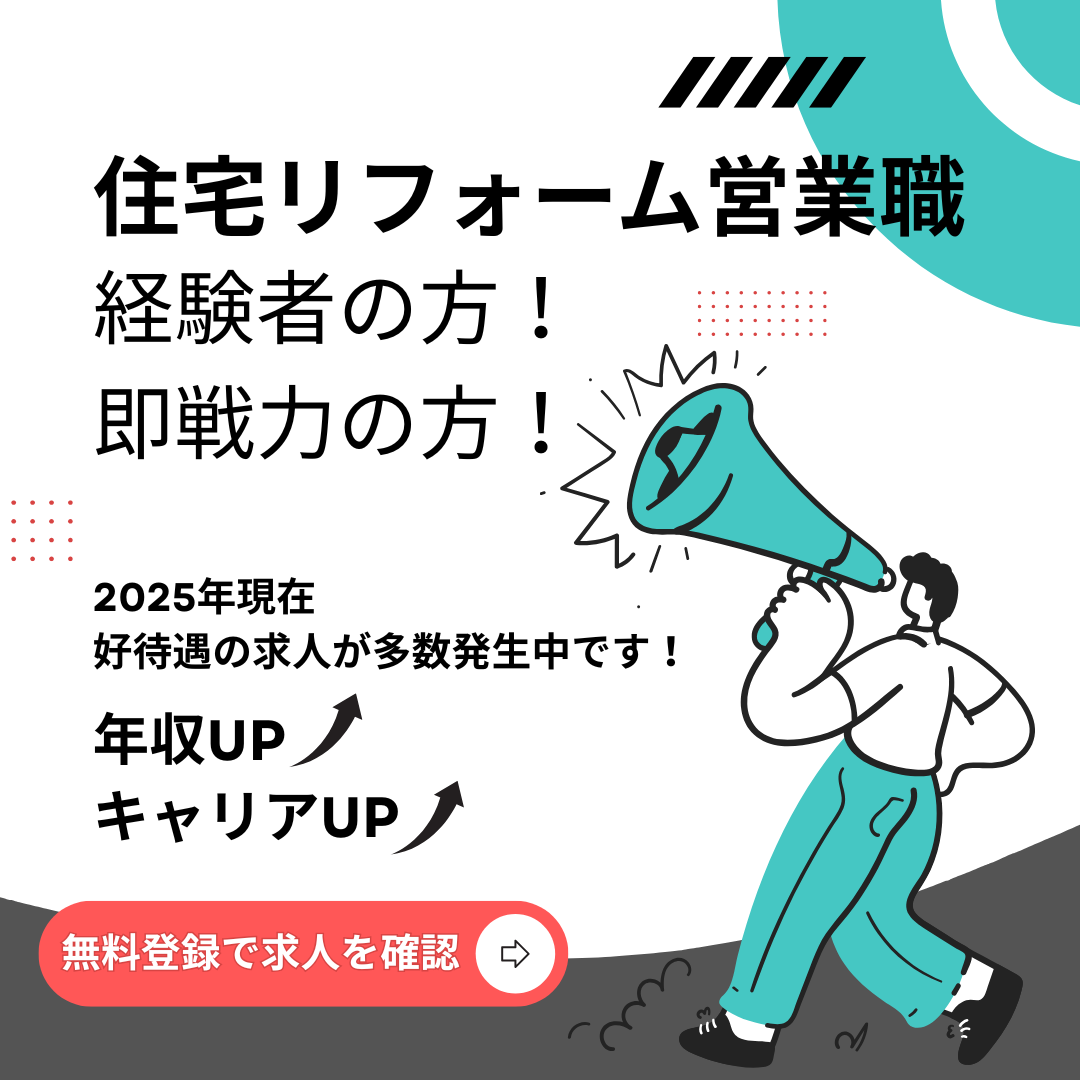-

【2026年先取り】窓リフォームの補助金は最大100万円!補助金の条件・申請方法を徹底解説
-

【2026年最新】トイレリフォームで活用できる補助金・助成金制度は?いくらもらえる?
-

【令和7年度募集開始】子育て支援型共同住宅推進事業を徹底解説!補助対象・要件・申請方法まとめ
-

【最新】給湯省エネ2026事業で損しない!補助金+節約で賢く交換するガイド
-

賃貸集合給湯省エネ2026事業とは?補助額や対象機器を解説
-

二重窓(サッシ)で補助金がもらえるって本当?申請方法完全ガイド【2026年】
-

【受付終了・2024年】子育てエコホーム支援事業を解説!
-

【2026年最新!】玄関ドアのリフォーム補助金ガイド!引き戸への交換でももらえる?
-

【2026年最新】断熱リフォーム補助金の完全ガイド!国・自治体のお得な制度と申請方法を解説
バリアフリーリフォームで活用できる補助金制度
バリアフリーリフォームに活用できる補助金制度は、大きく分けて以下の3種類です。
バリアフリーリフォームと聞くと高齢者向けというイメージを持たれる方も多いでしょう。実は車椅子ユーザーや障がいのある方、さらにはマンションや新築でも対象になる場合があります。「どれを選べばいいのか迷う…」という方は、まず以下の簡単な診断を受けましょう。
このように整理すれば、複雑に感じる補助金制度も選びやすくなります。
バリアフリーリフォームで活用できる補助金制度の概要
ここでは、国・自治体・介護保険の概要をまとめました。それぞれの全体像を把握したい方は、一つずつ見ていきましょう。
バリアフリーリフォームで活用できる国からの補助金制度は、みらいエコ住宅2026事業です。手すりの設置や段差解消といった基本的な工事はもちろん、断熱・耐震改修と組み合わせた大規模リフォームまで幅広く対象になります。
補助額の目安は数十万円〜100万円を超える場合もあるため、工事の規模が大きい方に特におすすめです。
主なバリアフリー工事の補助額(2025年度参考)※2026年度も同水準が見込まれます。
- 手すりの設置: 5,000円 /戸
- 段差解消: 6,000円 /戸
- 廊下幅等の拡張: 28,000円 /戸
- ホームエレベーター新設: 150,000円 /戸
- 衝撃緩和畳の設置: 17,000円 /戸
これらの金額を合計し、他の省エネ工事(窓・断熱・エコ給湯器など)の補助額と合わせた総額を受け取ることになります。
※ 制度ごとに募集期間があり、予算枠に達すると終了するケースがあるので最新情報を確認しましょう。
お住まいの自治体でも、独自の補助金制度を設けていることが多くあります。例えば東京都では高齢者住宅改修費助成事業があり、手すりの設置や段差解消をサポートしています。
制度は地域差が大きいため、必ず公式サイトや窓口で最新情報を確認することが重要。地元に根ざした支援が受けられるので、親や子ども世代と同居している家庭にとっても心強い制度です。
介護保険の住宅改修費支給制度(より詳細な記事はこちら)は、要介護・要支援の認定を受けている方が利用できる制度です。工事費用に対して最大20万円までが支給対象となり、そのうち9割(所得区分によって7〜8割の場合もあり)が介護保険から払い戻されます。
例えば1割負担の場合は、最大18万円が支給される仕組みです。なお、申請にはケアマネジャーなどが作成する住宅改修が必要な理由書が必要になるため、まずは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう。
バリアフリーリフォームで補助金制度を活用する条件
補助金制度を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここでは主な条件を整理し、注意点とあわせてご紹介します。
補助金制度によって申請対象者は異なり、「65歳以上」「障がいのある方」「要介護認定を受けている方」など条件が分かれます。なかには40歳未満の方や同居している家族が対象になる制度もあるため、家族ぐるみで考えるのがおすすめです。特に介護保険を使う場合は要介護認定が必須なので、この点は覚えておきましょう。
一戸建て、分譲マンション、賃貸など、住まいの形態によって利用できる制度が違います。例えばみらいエコ住宅2026事業は、これらすべての建物が対象です。利用時、賃貸の場合はオーナーの承諾が必要になり、マンションでは管理規約を確認することが欠かせません。
建物の形態を確認するために、登記事項証明書や賃貸契約書を求められることもあります。事前に準備しておくと手続きがスムーズです。
補助対象となりやすい工事の例は、以下のとおりです。
- 手すりの設置(玄関・廊下・トイレ・浴室など)
- 段差解消(スロープ設置、床のかさ上げなど)
- 浴室の改修(出入口を広げる、滑りにくい床材に変更など)
- トイレの改修(洋式化、スペース拡張など)
- 出入口や廊下の幅を広げる工事
これらは多くの制度で対象になりやすい工事ですが、制度ごとに対象範囲が異なるため注意が必要です。例えば手すりの設置は対象になるのに、扉の交換は対象外になることもあります。同じ工事でも認められないケースがある点は意外な落とし穴です。
また、長期優良住宅化リフォーム推進事業などでは、バリアフリー改修に加えて省エネや耐震改修をまとめて申請できる場合があります。必要な工事を組み合わせることで、制度をフル活用できる可能性もあるので、業者や自治体に確認してみましょう。
バリアフリーリフォームにおける補助金制度の申請方法
バリアフリーリフォームの補助金申請は、制度ごとに流れや必要書類が異なります。ここでは国・自治体・介護保険の申請方法を解説します。
国が行う補助金制度は、施工業者の登録確認や工事前の申請が必須です。事前準備を丁寧に行うことで、スムーズに補助を受けられます。
①施工業者が補助事業者として登録しているか確認する
②工事前に申請書を作成し、必要書類を添えて提出
③工事完了後、完了報告書を提出し、審査を受ける
④補助金が指定口座に振り込まれる
📝必要書類
・補助金交付申請書
・工事見積書・設計図面
・工事前後の写真
・工事請負契約書の写し
・本人確認書類(住民票など)
自治体の補助金は地域ごとに内容や条件が異なります。多くは着工前の申請が必要となるため、工事スケジュールを立てる前に確認しておきましょう。
①自治体の公式サイトや窓口で制度内容を確認
工事前に申請書を提出着工前に申請しないと対象外になる場合が多いため注意しましょう。
②審査・交付決定を受けてから工事を開始
③工事完了後に実績報告を提出
④補助金が交付される
📝必要書類
・申請書・実績報告書
・工事見積書・契約書
・工事前後の写真
・所有者確認書類(登記事項証明書、印鑑証明や振込口座情報)
介護保険の住宅改修費支給制度は、ケアマネジャーの協力が必要です。段取りと必要書類を確認し、不備のないように進めましょう。
①ケアマネジャーに相談し、住宅改修が必要と記載された「ケアプラン」を作成
②工事内容を盛り込んだ「住宅改修理由書」を主治医やケアマネが作成
③工事前に市区町村へ申請書類を提出
④承認後に工事を実施
⑤工事費を一度全額自己負担し、その後介護保険から9割(または7〜8割)が払い戻される
📝必要書類
・住宅改修費支給申請書
・ケアプラン
・住宅改修理由書(主治医やケアマネジャーが作成)
・見積書・図面
・工事前後の写真
・領収書
バリアフリーリフォームの補助金制度は併用可能?
「複数の制度を一緒に使えたら、もっと負担を減らせるのでは?」と気になる方も多いのではないでしょうか。結論としては、補助金制度によって併用できる場合とできない場合があります。
例えば、国の制度と自治体の制度は併用できるケースがありますが、同じ工事費を二重に申請することはできません。
制度を最大限に活用するには、上限額や補助率が高いものから優先して利用するのがポイント。どの制度をどう組み合わせられるかは、自治体や工事内容によって異なるため、業者や自治体窓口に確認して進めると安心です。
バリアフリーリフォームで補助金制度に申請をするときの注意点
バリアフリーリフォームで補助金制度に申請をするときは、あらかじめ押さえておくべき注意点を確認しましょう。
バリアフリーリフォームの補助金制度のほとんどは、工事を始める前に申請完了していることが条件です。契約や着工のタイミングを間違えてしまうと、せっかくの制度を受けられなくなってしまうことがあります。きちんと順序を守って進めるためにも、スケジュールに余裕を持たせて申請準備を進めることが大切です。
補助金の審査には、申請書や見積書だけでなく、工事前・工事中・工事後の写真などが必要になる場合があります。これらが不足していたり、書類に不備があると再提出を求められ、審査や補助金の支給が大幅に遅れる可能性があります。早めに必要書類を揃え、施工業者と連携して写真や契約書をきちんと準備しておくと安心です。
補助金には必ず上限額があります。たとえば20万円が上限の制度で30万円の工事をした場合、10万円は自己負担になります。あらかじめ見積もりの段階でシミュレーションし、どのくらいの補助が受けられるかを確認しておくことが大切です。工事内容を調整することで無駄な出費を抑えられる場合もあります。
バリアフリーリフォームは、住宅の安全性や暮らしやすさに直結する工事です。申請に不慣れな業者や実績の少ない業者に依頼すると、書類不備や施工不良などのトラブルにつながる恐れがあります。複数社から見積もりを取り、対応の丁寧さや説明のわかりやすさ、過去の施工事例や口コミを確認して、安心して任せられる業者を選びましょう。
バリアフリーリフォームに活用できる減税制度
ここでは、バリアフリーリフォームに活用できる5つの減税制度について解説します。
バリアフリー改修工事の費用の一部を、所得税から控除できます。対象は手すり設置・段差解消・浴室やトイレの改修などです。控除額は工事費の10%(最大60万円)で、自己資金でリフォームを行う方に向いています。
リフォーム費用をローンで借り入れた場合、年末のローン残高の0.7%を10年間にわたって控除できます(最大140万円)。大規模なリフォームを計画している方やローンを活用する方におすすめです。
工事完了の翌年度から、固定資産税が1/3減額される制度があります。対象は築10年以上の住宅で、65歳以上や要介護認定者、障がい者が居住している住宅です。長く住み続ける予定がある方には、大きな節税効果が期待できます。
親や祖父母から資金援助を受けてリフォームする場合、一定額までは贈与税が非課税になります。非課税枠は500万〜1,000万円と大きく、家族の支援を受けながら負担を軽減できるのが魅力です。
中古住宅を購入してバリアフリー改修を行う場合、登録免許税や不動産取得税が軽減されることがあります。対象工事や申請期限などの条件があるため、住宅購入を検討している方は早めに確認することが重要です。
【補助金制度以外】バリアフリーリフォームの費用を抑える方法
ここでは、補助金制度の活用以外で費用を抑える4つの方法を解説します。「制度の申請期間に間に合わなかった」「今すぐリフォームしたい」という方は、ぜひご検討ください。
リフォーム費用を抑える基本は、複数業者から同条件で見積もりを取ることです。価格の差だけでなく、工事内容や使用する材料、アフターフォローの違いも確認できます。金額だけで判断せず、対応の丁寧さや提案力も比較基準にすると、コストを抑えながら安心できる業者を選べます。
予算が限られている場合は、生活に直結する工事を優先するのもおすすめです。例えば浴室の段差解消やトイレの手すり設置など、毎日使う場所から改善すると効果が実感しやすくなります。将来を見据え、段階的にリフォームしていく計画を立てれば、無理なく安心な住まいづくりができるでしょう。
リフォームは必ずしも全面改修をする必要はありません。ドアの開閉方向を変える、既存の床にスロープを後付けする、部分的に手すりを設置するなど、工夫次第で費用を抑えられます。新しく買い替えるよりも今あるものを活かす発想を持つことで、無駄な出費を減らすことも可能です。
手すりやスロープ、介護ベッドなどは購入すると高額ですが、介護保険のレンタルを利用すれば1〜3割の自己負担で利用できる場合があります。必要なくなったら返却・交換ができるため、将来の状況変化にも柔軟に対応可能です。「買う前に借りる」という選択肢を持つことで、初期費用を大幅に抑えられるでしょう。
補助金制度を活用したバリアフリーリフォーム事例
ここでは、補助金制度を活用してバリアフリーリフォームを行ったハピすむの施工事例を紹介します。ぜひイメージづくりや制度活用の参考にしてください。


| 費用 | 約190万円 |
| 工事期間 | 1週間 |
| 面積 | – |
| 施工範囲 | トイレ、浴室 |
補助金制度を活用して、またぎやすい高さの浴槽にリフォームした事例です。以前よりも浴槽が低くなったため、またぐときの負担が少なくなりました。
滑りにくい床材や手すりも設けたことで、より快適で安全な浴室に。浴槽のまたぎに不満を抱えている方は、ぜひ浴槽交換を検討しましょう(施工:ヴィヴィ)。


| 費用 | 約370万円 |
| 工事期間 | 28日 |
| 面積 | – |
| 施工範囲 | 浴室、窓、キッチン |
在来浴槽からユニットバスにリフォームした事例です。滑りにくい床材や出入口の段差解消、手すりの設置などを行うために、補助金制度を活用してお得にバリアフリー化しました。
安全性が高くなったのはもちろん、見た目も爽やかになり、これまで以上に使いやすい浴室に。毎日の入浴タイムが楽しみになる浴室に生まれ変わりました(施工:コモドホーム)。


| 費用 | 約150万円 |
| 工事期間 | 6日 |
| 面積 | – |
| 施工範囲 | トイレ、浴室 |
ケガをきっかけに移動や立ち座りに負担がかかるようになった施主様のために、起居動作のしやすいトイレにリフォームしました。トイレと出入口枠との間には段差があったため、床を2cmかさ上げして段差を解消。つまずくリスクが少なくなり、生活がしやすい住まいになりました(施工:コモドホーム)。
【まとめ】補助金制度をフル活用して、バリアフリーリフォームをしよう
バリアフリーリフォームは安心して暮らすために大切なことではあるものの、費用面が不安な方も多いはず。そんなときは、対象となる補助金制度のフル活用して費用を抑えましょう。
条件や手続きは複雑ですが、実績のある業者と連携すれば後悔のないリフォームが実現します。まずは「ハピすむ」で信頼できる業者に相談して、補助金制度を活用しながら快適な住まいづくりを始めましょう。