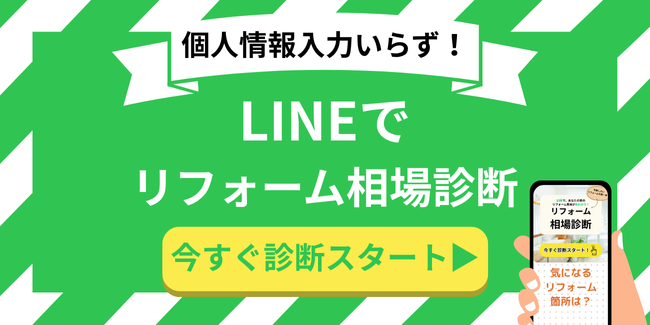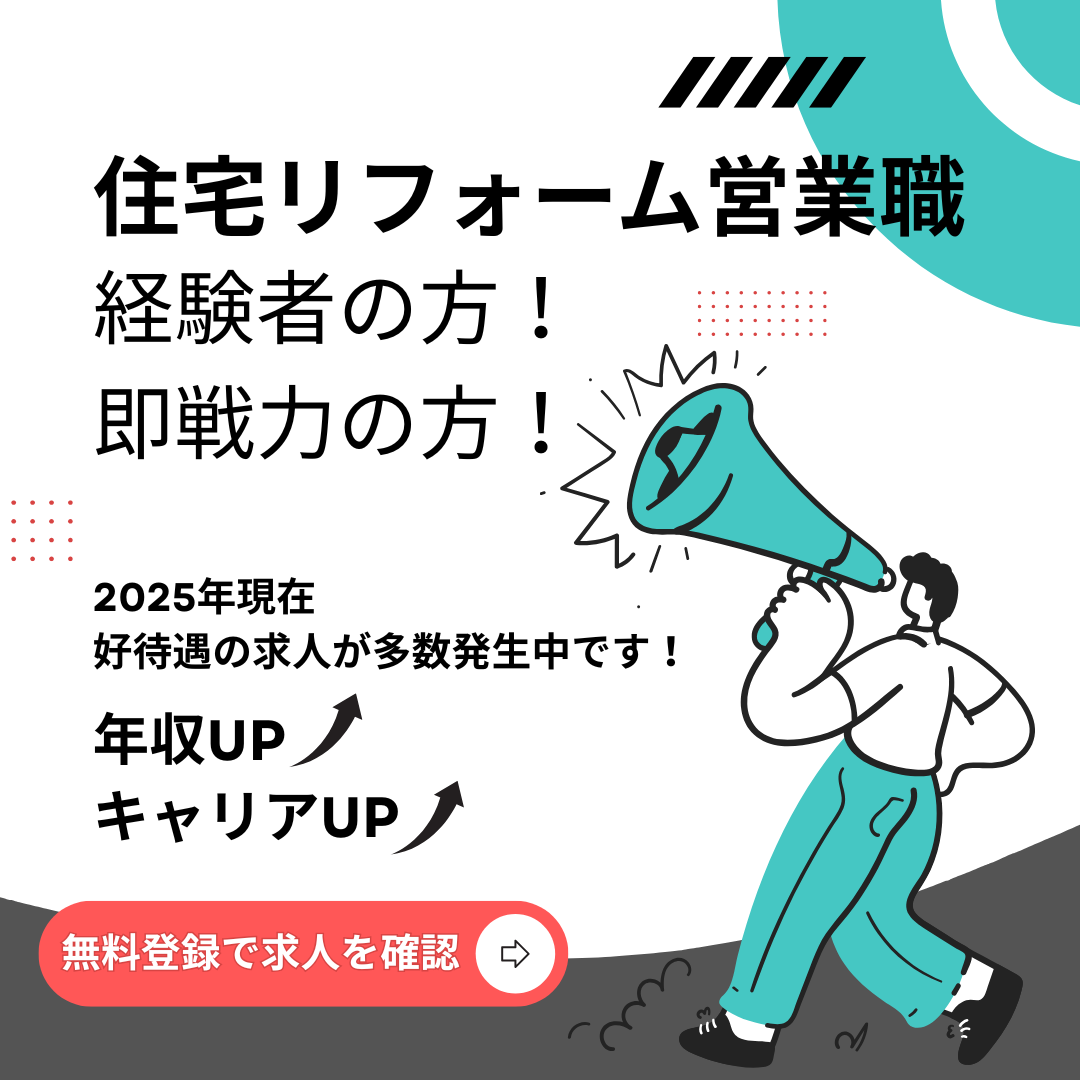目次
- 1 一戸建ての耐震補強工事にかかる費用
- 2 【重要】2025年4月の法改正(4号特例の縮小)で何が変わる?
- 3 【2025年最新】一戸建ての耐震補強工事で活用できる補助金制度
- 4 一戸建ての耐震補強工事の内容
- 5 地震で倒壊するおそれがある一戸建ての特徴
- 6 一戸建ての耐震補強工事の流れ
- 7 一戸建ての耐震補強で業者を選ぶ際の注意点
- 8 「一戸建ての耐震補強は意味がない」は本当?耐震補強工事の必要性
- 9 【構造別】木造・鉄骨造・RC造の耐震補強の違い
- 10 「耐震補強」と「建て替え」で迷った時の判断基準
- 11 【Q&A】一戸建ての耐震補強工事に関するよくある質問
- 12 【まとめ】補助金制度を活用した耐震補強で安心の住まいを実現しよう
一戸建ての耐震補強工事にかかる費用
一戸建ての耐震補強工事にかかる費用は、築年数や建物の状態、工事内容によって大きく異なります。特に、築年数は費用に最も影響を与える要因のひとつです。また、基礎や壁、屋根など、どの部分を補強するかによっても費用は変動します。
ここでは、耐震補強工事にかかる費用相場を「築年数別」と「工事内容別」に分けて解説します。ご自宅の状況に合わせて、かかる費用の目安を把握する参考にしてください。
【築年数別】耐震補強工事の費用相場
一戸建ての耐震補強工事にかかる費用は、築年数が大きな要因となります。築年数が古くなるほど、建物の劣化が進んでいる可能性が高く、補強範囲が広がるため、費用も高くなる傾向にあります。
一般的な木造2階建て住宅(延床面積:120平方メートル)の場合、築年数ごとの費用相場は以下のとおりです。
| 築年数 | 費用相場 |
|---|---|
| 60年以上 | 200万〜220万円 |
| 50年 | 180万〜200万円 |
| 40年 | 150万〜180万円 |
| 30年 | 130万〜150万円 |
ただし、これはあくまで目安であり、建物の状態によっては築年数が浅くても大規模な補強が必要となり、費用が高くなるケースもあります。正確な費用を知るためには、専門家による耐震診断を受けることが必要不可欠です。
【工事内容別】耐震補強工事の費用
耐震補強工事は、建物のどの部分を補強するかによって費用が大きく異なります。ここでは、工事内容別の費用相場をまとめました。
| 工事内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 基礎の補強 | 100万〜250万円 |
| 壁の補強 | 30万〜100万円 (1階部分のみ) |
| 柱の修繕 | 50万〜150万円 |
| 屋根の補強 | 50万〜150万円 |
上記はあくまで目安であり、建物の劣化状況や補強する範囲によって費用は変動します。複数の工事を組み合わせるのが一般的であり、その場合は合計費用が高くなることを考慮しておきましょう。
【重要】2025年4月の法改正(4号特例の縮小)で何が変わる?
2025年4月から、建築基準法の「4号特例」が縮小され、一戸建て住宅の耐震補強工事に大きな影響が出ます。具体的には、これまで多くの木造住宅リフォームで免除されていた「建築確認申請」が、耐震補強のような大規模な工事で義務化されることになります。
これにより、構造計算や申請書類の作成に追加費用が発生し、耐震補強にかかる総費用の増加が懸念されます。
費用負担の増加を考えると、国や自治体の補助金制度を賢く活用することがこれまで以上に重要となるため、まずは補助金制度に精通した専門家に相談してみましょう。
建築確認申請は申請と審査に数週間から数ヶ月かかるため、工期が長期化するおそれもあります。そのため、余裕をもったリフォーム計画が重要です。
【2025年最新】一戸建ての耐震補強工事で活用できる補助金制度
一戸建ての耐震補強工事には高額な費用がかかるため、費用負担を軽減する手段として補助金制度の活用が必要不可欠です。国や自治体は、住宅の耐震化を促進するためにさまざまな補助金制度を用意しています。
ここでは、耐震補強に特化した国の制度と、それと併用できる可能性のある自治体の補助金制度についてくわしく解説していきます。
【制度1】長期優良住宅化リフォーム推進事業
国が提供する数ある補助金制度の中でも、耐震補強工事を検討している方が最も注目すべきなのが、国土交通省が管轄する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」です。この事業は、住宅の長寿命化を目的としており、耐震性の向上が補助金を受け取るための必須要件とされています。
この制度は、耐震補強と合わせて省エネ改修や劣化対策などを行うことで、工事費用の一部を補助するものです。最大で160万円以上の補助金を受けられる可能性があるため、耐震補強を検討する際は、この制度を中心に計画を立てるのが賢明です。
【制度2】自治体の補助金制度
国の補助金制度に加えて、お住まいの自治体が独自に補助金制度を用意しているケースも少なくありません。国の制度と自治体の制度は併用できる場合もあるため、両方を活用すれば費用負担をさらに軽減できます。
たとえば、神奈川県横浜市や兵庫県神戸市などでは、木造住宅の耐震改修を促進するための手厚い補助金制度が用意されています。
耐震補強工事を検討する際は、まずお住まいの自治体のホームページを確認し、どのような補助金が利用できるか調べてみましょう。
お住まいの自治体にどのような補助金制度があるかは【(お住まいの市区町村名) 耐震補助金】などで検索すると見つけやすいでしょう。
一戸建ての耐震補強工事の内容
一戸建ての耐震補強工事は、主に「基礎」「壁」「柱」「屋根」の4つの部分を強化する工事が一般的です。これらの工事は、建物の構造や劣化状況に合わせてさまざまな方法が用いられます。
ここでは、それぞれの工事内容についてくわしくみていきましょう。
【工事1】基礎の補強
基礎は建物の土台となる非常に重要な部分です。地震の揺れはまず基礎に伝わるため、基礎にひび割れや劣化があると、建物全体が倒壊するおそれがあります。
基礎の補強方法は、以下の2つです。
- ひび割れの補修
- 基礎の増し打ち
ひび割れの補修では、コンクリートのひび割れ部分にエポキシ樹脂などの補強材を注入し、基礎の強度を高めます。なお、ひび割れの状態によっては効果が限定的であるため、補修前に基礎の状態を見極めなければなりません。
一方、基礎の増し打ちは既存の基礎に沿って鉄筋を組み、新しいコンクリートを打ち足して基礎を厚くする工法です。建物の周囲全体に基礎を増し打ちすることで、建物の強度を大幅に向上させる効果が期待できます。
【工事2】壁の補強
壁の補強は、地震の揺れによる建物の変形を防ぐために非常に重要な工事です。主な方法として、以下の2通りが挙げられます。
- 耐力壁の増設
- 制震ダンパーの設置
耐力壁の増設は、既存の壁の内側に構造用合板や筋交いを追加して、地震の力に耐える壁を増やします。特に、旧耐震基準で建てられた住宅は耐力壁が少ない場合が多いため、この工事が有効です。
一方、制震ダンパーの設置は、壁の中に制震ダンパーという特殊な装置を取り付けることで、地震の揺れを吸収し、建物の揺れを抑えます。耐力壁の増設と比べて、工事規模が小さく済むケースが多いといえるでしょう。
【工事3】柱の修繕
柱の修繕は、建物の垂直方向の強度を維持するために重要な工事です。主な方法として、以下の2つが挙げられます。
- 劣化部分の交換
- 接合部の補強
湿気やシロアリ被害などで傷んだ柱は、建物の強度を著しく低下させるため、このような柱は、健全な部分を残して新しい部材に取り替えなければなりません。
一方、接合部の補強は、地震の揺れで柱と梁が接合する部分が外れてしまうのを防ぐため、金物を使って補強します。これにより、建物の変形や倒壊を防ぐ効果が期待できます。
【工事4】屋根の補強
屋根は、建物の中で最も重い部分のひとつです。地震の揺れが大きいほど、屋根が建物にかける負荷も大きくなるため、屋根の補強は重要な工事といえます。
主な補強方法として、以下の2通りが挙げられます。
- 軽い屋根材への葺き替え
- 屋根の補強
日本瓦など重い屋根材を使用している場合、ガルバリウム鋼板などの軽い金属屋根に葺き替えることで、建物全体の重心が下がり、揺れにくくなります。費用はかかるものの、耐震性向上に大きく貢献する工事です。
一方、屋根の補強は、瓦が落ちないように固定したり、屋根の接合部を強化したりすることで、地震時の被害を抑えることが可能です。
地震で倒壊するおそれがある一戸建ての特徴
地震で倒壊するおそれがある一戸建てには、いくつかの特徴があります。ここでは、地震で倒壊するおそれがある一戸建ての特徴を、チェックリスト形式で解説します。
耐震補強の必要性を適切に判断するためにも、まずはご自宅の状況を把握することから始めましょう。
- 1981年5月以前に建てられた「旧耐震基準」の建物
- 2000年5月以前に建てられた木造住宅
- 増築や改築を繰り返している
- 壁が少ない、または偏っている
- 老朽化が激しい
- 1階部分が車庫や店舗になっている
ご自宅が上記のチェックリストに当てはまる場合、耐震補強の必要性が高いと考えられるため、次の「一戸建ての耐震補強工事の流れ」を参考に適切な対策を講じましょう。
一戸建ての耐震補強工事の流れ
一戸建ての耐震補強工事は、以下の4つのステップで進められます。
専門の建築士が現地調査を行い、建物の耐震性を数値で評価する「耐震診断」を受ける。
耐震診断にかかる費用は、一般的に10万〜40万円です。
耐震診断の結果に基づき、建物のどの部分をどのように補強するかの計画を立てる。この段階で、予算や工事中の生活に関する希望も相談し、詳細な見積もりをする。
計画に沿って、基礎、壁、屋根などの補強工事を実施する。
工事規模によって異なりますが、工期は一般的に1〜2ヶ月程度かかります。
工事完了後、補助金の申請や減税制度を利用するための証明書発行などの手続きを行う。
事前に、上記の「一戸建ての耐震補強工事の流れ」を理解し、工事をスムーズに進められるように準備しておきましょう。また、信頼できる業者に相談することも、耐震補強工事を成功させる鍵となります。
一戸建ての耐震補強で業者を選ぶ際の注意点
一戸建ての耐震補強工事は、建物の安全性を左右する重要な工事です。そのため、信頼できる業者選びが欠かせません。
悪徳業者による手抜き工事や不当な高額請求を避けるためにも、以下の3つの注意点を踏まえて業者を選ぶようにしましょう。
【注意点1】建築基準法に詳しい建築士が在籍しているか
2025年4月以降の法改正により、耐震補強のような大規模な工事では「建築確認申請」が義務化されます。この申請には、構造計算書などの専門的な書類が必要となり、正式な手続きを扱えるのは建築士事務所登録をしている業者に限られます。
そのため、法改正後の工事をスムーズに進めるためには、建築基準法に詳しく、建築確認申請の経験が豊富な建築士が在籍している業者を選ぶことが必要不可欠です。
【注意点2】実績が豊富であるか
耐震補強工事は専門性の高い分野であり、業者の技術力や経験が工事の品質を大きく左右します。そのため、これまでに一戸建ての耐震補強工事を数多く手掛けてきた実績が豊富にある業者を選ぶことが重要です。
実績が豊富であるかを見極めるには、業者のホームページなどで過去の施工事例を確認しましょう。「ご自身の家と似た築年数や構造の事例が掲載されているか」、「どのような補強内容でどのくらいの費用がかかったか」などをチェックすると、その業者の得意分野や技術力を把握できます。
実績が豊富な業者は、さまざまな状況に対応できるノウハウを持っているため、安心して任せることができるでしょう。
【注意点3】補助金制度に精通しているかどうか
一戸建ての耐震補強工事で費用を抑えるには、補助金制度の活用が必須です。しかし、国の主要な補助金制度である「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、登録事業者しか申請できないという点に注意しなければなりません。
そのため、依頼する業者がこの制度の登録事業者であるかを確認しましょう。また、制度内容に精通している業者を選ぶことで、複雑な申請手続きをスムーズに進められます。補助金制度の最新情報や、複数の制度を組み合わせて補助額を最大化する方法など、専門的な知識を持った業者に相談することで、費用負担を大幅に軽減できるといえます。
「一戸建ての耐震補強は意味がない」は本当?耐震補強工事の必要性
「一戸建ての耐震補強は意味がない」という意見を耳にしたことはありませんか?
「高額な費用を払ってまで耐震補強工事をする価値はあるのか」
これは、多くの住宅所有者が抱える最大の懸念です。しかし、耐震補強の本当の目的を知れば、その必要性が明らかになります。
耐震補強工事の目的は「建物を無傷に保つこと」だと誤解されがちですが、本当の目的は「家族の命と未来を守る」ことです。耐震補強は、建物の倒壊を防ぎ、安全に避難する時間を確保します。また、大規模な損壊を避けることで、自宅での生活再建の可能性を高め、地震後の生活を守ることにもつながります。
このように、耐震補強は地震の揺れによる被害をゼロにすることではなく、人命を守るための「時間稼ぎ」であり、家族の未来を守るための賢明な投資といえるでしょう。
【構造別】木造・鉄骨造・RC造の耐震補強の違い
一戸建ての耐震補強は、建物の構造によって補強方法が異なります。木造住宅は柱や梁、壁を補強する工事が主ですが、鉄骨造やRC造(鉄筋コンクリート造)では、異なるアプローチがとられます。
鉄骨造住宅は、主にブレースと呼ばれる筋交いを追加して、揺れに対する強度を高めます。また、柱と梁の接合部を強化する工事も行われます。木造に比べ、壁の補強は比較的容易なケースが多いでしょう。
RC造住宅は、壁や柱に炭素繊維シートを貼り付けることで、粘り強さを向上させます。さらに、構造体のひび割れ部分にエポキシ樹脂を注入し、強度を回復させる工事も一般的です。
構造の違いによって、耐震補強工事の費用相場も異なるため、事前に現地調査してもらったうえで正確な費用を算出してもらいましょう。
「耐震補強」と「建て替え」で迷った時の判断基準
「耐震補強」か「建て替え」かどちらを選ぶべきか、これは多くの人が直面する大きな悩みです。どちらを選ぶべきかは、建物の状態や予算、そして将来のライフプランによって異なります。
ここでは、後悔しない選択をするために役立つ3つの判断基準について解説します。
>>「耐震補強」と「建て替え」どちらを選ぶべきかについて詳しく見る
【判断基準1】建物の状態
耐震補強か建て替えかを判断する上で、最も重要なのが「建物の状態」です。特に、耐震診断の結果、建物の損傷度や耐震性がどのくらいかが大きな基準となります。
たとえば、建物の状態が比較的良好で、耐震補強工事によって必要な耐震性を確保できる場合は、耐震補強が現実的な選択肢となります。
一方、基礎や柱に深刻な劣化や構造的な問題があり、補強が困難または高額になる場合は、建て替えの方が費用対効果が高い可能性もあります。また、現在の間取りや設備に不満があり、大規模なリノベーションも検討している場合は、建て替えも視野に入れるべきでしょう。
【判断基準2】予算
予算は、耐震補強か建て替えかを決める上で非常に重要な要素といえます。一般的に、耐震補強は建て替えよりも費用を抑えられるケースが多い傾向です。
耐震補強工事の費用相場は100万〜200万円ですが、一方、建て替えの場合は解体費用を含めると2,000万円以上かかることも珍しくありません。補助金制度を活用すれば、耐震補強工事の費用負担をさらに軽減できます。
ただし、築年数が古く大規模な補強が必要な場合は、耐震補強工事の費用が建て替え費用に近づくこともあります。その際は、今後のメンテナンス費用や建物の寿命も考慮し、長期的な視点でどちらが経済的かを判断する必要があるでしょう。
【判断基準3】将来のライフプラン
将来のライフプランも、耐震補強か建て替えかを決める重要な判断材料です。
耐震補強は、現在の住宅に住み続けたい方や、大規模な住み替えを考えていない方にとって有効な選択肢です。また、今後数年以内に住み替えや売却を検討している場合、耐震補強をすることで資産価値を維持・向上させることができ、売却時のアピールポイントにもなります。
一方、将来的に家族構成が変わる、間取りを大きく変えたい、住宅設備を最新のものにしたいといった希望がある場合は、建て替えの方がライフプランに合っている可能性があります。
このように、耐震補強や建て替えかを判断する際は、将来のライフプランを視野に入れた長期的な視点が必要不可欠です。
【Q&A】一戸建ての耐震補強工事に関するよくある質問
- DIYによる一戸建ての耐震補強は可能?
-
DIYによる一戸建ての耐震補強は、費用を抑えられるというメリットがある一方、多くのリスクを伴うため推奨できません。
耐震補強は、建物の構造全体のバランスを考慮し、適切な箇所に適切な方法で補強を行う専門的な知識と技術が求められます。素人が部分的に補強を行っても、かえって建物のバランスを崩し、倒壊のリスクを高めるおそれがあります。
また、DIYでは壁の中や基礎のひび割れ、シロアリ被害などの劣化状況を正確に把握することは困難です。不適切な補強は、かえって現状復帰に多くの費用がかかることになりかねません。
安全のためにも、耐震補強は専門の業者に依頼し、建物全体を総合的に診断・補強してもらうことが必要不可欠です。 - 耐震補強の工事中は生活に支障が出る?
-
耐震補強工事中の生活への影響は、工事の内容や規模によって異なります。
部分的な補強工事であれば、住みながら工事を進められるケースがほとんどです。しかし、建物全体の大規模な補強や、基礎・屋根といった重要な部分の工事では、一時的に仮住まいが必要になることもあります。
工事中は騒音や振動、粉塵が発生することがあるため、これらの影響を考慮し、事前に業者と相談して工事スケジュールや生活への配慮について確認しておきましょう。工事中の影響工事内容によっては、電気や水道、ガスなどのライフラインを一時的に止める必要がある場合もあるため、業者との綿密なスケジュールの打ち合わせが重要です。
- 中古住宅は耐震補強が必要?
-
中古住宅の購入を検討している場合、耐震補強が必要かどうかは、建築された時期と耐震基準の関係性で判断することができます。日本の耐震基準は、以下の大きな改正により、段階的に強化されてきました。
日本の耐震基準- 旧耐震基準(〜1981年5月31日)
- 新耐震基準(1981年6月1日〜)
そのため、1981年5月以前に建てられた「旧耐震基準」の住宅は、現在の基準を満たしていない可能性が高く、耐震診断と補強が強く推奨されます。また、2000年にも木造住宅の耐震基準が強化されているため、2000年以前に建てられた木造住宅も注意が必要です。
【まとめ】補助金制度を活用した耐震補強で安心の住まいを実現しよう
この記事では、一戸建ての耐震補強工事について、費用相場から具体的な工事内容、補助金制度の活用法まで詳しく解説しました。
2025年4月の法改正により、今後は耐震補強にかかる費用が増加する可能性があるため、国や自治体が提供する補助金制度の活用がこれまで以上に重要となります。特に、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、耐震補強を必須要件としているため、積極的に検討すべき制度といえるでしょう。
耐震補強は、家族の命と財産を守るための重要な投資です。費用や工事内容で迷った場合は、信頼できる専門業者に相談し、ご自身のライフプランに合った最適な方法を選択しましょう。
耐震リフォームの業者選びで後悔しないために
必ず相見積もりを複数取って比較しましょう!
なぜならリフォームの費用・工事方法は、業者によって大きく異なるからです。
とはいえ「信頼できる業者が分からない」「何度も同じ説明をするのが面倒」と踏み出せない方もいらっしゃると思います。
そのような方こそハピすむの一括見積もり比較を活用しましょう!
大手ハウスメーカーから地場の工務店まで、審査を通過した1000社以上の中から、まとめて見積もりを依頼できます。
また、ハピすむでリフォームされた方には最大10万円分の「ハピすむ補助金」もご用意しています。
詳細はこちら>>>ハピすむ補助金プレゼントキャンペーンの流れ